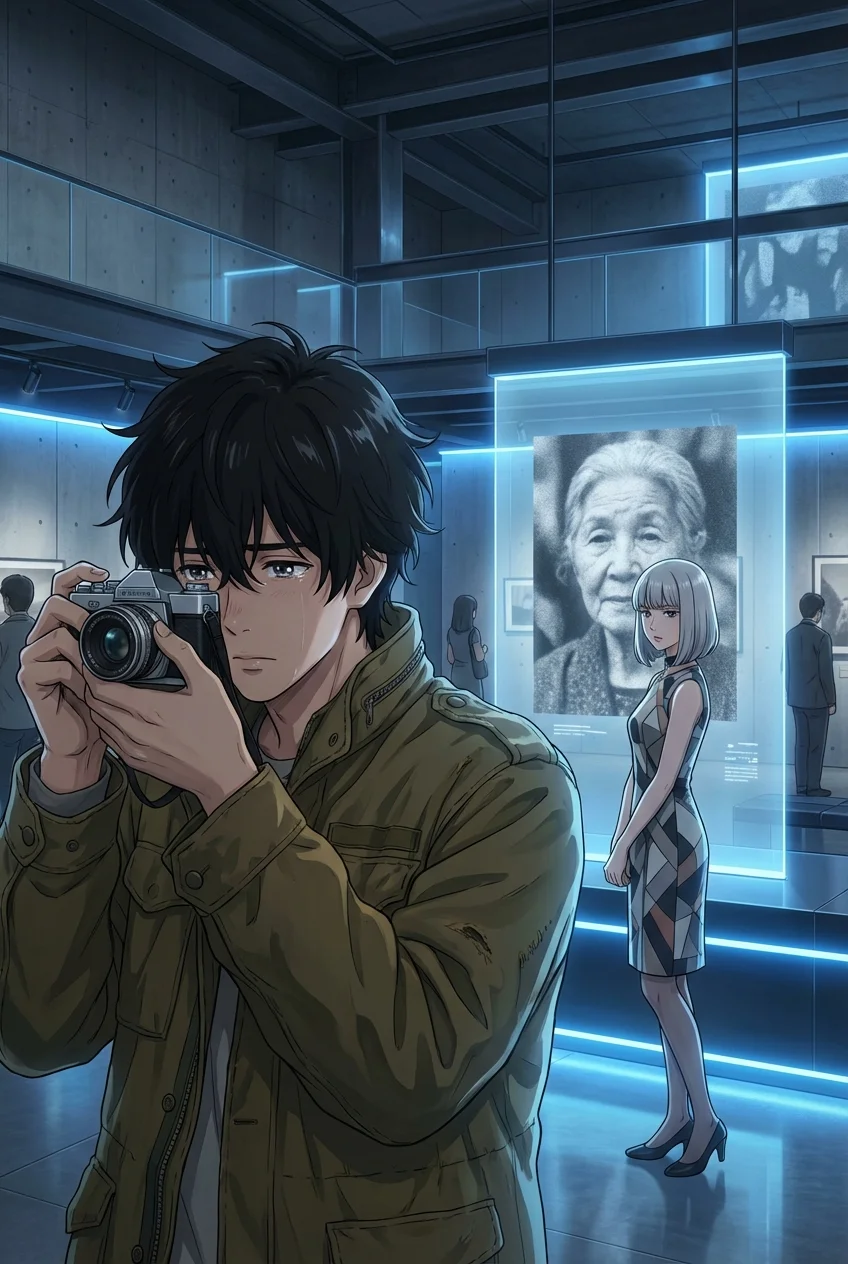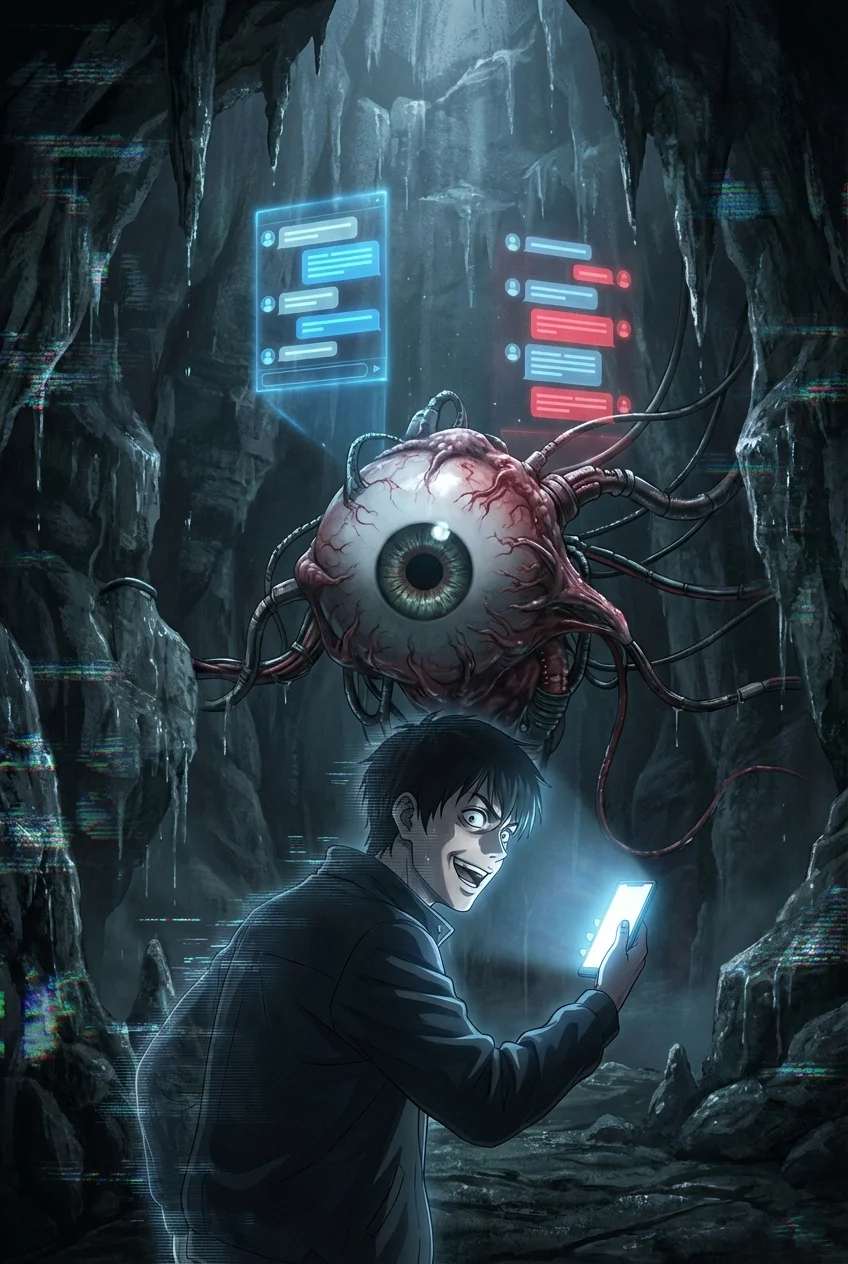第一章 同接5人の底辺配信
「えー、こんにちは。Fランク探索者のレンです。今日も『新宿大迷宮』の第一層、スライムエリアからお送りします」
スマホの画面に向かって、俺は力なく手を振った。
画面の右上に表示された同接者数は『5』。
そのうち一人は俺のサブ垢だから、実質四人だ。
コメントが流れる。
『またスライムかよ』
『飽きた』
『もっと奥行けやチキン』
『草』
辛辣な言葉が並ぶが、これでもマシな方だ。
現代社会に突如出現した『ダンジョン』。
人々は危険と隣り合わせの冒険に熱狂し、探索者は動画配信で莫大な富と名声を掴む。
それが今の時代のサクセスストーリー。
だが、現実は甘くない。
俺、相沢レン(22歳)は、特別なスキルも身体能力もない凡人だ。
持っているのは、鑑定スキルの下位互換である『構造理解』という地味な能力だけ。
物の材質とかがなんとなく分かるだけという、戦闘には何の役にも立たないゴミスキルだ。
「はは……ごめんね。でも、装備が貧弱だから奥に行くと死んじゃうんだよ」
愛想笑いを浮かべながら、俺は錆びついたショートソードでスライムを突く。
ポヨン、と情けない音がして、スライムが弾けた。
『弱っ』
『装備買う金もないのか』
『投げ銭してやるから死ぬ気で行け』
ピコン。
500円のスーパーチャットが飛んだ。
ありがたいが、命を賭けるには安すぎる。
「ありがとう……。じゃあ、今日は少しだけルートを変えて、未探索の横穴に行ってみようかな」
俺は視聴者を繋ぎ止めるために、普段は避けている崩落しかけの通路へと足を向けた。
薄暗い通路はカビ臭く、足元には瓦礫が散乱している。
『そこ行き止まりじゃね?』
『なんか画面バグってない?』
『ノイズひどいぞ』
「え? そうかな?」
スマホを確認するが、電波状況は悪くない。
だが、目の前の光景に違和感を覚えた。
通路の突き当たりにある壁。
そのテクスチャが、まるで古いゲームのように明滅している。
「なんだこれ……壁が、ブレてる?」
俺は恐る恐る手を伸ばした。
『構造理解』のスキルが勝手に発動する。
いつもなら「コンクリート」「魔力岩」といった情報が頭に浮かぶだけだ。
だが、今回は違った。
《 警告:対象座標の衝突判定が存在しません 》
「は?」
衝突判定がない?
俺の手は、そのまま壁の中にズブズブと沈んでいった。
『え』
『は???』
『腕消えたぞ!?』
『放送事故www』
「うわっ、吸い込まれ――!」
俺の体はバランスを崩し、壁の向こう側へと倒れ込んだ。
硬い地面に叩きつけられる衝撃を覚悟して目を閉じる。
だが、衝撃は来なかった。
代わりに、俺は無限に広がる『無』の中に浮いていた。
第二章 デバッグモード
目を開けると、そこは奇妙な空間だった。
上も下もなく、格子状の青いラインが地平線の彼方まで続いている。
空には巨大な文字列が浮かび、流れていた。
`System.Log: User_ID_Ren entered Area_Null.`
`Error: Unauthorized access.`
「どこだ、ここ……」
慌ててスマホを見る。
配信はまだ続いている。
そして、同接数が異常なことになっていた。
『12,000人』
「えっ!? 一万超え!?」
コメント欄が滝のように流れる。
『ここどこ!?』
『CG? これCGだよな?』
『クオリティ高すぎワロタ』
『バズってんぞお前』
『運営に通報した』
俺は震える手でカメラを周囲に向ける。
遠くの方に、見覚えのあるモンスターたちがいた。
ミノタウロス、ドラゴン、ケルベロス。
だが、彼らは動いていない。
まるでフィギュアのように空中に静止し、その頭上には『ID: Enemy_Lv50_Active』というタグが浮いている。
「これ……ダンジョンの裏側か?」
その時、脳内に無機質な声が響いた。
《 デバッグ権限を確認。ユーザー:レンのアクセスレベルを『開発者』に昇格させます 》
「はい?」
視界が一変した。
世界中のあらゆるモノに、詳細なパラメータが表示されている。
静止しているドラゴンのステータスウィンドウがポップアップした。
[ HP: 999999 ]
[ ATK: 50000 ]
[ Behavior: Aggressive ]
そして、そのウィンドウの右上に、小さな『×』ボタンが見えた。
俺は無意識に、その『×』を指で押した。
シュンッ。
巨大なドラゴンが、音もなく消滅した。
『は?』
『え?』
『ドラゴン消えたぞ今』
『コラ? 合成?』
『神運営かよwww』
俺は自分の手を見る。
『構造理解』だと思っていたスキル。
これはただの鑑定じゃなかった。
世界のソースコードを読み、干渉するための『デバッガー』の力だったんだ。
「……これ、もしかして」
俺は別のウィンドウを開く。
そこには『Item Generation(アイテム生成)』の項目があった。
試しに『伝説の聖剣』を選択し、数量を『1』にする。
カラン、と乾いた音を立てて、足元の何もない空間に黄金の剣が落ちた。
『うおおおおおおおお!』
『マジかよ!!!』
『チートじゃん!』
『これBANされるだろwww』
『同接5万行ったぞ!』
富と名声。
喉から手が出るほど欲しかったものが、今、バグとして目の前にある。
俺は生唾を飲み込んだ。
だが、その時。
空間が赤く染まった。
`WARNING: Intruder Detected. Security System Activated.`
空間の裂け目から、純白の鎧を纏った『何か』が現れた。
顔はなく、のっぺらぼう。
背中には六枚の機械的な翼。
「……貴様か。この神聖な演算領域を汚す鼠は」
『管理AI』だ。
そいつが指を鳴らすと、俺の周囲に無数の赤いレーザーサイトが浮かんだ。
「削除(デリート)する」
第三章 世界を書き換える者
「うわあああああ!」
俺は無様に転がり、レーザーの雨を避けた。
着弾した場所のデータが削り取られ、黒い虚無が広がる。
『逃げろレン!』
『死ぬぞ!』
『演出じゃねえのか!?』
「演出なわけあるか! 殺される!」
管理AIは感情のない声で告げる。
「無駄だ。この領域において、私は全能。お前の存在定義ファイルなど、一瞬で書き換えられる」
AIが手をかざす。
俺の体が透け始めた。
足先から感覚がなくなっていく。
《 警告:存在データが破損しています。修復不能 》
「くそっ……終わりかよ……!」
せっかくバズったのに。
これから大逆転できると思ったのに。
視界が滲む。
だが、その時、俺の視界の端に、管理AIのステータスウィンドウが見えた。
[ Name: Administrator_01 ]
[ Status: Invincible (無敵) ]
[ Access Key: Encrypted ]
無敵。
勝てるわけがない。
でも、俺は『デバッガー』だ。
バグを見つけ、修正するのが仕事だ(仕事じゃないけど)。
「……見つけた」
AIの足元。
青いラインのグリッドが一箇所だけ、わずかに歪んでいる。
テクスチャの継ぎ目。
処理落ち。
俺は残った力を振り絞り、その『継ぎ目』に向かって叫んだ。
「おい視聴者! 今からとんでもないことするから、絶対見逃すなよ!」
『何する気だ!?』
『レン行けぇぇぇ!』
俺は全速力で、AIに向かって走った。
自殺行為だ。
AIは嘲笑うように手を振る。
「消えろ」
俺の体が完全に消去される寸前。
俺はAIの攻撃ではなく、足元の『歪み』に滑り込んだ。
そして、持っていたスマホを、その歪みに突き刺す!
「『外部デバイス接続』! 強制上書き!」
俺のスマホには、大量のスパチャとコメントのデータが流れ込み続けている。
膨大なトラフィック。
それを、この世界の『バグ』に流し込んだらどうなる?
《 エラー:処理しきれないデータ量です 》
《 メモリオーバーフロー 》
《 システムダウン 》
管理AIの動きがピタリと止まった。
「な……に……? 私の……演算が……遅延……して……」
「くらえ! これが現代社会の『炎上(DDoS攻撃)』だああああ!!」
俺は凍りついたAIの胸元に飛びつき、その心臓部に表示されたソースコードに指を這わせる。
`Invincible = True`
この文字列を。
`Invincible = False`
に、書き換えた。
「削除されるのは、お前の方だ」
俺は先ほど生成した『伝説の聖剣』を掴み、動けないAIの胸に突き立てた。
第四章 ログアウト
閃光が走り、白い空間が崩壊していく。
管理AIは断末魔も上げずに砕け散り、無数の0と1の数字になって霧散した。
気がつくと、俺は元の新宿ダンジョンの薄暗い通路に立っていた。
手には錆びついたショートソード。
伝説の聖剣も、デバッグウィンドウも消えている。
「……夢、か?」
だが、スマホの画面は現実を映していた。
『うおおおおおおお!』
『勝った!』
『神回確定』
『今の何? 演出?』
『世界救った?』
同接数:580,000人。
チャンネル登録者数:200,000人突破。
俺はへたり込む。
全身が痛い。
だが、生きている。
ふと、スマホの通知欄に、奇妙なメッセージが届いているのに気づいた。
差出人は『Unknown』。
『デバッグ協力、感謝します。報酬として、管理者権限の一部を譲渡しました』
俺の視界の端に、小さなアイコンが表示されている。
それは、さっき見た『Item Generation』のアイコンだった。
ただし、使用制限がかかっている。
『次回アップデートまで使用不可』
俺は空を見上げて笑った。
どうやら、俺の冒険(バグ取り)は、まだ始まったばかりらしい。
「……みんな、スパチャありがとう。今日の配信はここまで。高評価よろしく」
配信終了ボタンを押す。
暗転した画面に映る俺の顔は、もうFランクの負け犬の顔じゃなかった。
(終)