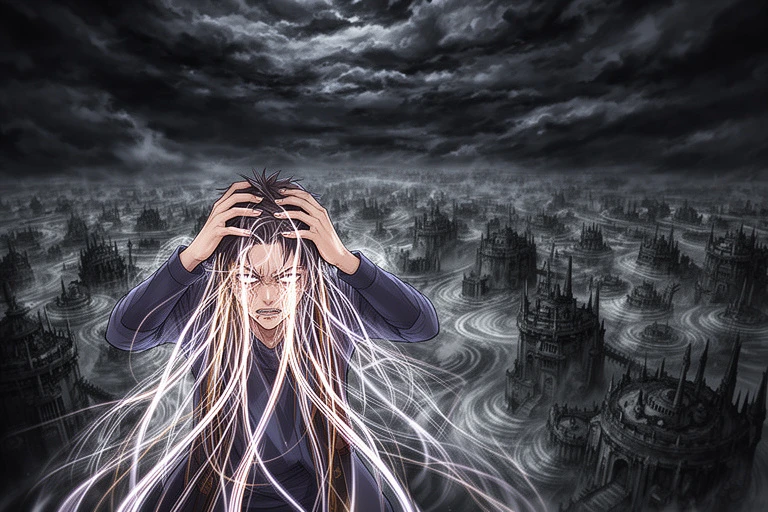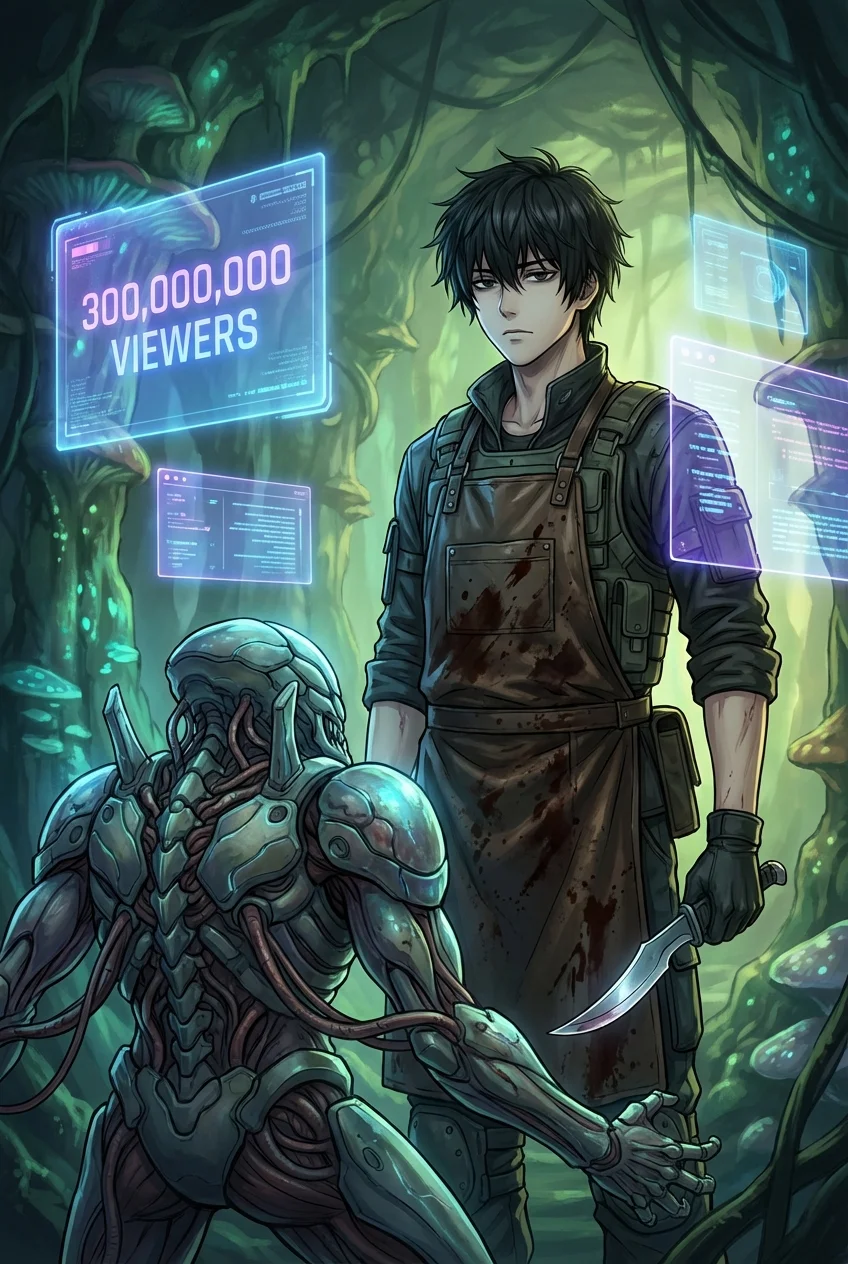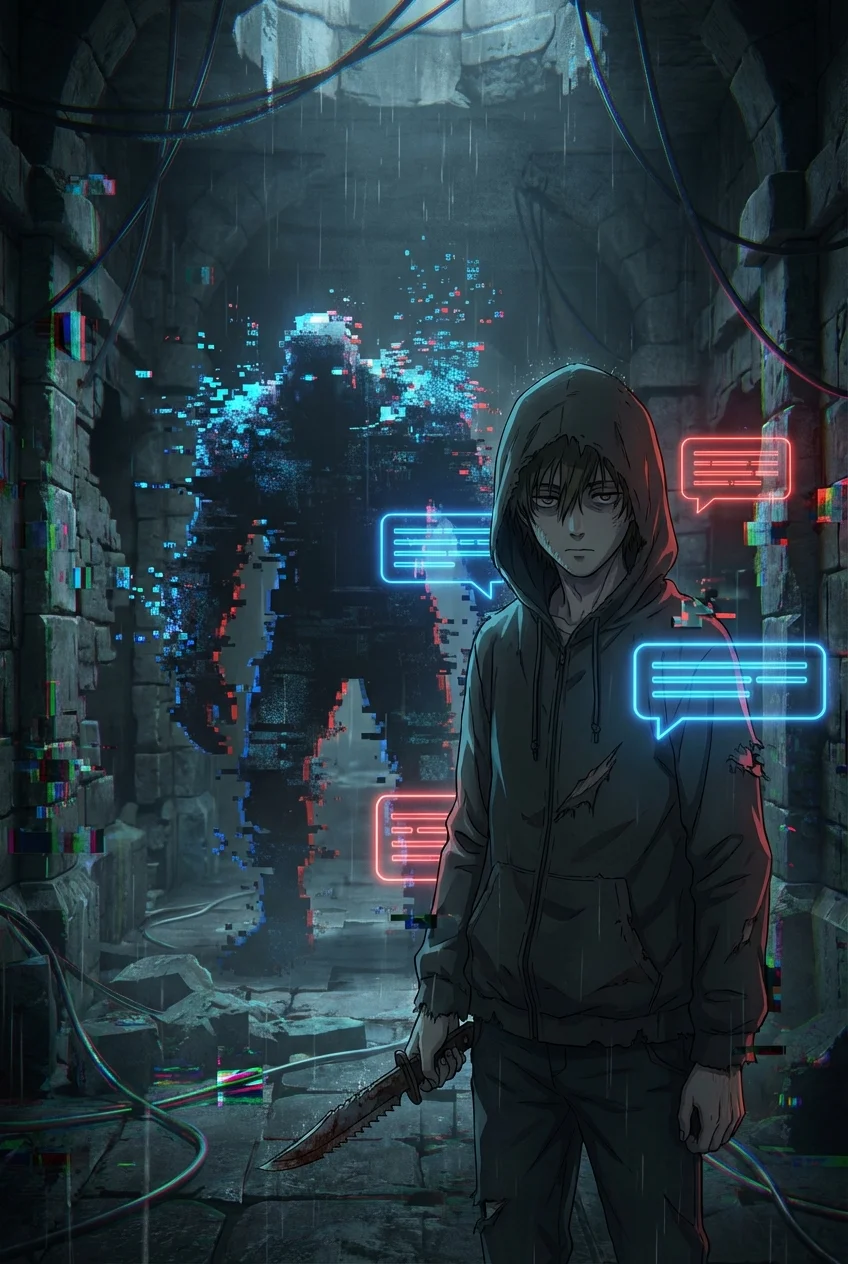第一章 電子の海の聖女
「こんルカ~! 今日もみんなの心を、ルカがいーっぱい癒やしちゃうぞ♡」
マイクに向かって、砂糖を煮詰めたような声を出す。
モニター上のコメント欄が、凄まじい速度で流れた。
『ルカちゃんマジ天使!』
『仕事の疲れが吹き飛ぶわ~』
『スパチャ投げるから名前呼んで!』
画面の中では、銀髪の美少女アバターが鈴を転がすように笑っている。
完璧なアイドル。
完璧な聖女。
けれど、僕――リアムの網膜には、まったく別の映像が焼き付いていた。
ディスプレイのベゼルから、ドロリとした黒い粘液が滲み出している。
それは床に滴り落ち、ジュッ、とカーペットを焦がす幻聴を伴っていた。
「わあ、みんなありがと~! ルカもみんなのこと、だーいすきっ!」
口角を吊り上げる頬が痙攣する。
胃の奥から、熱いものがせり上がってくる。
こみ上げる嘔吐感を、僕は無理やり唾液とともに飲み下した。
視界を埋め尽くす黒い粘液。
その正体は、リスナーたちの「本音」だ。
(チッ、この媚び声ムカつく。でも投げ銭しねーと負けた気がする)
(借金してスパチャしたんだぞ、もっと俺を見ろよ!)
(彼女にバレたら殺されるけど、ルカちゃんだけが俺の理解者だ……)
(その皮を剥いで、中身を犯したい)
文字ではない。
悪意と欲望が凝縮された『泥』となって、僕の足元に溜まっていく。
「う、っ……」
右耳が焼けるように熱い。
ヘッドホンに隠された耳たぶ。そこに突き刺さった青い鉱石の耳飾りが、高熱を発している。
ジジジ、ジジ……。
耳飾りから、不快なノイズが脳髄に直接流れ込んでくる。
それは、かつて僕を追放した異世界の神官たちの嘲笑にも、魔物の断末魔にも聞こえた。
皮膚が焼ける匂いが鼻をつく。
この痛みだけが教えてくれる。
ここは平和な日本じゃない。
形を変えただけの、新たな地獄だと。
「んんっ! ……えっと、きょ、今日はマシュマロ読みのコーナーだよね!」
動揺を悟られまいと、僕は声を張り上げた。
だが、明るく振る舞うほど、部屋の空気が変質していく。
室温が急激に下がった。
吐く息が白い。
それなのに、部屋中には腐った百合の花のような、甘ったるい腐臭が充満し始めた。
「エーテル……」
僕の唇が震える。
この感覚は知っている。
かつての世界で、魔獣が現れる直前に漂う濃密な魔力の澱み。
それが今、六畳一間の安アパートで起きている。
原因は明白だ。
五万人を超える視聴者の欲望が一点に集中し、次元の壁を溶かし始めているのだ。
キィィィィィン!
耳飾りのノイズが、頭蓋骨をきしませるほどの金切り声に変わった。
『もっと……もっと寄越せ……』
ディスプレイの向こうから、無数の青白い手が伸びてくる幻覚が見えた。
嫉妬、執着、独占欲。
それらが僕の喉元に絡みつき、気道を締め上げる。
「かはっ……!」
呼吸ができない。
アバターの動きが止まった。
『ルカちゃん?』
『放送事故?』
『なんかノイズすごくない?』
『顔色が変だぞ(アバターだけど)』
コメント欄がざわつく。
その一文字一文字が、鋭利な刃物となって僕の精神を削り取っていく。
「やめ……ろ……」
拒絶の言葉は、マイクのハウリングにかき消された。
違う。
僕は、ゴミ箱じゃない。
お前たちの汚い欲望を処理するために、この世界に堕とされたわけじゃない!
視界が赤く明滅する。
限界だった。
理性が弾け飛び、本能が鎌首をもたげる。
僕は震える手でマイクを鷲掴みにした。
「……黙りなさい」
その声は、甘ったるいアイドルのものではなかった。
腹の底から響く、冷徹で、絶対的な響き。
かつて数万の信徒を跪かせた、「聖女リアム」の声。
ピタリ、とコメントの流れが止まった。
「聞こえないの? その汚らわしい口を閉じろと言ったんです」
耳飾りが閃光を放った。
青い光が部屋中を奔り、絡みついていた黒い粘液を一瞬で蒸発させる。
ドンッ!
衝撃波がマイクを突き抜け、インターネットという神経網を駆け巡る。
画面の向こうの五万人が、同時に息を呑む気配がした。
恐怖ではない。
もっと根源的な、魂が震えるような畏怖。
僕の意志とは無関係に、アバターの表情が変化する。
作り物の笑顔が消え、冷ややかな、それでいて見る者すべてを射抜くような「聖なる瞳」が、画面の向こうを見下ろしていた。
「さあ、懺悔の時間です。貴方たちの罪を、私が裁いてあげましょう」
やってしまった。
キャラ崩壊どころの話ではない。
完全に放送事故だ。
けれど、僕は画面から目を離せなかった。
止まっていたコメント欄が、爆発的な勢いで流れ出したからだ。
『……っ!?』
『なに今の声』
『ゾクッとした』
『踏んでください』
『ああ、ルカ様……!』
『これが素顔? 最高かよ』
『一生ついていきます』
数字が跳ね上がる。
同接五万人が、六万、七万、十万へと、異常な速度で膨れ上がっていく。
耳飾りの熱が、心地よい温かさに変わっていた。
流れ込んでくるのは、汚泥のような欲望ではない。
もっと純粋で、狂信的な「祈り」。
僕は理解してしまった。
この世界の人々は、ただ癒やされたかったのではない。
圧倒的な何かによって、支配され、救済されたかったのだと。
(……ああ、そうか)
僕はマイクの前で、深く、妖艶に嗤った。
元の世界に戻る必要なんてない。
ここでなら、僕は本当の「神」になれるかもしれない。
アバターの瞳が、青く妖しく輝いた。