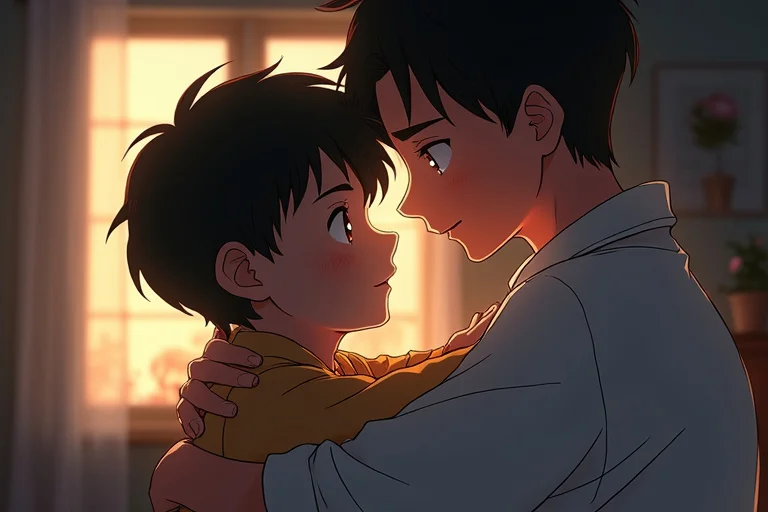第一章 不協和音の遺言
父、桐島聡の三回忌を終えた夜、俺は実家のリビングでひとり、埃をかぶりかけたアップライトピアノの前に座っていた。ピアノ調律師という仕事柄、放っておかれた楽器の沈黙がどうにも気にかかる。鍵盤の蓋をそっと開けると、象牙色の歯並びが月明かりにぼんやりと浮かび上がった。幼い頃、無口な父が唯一、俺の練習を黙って聞いていた場所だ。
指慣らしにショパンのノクターンを弾き始めた瞬間、俺の耳は奇妙な違和感を捉えた。中央のドの音。その響きに、本来あるはずのない微かな「揺らぎ」が混じっている。それは弦の錆やフェルトの摩耗による物理的な劣化とは明らかに異質だった。まるで、正しい音程に寄り添うように、もう一つの音が、ため息のように重なっている。
「……調律が狂ってるな」
独りごちて、何度もその音を確かめる。だが、叩けば叩くほど、その不協和音は意志を持っているかのように、その存在を主張してくる。それは悲しみでも怒りでもなく、ただひたすらに何かを訴えかけているような、切実な響きだった。
翌日、俺は本格的な調律道具を持ち込み、ピアノの解体を始めた。母の泰子は「もう誰も弾かないんだから、そんなに躍起にならなくても」と呆れ顔だ。だが、俺にはこの音の正体を突き止めなければならないという、妙な使命感が湧き上がっていた。
アクション機構を引き出し、ハンマーを調整し、チューニングピンをミリ単位で回していく。金属と木と羊毛が織りなす精密な小宇宙。俺はその秩序の番人だ。しかし、いくら完璧な調律を施しても、あの奇妙な「揺らぎ」は消えなかった。それどころか、俺が触れれば触れるほど、音は表情を変え始めた。ある時は、父が好きだった古いジャズのフレーズの断片のように聞こえ、またある時は、木工職人だった父が工房で木を削る、リズミカルな音を模倣しているかのようだった。
「まさか……」
あり得ない考えが脳裏をよぎる。この音は、父そのものではないのか。生前、父との会話はほとんどなかった。頑固で、不器用で、何を考えているのか全く分からない人だった。俺が調律師になると言った時も、ただ一言「そうか」とだけ。その背中が、肯定しているのか失望しているのか、最後まで分からなかった。
その父が、死してなお、このピアノを通して俺に語りかけている。俺を拒絶していたはずの父が、今になって。その考えは、俺の胸に温かい何かを灯すと同時に、深い混乱をもたらした。父は、一体何を伝えたがっているのだろうか。この不協和音は、父が遺した解けない謎、最後の遺言のように思えた。
第二章 沈黙との対話
それからというもの、俺は仕事の合間を縫って実家に通い、ピアノと向き合う日々を送っていた。それはもはや「調律」ではなかった。俺は父の「音」と対話しようと試みていたのだ。
ピアノの前に座り、静かに鍵盤に指を置く。まず、父の音を聴くことから始める。低い唸りのような響き、すすり泣きのような高音、焦燥感に駆られるようなトレモロ。日によって、時間によって、その音は千変万化だった。まるで、父が生涯で抱え込んだ、言葉にできなかった感情の奔流が、今になって堰を切ったかのように溢れ出してくる。
俺は、その音に応えるように鍵盤を叩いた。父の悲しげな音には、慰めるような優しいアルペジオを。焦りの音には、落ち着かせるような安定した和音を。それはまるで、言葉を知らない生き物と心を通わせるような、根気のいる作業だった。
母は、そんな俺の姿を遠巻きに、心配そうな目で見つめていた。「涼介、あなたは疲れているのよ。お父さんのことは、もう……」
「違うんだ、母さん。父さんはここにいる。このピアノの中に。俺に何かを伝えようとしてるんだ」
母は悲しげに微笑むだけで、それ以上は何も言わなかった。彼女には聞こえていないのだ。俺が調律師として、人より鋭敏な聴覚を持っているからこそ捉えられる、魂の周波数。そう信じていた。
ある雨の降る午後、父の音はひときゆわ激しくなった。嵐のように鍵盤の上を駆け巡る不協和音の連続。それは、耐え難い苦痛の叫びのように聞こえた。俺は必死に、その音を鎮めようと、バッハの平均律クラヴィーア曲集を弾き続けた。数学的な秩序と、神聖なまでの調和を持つ音楽。父の混沌とした音を、その美しい法則の中に包み込もうとした。
数時間弾き続けた頃だろうか。嵐は、不意に凪いだ。そして、ピアノから一つの澄んだ音が響いた。それは、今まで聞いたことのない、穏やかで、どこか懐かしい響きだった。赤ん坊が初めて発する、純粋な産声のような音。その音が響いた瞬間、父の苦しげな不協和音は、ピタリと止んだ。
俺は呆然とした。今の音は何だったんだ? 父の音とは明らかに違う、もう一つの音。そして、なぜ父の音は、この音が現れた途端に沈黙したのか。
まるで、ずっと探し続けていた何かを見つけた安堵と、それを邪魔してはいけないという配慮が入り混じったような、静寂。父の音は消えたわけではない。ただ、息を潜めて、その新しい音に耳を澄ませている。そんな気配だけが、部屋の空気の中に満ちていた。謎は解けるどころか、さらに深い迷宮へと俺を誘い込もうとしていた。
第三章 二つのレクイエム
その夜、俺は母に昼間の出来事を話した。父の音とは違う、赤ん坊の産声のような、澄んだ音のことを。俺の話を聞き終えた母は、ゆっくりと立ち上がり、押し入れの奥から古びた桐の箱を持ってきた。
「ずっと、あなたに話さなければならないと思っていたわ」
母は震える手で箱を開けた。中には、小さな産着と、一枚の写真が入っていた。そこには、赤ん坊を抱いて、ぎこちなくも幸せそうに微笑む、若い頃の父と母が写っていた。だが、その赤ん坊は俺ではない。俺が生まれるよりも、ずっと前の写真だ。
「この子は、樹(いつき)。あなたの、お兄さんよ」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。兄がいた? 一度も、そんな話は聞いたことがなかった。
母は、ぽつりぽつりと語り始めた。樹は、俺が生まれる二年前に、生後わずか半年で、突然の病でこの世を去ったという。子供を失った悲しみは、父から言葉を奪った。木工職人として、命を吹き込む仕事をしていた父にとって、我が子の命を救えなかった無力感は、どれほど深かっただろうか。
「あの人は、涼介が生まれてからも、ずっと苦しんでいた。あなたを愛せば愛すほど、樹への罪悪感が募るようだった。あなたの成長を喜ぶことが、樹を忘れることのように感じてしまったのね。だから、あなたとどう接していいか分からなくなってしまった。あの人の沈黙は……樹への弔いであり、あなたへの不器用な愛情の形だったのよ」
俺は、言葉を失った。父の無関心だと思っていたあの背中は、二人の息子への愛と罪悪感の狭間で、ただ一人、磔にされていたのだ。
「ピアノの音……私にも、ずっと聞こえていたわ」と、母は涙を浮かべた。「お父さんの、苦しい音。そして、時々聞こえる、樹の穏やかな音も。お父さんは、あなたの鋭い耳が、いつか樹の音に気づいてくれると信じていたのかもしれない。でも、自分の苦しみが、樹の静かな音をかき消してしまうことを恐れてもいた。だから、あんな不協和音を奏で続けていたのよ。樹の存在を知らせたい、でも自分の悲しみで覆ってはいけない……その葛藤が、あの音だったの」
全てが繋がった。父が奏でていた不協和音は、単なる苦しみではなかった。それは、先に逝った息子へのレクイエムと、残された息子へのラブソングがぶつかり合って生まれた、悲しくも美しい旋律だったのだ。父は、二人の息子を、たった一人で、その胸の中で愛し続けていた。
俺の頬を、熱い涙が伝っていく。今まで父に対して抱いていた、わだかまりや誤解が、雪のように溶けていく。知らなかった。何も、分かっていなかった。家族とは、目に見えるもの、聞こえる言葉だけが全てではない。その沈黙の裏には、これほどまでに深く、複雑な愛の歴史が刻まれていたのだ。
第四章 新しい和音
翌朝、俺は朝日が差し込むリビングで、再びピアノの前に座った。もう、迷いはなかった。やるべきことは、分かっている。
そっと鍵盤に触れる。すると、今まで聞こえていた父の苦しげな不協和音が、嘘のように静まっているのを感じた。代わりに、穏やかで澄み切った、兄・樹の音が、小さな光の粒のように空間を漂っている。父は、俺が真実に辿り着いたことを知り、役目を終えたかのように、静かにその音を兄に譲ったのだ。
俺は、ゆっくりと指を動かし始めた。
まず、兄の澄んだ音を拾い上げるように、優しいメロディを奏でる。会ったことのない兄へ。はじめまして、涼介だよ。あなたの存在を、今、確かに感じている。
次に、そのメロディに寄り添うように、低音で重厚な和音を重ねていく。それは、父が奏でていた不協和音の核にあった、深く、静かな愛情を表現した和音だ。父さん、聞こえるかい。あなたの愛は、ちゃんと俺たち二人に届いていたよ。もう、苦しまなくていいんだ。
そして最後に、俺自身の音を、その二つの旋律の上に重ねた。それは、調律師として培ってきた、正確で、けれど温かみのある音。過去への感謝と、未来への希望を込めた、俺自身の決意の音だ。
三つの音が、リビングの中で溶け合っていく。死者の音と、生者の音。過去の記憶と、現在の想い。それらは互いを打ち消すことなく、むしろ互いを引き立て合い、一つの完璧なハーモニーを奏で始めた。それは、俺たち家族だけの、新しい和音だった。
母が、いつの間にか俺の隣に立ち、その演奏に静かに耳を傾けていた。その目には涙が浮かんでいたが、表情は晴れやかだった。
演奏を終えた時、ピアノは完全に沈黙していた。だが、それは空虚な静寂ではなかった。全ての音が満ち足りて、調和の中に溶け込んだ、満ち足りた静けさだった。もう、父の不協和音も、兄の微かな音も聞こえない。けれど、俺には分かった。彼らはいなくなったわけじゃない。この家の空気の中に、俺たちの心の中に、美しい和音として、永遠に響き続けるのだ。
俺はピアノの調律師だ。だが、今日、俺が調律したのは楽器ではなかった。父が遺した音の家系図を紐解き、断絶していた家族の魂を、もう一度調和させたのだ。この家は、これからも様々な音を奏でていくだろう。喜びの音、悲しみの音。そのすべてを、俺は受け止め、美しい和音へと調律していく。それが、父と兄が俺に託した、新しい役目なのだから。
窓の外では、新しい一日が始まろうとしていた。その光は、まるで未来を祝福するプレリュードのように、部屋の中を優しく照らしていた。