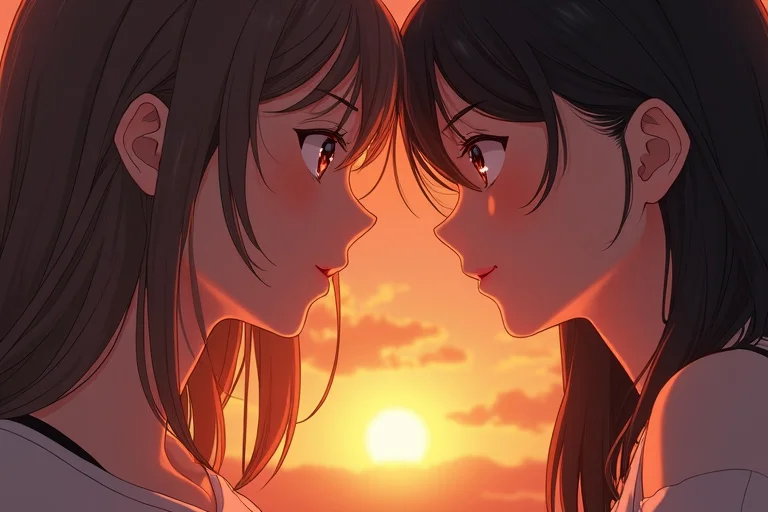第一章 亡霊のグラインド
父が死んでから、一年が経った。家の中には、父が吸っていたタバコの匂いのかわりに、消臭剤のクリーンな香りが満ちている。母が、父の痕跡を消すかのように、毎日律儀にスプレーを撒いているからだ。僕、水島健太は、その無機質な香りが息苦しくて、よく自室の窓を開けた。
父、雄一郎は、言葉数の少ない人だった。だが、その無口な背中は、僕にとって世界の中心を示す灯台のような存在だった。その灯台が消えてしまい、僕と母、美咲が乗る小舟は、静かな凪の中をただ漂っているようだった。母は気丈に笑う。けれど、その笑顔の下には、僕と同じ、あるいはそれ以上の深い喪失感が澱んでいるのを、僕は知っていた。
ある土曜の午後、母に頼まれて父の書斎を整理していた。本棚の奥、手垢で黒光りする革の辞典の影に、それはひっそりと置かれていた。木製のボディを持つ、アンティークのコーヒーミル。父が若い頃に蚤の市で手に入れ、毎朝、僕たちのために豆を挽いていたものだ。最近は電動ミルばかり使っていたから、すっかりその存在を忘れていた。
手に取ると、ずしりとした重みと、ひんやりとした木の感触が伝わってくる。ハンドルを回すと、ゴリ、ゴリ、と懐かしい音がした。空回しの音が、やけに寂しく響く。キッチンからコーヒー豆の袋を持ってきて、数粒、投入口に落としてみた。ゆっくりとハンドルを回す。豆が砕ける硬質な感触が、手に伝わる。
その時だった。
「…………た…………」
ゴリゴリという音に混じって、微かな声が聞こえた気がした。僕は手を止める。しん、と静まり返った書斎に、僕の心臓の音だけが響く。空耳か。もう一度、ハンドルを回す。
ゴリ、ゴリ、ゴリ……「け……ん……た……」
間違いない。雑音にまみれた、掠れた声。だが、その響きは、一年前に永遠に失われたはずの、父の声そのものだった。僕は凍りついた。ミルを握る手に汗が滲む。これは幻聴だ。父を思うあまり、脳が作り出した幻。そう自分に言い聞かせようとしても、耳の奥で反響する声の温かみが、それを許してくれなかった。
父は、このコーヒーミルの中にいる。
荒唐無稽な考えが、確信となって僕の心を鷲掴みにした。僕たちの家族の時間は、まだ終わっていなかったのだ。
第二章 孤独な対話
それから僕の日課は変わった。毎朝、誰よりも早く起き、キッチンの隅で父のミルと向き合う。豆を数粒入れ、ゆっくり、ゆっくりとハンドルを回す。それが、父との対話の時間だった。
「父さん、おはよう」
ゴリ、ゴリ……「……お……う……」
「今日の講義、気が重いんだ。プレゼンがあって」
ゴリ、ゴリ、ゴリ……「……だ……じょ……ぶ……だ……」
声はいつも途切れ途切れで、ノイズにまみれていた。それでも、僕にははっきりと父の言葉が聞こえた。生前、僕が落ち込んでいると、いつも背中を叩いて言ってくれた「大丈夫だ」。その一言が、ミルの無機質な音の向こうから聞こえてくるだけで、不思議と力が湧いてきた。僕は、自分だけの秘密の儀式に夢中になった。
しかし、僕の変化は、母との間に見えない壁を作り始めていた。
「健太、最近、朝が早いのね」
ある日、キッチンに入ってきた母が、僕の背中に声をかけた。僕は咄嗟にミルを隠すように身体を動かした。
「ああ、ちょっと……目が覚めて」
「またその古いのを使ってるのね。電動の方が楽なのに」
母の目は、僕が握りしめているミルを、どこか悲しげに見つめていた。その視線に耐えられず、僕は目を逸らした。
母は僕が、父の死から立ち直れずに、遺品に執着しているのだと思っている。違うんだ、母さん。父さんはここにいる。そう叫びたかったが、狂人扱いされるのが怖くて、言葉を飲み込んだ。僕と父だけの秘密。その甘美な響きは、同時に僕を現実の家族から引き離していく孤独の呪文でもあった。
次第に、僕は大学の友人との付き合いも疎かになり、一人でいる時間が増えた。僕には父さんがいる。他の誰もいなくてもいい。そんな歪んだ万能感が、僕の心を蝕んでいった。挽きたてのコーヒーの香りが満ちるキッチンで、僕は生きている母ではなく、物言わぬミルの中にいるはずの父の幻影とだけ、向き合っていた。
第三章 からくりの告白
季節が移り、冷たい雨が窓を叩く夜だった。激しい雷鳴が轟き、家が揺れた。その音で目を覚ました僕は、階下から微かな呻き声が聞こえるのに気づいた。慌ててリビングへ向かうと、ソファのそばで母が倒れていた。
「母さん! しっかりして!」
呼びかけても、母の目は虚ろで、額には脂汗が滲んでいる。過労と心労が重なったのだろう。救急車を呼ばなければ。頭では分かっているのに、身体が震えて動かない。パニックに陥った僕が、無意識に助けを求めたのは、いつもそばに置いていた父のミルだった。
「父さん! どうしよう、母さんが!」
僕は狂ったようにミルのハンドルを回した。ゴリゴリ、ゴリゴリ! 激しい音だけが響き、期待していた父の声はどこからも聞こえてこない。ただの、無慈悲な機械音。嵐の音と混じり合い、僕の不安を増幅させる。
「なんでだよ! 応えてくれよ、父さん!」
その時、倒れていた母が、か細い声で何かを呟いた。
「……あなたのお父さん……あのミルに……」
僕は母の口元に耳を寄せる。
「……健太が……落ち込んだ時のためにって……自分の声を……たくさん……録音して……小さな……装置を……」
雷光が窓を照らし、母の顔を白く浮かび上がらせた。その言葉の意味を理解した瞬間、僕の頭を鈍器で殴られたような衝撃が走った。
録音? 装置?
これは、父の魂なんかじゃなかったのか?
震える手でミルをひっくり返す。底の蓋を爪でこじ開けると、そこには、父の不器用なハンダ付けの跡が残る、指先ほどの小さな電子基板と、マイクロSDカードのスロットが埋め込まれていた。衝撃や回転を感知して、ランダムに録音された音声を再生する、単純なからくり。機械いじりが得意だった父が遺した、最後のプレゼント。いや、最後の悪戯だった。
「大丈夫だ」「頑張れ」「お前ならできる」。それらはすべて、父が生前に吹き込んでおいた、未来の僕へのメッセージだったのだ。父の亡霊との対話だと思い込んでいた時間は、ただの録音された音声を聞いていただけだった。
僕は愕然とした。同時に、母はずっとこの事実を知っていたのだと悟った。僕が毎朝ミルと「対話」する姿を、どんな想いで見ていたのだろう。息子の奇行を止めもせず、ただ静かに見守っていた母の深い愛情と、その胸の内にあったであろう計り知れない悲しみに思い至り、涙が溢れて止まらなくなった。僕が向き合うべきだったのは、このミルではなく、同じ痛みを抱えて隣にいた、母だったのだ。
第四章 夜明けのコーヒー
救急車で運ばれた母は、幸いにも大事には至らず、翌日には退院することができた。家に帰ってきた母は、少し痩せたように見えたが、その表情はどこか晴れやかだった。
僕は、キッチンのテーブルで、母と向かい合って座った。そして、昨夜のことから、ミルにまつわる僕の愚かな思い込みまで、全てを話した。母は、僕の話を黙って聞いていた。
「ごめんなさい、母さん。俺、ずっと……」
「いいのよ」
母は僕の言葉を遮り、優しく微笑んだ。「あなたのお父さんは、本当にあなたのことが心配だったの。自分が死んだ後、健太が塞ぎ込んでしまわないかって。だから、あんなものを遺して……。でも、あなたが毎朝、あんなに真剣にミルと話しているのを見て、本当のことを言うタイミングを失ってしまったの。ごめんなさいね」
母もまた、僕を傷つけることを恐れていたのだ。僕たちは、互いを思いやるあまり、すれ違っていた。父の死が作った溝は、父が遺した愛のからくりによって、ようやく埋まろうとしていた。
翌朝、僕は母のためにコーヒーを淹れた。父のミルで、豆を挽く。ゴリ、ゴリ、という音は、もう父の声には聞こえない。それはただの、豆が砕ける音だ。しかし、その無機質な音と、立ち上る豊かな香りは、以前よりもずっと雄弁に、父の温かい愛情を僕に伝えてくれた。
「いい香りね」
母が微笑む。
「うん。父さんのコーヒーの味、覚えてる?」
「もちろんよ。少し酸味が強くて、でも後味は優しくて……あなたのお父さんみたいだったわ」
カップに注がれた黒い液体は、湯気と共に父の思い出を立ち上らせる。僕たちは、父の不在を嘆くのではなく、父との思い出を語り合いながら、そのコーヒーを飲んだ。
父はミルの中にはいなかった。でも、父の愛は、確かにそこにあった。そして、僕の隣には、その愛を分かち合える母がいる。父が本当に望んでいたのは、僕が過去の幻影に囚われることではなく、こうして残された者同士で支え合い、未来へ向かって歩いていくことだったのだろう。
窓から差し込む朝の光が、二つのコーヒーカップを優しく照らしていた。