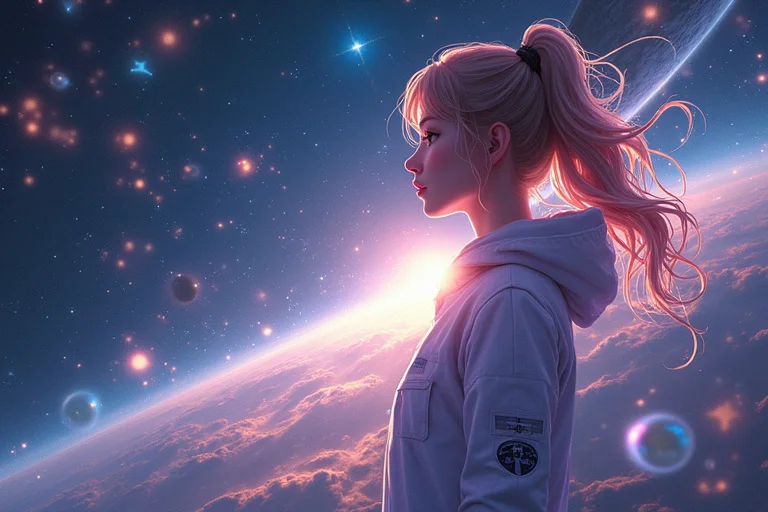第一章 色褪せる世界
俺には、世界が常に色彩の奔流として見えていた。人が触れた本の頁には思考の残滓が琥珀色に揺らめき、交わされた言葉は空気中に淡い銀の軌跡を描く。あらゆる情報に宿る『残響(レゾナンス)』。それが、俺の目に映る世界の真の姿だった。
しかし最近、その色が急速に失われつつある。
市場の喧騒の中、人々は空を指して首を傾げていた。「あの色、なんて言ったかしら」「さあ……ただ、空の色、だろう?」。彼らの言葉が、灰色がかった靄となって霧散する。俺の目には、彼らが失った概念――『青』の残響が、悲しいほど鮮やかな瑠璃色の粒子となって宙を漂っているのが見えた。
衝動的に、その瑠璃色に手を伸ばす。粒子が左腕に触れた瞬間、吸い込まれるように肌へと同化していく。脳裏に、抜けるような夏空の記憶、深い海の静寂、誰かが愛した青い瞳の面影が流れ込んできた。そして、代償のように左腕の輪郭がまた少し、向こうの景色が透けるほどに薄くなる。情報の密度が、俺自身の存在を侵食していくのだ。
その時、世界がぐにゃりと歪んだ。遠くの時計塔がゼリーのようにしなり、地面が波打つ。人々が短い悲鳴を上げ、その場にうずくまる。周期的な世界の異常――『揺らぎの時』。だが、その周期は明らかに短くなっている。世界からまた一つ、大切な色が剥がれ落ちていく予感が、俺の透けた腕に冷たい痺れを走らせた。
第二章 共鳴石の囁き
世界の歪みを正す術を探して、俺は埃と古紙の匂いが満ちる中央図書館の最奥にいた。人々が忘れ去った伝承や、意味を失った古文書の中に、何かしらの手がかりがあるはずだと信じて。
「あなたも、『情報崩壊』について?」
不意にかけられた声に振り向くと、一人の女性が立っていた。ユナと名乗った彼女は、この図書館の司書で、古代史の研究者だという。その瞳には、世界の異変を憂う知的な光が宿っていた。彼女の手には、鈍く黒光りする掌大の石が握られている。
「これは『共鳴石』。古代の遺物よ。言い伝えでは、世界の調律が乱れた時に、道を示すとか……」
ユナがそう言って石を差し出した瞬間、石が脈動するように淡い光を放ち始めた。俺の存在に、俺がその身に宿した『残響』に、呼応しているのだ。
「触ってみて」
促されるまま、透けた指先でそっと石に触れる。その瞬間、温かい光と共に、金色の残響が奔流となって流れ込んできた。それは、とうの昔に世界から消え去ったはずの、ある王国の祝いの歌だった。歓喜に満ちたメロディ、人々の笑い声、祝福の言葉。指先がさらに透けていく感覚と引き換えに、失われたはずの音楽が、俺の中で再び鳴り響いていた。
第三章 透ける存在証明
ユナと共に、俺たちは共鳴石の謎を追い始めた。石の表面に刻まれた微細な模様。それは、今は誰も読むことのできない、消滅した古代の文字だった。
「解読できそう。もう少し……もう少し時間があれば」
ユナは日に日に憔悴しながらも、古文書の山と向き合い続けた。彼女の横顔を照らすランプの光が、橙色の穏やかな残響を放っている。俺はその色に触れたい衝動を必死に抑えた。彼女との時間が、俺の存在をさらに希薄にしてしまうことが怖かった。
次の『揺らぎの時』は、予兆もなく訪れた。図書館の窓の外で、街並みが蜃気楼のように揺らめき、建物のいくつかが砂のように崩れていく。人々がパニックに陥る中、俺はそれ以上に恐ろしいものを見ていた。人々の心から、鮮やかなピンク色の残響――『愛しい』という感情の核が、糸が切れたように霧散し始めているのを。
「やめろ……!」
俺は叫び、両手を広げて街へ飛び出した。母親が子供を抱く温もり、恋人たちが交わす眼差し、友への信頼。それらの残響を、失ってたまるものか。必死にかき集めたピンク色の光は、俺の胸に吸い込まれていく。心臓のあたりが熱を失い、自分の肋骨が透けて見えるのが分かった。激しい痛みと、奇妙な充足感が俺を襲う。俺だけが、この世界から零れ落ちるものを、繋ぎ止められる。その確信が、絶望と共に胸を満たした。
第四章 アンカーの真実
「……分かったわ、カイ」
数日後、疲れ切った表情のユナが、一枚の羊皮紙を俺の前に広げた。彼女が解読した共鳴石の文面だ。その内容は、俺たちの想像を遥かに超えていた。
この世界は元々、形を持たない情報の混沌だった。それを安定させ、物理法則という『輪郭』を与えたのは、自らの存在を捧げた最初の『アンカー』だったという。
「アンカーは、世界の情報をその身に留め、定着させる楔。でも、その力は永続じゃない。永い時を経て力が弱まると、世界は再び混沌に還ろうとする。それが『情報崩壊』の正体よ」
ユナの声が震えていた。
「共鳴石は……次のアンカーを探すためのもの。情報の残響を、その存在に同化させられる、特別な資質を持つ者を……」
彼女の言葉が、途切れる。その視線が、俺の透けた胸と左腕に注がれていた。俺が、新たなアンカー。その言葉の意味を理解した瞬間、全身の血が凍るような感覚に襲われた。アンカーになるということは、自身が楔となり、世界に溶けて消えるということだ。
「そんなの、駄目よ……。あなたがいなくなってしまったら……!」
ユナの瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。その涙は、悲しみの色を宿した、水晶のような残響となって床に染みを作った。
第五章 色彩の決断
空が、鉛を溶かしたような灰色に染まっていた。観測史上最大級の『揺らぎの時』が、世界全体を包み込もうとしている。遠くで地響きが鳴り、空間そのものが軋む音が聞こえる。世界の終わりが、すぐそこまで来ていた。
俺が崩壊の中心地へ向かおうとすると、ユナが俺の腕を掴んだ。その手は小さく、震えていた。
「行かないで、カイ。あなたがいなくなったら、世界が救われたって意味がない……!」
彼女の悲痛な声が、俺の心を締め付ける。俺は、ほとんど透けてしまった右手で、そっと彼女の頬に触れた。肌の温かさを、もうほとんど感じることができない。
「俺が消えても、俺が見た色は、君たちの世界に残る。この空の青も、祝いの歌も、人を愛しいと思う心も。……君が忘れないでいてくれるなら、俺はそこにいる」
ユナの手に、光を失った共鳴石を握らせる。俺が取り込んだ残響の一部、彼女と過ごした日々の琥珀色の記憶を、そこに込めて。
「さよなら、ユナ」
振り返らずに、俺は歩き出した。背後で、彼女の嗚咽が聞こえた。その音さえも、俺にとっては守るべき、美しい世界の残響だった。
第六章 世界を編む色
崩壊の中心は、色彩の地獄だった。あらゆる情報がその形を失い、混沌とした色の渦となって、中心に開いた虚無の穴へと吸い込まれていく。世界の記憶そのものが、悲鳴を上げていた。
もう迷いはなかった。
俺は渦の中心へと、その身を投じた。
瞬間、俺の体を構成していた全ての残響が解放される。左腕に宿した、どこまでも広がる空の『青』。指先に宿した、心を震わせる音楽の『金』。胸に抱いた、誰かを想う心の『ピンク』。そして、ユナと過ごした日々の、温かい記憶の『琥珀色』。
俺という存在の輪郭が完全に消え失せ、無数の光の粒子となる。その一つ一つが、消えゆくはずだった情報と結びつき、新たな法則として世界に編み込まれていく。意識が薄れゆく中、俺は最後に見た。灰色だった世界が、鮮やかな色彩を取り戻していく美しい光景を。
ああ、これでいい。俺は、この色たちを、愛していたのだから。
第七章 君の見る空に
『揺らぎの時』は、終わった。世界は嘘のように穏やかな姿を取り戻し、人々は失いかけた全てを、まるで一度も失ったことなどなかったかのように、当たり前に享受している。
中央図書館の窓辺で、ユナは空を見上げていた。そこには、カイが守った、深く澄み渡る青が広がっている。
彼女は、掌で冷たくなった共鳴石を強く握りしめた。もう光ることも、囁くこともない、ただの石。けれど、確かに彼の温もりが残っている気がした。
ふと、優しい風が彼女の髪を撫でた。その風に乗り、陽光を弾いてきらきらと輝く、微かな琥珀色の光の粒子が舞っているのが見えた。まるで、彼がそこにいると、そう告げているかのように。
世界は救われた。カイという青年がいたことを、彼の孤独を、その決断を知っているのは、もうユナ一人だけ。
彼の存在は消えた。だが、彼が愛した世界の色は、今も、そしてこれからも、世界の至る所で静かに、そして力強く輝き続けている。ユナが見上げる空の、その青さの中に。