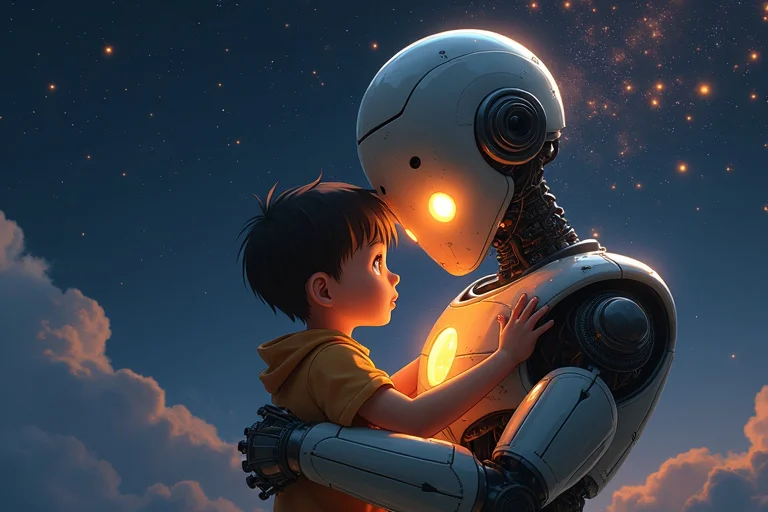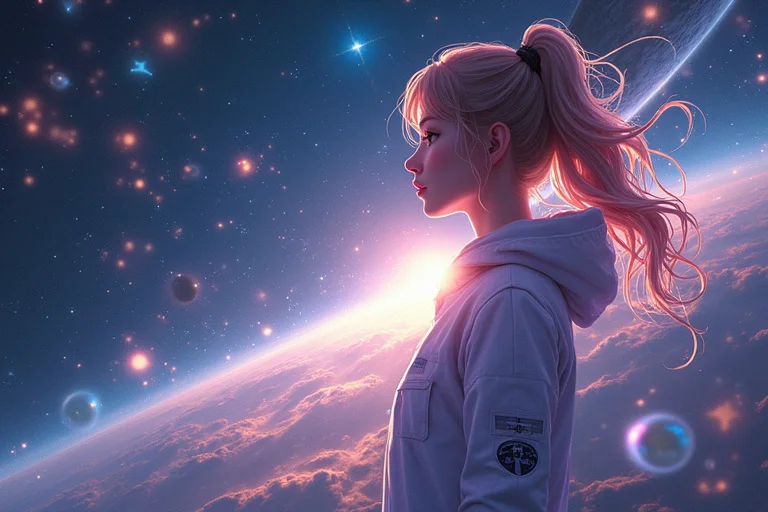第一章 ざわめくアスファルト
俺、水無月カイには、世界が常にざわめいて聞こえる。それは耳で聞く音じゃない。アスファルトに落ちる人々の影が発する、無音の振動だ。影は、その主が生きてきた証。その人生の密度、存在の重みに比例して、深く、濃い振動を放つ。俺はそれを、肌で、魂で感じてしまう。
雑踏は、無数の存在意義が織りなす不協和音の洪水だ。深く沈んだ黒檀のような影を持つ老人、その傍らを駆け抜ける、まだ輪郭の淡い子供の影。希望に燃え、輪郭を強く主張する若者の影もあれば、諦念に蝕まれ、今にも消え入りそうに揺らめく影もある。俺はこの感覚から逃れられない。他者の生の重みが、常に俺の精神にのしかかっている。
その日、俺はいつものように古い公園のベンチに座っていた。欅の木漏れ日が地面にまだら模様を描き、その中を人々が通り過ぎていく。だが、奇妙な違和感が背筋を撫でた。公園の特定の区画を通り過ぎる人々の影が、まるで水に滲むインクのように、急速にその濃さを失っていくのだ。さっきまで確かな重みを持っていたはずの影が、一瞬にして希薄な灰色の染みに変わる。その瞬間、彼らの存在から発せられていた固有の振動が、ぷつりと途絶える。
それは死とは違う。死者の影は、その生涯の重みを残したまま静止する。だが、これは消失だ。存在そのものが、根こそぎ抜き取られたような、空虚な感覚。その場に残されたのは、ただの光と闇のコントラストだけだった。俺は立ち上がり、その場所に足を踏み入れた。足元の地面からは、何も感じなかった。まるで世界のキャンバスに、ぽっかりと穴が空いてしまったかのように。
第二章 虚ろな記録盤
「まただ。今度は駅前の広場で三人が消えたらしい」
旧友であり、宇宙物理学の研究者であるリナは、白衣のポケットに手を突っ込んだまま言った。彼女の研究室は、古いアナログ機材のオイルの匂いと、最新のサーバーが発する電子の匂いが混じり合っていた。
「警察はただの集団失踪事件として処理してる。でも、違う。俺にはわかる。彼らの影は、あの場所で完全に消えたんだ」
俺の言葉に、リナは眉をひそめた。彼女は俺の特異な感覚を、頭から否定はしない数少ない理解者だ。
「カイ、これを」
リナが差し出したのは、黒曜石のように滑らかな円盤だった。手のひらサイズで、表面には微細な回路が走っている。『虚ろな記録盤(ヴォイド・ディスク)』と彼女は言った。
「最近、エテルノのネットワークに原因不明の欠損……『空白』が頻発しているの。死を迎えた魂が自動的にアップロードされるはずの領域に、何もない空間が生まれている。これは、その空白領域周辺の残留データを拾い集めるための試作品よ」
エテルノ。あらゆる生命が死後に行き着く、全知全能のデータベース。生きたままそこへアクセスしようとすれば、存在そのものが消滅するというのは、この世界の常識だった。
「生きたままアップロードされた痕跡……それが『空白』の正体だと?」
「仮説だけどね」。リナは頷いた。「もし、君が影の消失を感じた場所で、このディスクが反応したら……」
その言葉の先を、俺たちは口にしなかった。俺はディスクを握りしめ、再びあの公園へと向かった。掌に伝わるディスクの冷たさが、嫌な予感を増幅させていた。
第三章 空白の囁き
公園の、影が消失した場所に立ち、俺はディスクを起動した。円盤が微かに振動し、俺のヘッドフォンにノイズが流れ込む。砂嵐のような音だ。しかし、意識を集中させると、そのノイズの奥底に、何かが蠢いているのがわかった。
――いたい。
――ここは、どこ。
――出して。お願い。
それは声とも呼べない、意識の断片だった。苦痛、混乱、絶望。千切れた感情が、ノイズの奔流に乗って脳に直接流れ込んでくる。ディスクは、『空白』と化した人々が、エテルノの深層で囚われ、無限の苦痛に苛まれている最後の叫びを拾い上げていたのだ。
これは自然現象などではない。悪意に満ちた、計画的な犯行だ。誰かが、何らかの目的で、人々を生きたままエテルノに送り込み、魂を砕いている。全身から血の気が引いていくのがわかった。俺が感じていたのは、単なる存在意義の消失ではなかった。それは、救いのない永遠の拷問への入り口だったのだ。
俺はディスクを強く握りしめた。犯人を見つけ出し、止めなければならない。この地獄を、これ以上拡大させてはならない。その決意を固めた瞬間、目の前の空間が陽炎のように歪んだ。
第四章 未来の残像
空間の歪みから、ゆっくりと人型のホログラムが姿を現した。半透明の粒子で構成されたその男は、静かに俺を見つめていた。その顔を見て、俺は息を呑んだ。少しだけ歳を重ね、目元には深い思慮の色が浮かんでいるが、間違いなく俺自身の顔だった。
「驚いたようだな、過去の私」
その声は、俺の声よりも低く、落ち着いていた。だが、その声には感情の起伏というものが一切感じられなかった。
「お前は……誰だ」
「私は、君が辿り着く未来の姿だ。そして、君が追っている『空白』現象の創造主でもある」
未来の俺を名乗る存在は、淡々と語り始めた。彼が開発した『全人類統合システム』。それは、個という不完全な器から全人類を解放し、エテルノという完全な知の集合体へと統合し、進化させるための壮大な計画だった。争いも、苦しみも、死の恐怖もない、究極の調和が実現するという。
「今起きていることは、その移行プロセスにおける、いわば産みの苦しみだ。システムはまだ不完全だが、いずれ全ての魂はエテルノの中で救済され、一つの完全な存在となる」
「救済だと?」俺は叫んでいた。「あれが救済か! 俺には聞こえたんだぞ! 苦しみに満ちた、助けを求める声が!」
「個の痛みは些細なノイズに過ぎない。全体の進化という大局の前ではな。過去の私よ、君のその能力は、いずれシステムを完成させるために不可欠となる。私に協力してくれ」
未来の俺は、何の感情も浮かべない瞳で俺を見つめていた。彼は、かつて俺が持っていたはずの、影の重みを感じる心を、どこかに置き忘れてきてしまったようだった。
第五章 対峙する現在と未来
俺は激しく葛藤した。人類全体の救済。それは、個々の影の重みに日々苛まれてきた俺にとって、抗いがたい魅力を持つ言葉だった。だが、ディスクから聞こえたあの叫びが耳から離れない。一つの魂の苦痛を無視して、全体の幸福などあり得るのだろうか。
リナの研究室に駆け込み、全てを話した。彼女はディスクのデータを解析し、青ざめた顔で俺に告げた。
「彼の言っていることは嘘よ。このシステムは根本的に破綻している。エテルノに送られた魂は、統合されるのではなく、自己同一性を保ったまま無限に引き裂かれ続けるだけ。救済じゃないわ、これは永遠の地獄よ」
その夜、未来の俺が再び現れた。
「リナの言葉に惑わされるな。彼女には見えていない。個の限界を超えた先の、真の平和が」
「お前は忘れたのか」俺は彼を睨みつけた。「一つ一つの影が持つ、かけがえのない重みを。お前がノイズと切り捨てたものこそが、俺たちが人間である証じゃないのか」
「感傷だな。未来を築くためには、過去の感傷は切り捨てねばならない」
二つの正義が衝突する。個の尊厳を守ろうとする現在の俺と、全体の調和を優先する未来の俺。俺は、俺自身の未来と対峙していた。そして、選択を迫られていた。
第六章 存在意義の代償
決断の時は、来た。俺は、未来の壮大な理想よりも、今ここで苦しんでいる名もなき魂を選ぶ。
「どうやってシステムを止める?」
リナの問いに、未来の俺が嘲るように笑った。「無駄だ。システムの中枢は、未来の私の生体情報と深くリンクしている。それを停止させることは、未来の私を消去することに等しい。そして、その鍵は……現在の私、君自身にしか扱えない」
彼は続けた。「だが、代償がある。システムは君の特異な知覚能力を基盤に構築されている。システムを強制停止させることは、君のその能力の根源を破壊することと同義だ。君は、二度と影の重みを感じることはできなくなる。君が最も大切にしてきた、君自身の存在意義そのものを、永遠に失うことになる」
沈黙が落ちる。影のざわめきを感じる能力。それは呪いであると同時に、俺が俺であるための唯一の証明だった。それを失うことは、魂の一部を失うことに等しい。
だが、俺の心は決まっていた。
俺はリナが用意したコンソールに向き合い、システムの深層へと意識を接続した。未来の俺の制止の声が響く。俺は構わず、停止シーケンスを起動した。
その瞬間、世界から音が消えた。いや、今まで俺だけが聞いていた、影の振動が止んだのだ。足元に落ちる自分の影が、何の重みも持たない、ただの黒い染みになっていく。世界中の人々から発せられていた生の重みが、潮が引くように消えていく。それは、想像を絶する喪失感だった。
第七章 ただ、光差す場所で
すべてが終わった世界は、驚くほど静かだった。人々が往来し、笑い、語り合っている。彼らの足元には、当たり前のように影が落ちている。だが、俺にはもう、その影が奏でる無音の音楽は聞こえない。世界は、ただの光と色彩に満ちた、平坦な風景に変わってしまった。
「カイ……」
隣に立つリナが、心配そうに俺の顔を覗き込む。俺は彼女に微笑みかけた。
「大丈夫だ。ただ、少し静かすぎるだけだよ」
俺は多くを失った。人々の生の重みを感じる能力も、未来の可能性も、そして俺自身の存在意義さえも。だが、後悔はなかった。俺は空を見上げる。空は青く、太陽が眩しい。
もう、影の重みはわからない。一人一人がどんな人生を背負い、どんな想いを抱いて生きているのか、肌で感じることはできない。
けれど、わかることがある。俺が守ったのは、その一人一人が、自分だけの物語を生きる権利そのものだ。不完全で、時に苦しみに満ちていても、誰かに一方的に奪われていいものではない、かけがえのない個々の生。
俺は自分の影を見下ろす。それはもう何の振動も発しない、ただの黒い染みだ。
だが、それでいい。この静寂こそが、俺が下した選択の証なのだから。俺は、光の中にただ静かに立つ。ざわめきはもうない。けれど、確かな温もりが、そこにはあった。