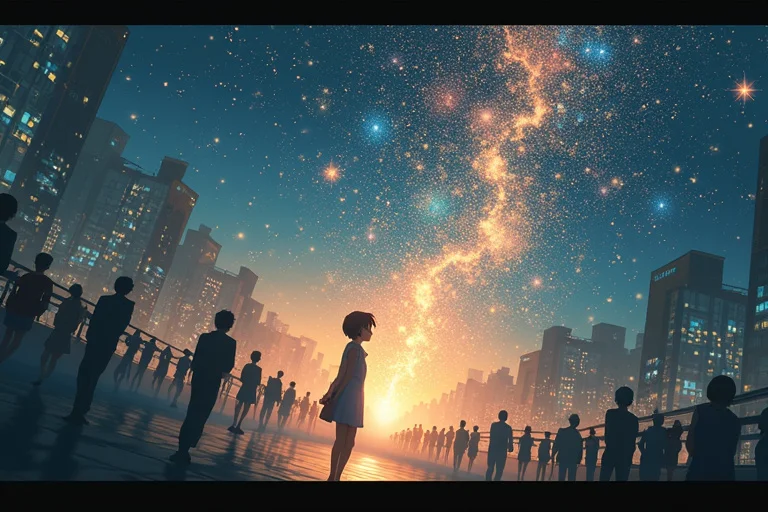第一章 叫ぶ生姜焼きと魔法の杖
小山田譲(おやまだ ゆずる)の人生は、だいたいにおいて凪いでいた。亡き祖母から受け継いだ路地裏の小さな定食屋「おやまだ食堂」のカウンターに立ち、黙々と鍋を振る毎日。客との会話は「ご注文は」「へい、お待ち」の二言で事足りる。人付き合いが致命的に下手な彼にとって、料理は唯一、世界との接続を許された言語だった。
その平穏が、最近、妙な不協和音を奏で始めている。
その日も、昼の喧騒が引けた午後二時。常連の田中さんが、分厚い胸板を揺らしながら、いつもの「豚の生姜焼き定食」を頬張っていた。厳つい顔に鋭い眼光、ゼネコンの現場監督という肩書きが服を着て歩いているような男だ。譲はカウンターの内側で、黙々と食器を洗いながら、その咀嚼音に耳を澄ませていた。肉が噛み砕かれ、タレの染みた白米が喉を通る音。それは譲にとって、自らの仕事が肯定された証であり、ささやかな安らぎだった。
だが、田中さんが最後の白米をかき込み、味噌汁をぐっと飲み干した、その瞬間だった。
「うおおおおっ! 我が心に輝くは、愛と勇気のクリスタル! プリティソルジャー・マジカルピーチ、ただいま見参ッ!」
ガタン!と椅子を蹴立てて立ち上がった田中さんが、空になった味噌汁のお椀を天に掲げ、高らかに叫んだ。その目は潤み、頬は紅潮している。譲の手から、洗いかけの皿が滑り落ちそうになった。
田中さんは止まらない。おもむろに高級そうなビジネスバッグを開くと、中から出てきたのは企画書や図面ではなく、フリルのついたピンク色の衣装をまとった魔法少女のフィギュアだった。全長三十センチはあろうかという精巧な代物だ。彼はそれを愛おしそうに掲げると、食堂の狭い通路で、奇妙きてれつなステップを踏み始めた。
「ピーチ・スパイラル・ハリケーン! 今こそ、悪を浄化するのよ!」
フィギュアを振り回しながら、一人芝居を続ける田中さん。その姿は、近隣の工事現場を束ねる鬼監督の威厳など微塵も感じさせない。ただの、純粋で、熱狂的な、中年男性ファンだった。
「た、田中さん…?」
譲がようやく絞り出した声は、か細く震えていた。我に返った田中さんは、自分の手の中にあるフィギュアと、呆然と立ち尽くす譲の顔を交互に見比べ、みるみるうちに顔を青ざめさせた。
「あ、いや、これは、その…ち、違うんだ! 断じて違う!」
田中さんはフィギュアを乱暴にカバンに押し込むと、釣り銭も受け取らずに、猛烈な勢いで店を飛び出していった。ドアベルがちりん、と悲しい音を立てる。残されたのは、静寂と、床に落ちたままの味噌汁のお椀、そして生姜焼きの甘辛い香りが漂う空気だけだった。
譲は、深いため息をついた。まただ。ここ最近、こんなことばかり続いている。アジフライを食べた女子高生が、中学時代の自作ポエムを涙ながらに朗読し始めたり。カツ丼を平らげた好々爺が、五十年前の初恋相手に送れなかったラブレターの内容を、一字一句間違えずに絶叫したり。
僕の料理は、人を狂わせる呪いでもかかっているのだろうか。譲はカウンターに突っ伏し、じわりと滲み出す自分の無力さに、ただ唇を噛みしめることしかできなかった。
第二章 呪いのスパイス瓶
客の奇行は、SNSという名の追い風に乗って、あっという間に近所に広まった。「あの店の飯を食うと、隠してた性癖がバレるらしい」「黒歴史暴露食堂だろ?」そんな不名誉なあだ名までつけられ、客足は面白いように遠のいていった。かつては昼時ともなれば満席だった店内に、今は空席ばかりが目立つ。
譲は完全に自信を失っていた。祖母の味を守りたい。ただそれだけだったのに、どうしてこうなってしまったのか。原因を突き止めようと、彼はあらゆる可能性を潰していった。
食材は? 馴染みの八百屋と肉屋から仕入れる、いつも通りの新鮮なものだ。水は? 水道水だが、念のため浄水器も通している。調理器具は? 祖母の代から使い込まれた鉄のフライパンも、毎日丁寧に手入れしている。どれも問題があるとは思えなかった。
残るは、調味料だ。譲は厨房の棚にずらりと並んだ瓶を一つ一つ手に取った。醤油、みりん、酒、塩、砂糖…。ごく普通の、どこにでもある調味料ばかりだ。その中で一つだけ、異質な存在感を放つものがあった。
それは、ラベルの剥がれかかった、古びたガラス瓶だった。中には、何種類ものハーブやスパイスが混ざり合った、くすんだ緑色の粉末が入っている。祖母が「おやまだ食堂の隠し味よ」と言って大切にしていたもので、譲もまた、祖母の教え通り、ほとんど全ての料理にほんの少しだけ振りかけていた。『秘密のスパイス』と、彼は心の中で呼んでいた。
「まさか、これか…?」
譲は瓶の蓋を開け、匂いを嗅いでみる。ローズマリーやタイムのような、少し鼻にツンとくる、だが食欲をそそる複雑な香りだ。指先に少量つけて舐めてみても、少し塩気と苦味があるだけで、人の正気を失わせるような劇薬の味はしない。
それでも、疑念は拭えなかった。これを使わなければ、呪いは解けるかもしれない。しかし、それは同時に、祖母から受け継いだ味を捨てることを意味した。譲にとって、それは自分の存在意義を否定するにも等しい行為だった。
どうすればいいのか分からず、彼はただスパイス瓶を握りしめたまま、客のいない静かな食堂で途方に暮れていた。閉店時間をとうに過ぎた窓の外は、すでに濃紺の闇に包まれている。その闇が、まるで自分の未来そのものであるかのように思えて、譲は深い孤独感に苛まれた。誰もいない。誰も助けてくれない。この店も、僕も、このまま静かに消えていくだけなのだろうか。
第三章 味のないジャーナリストと涙の塩むすび
そんなある日の午後、店のドアベルが軽やかな音を立てた。現れたのは、場違いなほど洗練されたスーツを着こなした一人の女性だった。歳の頃は譲と同じくらいだろうか。通った鼻筋に、知的な光を宿した大きな瞳。霧島玲奈、と彼女は名乗った。有名なグルメ雑誌のジャーナリストだという。
「面白い噂を耳にしまして。こちらの料理をいただくと、人生が変わる、と」
玲奈は面白がるような笑みを浮かべて言った。その言葉には、隠しきれない揶揄の色が滲んでいる。譲は、また冷やかしだ、と心を閉ざした。
「うちはただの定食屋です。特別なものはありませんよ。それに、もうすぐ仕込みの時間なんで」
ぶっきらぼうに追い返そうとする譲に、玲奈は怯まなかった。彼女はカウンターの席にすっと座ると、きっぱりと言った。
「一番シンプルなものをください。シェフの魂がこもった一品を」
その真っ直ぐな瞳に気圧され、譲はため息をついた。仕方なく、彼は厨房に立つ。シンプルなもの。ならば、塩むすびだ。炊き立ての白米を手に取り、掌に粗塩を馴染ませる。
その瞬間、昨日まで感じていた孤独や不安が、再び胸の奥からせり上がってきた。この店も、自分の人生も、もうおしまいかもしれない。誰にも理解されないまま、一人で朽ちていくのか。じわりと、目の奥が熱くなる。だが、客の前で涙を見せるわけにはいかない。譲は奥歯をぐっと噛み締め、こぼれ落ちそうな感情を米の一粒一粒に押し込めるように、力を込めてむすびを握った。秘密のスパイスは、もちろん使わなかった。
「どうぞ」
湯気の立つ、ただの塩むすびが二つ乗った小皿を、玲奈の前に置く。彼女は優雅な手つきで一つを手に取ると、小さく、そして完璧な一口を味わった。
譲は、固唾を飲んで彼女の反応を待った。今度は何が起こる? 彼女は突然、編集長への不満をぶちまけるのか? あるいは、誰にも言えない秘密の趣味でも暴露するのか?
しかし、玲奈の反応は、譲の予想を遥かに超えていた。
彼女は、ただ静かに、ぽろぽろと涙をこぼし始めたのだ。完璧に施されたメイクが、涙の筋となって頬を伝っていく。
「…しょっぱい。しょっぱいですね、このおむすび」
嗚咽を漏らしながら、彼女は言った。
「私…もうずっと、味が分からなかったんです。ストレスで、味覚障害になってしまって。ジャーナリストとして致命的だから、誰にも言えずに、ずっと…ずっと一人で、味の分かるフリをしてきた。美味しいフリ、幸せなフリをしてきた。でも、このおむすび…なんだか、とても悲しくて、しょっぱい味がする…」
譲は雷に打たれたような衝撃を受けた。スパイスは使っていない。使ったのは、米と塩と、そして…自分の感情だけだ。
あの時、握りながら感じていた絶望的な孤独と悲しみ。それが、この塩むすびに乗り移ったというのか? そして、同じ孤独を抱える彼女の心の琴線に、触れたというのか?
原因は、スパイスなんかじゃなかった。僕自身だったんだ。僕の感情そのものが、隠し味になっていた。生姜焼きを作った時の「もっと評価されたい」という承認欲求が、田中さんの隠された自己表現欲を刺激し、アジフライを揚げた時の「過去に戻りたい」という郷愁が、女子高生の黒歴史ポエムを呼び覚ました。
それは呪いではなかった。言葉下手な自分が、無意識に発していた、魂の叫びだったのだ。
第四章 人生相談食堂へ、ようこそ
その日を境に、「おやまだ食堂」は静かに変貌を遂げた。譲は、自分の特異な能力を玲奈に打ち明けた。味覚を失い、食への情熱を見失いかけていた彼女は、彼の能力に強い興味を示した。「これは現代社会に必要な魔法よ」と彼女は言った。二人は協力して、能力のコントロールを試み始めた。
それは、まるで感情の調味料を作るような作業だった。楽しい気分の時に作った料理は、食べた人の楽しかった記憶を。優しい気持ちで作った料理は、心の奥底にある温かい思い出を呼び覚ますことが分かってきた。失敗も多かった。少しでもネガティブな感情が混ざると、途端に気まずい暴露大会が始まってしまう。譲は、自分の心を穏やかに保つ訓練を、料理を通して学んでいった。
ある雨の日の夕方。店に、一組の親子がやってきた。白髪の頑固そうな父親と、うつむきがちな四十代の息子。二人の間には、長年の確執が生んだ、分厚く冷たい壁があるのが見て取れた。注文は、二人とも「出汁巻き玉子」。
譲は、深呼吸をした。そして、卵を割りながら、自分の父親との数少ない温かい記憶を、必死に思い起こした。キャッチボールをした時の、革の匂い。初めて自転車に乗れた時に、無骨な手で頭を撫でられた感触。不器用だけど、確かにそこにあった親子の愛情。その温かい感情だけを、そっと卵に溶かし込む。
ふっくらと焼き上がった黄金色の玉子焼きを、二人の前に差し出す。父親が、息子が、無言でそれに箸をつけた。
一口、また一口と食べるうちに、父親の険しい顔が、少しずつ崩れていく。
「…すまなかったな。お前が会社を継がないと言った時、俺は、お前の夢を応援してやれなかった」
ぽつりと、父親が呟いた。息子の肩が、びくりと震える。
「親父こそ…。俺、ずっと言えなかったけど…親父みたいな職人になりたいって、本当は、ずっと思ってたんだ」
堰を切ったように、二人は言葉を交わし始めた。それは、何十年もの間、心の奥底にしまい込んでいた、本当の気持ちだった。譲はカウンターの内側で、その光景を静かに見つめていた。涙でぐしょぐしょになった顔で玉子焼きを頬張りながら、謝罪と感謝を繰り返し口にする二人を見て、譲の胸にも温かいものが込み上げてきた。
「おやまだ食堂」が、以前のように繁盛することはないかもしれない。人を狂わせる店という噂は、今や「悩みが解決する不思議な食堂」という、これまた奇妙な評判に変わりつつある。
譲は、カウンターを拭きながら、窓の外に広がる夜景を眺めた。もう、孤独は感じなかった。言葉は少なくてもいい。自分には、料理がある。心を込めて作った一皿が、誰かの心を温め、閉ざされた扉を開く鍵になるのなら。
「へい、おまち」
新しく入ってきた客に、譲は少しだけ口角を上げて声をかける。それは、彼が自分の居場所を見つけた証の、温かく、そしてほんの少しだけ誇らしげな微笑みだった。彼の作る料理の味は、今日も誰かの人生の、隠し味になる。