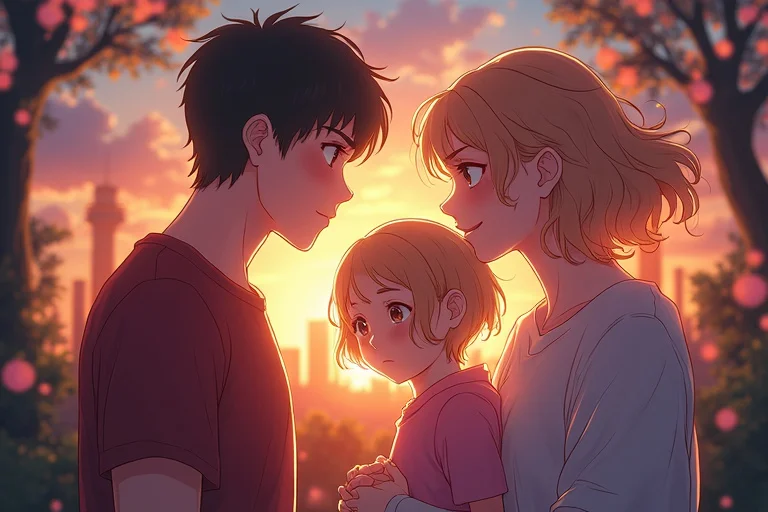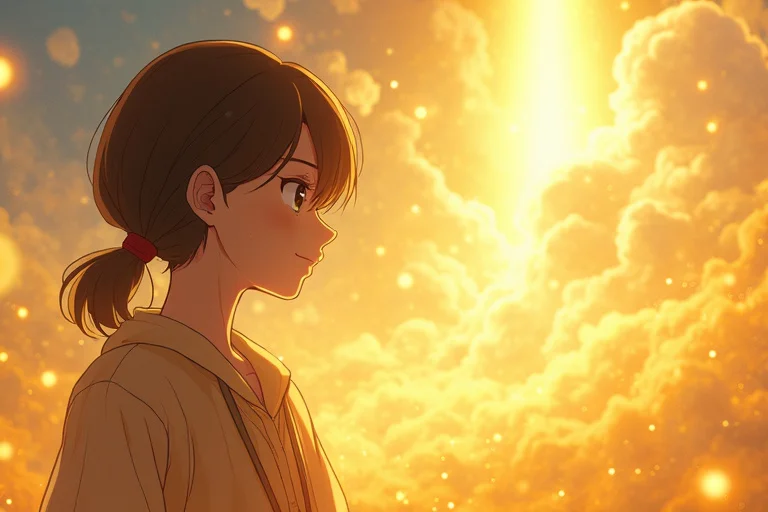第一章 生姜焼きとパントマイム
路地裏の陽だまりに忘れられたように佇む、定食屋「あじさわ」。その引き戸を開けるのは、近所の常連客か、道に迷った猫くらいのものだった。店主の味沢譲(あじさわ ゆずる)は、カウンターの内側で今日もため息をついていた。まだ二十代後半だというのに、その背中はすでに老舗の暖簾のようにくたびれている。先代である祖父から店を継いで三年。客足は減る一方で、自慢の出汁の香りだけが虚しく店内に満ちていた。
「いらっしゃい」
力なく声をかけた先にいたのは、常連の田中さんだった。くたびれたスーツに身を包んだ、うだつの上がらないサラリーマン。それが世間の評価であり、おそらくは自己評価でもあった。
「いつもの、お願い」
「はい、生姜焼き定食ですね。すぐ作ります」
譲は手際よく豚ロースに片栗粉をまぶし、熱したフライパンに滑らせる。ジュワッという快い音と共に、醤油と生姜の香ばしい匂いが立ち上った。完璧な焼き加減、秘伝のタレの黄金比。味には絶対の自信がある。なのに、どうして客が来ないのか。料理は科学であり、芸術でもある。だが、経営は魔法か何かで、譲にはその呪文がさっぱり分からなかった。
熱々のご飯と、湯気の立つ味噌汁、小鉢を添えて定食を出す。田中さんは「どうも」とだけ言うと、無心で箸を進めた。その食べっぷりはいつも見ていて気持ちがいい。まるで、一日の憂さをすべて胃袋に詰め込んで消化しようとしているかのようだ。
あっという間に平らげた田中さんは、千円札をカウンターに置くと、いつものように会釈だけして店を出ていった。その背中を見送りながら、譲はまたため息をつく。今日も売り上げは芳しくない。
その、直後のことだった。
店のガラス戸越しに見える路地で、信じられない光景が繰り広げられた。今しがた店を出た田中さんが、突然カクカクと奇妙な動きを始めたのだ。見えない壁をまさぐり、存在しない階段を上り、架空の強風に煽られてよろめく。その動きは素人芸などではなかった。指先からつま先まで神経の行き届いた、神業のようなパントマイム。道行く人々が足を止め、あっという間に人だかりができた。やがて、どこからか投げ銭まで飛び交い始めた。
「……え?」
譲はカウンターから乗り出し、目をこすった。あの田中さんが? いつも「疲れた」が口癖で、満員電車に揺られるだけで息も絶え絶えになっていた、あの田中さんが?
拍手喝采の中、田中さんは深々とお辞儀をすると、まるで何事もなかったかのように雑踏に消えていった。残されたのは、呆然とする譲と、路地に漂う生姜焼きの残り香だけだった。譲の平凡な日常に、最初の亀裂が入った瞬間だった。
第二章 才能開花レストラン
田中さんのパントマイム事件から数日。譲はあれは夢だったのではないかと思い始めていた。しかし、その疑念を打ち砕くように、第二、第三の奇妙な出来事が続発した。
口下手で、注文するのも一苦労だった大学生の鈴木くんが、譲の作った唐揚げ定食を食べたその日の午後、大学のディベート大会で審査員が舌を巻くほどの弁論術を披露して圧勝した。近所の奥様は、アジフライ定食を食べた後、自宅の庭で誰も見たことのない美しい花を咲かせたという。
噂は、都市伝説のようにじわじわと、しかし確実に広がっていった。
「あじさわの飯を食うと、眠っていた才能が目覚めるらしい」
その日を境に、店の引き戸はひっきりなしに開けられるようになった。訪れるのは、もはや昔ながらの常連客ではない。目にギラギラとした野心を宿した、多種多様な人々だった。
「俺、ラッパーになりたいんすよ! とにかく語彙力が増えるやつ、お願いします!」
「私は……世界的なフィギュアスケーターに。バランス感覚が良くなる定食、ありますか?」
「株で大儲けしたい。未来予知の才能が欲しいんだが、どのメニューがいい?」
譲は戸惑った。彼はただ、美味しい定食を作りたいだけだ。客の腹と心を満たす、温かい一食を提供したい。それだけだったのに、いつの間にか店は「才能開花レストラン」などという胡散臭い名前で呼ばれるようになっていた。
それでも、店が繁盛するのは素直に嬉しかった。空っぽの客席が埋まり、賑やかな声が響く。次々と入る注文に、休む暇もない。譲は混乱しながらも、フライパンを振り続けた。彼の料理を食べた客たちは、確かに何らかの変化を体験した。ある者は突然流暢な外国語を話し始め、ある者は難解な数式を解き明かした。店の前の路地は、即席のパフォーマンス会場と化し、毎日がカーニバルのようだった。
だが、譲の心は晴れなかった。客は彼の料理の「味」を見ていない。彼らは料理を、才能を手に入れるための「手段」としか見ていなかった。カウンター越しに見える客の目は、皿の上ではなく、その先にある成功や名声に向けられている。
「俺が作りたいのは、こんな料理だっただろうか……」
忙しさとは裏腹に、譲の心には冷たい隙間風が吹き始めていた。料理人としての喜びを見失いかけていた。
第三章 鯖の味噌煮と母の涙
そんなある日、店の引き戸が静かに開いた。入ってきた男の放つ空気に、店内の喧騒が一瞬にして静まり返る。鋭い眼光に、寸分の隙もなく着こなされた高級スーツ。日本で最も影響力のある料理評論家、神宮寺辰巳(じんぐうじ たつみ)だった。彼の辛辣な批評で、一夜にして星付きレストランが閉店に追い込まれたという逸話は数知れない。
「噂の店に、確かめに来た」
神宮寺の低い声が響く。客たちは固唾を飲んで成り行きを見守っていた。譲は、心臓が喉から飛び出しそうになるのを必死でこらえた。この男に認められれば本物だ。だが、もし酷評されれば、この奇跡のブームも終わるだろう。
「……何になさいますか?」
かろうじて絞り出した声は、自分でも情けないほど震えていた。
神宮寺はメニューを一瞥すると、こともなげに言った。
「鯖の味噌煮。定食で」
ごくり、と譲は唾を飲み込んだ。鯖の味噌煮。祖父から受け継いだ、この店で最も手間のかかる、そして最も自信のある一品。しかし、才能開花という点では、どんな効果があるか全くの未知数だ。世界征服の才能でも目覚めてしまったらどうしよう。
譲は震える手で、それでも持てる技術のすべてを注ぎ込んだ。丁寧に下処理した鯖を、絶妙な塩梅の煮汁でじっくりと煮込む。白味噌と赤味噌のブレンド、隠し味の酒粕。店中に、ふくよかで優しい香りが満ちていく。
神宮寺の前に、完璧な照りをまとった鯖の味噌煮が置かれた。彼は無言で箸を取ると、一口、身をほぐして口に運んだ。そして、ゆっくりと咀嚼し、目を閉じた。
店内の誰もが息を止める。一体、どんな奇跡が起こるのか? この男が、突如としてオペラを歌い出すのか? それとも、壁を通り抜ける超能力に目覚めるのか? 全員の視線が神宮寺に突き刺さる。
一分が、まるで一時間のように感じられた。
やがて、神宮寺は静かに目を開けた。その険しかった目元が、信じられないほど穏やかに緩んでいる。そして、彼の頬を、一筋の涙が静かに伝った。
才能の開花ではなかった。少なくとも、誰もが期待したような派手なものでは。
神宮寺は、ハンカチでそっと涙を拭うと、震える声で言った。
「……思い出したよ。幼い頃に亡くした、母さんの味だ。日曜の昼下がり、縁側で食べた、あの鯖の味噌煮の味。味噌の香り、陽の光の暖かさ、僕の名前を呼ぶ母さんの声……全部、思い出した」
彼の開花した才能は、「失われた温かい記憶を、五感のすべてで完璧に追体験すること」だった。
神宮寺は、もはや評論家ではなかった。ただの息子として、懐かしい味に再会した男の顔をしていた。
「素晴らしい。君の料理の本当の価値は、奇跡を起こすことじゃない。人の心を……その人の一番温かい場所へ、帰してくれることだ。ありがとう。本当に、ありがとう」
深々と頭を下げる神宮寺に、譲は言葉を失っていた。雷に打たれたような衝撃が、全身を貫いていた。
第四章 ただ、温かい豚汁を
神宮寺が帰った後も、譲はしばらくカウンターの中で立ち尽くしていた。彼の言葉が、頭の中で何度も反響していた。「人の心を、一番温かい場所へ帰してくれる」。
そうか、そうだったのか。
田中さんのパントマイムは、子供の頃、学芸会で主役を演じた楽しかった記憶の再現だったのかもしれない。鈴木くんの弁論術は、昔、祖父に褒められたくて必死に物語を語った、あの日の情熱だったのかもしれない。才能開花は、結果でしかない。譲の料理は、食べた人の心の奥底に眠る、最も純粋で、最も輝いていた瞬間の記憶を呼び覚ます「鍵」だったのだ。
それに気づいた瞬間、譲の心にかかっていた霧が、すっきりと晴れていくのを感じた。彼が作りたかったのは、奇跡の料理じゃない。人の心を温める、ただの美味しい定食だった。やっと、自分の料理の本当の価値を見つけられた気がした。
翌日から、定食屋「あじさわ」の雰囲気は少し変わった。相変わらず店は「才能開花」を求める客で賑わっていたが、譲の姿勢が違っていた。彼は客の突飛な要求に笑顔で耳を傾けながらも、ただひたすらに、心を込めて料理を作った。その人の疲れた顔を見て、冷えた体を温めるには何がいいか。その人の寂しそうな目を見て、心をほぐすにはどんな味がいいか。それだけを考えるようになった。
ある寒い日の夕方、一人の若い女性客が訪れた。
「あの……私、歌手になるのが夢なんです。声が、透き通るように美しくなる料理を、お願いします!」
切実な願いに、以前の譲なら困惑しただろう。しかし、今の彼は違った。
彼はにっこりと、心からの笑顔で言った。
「はい、喜んで。今日は冷えますからね。心も体も芯から温まる、特製の豚汁定食がおすすめですよ」
譲は、大根、人参、ごぼう、豚肉がたっぷり入った、湯気の立つ豚汁を彼女の前に置いた。特別なことは何もない。ただ、祖父から教わった通り、丁寧に灰汁を取り、愛情を込めて作った、日本のどこにでもある家庭の味だ。
女性は、一口、豚汁をすすった。そして、ふわりと目を細めた。彼女の脳裏にどんな記憶が蘇ったのか、どんな才能が芽吹いたのか、それは誰にも分からない。歌手になれたのかどうかも、物語は語らない。
ただ、彼女はとても、とても幸せそうな顔で、夢中になって定食を食べていた。
その姿を、譲は満ち足りた気持ちで見守っていた。カウンターの向こうには、彼がずっと取り戻したかった、温かくて、ささやかな光景が広がっていた。彼の料理はこれからも、誰かの心を、それぞれの「故郷」へと連れて帰るのだろう。派手な奇跡ではなく、ささやかな温もりを、一杯の椀に込めて。