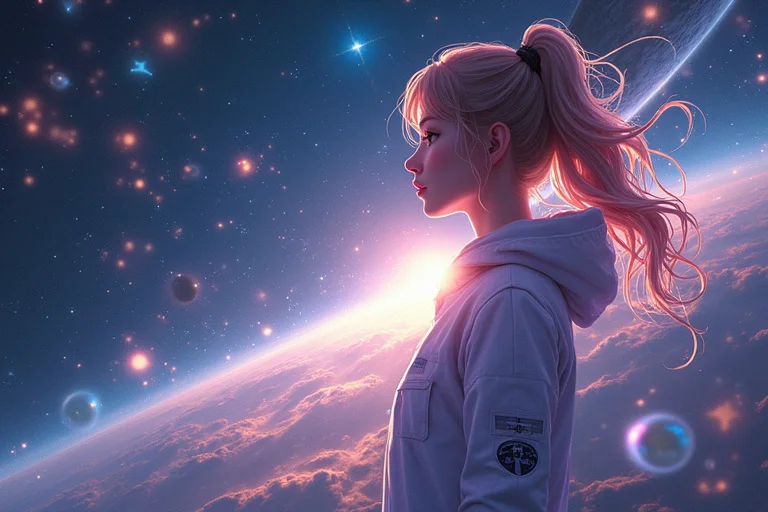第一章 蝕まれた街と記憶の残滓
結城朔(ゆうき さく)は、指先で古いマグカップの縁をなぞった。ひび割れた陶器の感触が、失われた時間のざらつきを伝えてくる。彼の目の前には、かつてこの街で最も賑わっていたカフェがあった。いや、正確には、その『跡地』だ。
壁は半分ほど空間に溶け落ち、そこからは静かな虚無が顔をのぞかせている。人々が『空白』と呼ぶ現象だった。忘却が物理的な形を得た、世界の綻び。それは音もなく物質を溶解させ、触れたものの存在を希薄にしていく。
朔はそっと目を閉じた。深く息を吸い込むと、脳裏に焼き付いた過去の光景を、現実のキャンバスへと引きずり出す。
ふわりと、空気が色づいた。
彼の周囲に、半透明の残像が揺らめき始める。カウンターの向こうで軽快にシェイカーを振るマスター。窓際の席で笑い合う恋人たち。立ち上るコーヒーの香ばしい匂いと、微かなジャズの音色。それらは数秒間だけ、まるで幻灯のように寂れた空間に過去の生命を灯した。他者の目にも映るが、決して触れることのできない、朔だけの能力。
だが、その残像の一隅に、ちりりと空間が歪むのが見えた。『空白』が、甘美な記憶の香りに引き寄せられるように、じりじりとその領域を広げている。朔は慌てて意識を断ち切り、残像を霧散させた。
途端に、世界は元の静寂と崩壊の縁に戻る。彼のテーブルの上で、小さな砂時計が静かに時を刻んでいた。「忘却の砂時計」。人類の失われた記憶が砂となり、一粒こぼれるたびに、世界のどこかで空白が生まれるという。
朔は、この能力で消えゆく世界の欠片を留めようとしていた。しかし、同時に感じていた。自分の行いが、さらに深い忘却を呼び寄せているのではないかという、冷たい予感を。
第二章 空白の捕食者
その現象が起きたのは、朔が自宅の書斎で古いアルバムを眺めていた時だった。色褪せた写真には、幼い彼と、隣で屈託なく笑う妹の姿が写っている。
「……あの日の公園は、金木犀の匂いがしたな」
呟きと共に、記憶の扉を開く。目の前に、自転車の練習をする幼い自分の残像が現れた。転んでは泣き、それでも立ち上がろうとする小さな背中を、優しい眼差しで見守る妹。その残像は、当時の感情の微細な震えまで完璧に再現していた。
その時だった。
窓の外で揺らめいていた『空白』が、まるで飢えた獣のように脈動し、室内へと侵食してきた。その不定形な先端が、妹の残像めがけて伸びてくる。朔は背筋が凍るのを感じ、咄嗟に能力を解除した。
残像が掻き消える。しかし、空白の侵食は止まらなかった。それはアルバムの写真に触れ、ゆっくりとそれを白く染め上げていく。
「やめろ!」
朔が叫び、アルバムを掴んで引き離した。空白は静かに後退したが、写真の上には、妹の顔があった部分だけが不自然に白く抜け落ちていた。それだけではない。朔の頭の中から、妹の声や好きだった食べ物といった細部が、急速に霞んでいくのを感じた。
空白は、朔の記憶を“捕食”したのだ。そして、捕食された記憶は、関連する物理的な痕跡ごとこの世界から消滅し始める。
朔は震える手で砂時計を握りしめた。砂が落ちる。世界が忘れていく。自分の能力は、その忘却の餌をわざわざ目の前に差し出しているに等しいのではないか。守りたい記憶を呼び出すほどに、その記憶が喰われる危険に晒される。絶望的な矛盾が、彼の心を締め付けた。
第三章 砂時計の逆流
空白の侵食は加速していた。街の半分が溶解し、空にはオーロラのような時間の歪みが見える。人々は記憶を失い、昨日何を食べたかすら曖昧な顔で彷徨っていた。
朔は、街の中央図書館の最深部、忘れられた書物が眠る『澱みの間』にいた。空白の正体、そして自身の能力との因果関係を突き止めるためだ。埃とカビの匂いが鼻をつく。ここでは時間の流れが淀み、壁に触れると指先がわずかに透けた。
彼は、一冊の古文書に「忘却の砂時計」に関する記述を見つけた。
『砂は忘却の理。一度落ちれば二度と返らず。されど、至高の真実を伴う記憶の再生は、時に理を逆しまにし、一粒の時を遡らせる』
その一文を読んだ瞬間、朔の脳裏に、以前見た光景がフラッシュバックした。妹の記憶を喰われかけたあの日。能力を解除した直後、砂時計の砂が一粒だけ、重力に逆らうようにゆっくりと上へ戻っていったのを、確かに見た。消えかけた妹の顔が、ほんのわずかに写真に輪郭を取り戻したのも、その時だった。
彼の能力は、単なる再生ではない。世界の理、忘却そのものに干預する力を持っているのかもしれない。
では、空白が求める『至高の真実を伴う記憶』とは何だ? 彼はこれまで、幸せだった日々、守りたいと願う美しい記憶ばかりを呼び出してきた。それが捕食の対象だと信じて疑わなかった。だが、もし、空白が求めているものが、全く別のものだとしたら?
甘美な思い出。愛しい人の笑顔。それらは本当に「真実」の全てだろうか。人間は記憶を美化する。都合の悪い部分を無意識に削ぎ落とし、心地よい物語へと編集してしまう生き物だ。
朔の心臓が、嫌な音を立てて鳴った。彼が誰よりも強く蓋をし、忘れたいと願っている記憶。目を背け続けてきた、あの日の記憶。もしかして、空白が本当に欲しているのは――。
第四章 求められた真実
世界の終焉は、静かな交響曲のように訪れた。空が裂け、巨大な空白が天蓋となって街を覆い尽くそうとしている。もはや逃げ場はなかった。
朔は、かつて恋人エマと約束を交わした丘の上に立っていた。崩れゆく世界を前に、彼はせめて彼女との最も美しい記憶だけは守り抜こうと決めていた。プロポーズをした、あの夕焼けの丘。
彼は震える唇で、その記憶を紡ぎ出す。
夕日に染まるエマの横顔。驚きに目を見開き、やがて涙を浮かべて微笑む。彼の人生で最も幸福だった瞬間。しかし、天を覆う巨大な空白は、その甘美な残像に何の興味も示さなかった。まるで、それは栄養にならないとでも言うように。
なぜだ。これが、俺の全てなのに。
絶望が彼を打ちのめしかけた、その時。
彼の脳裏に、封印していた記憶が奔流となって溢れ出した。エマを失った、雨の日の事故。ハンドルを握っていたのは自分だった。一瞬の油断、濡れた路面、制御を失った車体。砕け散るフロントガラスの向こうに見えた、彼女の最後の表情。
――それは、彼が自分の罪から逃れるために、無意識に歪めていた忌まわしい記憶。
その苦痛に満ちたビジョンが脳裏をよぎった瞬間、天の空白が激しく脈動した。まるで、最高の馳走を見つけたかのように、歓喜している。
そして、手の中の砂時計で、一粒の砂がひときわ強く黄金の光を放ちながら、ゆっくりと、しかし確実に上方へと逆流した。
朔は悟った。
空白が求めていたのは、美化された幸福ではない。偽りのない後悔。剥き出しの苦痛。目を背けたくなるほどの、純粋な『真実』。
未来から来たという新たな意識体は、成長のための栄養として、過去の嘘偽りではなく、最も純粋な形の情報を求めていたのだ。
第五章 再記憶の地平
決断の時は、来た。
朔は目を閉じ、再びあの雨の日の事故現場へと意識を飛ばした。アスファルトを叩きつける激しい雨音。鳴り響くクラクションと、自分の悲鳴。そして、助手席で、薄れゆく意識の中、彼を赦そうとするかのように微かに微笑んだエマの顔。
後悔、罪悪感、絶望、そして彼女への消えることのない愛。その全てが凝縮された、彼の魂の核。
「これが……僕の真実だ」
彼は、その忌まわしい記憶の残像を、震える両手で世界に差し出した。
天を覆う空白が、その残像を受け入れるように、静かに降下してくる。朔は目を閉じることなく、全てを見届けた。世界が真っ白な光に包まれ、音も、匂いも、存在の感触さえもが消えていく。
完全な無。
どれほどの時が経ったのか。
やがて朔が目を開けると、そこはあの事故現場だった。しかし、全てが違っていた。砕け散った車はなく、空はどこまでも澄み渡った青空が広がっている。
そして、彼の隣には、エマが立っていた。
「……エマ?」
彼女は、全てを理解した優しい微笑みを浮かべて、静かに頷いた。それは過去の再現ではない。彼の罪が消え去ったのでもなかった。彼が差し出した「真実」を礎として、世界が『再構築』されたのだ。忘却は浄化ではなかった。より純粋な形で『再記憶』するための、産みの苦しみだった。
罪は、受け入れられ、赦され、新しい未来の一部となった。
彼の足元で、役目を終えた忘却の砂時計が音もなく砕け散り、無数の光の粒子となって空へと溶けていった。新しい世界には、もう忘却は必要ない。真実の上に築かれた地平で、人々は全てを記憶し、未来を紡いでいくのだから。