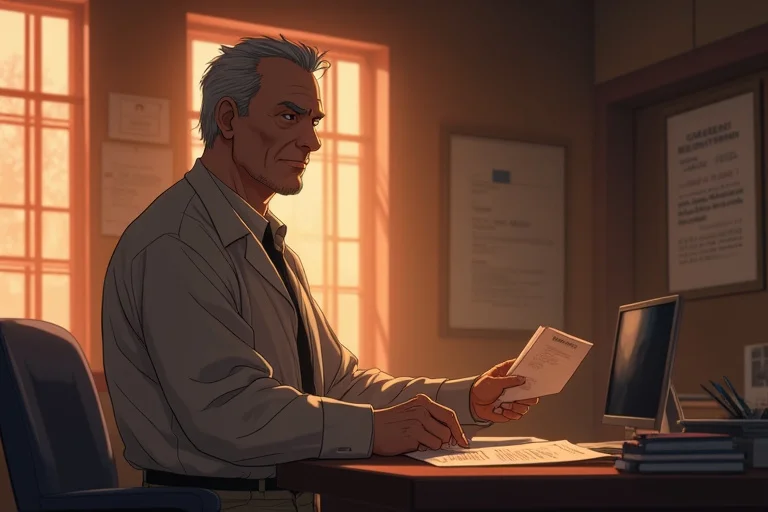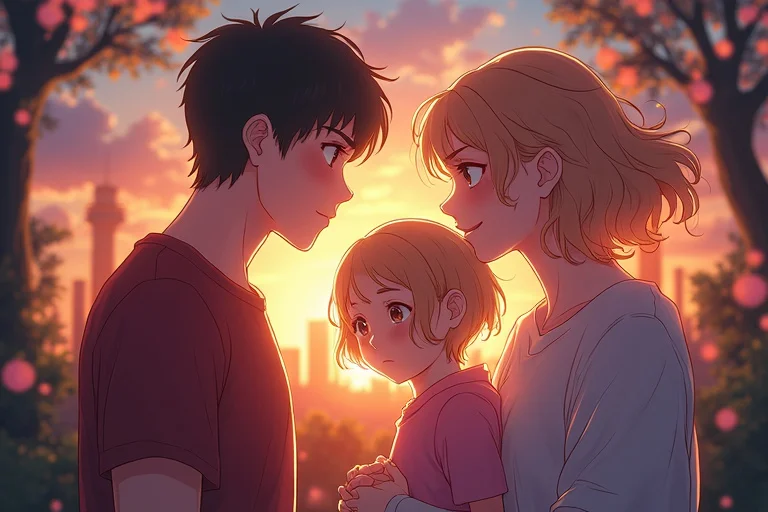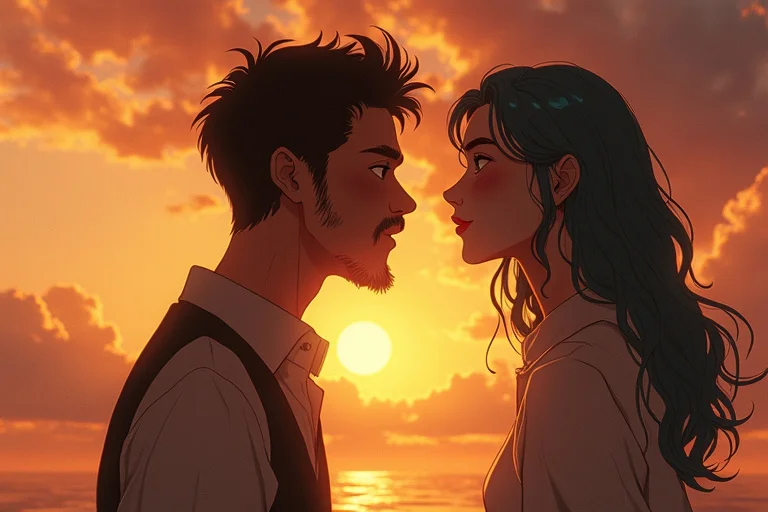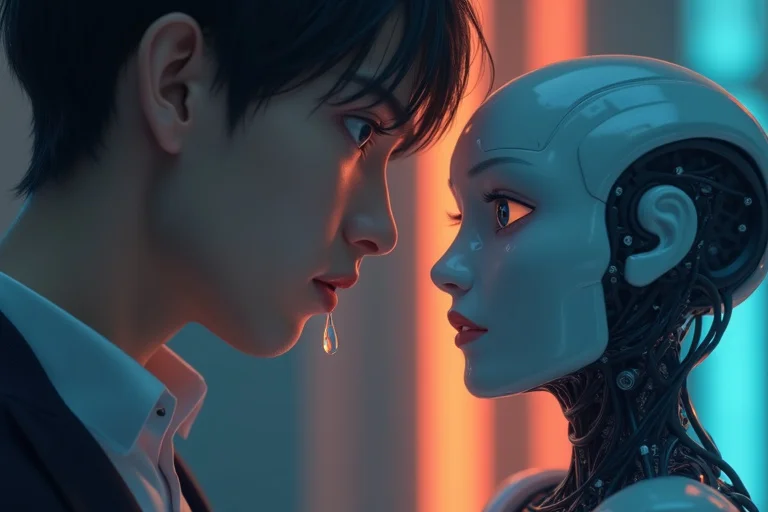第一章 空白の履歴書
志田健斗の人生は、灰色の方眼紙のように正確で、そして退屈だった。市役所の戸籍係として働き始めて五年。彼のデスクは常に完璧に整頓され、提出する書類に誤字脱字があったためしはない。彼の朝は、六時〇分〇秒に鳴るアラームで始まり、夜は、十時三十〇分〇秒に消灯する。その間の時間は、決められたタスクと、栄養バランスだけを考慮した味気ない食事で埋め尽くされていた。変化を嫌い、予定調和を愛する。それが志田健斗という男だった。
その完璧なはずの日常に、最初の亀裂が入ったのは、ある火曜日の朝のことだった。
目覚めた健斗は、枕元に置かれた昨夜の夕食のレシートを見て首を傾げた。コンビニで買った「たっぷり野菜の中華丼」。しかし、彼の記憶には、その中華丼を食べた形跡が一切ないのだ。舌の上に、あの独特の、とろみのついた餡の感触が蘇らない。昨夜、自分はいったい何を考えていた? 何を観て、何を感じた? 記憶が、まるで虫食いの葉のように、ぽっかりと穴が空いていた。
最初は、ただの疲労だと思った。連日の残業で、脳が休息を求めているのだろう、と。しかし、その奇妙な記憶の欠落は、日を追うごとに健斗の日常を侵食していった。
水曜日の朝には、前日に部長から受けた重要な指示を忘れていた。覚えているのは、部長のカツラがほんの少しだけ、本当にミリ単位でズレていたことだけだ。
木曜日の朝には、親友と電話で交わした週末の約束が抜け落ちていた。代わりに鮮明に覚えているのは、電話口の向こうで聞こえた、親友の子供が「パパのおならはメロンのにおい!」と叫んだ声だけだった。
金曜日には、一週間かけて準備したプレゼンテーションの内容が思い出せず、ただ、会議室の窓の外で二羽の鳩が熾烈なパンくずの奪い合いを演じていた光景だけが、脳裏に焼き付いていた。
彼の記憶は、不気味な選別を始めたようだった。人生の「本編」であるはずの、仕事や人間関係といった重要なデータは消去され、取るに足らない「NGシーン」や「メイキング映像」のような、シュールで滑稽な断片だけが残るのだ。
健斗は恐怖に震えた。彼のアイデンティティそのものである「正確さ」と「几帳面さ」が、足元から崩れ落ちていく。彼の人生は、面白い出来事の断片だけがランダムに浮かぶ、意味不明なコラージュ作品になり果てようとしていた。彼は藁にもすがる思いで、自分の記憶に残った事柄をメモ帳に書き出してみた。
・部長のカツラ(0.5mmのズレ)
・おなら=メロン臭説
・鳩の仁義なき戦い
・向かいの家の犬が、自分の尻尾を本気で追いかけている
・電車で隣に座ったおじさんの寝言が、流暢なフランス語だった
リストを眺めて、健斗は愕然とした。これらはすべて、無意識のうちに彼が「面白い」と感じたことだった。そうだ、間違いない。彼の脳は、「面白い」と判断した情報以外、すべてを記憶のゴミ箱に放り込んでいるのだ。
真面目を絵に描いたような男、志田健斗は、かくして「面白くないことは、覚えていられない」という、ふざけた呪いにかかってしまったのである。
第二章 笑いの処方箋
呪いの正体に気づいた健斗は、次なる行動に出た。それは、「笑いの強迫的摂取」だった。記憶を失わないためには、日常のあらゆる出来事を「面白い」に変換しなくてはならない。彼は、まるで受験生のように、笑いを猛勉強し始めた。
通勤電車では、難しい専門書を読むのをやめ、落語のCDを聞いて無理やり口角を上げた。昼休みには、栄養バランスの取れた弁当を三分でかきこみ、残りの時間をスマートフォンの面白動画の鑑賞に費やした。夜は、お笑い芸人のDVDを擦り切れるほど見て、ツッコミのタイミングやボケの構造を分析した。デスクの引き出しには、こっそりと「ウケる!ダジャレ100選」を忍ばせた。
だが、努力は空回りするばかりだった。義務感で摂取する笑いは、少しも彼の心を潤さなかった。むしろ、無理に笑おうとすればするほど、世界は色を失い、すべてが退屈な灰色に見えてくる。結果、彼の記憶の欠落はさらに深刻になった。市民に渡すべき書類の束を、うっかりシュレッダーにかけそうになったり、婚姻届を出しに来たカップルに、間違えて死亡届の書き方を説明してしまったり。彼の評判は、「真面目で優秀な志田さん」から、「最近ちょっとおかしい志田さん」へと急降下していった。
そんな健斗の異変に、最初に気づいたのは同僚の早川栞だった。彼女は、健斗とは正反対の人間だった。デスクの上はいつもカラフルな付箋で埋め尽くされ、笑い声はフロアの端まで響き渡る。一見、大雑把に見えるが、不思議と人望があり、彼女の周りにはいつも穏やかな空気が流れていた。
「志田さん、最近、面白いことでもあったんですか?」
ある日の昼休み、栞は健斗のデスクにやってきて、彼のパソコン画面に映る漫才の動画を覗き込んだ。
「いや、これは、その……記憶のための、訓練でして」
しどろもどろになる健utoに、栞はきょとんとした顔をした。追い詰められた健斗は、半ばヤケクソで、自分の身に起きている奇妙な症状をすべて打ち明けた。
彼の突拍子もない告白を、栞は笑い飛ばすかと思った。しかし、彼女は真剣な眼差しで彼の話を聞き終えると、ふっと息を吐いて言った。
「なるほど。それは大変ですね。でも、なんか……ちょっと面白そう」
「面白くありません! これは僕の人生の危機なんです!」
「まあまあ。でも、無理やり笑おうとするから、余計に面白くなくなるんじゃないですか? 心が動いてない笑いなんて、カロリーゼロのスイーツみたいなものですよ。食べた気にならない」
栞はそう言うと、一枚の付箋に何かを書き、健斗のモニターにぺたりと貼った。「処方箋です」と彼女はいたずらっぽく笑った。
付箋には、下手な地図と「金曜19時、ハチ公前集合」という文字が書かれていた。金曜の夜、健斗が半信半疑でハチ公前に行くと、栞は待っていた。
「さあ、行きましょう。志田さんの心を動かす、とっておきの場所に」
彼女が健斗を連れて行ったのは、お笑いライブでも、コメディ映画でもなかった。それは、都心から少し離れた、古びた商店街の片隅にある「世界の奇妙なボタン博物館」だった。軍服の荘厳なボタン、宇宙服の機能的なボタン、貴婦人のドレスを飾った宝石のようなボタン。そこには、ただひたすらに、ありとあらゆるボタンが並んでいた。
「どうです? 面白いでしょう?」
「面白い、というか……なぜボタン……?」
「世の中には、こんなにもボタンのことを愛している人がいる。その情熱が、面白くないですか?」
栞は、一つ一つのボタンを、まるで旧友に会ったかのように楽しそうに眺めている。その姿を見ていると、健斗の心の中に、今まで感じたことのない種類の感情が、じんわりと湧き上がってくるのを感じた。それは、無理やり作った笑いとは違う、穏やかで、温かい何かだった。
第三章 記憶のアーカイブ
栞との交流が始まってから、健斗の記憶には少しずつ変化が訪れた。彼の記憶に残るのは、もはやシュールな光景だけではなくなっていた。「世界の奇妙なボタン博物館」の埃っぽい匂い。路地裏で見つけた、猫の形をしたパン屋の看板。栞が教えてくれた、やたらと味の濃いラーメン屋の店主の笑顔。それらは、爆笑するような面白さではない。しかし、確かに彼の記憶に残り、翌朝になっても消えることはなかった。
だが、健utoの根本的な悩みは解決していなかった。仕事の記憶は、相変わらず抜け落ちがちだった。そしてある日、彼はキャリアを揺るがす、致命的なミスを犯してしまう。
市が管理する、とある地域の住民基本台帳の重要データを、誤って削除してしまったのだ。バックアップはあるものの、復旧には多大な時間と手間がかかる。フロアに響き渡る部長の怒声。同僚たちの冷ややかな視線。健斗は、全身の血が凍りつくのを感じた。縮こまり、ただひたすらに頭を下げることしかできない。情けなさと、自己嫌悪で、目の前が真っ暗になった。
その夜、健斗は眠れなかった。もう市役所にはいられないだろう。正確さだけが取り柄だった自分が、その唯一の長所を失ってしまった。明日、記憶を失った状態で出勤し、再び同じ過ちを繰り返すかもしれない。その恐怖に、彼は押しつぶされそうだった。こんな辛く、惨めな出来事は、きっと朝になれば綺麗さっぱり忘れているに違いない。そう、願った。
しかし、翌朝。健斗は、昨日の出来事を、驚くほど鮮明に覚えていた。
部長の怒りに歪んだ顔。こめかみに浮き出た青筋。同僚たちの囁き声。床に落ちた自分の汗のシミ。そのすべてが、高解像度の映像のように、脳内で再生される。
なぜだ?
健斗は混乱した。これは、まったく「面白い」出来事ではない。むしろ、人生で最も面白くない、最悪の一日だったはずだ。それなのに、なぜ記憶に残っている?
彼は、これまで書き溜めてきた「記憶に残ったことリスト」を、もう一度見返した。
カツラのズレ。おならの匂い。鳩の戦い。そして、栞と見たボタンの数々。
それらをじっと見つめているうちに、健斗は雷に打たれたような衝撃と共に、ある一つの真実にたどり着いた。
彼が記憶していたのは、単に「面白い」ことではなかったのだ。
彼が記憶していたのは――「心が、大きく動いたこと」だった。
カツラのズレに「驚き」、子供の言葉に「意表を突かれ」、鳩の戦いに「滑稽さを感じ」、ボタンの情熱に「感心した」。それらはすべて、平坦だった彼の心に、さざ波を立てた出来事だった。真面目すぎる人生を送ってきたせいで、彼は自分の中に湧き上がるそれらの微細な感情の揺れ動きを、すべて「面白い」という一つの粗雑なカテゴリに分類してしまっていたのだ。
そして、昨日の出来事。部長に叱責された時の、身を裂くような「悔しさ」。同僚の視線が突き刺さる「情けなさ」。絶望的な「恐怖」。それらは、彼の人生で経験したことのないほど、巨大な感情の津波だった。だから、忘れられるはずがなかったのだ。
彼は、このふざけた呪いのおかげで、初めて自分自身の「感情」の存在に、その多様性に、気づかされたのだった。
呆然とする健斗の元に、栞からメッセージが届いた。「データ、見つかりましたよ。別のサーバーに自動バックアップされてました。部長、勘違いだったみたいで、すごく恐縮してました」。
安堵で、全身の力が抜けた。そして、こみ上げてきたのは、栞へのどうしようもないほどの「感謝」の気持ちだった。この温かい感情もまた、きっと明日の朝まで覚えているだろう。健斗は、そう確信した。
第四章 カラフルな人生のスケッチブック
呪いの正体は、呪いではなかった。それは、健斗に感情の豊かさを教えるための、不器用で、遠回しな啓示だったのかもしれない。
あの日を境に、健斗は記憶を失うことを恐れなくなった。彼は、自分の心が動く瞬間を、恐れず、むしろ喜んで受け入れるようになった。
仕事にも変化が訪れた。彼は相変わらず真面目だったが、以前のようなロボット的な正確さではなく、人間味のある柔軟さが加わった。窓口で、手続きに戸惑う老婆がいれば、マニュアル通りの説明ではなく、彼女の心が「安らぐ」ような、優しい言葉をかけるようになった。同僚がミスをすれば、それをただ指摘するのではなく、相手の「悔しさ」に寄り添い、一緒に解決策を探すようになった。
健斗は、小さなスケッチブックを持ち歩くようになった。そして、心が動いた瞬間を、忘れないように書き留めていった。それはもはや「面白いことリスト」ではなかった。
雨上がりのアスファルトの匂いが運んできた、幼い頃の「懐かしさ」。
窓口に来た若い夫婦が、生まれたばかりの赤ん坊の名前を嬉しそうに話す姿から感じた「幸福感」。
栞が、差し入れてくれたコーヒーの温かさから伝わる「優しさ」。
彼のスケッチブックは、様々な感情の色で、少しずつカラフルに染まっていった。
ある晴れた午後、健斗と栞は、公園のベンチに並んで座っていた。木漏れ日が、二人の足元で優しく揺れている。
「最近、もう漫才の動画は見てないんですか?」と栞が尋ねる。
「うん。もう必要ないんだ」健斗は穏やかに答えると、例のスケッチブックを彼女に差し出した。
栞は、ゆっくりとページをめくった。そこには、健斗の拙いけれど温かいタッチで、様々な光景が描かれていた。信じられない体勢の猫、鳩、奇妙なボタン、そして、鬼のような形相で怒る部長の似顔絵。栞はくすくすと笑った。
そして、最後のページで、彼女は手を止めた。
そこには、自分でも気づかなかった、優しい笑顔の自分の横顔が描かれていた。
「これも、忘れられない記憶なんだ」健斗が、少し照れながら言った。
栞は、彼の横顔を見つめて、尋ねた。「それも、面白かったんですか?」
健斗は、ゆっくりと首を振った。そして、今まで見せたことのないような、柔らかい微笑みを浮かべた。
「ううん。面白い、だけじゃない」
彼は、栞の目を見て、言葉を続けた。
「……嬉しい、かな。あと、多分、愛おしい」
灰色の方眼紙のようだった彼の世界は、もうどこにもない。喜び、驚き、悔しさ、そして愛おしさ。様々な色で彩られた、豊かで味わい深い人生が、そこには広がっていた。
面白くないことは、覚えていない。でも、彼の心は今、面白さだけでは語れない、無数の大切な感情で満たされていた。空っぽだったはずの彼の人生の履歴書は、いつの間にか、誰にも真似できない、世界で一冊だけの、カラフルなスケッチブックになっていた。