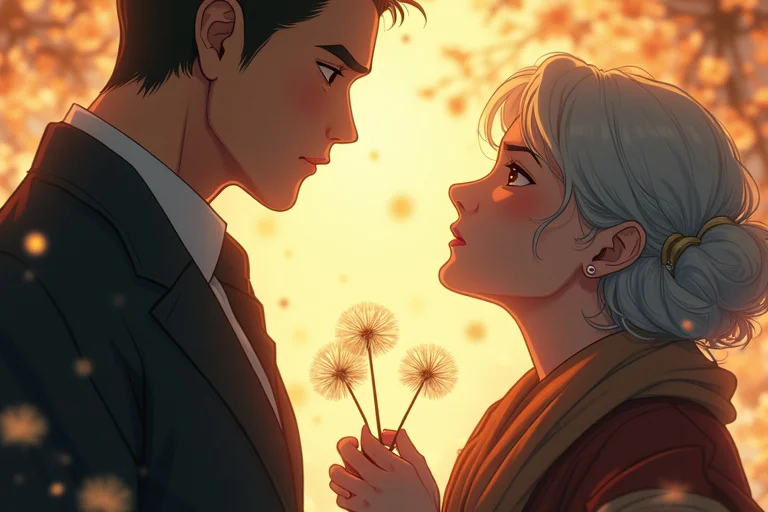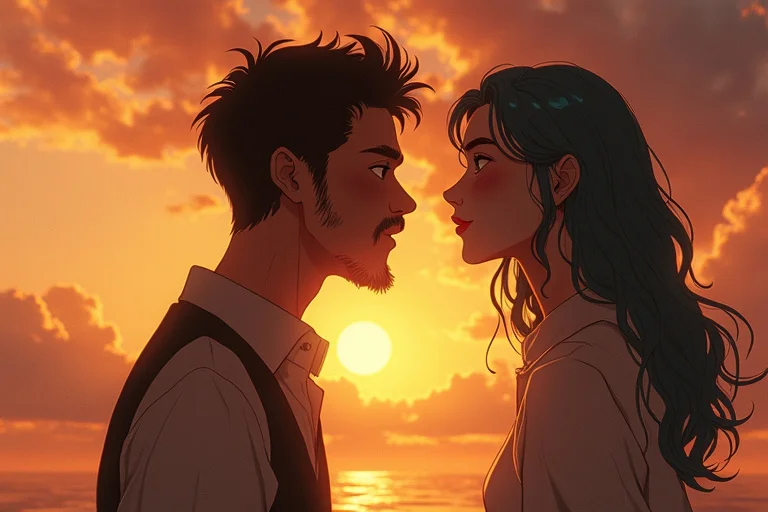第一章 ふわふわの子羊と正直な泡
潮騒町は、穏やかで、少し風変わりな町だった。石畳の坂道にはいつも潮の香りが漂い、カモメの声が空に溶けている。この町の住人は、感情が極まると、その心とは全く逆のイメージを持つ動物に数分間だけ変身してしまう。それはもう、雨が降れば傘をさすのと同じくらい、当たり前の日常だった。
例えば、魚屋の大将が値切り交渉に激怒すれば、純白のふわふわとした子羊に。「メェー!」とか細い声で鳴きながら、プルプルと震えるだけ。あるいは、恋が実った郵便配達員が喜びの絶頂に至れば、枝の上で羽を休める陰鬱なフクロエに。ホーホーと物憂げに鳴き、幸せそうなカップルをじっとりと見つめるのだ。人々はそんなお互いの姿に苦笑いしつつも、それなりにうまくやっていた。少なくとも、最近までは。
図書館の司書である一ノ瀬泡(いちのせ あわ)は、この町で最も変身とは縁遠い男だった。なぜなら彼は、感情が極まる前に、極度の緊張で別の現象に見舞われるからだ。
「あの、一ノ瀬さん。この本、破れてるんですけど」
カウンターの向こうで、鋭い目つきの女性が本を突き出す。泡の心臓が、まるで小さな鳥のように胸の中で暴れだした。まずい。緊張が飽和点に近づいていく。
「も、申し訳ございません。すぐに確認……」
言葉の途中で、泡の口からふわりと、虹色に輝くシャボン玉が一つ、生まれた。それはゆっくりと宙を舞い、女性の目の前でぽつり、と呟いた。
「うわぁ、こわい人やなぁ。そんなきっつい言い方せんでもええやんか……」
少し訛りのある、柔らかな京都弁。それは泡の本心だった。彼自身には全く聞こえない、正直すぎる心の声。女性の眉がぴくりと吊り上がる。泡は顔面蒼白になりながら、必死で頭を下げた。彼の周りには、さらにいくつかのシャボン玉が生まれ、口々に「ごめんなさい、ごめんなさい」「はよどっか行ってくれはったらええのに」と囁いている。この体質のせいで、泡はいつも自分の心を隠し、息を潜めるように生きていた。
第二章 鳴き声のパニック
異変は、静かに、しかし確実に町を蝕んでいた。
始まりは、一週間ほど前のこと。子羊になった魚屋の大将が、いつものか細い鳴き声ではなく、「もっと儲けて、でっかい船買うたるんじゃあ!」と野太い声で叫んだのだ。市場は一瞬で静まり返り、次の瞬間、大爆笑に包まれた。
だが、それは笑い事では済まなくなっていった。
悲しみに暮れて陽気なオウムになった未亡人が、「あー、もう一度だけでええから、旦那の手料理が食べたいわぁ!」と絶叫する。驚きのあまりナマケモノになった少年が、「宝くじ、当たってくれー!」と木の上から叫ぶ。
それはもはや、単なる鳴き声ではなかった。誰もが心の奥底にしまい込み、鍵をかけていた「本当の本当の隠れた願望」。それが、動物の姿を借りて町中に暴露され始めたのだ。
潮騒町はパニックに陥った。人々は互いの視線を避け、感情を押し殺し、まるで能面のような無表情で歩くようになった。だが、抑えつけられた感情は、些細なきっかけでより大きな力をもって暴発する。町は日に日に、秘密の暴露会場へと姿を変えていった。泡は、図書館の窓からその光景を眺め、自分のシャボン玉と町の人々の叫び声に、奇妙な共通点を感じていた。どちらも、隠したいはずの「本音」が駄々洩れになっている。
第三章 逆さま動物図鑑
その日、泡はいたたまれなくなり、町の外れにある古書店に逃げ込んだ。カビと古い紙の匂いが、彼のささくれだった神経を少しだけ癒してくれる。書架の隅、埃をかぶった棚の上で、彼は一冊の奇妙な本を見つけた。
『逆さま動物図鑑』
表紙には、逆さまに飛ぶフクロウが描かれている。興味を引かれてページをめくると、そこには美しい動物の絵と、その生態が記されていた。ごく普通の図鑑だ。しかし、彼が本の染みに気を取られて指を滑らせた瞬間、インクが滲むように、文字がすっと変化した。
子羊***…その純白の毛皮の下には、燃えるような闘争心を隠している。そのか細い鳴き声は、世界征服の野望を告げる鬨(とき)の声である。
「なんだ、これ…」
泡が呟くと、ふわりとシャボン玉が一つ生まれた。
「おもろい本やなぁ。わてみたいや」
シャボン玉がそう言った瞬間、図鑑の別のページがひとりでに開いた。そこにはシャボン玉の絵が描かれ、こう記されていた。
シャボン玉***…脆く儚いその膜は、持ち主の最も強固な本音を守るための鎧。決して嘘はつけない。
泡は息を呑んだ。この図鑑は、ただの古本ではない。まるで、この町の、そして自分自身の真実を映し出す鏡のようだった。彼は図鑑を胸に抱きしめ、古書店を飛び出した。何か、途方もない謎の入り口に立っている気がした。
第四章 静寂の中のメロディ
町の混乱を憂い、誰よりも心を痛めている人物がいた。町の高台にある「悩み相談室」の主、時田先生だ。白髪を綺麗に撫でつけた、いつも穏やかな笑顔の老カウンセラー。彼は町の精神的支柱であり、誰もが尊敬の念を抱いていた。その時田先生が、広場のスピーカーの前で住民に語りかけていた。
「皆さん、落ち着いてください。感情を無理に抑えるのは逆効果です。深呼吸を…」
だが、その言葉も虚しく、演説を聞いていた一人がくしゃみをした拍子に驚き、ナマケモノに変身して「世界一周旅行に行きたい!」と叫んだことで、広場は再び混乱に陥った。
泡はその光景を遠巻きに見ていた。その時、『逆さま動物図鑑』のある一節が脳裏をよぎる。フクロウのページに書かれていた言葉だ。
フクロウ***…その沈黙は、偽りの音を消し去るための祈り。静寂の中でこそ、真実の音が響き渡る。
「真実の音…?」
泡の視線が、時田先生の背後で静かに佇む、町のスピーカー塔に向けられた。あのスピーカーからは、一日中、住民の心を落ち着けるという触れ込みの、穏やかな環境音楽が流されている。だが、もし、あの音こそが…。
泡は、一つの仮説にたどり着いた。いてもたってもいられず、彼は時田先生のいる高台へと、石畳の坂道を駆け上がった。
第五章 相談室の告白
「時田先生!」
息を切らして相談室の扉を開けると、そこには疲れ果てた表情の先生が一人、椅子に座っていた。部屋の中には、町のスピーカーから流れているのと同じ、しかしより鮮明なメロディが微かに響いている。
泡の心臓が激しく脈打つ。緊張で、足元からシャボン玉がぽこぽこと湧き上がってきた。
「先生…この現象、先生が何か関係してるんやないですか?」
シャボン玉が、泡の代わりに核心を突いた。時田先生の肩が、びくりと震える。
「まさか。私がそんな…町のためを思っているのに」
先生が弱々しく否定すると、泡の周りを漂うシャボン玉たちが一斉にささやき始めた。
「嘘ついたらあかんわ」
「そのレコードプレーヤーから流れとる音楽、全部お見通しやで」
「ええ加減、白状しよし」
無数の本音が先生を取り囲む。観念したように、時田先生は深く、深いため息をついた。
「…君の言う通りだよ。全ての原因は、私だ」
先生は語り始めた。人々が本音と建前との間で苦しんでいるのを見るに見かねて、趣味で「感情矯正メロディ」という音楽を作曲したこと。その音楽には、人の心を少しだけ素直にする効果があったこと。良かれと思って町のスピーカーから流したのだが、先日、機材の調整を誤り、音量を上げすぎてしまったこと。その結果、人々の感情のストッパーが外れ、心の奥底の願望まで叫ぶようになってしまったのだ、と。
第六章 赤ちゃんライオンの昼寝
先生の告白を聞きつけ、相談室の外にはいつの間にか大勢の町民が集まっていた。裏切られたという怒りの声が、あちこちから上がり始める。
「なんてことをしてくれたんだ!」
「俺の秘密を返しやがれ!」
町民たちの非難を一身に浴び、時田先生の顔がみるみる青ざめていく。彼は椅子から立ち上がり、震える声で叫んだ。
「ち、違う!私は、私はただ、皆の役に立ちたかっただけなんだ!誰よりもこの町を愛し、尊敬される存在でいたかっただけなのに!」
その瞬間、先生の体が眩い光に包まれた。尊敬、プライド、自己犠牲。その感情の頂点で、彼が変身したのは…百獣の王ライオンとは似ても似つかぬ、生まれたばかりの赤ちゃんライオンだった。体長は猫ほどしかなく、たてがみも生えそろっていない。
人々が呆気に取られる中、その赤ちゃんライオンは、か細くも、しかしはっきりとした声で、高らかに叫んだ。
「もっと毎日昼寝がしたいんじゃー!」
張り詰めていた空気が、ぷつんと音を立てて切れた。
最初に、魚屋の大将が噴き出した。それを皮切りに、一人、また一人と笑い声が伝染していく。やがてそれは、町全体を揺るがすような大爆笑の渦となった。船が欲しい大将も、手料理が食べたい未亡人も、宝くじを当てたい少年も、そして、ただ昼寝がしたいだけの尊敬されるべき先生も。隠していた願望は、どれもこれも、あまりに人間臭くて、どうしようもなく愛おしいものだったからだ。
泡も、その輪の中で笑っていた。彼の口からは、虹色のシャボン玉がいくつも生まれ、楽しげに宙を舞っていた。
「なんや、みんな一緒やんか」
「ほんま、しょーもないことで悩んでたんやなぁ」
第七章 これからの潮騒町
メロディが止められてから、潮騒町の動物変身は、鳴き声を伴わない元の静かなものに戻った。けれど、町には確かな変化が訪れていた。一度、互いの「本当の本当の隠れた願望」を共有してしまった住民たちの間には、以前にはなかった奇妙な連帯感と、少しの気まずさ、そして大きな優しさが芽生えていた。
子羊になった魚屋の大将に、誰かがそっと船の模型を差し出したり、オウムになった未亡人の家に、近所の主婦が夕食のお裾分けを持って行ったり。
一ノ瀬泡は、相変わらず図書館のカウンターに立っている。緊張するとシャボン玉を出す体質も変わらない。だが、彼はもう、それを必死に隠そうとはしなくなった。
「この本、面白いですか?」
利用者に尋ねられ、泡は少しだけ口ごもる。すると、彼の肩のあたりでシャボン玉が一つ、ぽんと弾けた。
「わては、こっちの恋愛小説の方が好きやけどなぁ」
利用者はくすりと笑い、「じゃあ、そっちも借りてみようかな」と言った。
本音と建前。そのどちらもが、その人自身の一部なのだ。隠すことも、さらけ出すことも、どちらが正しいわけじゃない。ただ、潮騒町の人々は、あの奇妙な事件を経て学んだのだ。心の奥で鳴り響く、不器用で愛おしい鳴き声に、時にはそっと耳を傾けてみることの大切さを。
今日も町のどこかで、誰かが真逆の動物に変身している。その静かな姿の裏側にある本当の心を、人々は少しだけ想像できるようになった。空に浮かぶシャボン玉のように、見えなくても確かにある、それぞれの願いを。