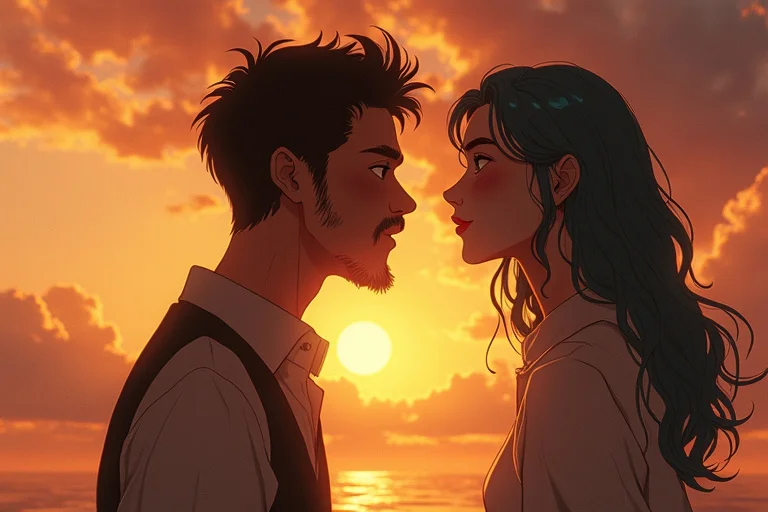第一章 不可解な侵入者、庭の片隅に
深夜零時を少し過ぎた頃、田中健太は自室の窓からぼんやりと庭を眺めていた。都会の空には星がまばらで、彼の心のように平凡な夜だった。IT企業のシステムエンジニアとして働く健太は、三十を過ぎても独身。趣味といえば休日の映画鑑賞と、稀に訪れる裏庭のガーデニング(主に雑草抜き)くらいで、刺激とは無縁の人生を送っていた。しかし、その夜、彼の視界の端で、ありえない光が瞬いた。庭の片隅、古びた物置の陰で、ごく短く、しかし脳裏に焼きつくほど鮮烈な青白い閃光が走ったのだ。
「……気のせいか?」健太は目を擦ったが、まぶたの裏にはまだ残像がこびりついている。全身に鳥肌が立った。それはまるで、雷の稲妻のようでありながら、もっと凝縮され、指向性を持った光だった。彼は半信半疑のまま、カーテンを閉め、布団に潜り込んだ。だが、胸のざわつきは収まらない。まさか、まさか、そんな馬鹿な。
翌朝、健太は目覚まし時計が鳴る前に飛び起きた。昨夜の閃光が幻ではなかったと確認するかのように、彼は急いで庭に出た。まだ薄暗い早朝の空気はひんやりとしていて、露が草葉を濡らしている。物置の陰に、健太は息を飲んだ。そこには、昨夜までは確かに存在しなかった「何か」があった。
それは、サッカーボールほどの大きさで、楕円形をしている。色は、深海のような青色から、時折、蛍光緑、そして不気味な紫へと、ゆっくりと移り変わっていた。表面は不自然なほどツルツルと滑らかで、雨上がりのミミズのように僅かにヌルヌルしているようにも見えた。何より奇妙なのは、その「物体」が、まるで生きているかのように微かな光を発していることだった。脈打つような光は、健太の心臓の鼓動とシンクロしているかのようだ。
健太はゆっくりと物体に近づいた。草木に埋もれるように鎮座するそれは、金属のようにも粘液のようにも見えた。科学では説明できない。彼は確信した。これは、宇宙からの飛来物だ。そして、この中に、あるいはこれ自体が、未知の生命体なのだと。彼の平凡な日常は、この一瞬で色を変えた。心臓が高鳴り、全身の血潮が沸騰するような興奮に包まれた。彼は震える手でスマートフォンを取り出し、慌てて写真を撮った。数枚の写真を撮り終えると、彼はそっとその場を離れた。秘密だ。これは、僕だけの秘密だ。
家に戻った健太は、朝食の準備をする母に気づかれないよう、何食わぬ顔でコーヒーを淹れた。「健太、今日は早いじゃない。何かあったの?」母の問いに、健太はぎこちなく「いや、別に」と答えるのが精一杯だった。彼の頭の中は、庭の「ヌルヌルした隣人」のことでいっぱいだった。彼は仕事中も上の空で、ネットでUFO、未確認生物、地球外生命体、宇宙船の残骸といったキーワードをひたすら検索し続けた。しかし、彼の庭にある物体に酷似する情報は一つとして見つからなかった。それは、やはり地球上のどんなものとも違うのだ。健太の胸は、更なる高揚感で満たされた。
第二章 謎の生命体との、秘密の交流
その日から、健太の生活は一変した。仕事から帰ると、彼は真っ先に庭の「ヌルヌル」の様子を見に行くのが日課となった。彼は「ヌルヌル」を『ポヨ』と名付けた。なんとなく、丸っこい形と、生命感のない有機的な雰囲気にぴったりだと思ったのだ。ポヨは相変わらず、ゆっくりと色を変え、微かに光を放っている。しかし、それ以外に大きな変化はなかった。
「ポヨ、今日の気分はどうだい?」健太は、夜中にそっと庭に出て、ポヨに話しかけた。ポヨはただ、青から緑、紫へと、その神秘的な色を揺蕩わせるだけだ。健太はそれでも諦めなかった。彼は、ポヨが「音」に反応するのではないかと考えた。翌日、彼は秋葉原で最新の超音波スピーカーを購入し、庭に設置した。そこから、モーツァルトのレクイエム、宇宙の環境音、果ては最新のポップスまで、あらゆるジャンルの音楽を流してみた。ポヨは、何一つ反応しない。
「もしかしたら、食料が必要なのか?」健太は次に、「食料」の供給を試みた。彼はスーパーで、新鮮な有機野菜、最高級の和牛、そしてなぜかネギを買い込んだ。ポヨの近くにそれらを並べ、「さあ、好きなだけ食べていいんだよ」と優しい声で語りかける。しかし、一晩経っても、それらの食材には一切手付かずだった。むしろ、近くに置いていたバナナには、小さい虫が群がっていた。
健太は困惑したが、諦めなかった。彼はポヨが「地球の環境に慣れていないだけだ」と前向きに解釈した。健太はポヨのために、庭の物置を改造し始めた。ビニールシートで簡易的な温室を作り、湿度計や温度計を設置した。まるで、病気の子供を看病する親のように、彼は献身的にポヨの世話を焼いた。
「健太さん、最近、庭で何をなさってるの?」ある日、隣に住むおせっかいな佐藤さんが、塀越しに声をかけてきた。佐藤さんは、町内会の役員も務める情報通だ。健太がポヨの温室を建設している姿は、どう見ても怪しいだろう。「あ、いや、ええと……新しい品種のバラを育てる準備で……」健太はしどろもどろになりながら答えた。「あら、バラ? 健太さん、そんな趣味があったかしら? 珍しいわねえ。今度見せてちょうだいね!」佐藤さんはにこやかにそう言うと、去っていった。健太は冷や汗を拭った。秘密は守らなければならない。ポヨの安全のためにも。
その夜、健太は温室の温度を少し上げてみた。すると、ポヨの表面の色が、普段よりも鮮やかなエメラルドグリーンに輝き始めたのだ!「やった! ポヨ、君は暖かいのが好きなんだね!」健太は歓喜した。彼の努力が報われた瞬間だった。ポヨが健太に応えようとしている。健太の心は、宇宙との交信に成功した科学者のように高揚した。彼はポヨとの絆が、日増しに深まっていることを確信した。
第三章 衝撃の真実、あるいは、あまりにも日常的な結末
ポヨとの交流(と健太が一方的に信じているもの)が深まるにつれて、健太はポヨがどこから来たのか、何をしに地球へ来たのかを知りたいという欲求に駆られた。彼はポヨの生態をより詳細に調べる必要があると感じた。彼は厚手のゴム手袋を用意し、庭の温室へ向かった。
「ポヨ、怖がらないで。僕は君の敵じゃない。ただ、君のことをもっと知りたいだけなんだ」健太はそっとポヨに語りかけ、そのヌルヌルした表面に触れようとした。指先がポヨに触れる寸前、突然、背後から優しい声が聞こえた。
「あら、健太、こんなところで何してるの?」
心臓が飛び跳ねるかと思うほど驚いた健太は、慌てて振り返った。そこには、普段は朝食時まで寝ているはずの母が立っていた。「お、お母さん!どうしたの?」健太は顔を真っ赤にして答えた。こんな秘密の場所に、まさか母が来るなどと。
「んもう、健太ってば、朝から大声出して。こんなところに何してるのかって聞いてるのよ。また変なことしてるんじゃないでしょうね」母はそう言いながら、健太の足元に視線を落とした。そして、健太が隠していたポヨを発見した。「あら、これって……」
母は屈むと、躊躇いもなくポヨを手に取った。健太は「やめろ!」と叫ぼうとしたが、声が出ない。母の指先が、ヌルヌルしたポヨの表面を撫でる。健太の脳裏には、ポヨが母に襲いかかる光景が、走馬灯のように駆け巡った。しかし、何も起こらない。ポヨはただ、母の手の中で、青から緑、紫へと、相変わらず色を変えているだけだ。
「これ、隣の佐藤さんが言ってたやつじゃない? 新しい観葉植物の鉢カバーだって」母はそう言いながら、ポヨの底をひっくり返した。健太は息を飲んだ。ポヨの底部には、これまで健太が一度も気付かなかった、小さな文字とバーコードが印字されていた。そこには、地球の、あまりにも日常的な、見慣れたメーカーのロゴが刻まれていた。
『最新素材! 環境適応型スマート鉢カバー』
健太の頭の中で、壮大な宇宙が崩壊する音が響いた。あれほど神秘的で、生命感に満ちた輝きを放っていたポヨは、ただの「鉢カバー」だったのだ。しかも、隣の佐藤さんのもの。湿度や温度によって色が変わる機能は、健太が必死に解読しようとした「宇宙生物の感情表現」ではなく、ただの「スマート機能」だった。超音波スピーカーも、最高級の和牛も、ネギも、すべてが無意味だった。あの、胸が高鳴るエメラルドグリーンの輝きも、単なる温度変化による反応だったのだ。
健太の全身から、力が抜けた。何食わぬ顔で鉢カバーを眺める母。その背後には、今日も変わらず、どこまでも青い空が広がっていた。宇宙からのメッセージも、未知の生命体も、すべては健太の壮大な勘違いだったのだ。耳の奥で、自分がポヨに語りかけた優しい言葉が、木霊のように反響する。彼は恥ずかしさで、地面に開いた穴に飛び込みたくなった。
第四章 僕と、ヌルヌルした世界の再定義
衝撃的な真実を知った健太は、その日一日、まるで抜け殻のようだった。母は「あら、やっぱり佐藤さんのだったわ。変わったデザインだけど、最近流行ってるらしいわね」と、健太の壮大な勘違いを知る由もなく、無邪気に鉢カバーを佐藤さんの家に届けに行った。健太は、自分の部屋で布団をかぶり、ひたすら現実から目を背けた。あの情熱、あの興奮、あの秘密のドキドキは、すべて「鉢カバー」に向けられていたのだ。なんて滑稽な、なんて情けない自分だろう。
翌朝、健太は重い足取りで庭に出た。そこには、もはやポヨはいない。空っぽになった温室を見て、彼は呆然と立ち尽くした。だが、その時、塀越しに「健太さーん!」と声が聞こえた。佐藤さんだ。健太はビクッと体を震わせた。
「健太さん、この鉢カバー、本当に面白いわね! アプリと連動して植物の健康状態まで教えてくれるんですって! 昨日、お母様が届けてくださって、本当に助かったわ。健太さんの温室の温度、ぴったりだったのよ! 新しいバラを育てるのにちょうど良いって、お母様がおっしゃってたわね」
佐藤さんは、健太の目の前で、例の鉢カバーを嬉しそうに掲げている。健太は恥ずかしさで死にそうになった。バラを育てる準備? 温室の温度がぴったり? それはすべて、宇宙生物のためだったのだ。彼はもはや、何も言うことができなかった。
しかし、佐藤さんは続けた。「ところで健太さん、この鉢カバー、ちょっと特殊な匂いがするのよね。何ていうか、ちょっと、こう……ヌルヌルしたような匂い?」
健太はハッとした。ヌルヌルした匂い。それは、彼がポヨに感じていた、あの独特の質感と結びつく言葉だった。佐藤さんは、ごく日常的なものの中に、自分と同じ「ヌルヌル」という感覚を見出していたのだ。健太はふと、これまで自分が見ていた「宇宙人」が、実は日常の中に潜む、誰も気づかないような「面白さ」だったのではないか、と思い始めた。自分の異常なまでの好奇心は、決して無意味ではなかったのだ。それは、平凡な世界に色を塗ろうとする、健太自身の純粋な探究心だった。
健太はその後、庭の温室を解体し、小さな家庭菜園を作ることにした。ミニトマトやバジル、そしてなぜかネギを植えた。毎日、彼はそれらの植物に水をやり、話しかける。成長が遅い時には心配し、実がなった時には喜びを表現する。それはまるで、かつてポヨに話しかけていた頃と同じ熱量だった。
健太はもう、夜空を見上げて宇宙人を探すことはなくなった。しかし、彼の日常は以前よりもずっと豊かになっていた。小さな植物たちの生命の営み、季節の移ろい、そして佐藤さんの無邪気な好奇心。それらすべてが、健太にとっての新たな「ヌルヌルした面白さ」となったのだ。彼は、特別な「宇宙人」などいなくとも、この世界には、まだ見ぬ奇妙で愛すべきものが溢れていることを知った。そして、自分の心の中にある、そうした「奇妙さ」を受け入れ、楽しむことができるようになっていた。彼は、少しだけ大人になり、自分の「変わり者」ぶりを、ユニークな個性として笑い飛ばせるようになった。佐藤さんとは、今では「あのヌルヌルした鉢カバー」をきっかけに、庭の植物について語り合う、奇妙な友情が芽生えつつある。健太の平凡な日常は、あのヌルヌルした鉢カバーが庭に現れて以来、確かに変わったのだ。それは、宇宙人がもたらすような劇的な変化ではなかったが、彼の心を深く、そして温かく満たすものだった。