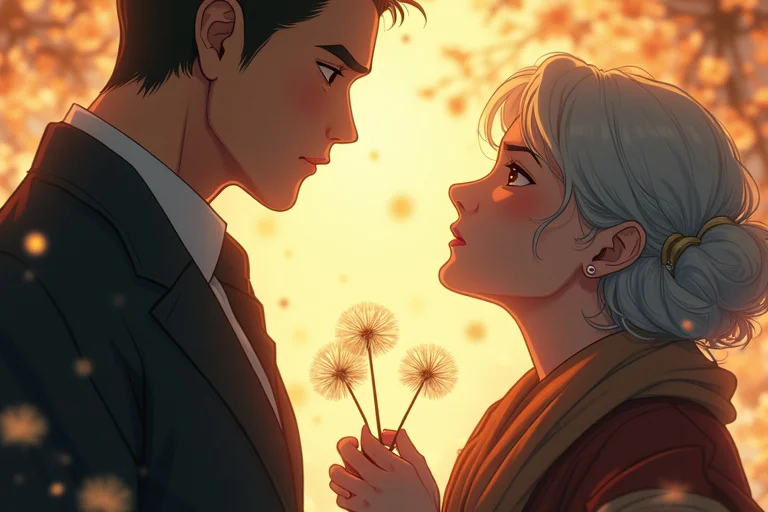第一章 無価値な男と一瞬の奇跡
この世界では、ユーモアが通貨だった。朝の挨拶に気の利いた冗談を添えれば、焼きたてのパンが手に入る。会議で機知に富んだ比喩を使えば、給料に「爆笑ボーナス」が上乗せされる。逆に、センスのない人間は社会の底辺で喘ぐしかなかった。人々は日々の支払いを「苦笑」や「微笑」で済ませ、大きな買い物には「大爆笑」が必要だった。
そして、僕、小林純平(こばやしじゅんぺい)は、紛れもなくこの世界の貧困層だった。
生まれついての真面目さと、致命的なまでのユーモアの欠如。僕が何か言えば、場の空気は北極の氷河期のように冷え込み、人々は財布(もちろん比喩的な意味だ)の紐を固く結ぶ。僕の全財産は、道行く人に会釈してかき集めた、雀の涙ほどの「愛想笑い」だけ。今日もそのなけなしの財産で、かろうじて固くなったパンの耳を一枚手に入れた。
「ああ……腹の足しにもならない」
公園のベンチでパンをかじりながら、僕は空を見上げた。空は皮肉なほどに青く澄み渡っている。広場では、人気のコメディアンが青空ライブを開いていた。彼の放つ一言一句に、人々は腹を抱えて笑い転げ、そのたびに目に見えない価値のシャワーが彼に降り注ぐ。いいなあ、面白い人間は。面白いだけで、あんなにも豊かになれるなんて。
僕だって、努力しなかったわけじゃない。ユーモア教本を読み漁り、鏡の前で何時間も変顔の練習をした。しかし、僕が実践すると、それはすべて「痛々しい悪あがき」にしかならなかった。僕のジョークは、もはや公害の域に達しているとさえ言われた。
そんな絶望的な日々の中、奇跡は唐突に訪れた。
その日、僕は空腹のあまり、街で一番と評判のパン屋『ブーランジェリー・エクスプロジオン』の前で立ち尽くしていた。ガラスケースの向こうで黄金色に輝くクロワッサンが、僕を誘惑する。値段は、驚異の「大爆笑一つ」。僕には到底手の届かない、夢のまた夢だ。
「……どうしても、食べたい」
その一心で、僕は震える足で店に入った。恰幅のいい店主が、いぶかしげな目で僕を見る。僕はなけなしの勇気を振り絞り、ここ一週間、寝る間も惜しんで考え抜いた渾身のジョークを口にした。
「あの……布団が、吹っ飛んだ……」
しん、と店内が静まり返った。ああ、まただ。いつもの氷河期だ。店主の眉間の皺が、マリアナ海溝よりも深く刻まれていく。僕は顔から火が出るのを感じ、慌てて店を飛び出そうとした。その、瞬間だった。
「ぶっふぉおおおおおおっ!」
店主が突然、火山が噴火するような勢いで吹き出した。彼はカウンターに突っ伏し、肩を震わせ、涙を流しながら笑い転げている。「ひ、ひぃ……ふ、布団が……! こ、こんな完璧な『無』は……聞いたことがない……! 芸術だ!」
何が何だか分からないまま、僕は店主から「お代は十分すぎるほど頂いた」と、山盛りのクロワッサンを渡された。温かくて、バターの香りがする夢のパンを抱え、僕は呆然と家路についた。
あれは一体、何だったんだ?
僕の人生で最もスベったはずのダジャレが、なぜ「大爆笑」の価値を生んだのか。
その日から、僕はその奇跡の謎に取り憑かれた。もう一度、あの感覚を。もう一度、あの豊かさを手に入れたい。僕の心に、これまで抱いたことのない熱い炎が静かに灯ったのだった。
第二章 伝説への扉と絶望的な修行
あの奇跡のクロワッサン以来、僕の人生は何も変わらなかった。相変わらず僕のジョークは極寒の空気を作り出し、人々は僕を避けるように通り過ぎていく。あの日の店主の爆笑は、やはり幻だったのだろうか。
「いや、幻じゃない。あの価値は本物だった」
僕は諦めきれなかった。あの謎を解き明かせば、僕も面白い人間になれるかもしれない。情報をかき集めるうち、僕は一つの名前にたどり着いた。かつて「爆天(ばくてん)」という名で一世を風靡した、伝説のコメディアン。彼はユーモアの本質を極め、その笑いは国さえ動かしたと言われている。しかし、十数年前に忽然と姿を消し、今ではその存在を知る者も少ない。
僕は、彼ならあの奇跡の謎を解いてくれるかもしれないと信じ、藁にもすがる思いでその行方を追った。数ヶ月にわたる聞き込みの末、僕はついに、街外れの古びた屋敷に隠居しているという彼を見つけ出した。
「弟子にしてください!」
埃っぽい門の前で、僕は土下座した。中から現れたのは、好々爺然とした老人。しかし、その眼光だけは剃刀のように鋭く、僕の全身を射抜くようだった。彼こそが、伝説の爆天だった。
「帰れ。ワシはもう引退した身だ」
爆天は冷たく言い放った。しかし、僕は諦めなかった。雨の日も風の日も門の前に座り込み、僕がなぜ彼を必要としているのか、あのクロワッサンの日の出来事を切々と語った。三日目の夜、根負けしたのか、爆天は重いため息をついて僕を家の中に招き入れた。
こうして、僕と伝説のコメディアンとの奇妙な共同生活が始まった。しかし、彼の修行は僕の想像を絶するものだった。
「いいか、純平。まず、その教本をすべて燃やせ」
爆天は僕が大切にしていたユーモア教本の山を指さした。
「次に、モノボケもダジャレも禁止だ。変顔もだ」
「えっ、じゃあ何をすれば……」
「黙って庭の掃除をしろ。一日中だ。ただし、真面目にやれ。一点の曇りもなく、ただひたすらに真面目にだ」
意味が分からなかった。面白くなるための修行が、庭掃除? しかし、僕は彼の言葉を信じるしかなかった。来る日も来る日も、僕は無心で庭の草をむしり、落ち葉を掃いた。面白いことなど、何一つ考えなかった。
一ヶ月後、爆天は僕を座らせ、こう言った。
「よし、何か言ってみろ」
僕は困惑した。あれだけジョークを禁じられていたのに。僕は必死に頭を捻り、当たり障りのないことを言った。
「今日は、いい天気ですね」
爆天は、深く、深く頷いた。
「……ダメだ。まだ邪念がある。『いい天気ですね』の中に、ほんの少しだけ相手に媚びようという気持ちが見える。お前の言葉は、もっと純粋な『無』でなければならん」
絶望的な気分だった。僕には彼の言う「無」が何なのか、さっぱり理解できなかった。彼は僕に面白くなる方法を教える気などないのではないか。ただ、無償の庭師として僕を利用しているだけではないのか。疑念が心を蝕んでいく。それでも、僕にはもう、彼を信じる道しか残されていなかった。僕はただ、言われるがままに、面白くなることを忘れ、ひたすらに「真面目」を追求し続けた。
第三章 逆転の舞台
「純平、お前を『全日本ユーモア選手権』に出す」
修行開始から半年が過ぎたある日、爆天は唐突にそう告げた。僕は耳を疑った。ジョークの一つも許されず、ただ真面目に暮らすことだけを強いられてきた僕が、国中の猛者が集う最高の舞台に?
「無茶です! 僕が出たら、大会の歴史に残る放送事故になります!」
「それでいい」
爆天はニヤリと笑った。その顔は、まるで壮大ないたずらを企む子供のようだった。
「何も考えるな。何も付け加えるな。お前はただ、舞台に立って、ありのままでいればいい」
僕は抵抗した。しかし、彼の決定は覆らない。僕は半ば強制的に、選手権の予選にエントリーさせられた。もちろん、予選会場は阿鼻叫喚の地獄と化した。僕が舞台に立っただけで、審査員の顔は凍りつき、観客は冷たい沈黙に包まれた。誰も笑わない。誰も。
だが、なぜか僕は予選を通過した。後で聞けば、審査員の一人が「彼の『スベり』には、一周回って哲学的な深みがある」などと訳の分からないことを力説したらしい。そして、僕はあれよあれよという間に決勝の舞台にまで駒を進めてしまった。
決勝当日。きらびやかな照明、数千人の観客、テレビカメラ。僕は手足が氷のように冷たくなり、心臓が喉から飛び出しそうだった。舞台袖で、爆天が僕の肩を叩いた。
「純平。お前の武器は、面白さじゃない。お前の武器は、お前自身だ。行け」
順番が来て、僕は震える足でステージの中央へと歩み出た。スポットライトが眩しい。観客の顔は、期待に満ちている。僕はマイクを握りしめ、深呼吸した。そして、爆天に言われた通り、ただ、ありのままの自分でいようと決めた。僕が半年間、考えに考え抜いた「究極に普通のこと」を、ただ口にした。
「……こんばんは。小林純平です。本日は、お集まりいただき、ありがとうございます」
会場が、しん……と静まり返った。それは予選の時とは比べ物にならない、宇宙的な静寂だった。観客たちの顔から、みるみる表情が消えていく。ざわめきすら起きない。完全な「無」。僕は頭が真っ白になり、全身から汗が噴き出した。
ああ、終わった。僕の人生も、日本のコメディ界も、今日ここで終わるんだ。
絶望が僕を飲み込もうとした、その時だった。
「くっ……くくく……!」
審査員席に座っていた、最も高名な評論家が、肩を震わせ始めた。彼は口元を押さえ、必死に笑いを堪えている。しかし、こらえきれなかったのだろう。
「ぶはははははは! なんだこれは! この完璧なまでの『面白くなさ』は! 一点の遊びもなく、計算され尽くしたかのような純粋な退屈! 間! 表情! 声のトーン! 全てが奇跡的なまでに、面白くない! これは……これは天才だ!」
彼の爆笑は、まるで伝染病のように客席へと広がっていった。一人、また一人と、人々が腹を抱え始める。「た、確かに!」「このスベり方は芸術の域だ!」「面白くなさすぎて、逆に面白い!」
会場は、やがて地鳴りのような爆笑の渦に包まれた。僕は、何が起きているのか理解できないまま、ステージの中央で立ち尽くすしかなかった。人々は、僕の「面白くなさ」に、涙を流して笑い転げているのだ。
舞台袖から、満足げな顔で爆天が現れた。彼はマイクを手に取り、叫んだ。
「諸君、これがユーモアの新たな地平だ! 面白いことを言うだけが笑いではない! この男、小林純平は、その存在そのものが『究極のアンチ・ユーモア』として完成されているのだ! ワシは彼の才能に、最初から気づいていた!」
そうか。そういうことだったのか。
あのクロワッサンの日の奇跡も、爆天の謎の修行も、すべてはこの瞬間のためだったのだ。彼は僕に面白いことを教えるのではなく、僕の中に眠っていた「究極の面白くなさ」という唯一無二の才能を、極限まで磨き上げてくれていたのだ。
その年のユーモア選手権は、小林純平という無名の新人が、一言も面白いことを言わずに優勝するという、前代未聞の結果に終わった。
第四章 新たな王の誕生
あの日を境に、僕の世界は一変した。僕は「面白くない」ことで、最も面白い人間になったのだ。人々は僕を、敬意と少しの畏怖を込めて、こう呼んだ。「沈黙卿(サイレント・ロード)」と。
僕のショーのチケットは、発売と同時に完売する。満員のホールで、僕はただステージに立ち、真面目な顔で時候の挨拶をしたり、昨日の夕食の献立を淡々と述べたりするだけ。すると観客は、僕のその完璧なまでの「無芸」の芸に、歓喜の涙を流して喝采を送るのだ。
かつて僕を蔑んだ人々は、今や僕の一挙手一投足に「大爆笑」の価値を見出す。僕はもう、なけなしの「愛想笑い」で固いパンを買う必要はない。僕の銀行口座には、人々からの賞賛と笑いが、天文学的な数字となって積み上がっていく。
だが、最も大きな変化は、僕の内面に起きていた。
僕はもう、面白い人間になろうと足掻くのをやめた。自分の欠点だと思い、ずっと呪い続けてきた「面白くなさ」が、実は誰にも真似できない最高の個性なのだと、ようやく受け入れることができたからだ。
ある公演の夜。僕は出番を前に、楽屋の鏡に映る自分の顔をじっと見つめていた。そこにいたのは、もう卑屈で自信なさげな貧乏人ではなかった。背筋を伸ばし、静かな自信に満ちた一人の表現者としての僕がいた。
「師匠」
背後から、爆天が声をかけた。彼は今や、僕の専属プロデューサーだ。
「今日の客も、お前の『無』を待ち望んでいるぞ」
「はい」
僕は静かに頷いた。
「ありがとうございます、師匠。僕を、僕のままにしてくれて」
爆天は、初めて出会った時のような、優しい笑みを浮かべた。
「礼を言うのはワシの方だ、純平。お前はワシに、笑いの世界の、まだ見ぬ景色を見せてくれた」
スポットライトが僕を照らす。割れんばかりの拍手と、期待に満ちた笑い声。
僕はステージの中央に進み出て、深く、深く一礼した。何も言わない。ただ、そこにいるだけ。それだけで、会場は幸福な爆笑の渦に包まれる。
僕はゆっくりと顔を上げた。観客一人ひとりの笑顔が、光の粒子のように降り注いでくる。それは温かく、僕の心の隅々までを満たしていくようだった。
かつてあれほど渇望した「笑い」。それを、僕は僕自身のままで、今、この手で生み出している。
幕が下り、静寂が戻った楽屋で、僕はもう一度鏡の前に立った。
鏡の中の男が、ゆっくりと口角を上げる。それは、誰かに媚びるための「愛想笑い」でも、無理に作った「変顔」でもない。僕の心の中から、じんわりと滲み出てきた、生まれて初めての、穏やかで、満ち足りた微笑みだった。
面白さとは、一体何なのだろう。その答えはまだ分からない。けれど、もう探す必要はないのかもしれない。僕という存在が、その一つの答えなのだから。