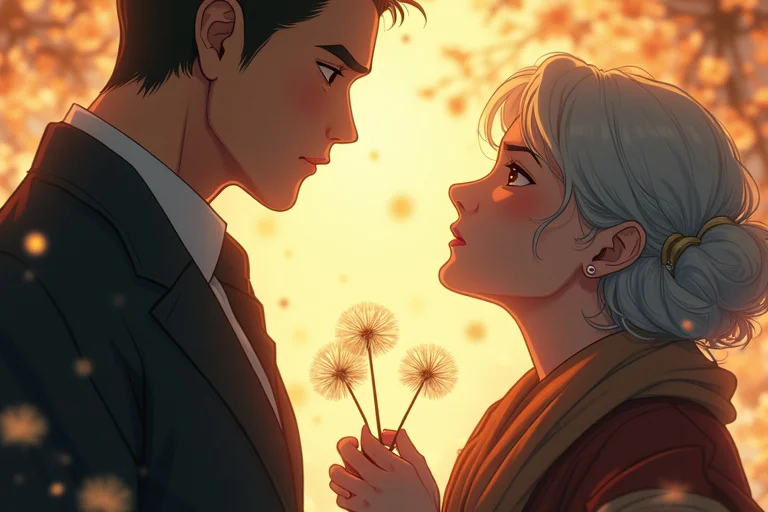第一章 月からの婚姻届
灰田道夫の人生は、無味乾燥なビスケットのようなものだった。それも、湿気って味の抜けたやつだ。市役所の戸籍係という仕事は、人生の節目に立ち会う華やかな職場のはずだが、彼にとってはただの文字列と印鑑の連続でしかない。彼の表情筋は、長年の不使用により化石化していると噂されていた。同僚たちが「鉄仮面」とあだ名するのも無理はなかった。
しかし、灰田が感情を押し殺しているのには、深刻な理由があった。彼の感情は、物理的な形を伴って具現化してしまうのだ。
喜びを感じれば、ふわふわしたタンポポの綿毛が。悲しめば、ずしりと重い黒曜石の涙滴が。腹を立てれば、チリチリと熱を帯びた唐辛子の種が、ポケットや服の隙間からポロリとこぼれ落ちる。それは、生まれた時からの呪いのような体質だった。幼い頃、遠足が嬉しくてリュックサックを綿毛でパンパンにしてしまったり、いじめられて泣いた日には、帰り道に黒曜石をばら撒いて母親を心配させたりした。
以来、灰田は感情を抱くことをやめた。心を凪いだ水面のように保ち、どんな出来事にも動じない。それが、彼が三十五年かけて習得した唯一の生存戦略だった。
そんな彼のビスケットのような日常に、ある日、とんでもない異物が混入した。
「婚姻届を出しに来たよ」
カウンターの向こうに現れたのは、背中の曲がった小柄な老婆だった。年の頃は九十に近いだろうか。しかし、その瞳だけは悪戯好きな少女のようにキラキラと輝いていた。老婆――天野ハツエは、しわくちゃの手で一枚の紙を灰田の前に突き出した。
灰田は機械的にそれを受け取る。そして、眉一つ動かさずに固まった。
夫となる者の氏名欄に、こう書かれていたのだ。
『月ノ兎様(つきのうさぎさま)』
住所は『月面、静かの海』。職業は『餅つき』。
灰田は無表情のまま、ゆっくりと顔を上げた。
「天野さん。これは、受理できません」
「なんでさ」
ハツエは唇を尖らせる。
「戸籍法上、実在しない人物との婚姻は認められておりません。月にはウサギは……おりませんし、そもそも生物が存在しません」
正論だった。完璧な正論だった。しかし、ハツエはケラケラと笑った。
「あんた、つまんない男だねぇ。心にタンポポの一本も咲いてないのかい?」
その瞬間、灰田のズボンのポケットが、内側から微かに蠢いた。ポケットの中で、ねじくれた一本の針金――『困惑』の感情が、生まれ落ちたのだ。彼は咄嗟にポケットに手を突っ込み、その存在を握りつぶした。危なかった。ほんの少しでも気を抜けば、カウンターの上に転がり出てしまうところだった。
「とにかく、これはお受け取りできません」
「ちぇっ。また来るからね。兎様によろしく言っとくれ」
ハツエはそう言い残し、軽やかな足取りで去っていった。
灰田は、深く、誰にも気づかれないようにため息をついた。ポケットの中の針金が、指にちくりと食い込む。嵐の前の、不穏な静けさ。彼の無味乾燥な日常が、音を立ててひび割れ始めた瞬間だった。
第二章 タンポポと唐辛子
ハツエの襲来は、一度きりではなかった。彼女は宣言通り、それから毎日、飽きもせず市役所にやってきた。ある日は兎様との馴れ初めをオペラ調で歌い上げ、またある日は「新居のリフォーム」と称して月の土地の権利書(もちろん手書き)を持参した。
そのたびに灰田のポケットは、様々な感情のガラクタで満たされていった。
「あんたも、兎様との結婚式に来るといいよ。スピーチを頼むから」と言われれば『困惑の針金』が数本。他の職員が笑いをこらえる中、一人真顔で対応する灰田のポケットの奥底では、『怒りの唐辛子の種』がじりじりと熱を発していた。
彼は毎晩、家に帰るとポケットの中身を小さなビニール袋に捨てるのが日課だった。針金、唐辛子、針金、唐辛子……。まるで、不毛な感情のゴミを仕分けしているようだった。
そんなある日、ハツエは大きなタッパーを抱えてやってきた。
「兎様と、あんたのために焼いてきたよ。星屑クッキーさ」
蓋を開けると、バターの甘い香りがふわりと広がった。金平糖がまぶされた、不格好だが美味しそうなクッキーだった。
「いえ、結構です。職務中ですので」
灰田が冷たく断ると、隣の席の若い女性職員、佐藤さんが「わあ、美味しそう! 私、一ついただいてもいいですか?」と身を乗り出した。
「もちろんだよ、お嬢ちゃん。たくさんお食べ」
ハツエがにこやかに差し出すと、佐藤さんは一つ口に放り込み、目を丸くした。
「美味しい……! なんですかこれ、すごく優しい味がします!」
その言葉に、灰田の意志がわずかに揺らいだ。ハツエは勝ち誇ったように、一枚のクッキーを灰田の口元にぐいと押し付けた。
「いいから、食べな。心がカサカサの男には、栄養が必要さ」
抵抗する間もなく、クッキーが口の中に押し込まれる。サクッとした食感。バターと、ほんのり香るシナモン。そして、砂糖の甘さだけではない、温かくて、どこか懐かしい味。灰田は、何年も忘れていた感覚に襲われた。これは、ただのクッキーじゃない。心が、じんわりと温められるような……。
その時だった。
ふわっ。
灰田の胸ポケットから、白い何かが舞い上がった。それは一本の、タンポポの綿毛だった。
『喜び』の感情。
綿毛は、空調の風に乗ってゆるやかに漂い、ハツエの黒いカーディガンの肩に、そっと着地した。
時が止まった。佐藤さんは不思議そうに綿毛を見ている。しかし、ハツエは違った。彼女は、その白い綿毛を驚きもせず指でつまみ上げると、灰田を見て、悪戯っぽくニヤリと笑った。まるで、すべてお見通しだと言わんばかりに。
灰田は血の気が引くのを感じた。見られた。この呪われた体質を、この得体の知れない老婆に見抜かれた。彼は全身が凍りつくのを感じながらも、かろうじて平静を装った。しかし、ポケットの中では、パチパチと音を立てて『驚きの線香花火』が激しく火花を散らしていた。
第三章 嵐の夜の訪問者
あの日以来、灰田はハツエを徹底的に避けるようになった。彼女が窓口に来ると、他の職員に代わってもらった。トイレに立つふりをして席を外した。まるで、天敵から身を隠す小動物のように。
ハツエは、それでも毎日やってきた。そして、灰田の姿を探しては、少し寂しそうに帰っていくのだった。そんな日々が二週間ほど続いた頃、街は大型の台風に見舞われた。風が唸りを上げ、雨が窓ガラスを叩きつける。市役所も早々に閉庁することになった。
誰もいなくなった薄暗い庁舎で、灰田は一人、ぼんやりと外を眺めていた。今日は、ハツエは来なかった。当たり前だ。こんな嵐の中、外出する老人がいるはずもない。なのに、なぜだろう。胸のあたりが、妙にざわつくのだ。いつも彼女が座っていた待合の椅子が、やけに空虚に見えた。
気づけば、灰田は古い住所録のファイルをめくっていた。「天野ハツエ」の名前はすぐに見つかった。市役所から歩いて十五分ほどの、古い木造アパートの一室。
なぜ、自分はこんなことをしているのだろう。自問しながらも、足は勝手に動き出していた。傘を強く握りしめ、彼は嵐の中へと飛び出した。
ずぶ濡れになりながらアパートに着くと、ハツエの部屋のドアは固く閉ざされていた。何度ノックしても返事はない。不安が胸をよぎったその時、隣の部屋のドアが開き、中年女性が顔をのぞかせた。
「あの……天野ハツエさんのことで、何かご存知ですか?」
灰田が尋ねると、女性は怪訝な顔をした。
「天野さん? ああ、二階の。あそこのおばあちゃんなら、一月ほど前に娘さんに引き取られて、施設に入ったわよ。もうここには住んでないわ」
……一月前?
灰田の頭は真っ白になった。じゃあ、毎日市役所に来ていたあのハツエは、一体誰だったんだ? 混乱する灰田に、女性は一枚のメモを渡した。
「娘さんの連絡先なら、これ」
震える指で、灰田はその番号に電話をかけた。数コールして繋がった相手は、落ち着いた声の女性だった。灰田が事情を話すと、電話の向こうで長い沈黙があった。そして、すすり泣き混じりの声が聞こえてきた。
「母は……天野ハツエは、一週間前に、眠るように亡くなりました」
雷が、すぐ近くに落ちたような衝撃だった。
「母は、晩年、アルツハイマー型認知症を患っておりまして……。亡くなった父のことを、ずっと『月に住むウサギ様』だと思い込んでいたんです。父は宇宙物理学の研究者で、生前よく『いつか月に住むウサギに会いに行くんだ』と、母に冗談を言っていましたから……」
灰田は言葉を失った。毎日市役所に通い、彼を振り回していたハツエは、彼女の強い想いが生み出した幻影か、あるいは、愛情深い幽霊だったというのか。コメディだと思っていた日常は、あまりにも切ない幻想劇だった。
「母は、あなたのことをよく話していました。『市役所に、心が空っぽになっちまった、可哀想な若い男がいるんだ。あの子の心に、綺麗な花を咲かせてやりたい』って……。もしよろしければ、一度、お会いできませんか。母が、あなたに渡してほしいと、最後まで握りしめていたものがあるんです」
第四章 ポケットから、春
翌日、灰田は指定されたハツエの娘の家を訪れた。そこは、小さな庭に季節の花が咲き乱れる、温かい雰囲気の家だった。仏壇に静かに手を合わせると、娘さんが桐の小箱を差し出した。
「これが、母からです」
蓋を開けた瞬間、灰田は息を呑んだ。
箱の中には、色とりどりの感情の欠片が、宝石のようにきらめきながら、たくさん詰まっていた。
ふわふわした、たくさんの『喜びのタンポポの綿毛』。
ほんのり温かい、桜色の『愛情のマシュマロ』。
そして、底の方には、冷たくて重い、いくつかの『悲しみの黒曜石の涙滴』。
「母も、あなたと同じだったようです。感情が、形になって現れる体質でした。だから、あなたの苦しみが、痛いほどわかったんだと思います。あなたのポケットから綿毛が飛び出したあの日、母は本当に嬉しそうでした。『あの子の心にも、まだ花が咲く』って……」
ハツエもまた、同じ呪いを抱え、それでも人を愛し、誰かのために心を動かすことをやめなかったのだ。灰田をからかい、困らせていた日々の中で、彼女はこんなにも豊かな感情を抱いてくれていた。箱の中の欠片一つ一つが、ハツエの生きた証のように思えた。
灰田の目から、熱いものがこぼれ落ちた。それは涙だった。すると、彼のポケットから、ずしりと重い黒曜石の涙滴が一つ、ことりと床に転がった。続いて、ハツエへの感謝の気持ちが、ほんのり温かい桜色のマシュマロとなって現れる。驚きと、後悔と、どうしようもないほどの愛しさが入り混じり、ポケットの中は、これまで経験したことのない、感情の嵐に見舞われた。
市役所に戻った灰田は、もう以前の彼ではなかった。
彼の足元に、ポケットからあふれ出した感情の欠片がぱらぱらとこぼれ落ちるのを、同僚たちが唖然として見ていた。黒曜石、マシュマロ、パチパチ弾ける線香花火。まるで、奇妙な手品師のようだった。
佐藤さんがおずおずと尋ねる。
「灰田さん……大丈夫ですか? それ、一体……」
灰田は、こぼれ落ちた欠片たちを、愛おしそうに見つめた。そして、何十年ぶりかに、自分の意思で口角を上げた。それはまだぎこちない、小さな微笑みだったが、紛れもない『笑み』だった。
「ちょっと、ポケットに春が来すぎたみたいです」
その言葉が合図だったかのように、彼の足元から、何十、何百というタンポポの綿毛が、ふわり、ふわりと舞い上がった。庁舎の窓から差し込む西日が、それを金色に照らし出す。それはまるで、ハツエが遅れて届けに来てくれた、温かい春そのものだった。
もう、感情を隠す必要はない。嬉しい時は笑い、悲しい時は泣けばいい。ポケットからこぼれ落ちるガラクタは、呪いなんかじゃない。自分が豊かに生きている証なのだ。
灰田道夫の「鉄仮面」は、その日、音を立てて剥がれ落ちた。窓の外には、いつの間にか、優しい光を放つまんまるな月が浮かんでいた。まるで、兎様が静かに微笑んでいるかのように。彼のビスケットのような人生は、これからきっと、星屑クッキーのように甘く、豊かな味わいになっていくのだろう。