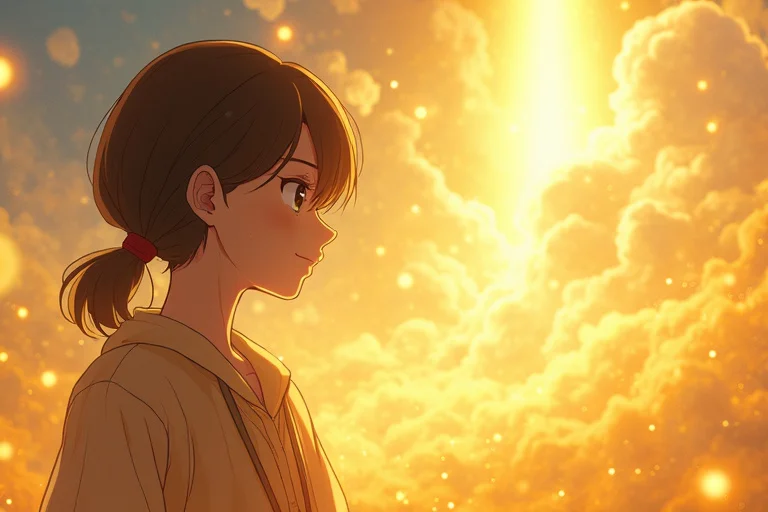第一章 エンドレス・スリップ
天野翔(あまの しょう)、芸名アマショーの芸人人生は、もはや地獄という言葉ですら生ぬるい、無間地獄の様相を呈していた。彼の主戦場である、寂れた地下ライブハウスの空気は、いつも鉛のように重い。スポットライトの熱だけが虚しく肌を焼き、まばらな客席から注がれるのは、好奇心ではなく、同情と侮蔑が入り混じった冷ややかな視線だった。
今夜もそうだ。翔が自信満々で繰り出した渾身のフリップ芸、「もしも戦国武将がスマホを持ってたら」。信長が「本能寺なう。マジ卍」と炎上ツイートするネタで、客席は深海のごとく静まり返った。ヒリつくような沈黙。汗がこめかみを伝い、マイクを握る手が滑る。
「えー、次が最後ですけども」
絞り出した声は、自分でも驚くほど上ずっていた。彼は最後のフリップをめくる。そこに書かれていたのは、彼が三日三晩考え抜いた、起死回生の一発ギャグ。
「セミってさあ、七日間しか生きられないって言うけど……俺の芸人人生より、濃密セミじゃない?」
シーン……。
時間が止まったかのような静寂。客の一人が、あからさまに大きなため息をついた。その音が、翔の心を粉々に砕く合図だった。彼は逃げるように舞台を降り、楽屋の隅で膝を抱えた。芸人仲間からの慰めの言葉も、耳をすり抜けていく。自意識が、敗北感という名の粘着テープでぐるぐる巻きにされていた。
重い足取りでライブハウスを出る。深夜の冷たい風が、火照った頬に心地よかった。見上げた空には、情けない三日月が浮かんでいる。
「濃密セミ……ってなんだよ……」
自嘲の言葉が漏れた。その時だった。
ゴウッ、と耳元で風を切る音がした。見上げた視線の先、雑居ビルの屋上から、古びた看板が剝がれ落ちてくるのがスローモーションで見えた。『スナック哀愁』。その文字が、なぜかやけにハッキリと目に焼き付いた。
次の瞬間、世界は暗転した。痛みも、驚きも感じる暇はなかった。ああ、俺の人生、最後のオチもスベったままか。そんな、どうでもいい思考が、意識の最後に浮かんで消えた。
はずだった。
「――次が最後ですけども」
ハッとして顔を上げる。目の前には、見慣れた舞台の照明。手には、あの忌まわしいフリップ。耳には、自分の上ずった声が反響している。
デジャヴ? いや、違う。これは、さっきと寸分違わぬ光景だ。客席の、あの大きなため息をついた男も、同じ席で腕を組んでいる。
混乱する頭で、翔は無意識に最後のフリップをめくった。
「セミってさあ……」
口が勝手に動く。やめろ、それを言ったら、また……!
「……濃密セミじゃない?」
再び、深海の静寂。そして、絶望的な敗北感。
訳が分からないまま、翔はふらふらとライブハウスを出た。さっきと同じ道、同じ三日月。まさか、と思いながら例のビルの前を通りかかる。
その瞬間、またしてもゴウッという風切り音。見上げると、『スナック哀愁』の看板が、寸分たがわぬ軌道で迫ってきていた。
「うわああああ!」
今度は叫び声と共に、意識がブラックアウトした。
そして彼は、また舞台袖にいた。
「……アマショー、出番だぞ」
ディレクターの声が、地獄の鐘の音のように聞こえた。どうやら俺は、人生で最悪にスベったあの瞬間を、死ぬたびに繰り返す呪いにかかってしまったらしい。
第二章 ウケの公式を求めて
ループは、地獄の反復練習だった。看板に潰されるのに飽きた頃には、階段から足を踏み外したり、猛スピードの自転車にはねられたり、マンホールに落ちたりと、まるでタチの悪いコントのように、翔は様々な死に方で舞台袖へと強制送還された。三十回目を数える頃には、彼は絶望を通り越し、奇妙な使命感に燃えていた。
「このループを抜け出す方法は一つしかない。あの舞台で、客を爆笑させることだ!」
彼は変わった。ネタを練り直し、話し方を変え、間の取り方を研究した。流行りの芸人の動画を擦り切れるほど見て、ウケるための「公式」を探し求めた。
「ツッコミは、相手のボケから三歩引いて、斜め45度から斬り込むのがセオリーらしい」
「フリップのめくり方一つで、期待感が変わる。めくる速度は秒速1.2メートル……」
ブツブツと呟きながら、彼は狂ったように練習を重ねた。楽屋の仲間たちは、急に研究熱心になった翔を気味悪がったが、彼に構っている暇はなかった。
しかし、結果は惨憺たるものだった。小手先のテクニックは、彼の空回りを助長するだけだった。客席の温度は、氷点下から一向に上がる気配がない。ループを五十回繰り返した頃、翔の心は完全に折れかかっていた。
ある日のループ。いつものようにスベり、いつものように死ぬ前の猶予時間。翔はあてもなく公園のベンチに座っていた。もう、どうでもいい。次の死に方は、どんなマヌケな死に方だろうか。そんなことを考えていると、隣のベンチに座っていた老人が、独り言のように呟いた。
「間が悪いねえ」
見ると、老人はスマホで漫才動画を見ていた。翔が昨日、研究のために見たばかりの若手コンビだ。
「そうですかね。今、一番勢いありますけど」
翔は、無意識に反論していた。
「勢いだけだよ。客にウケよう、ウケようって気持ちが前に出すぎてる。だから、笑いが窮屈なんだ。本当に面白い芸ってのはな、演者が一番楽しんでるもんなんだよ」
老人は、こともなげにそう言った。その言葉は、翔の心に小さな石ころのように投げ込まれ、静かな波紋を広げた。
演者が、一番楽しむ?
俺は、楽しんでいるだろうか。客の顔色を窺い、ウケるかどうかばかりを気に病んで、心の底から自分のネタを楽しんだことなんて、一度でもあっただろうか。
その日は、トラックにはねられてループが終了した。戻った舞台袖で、翔は老人の言葉を反芻していた。
楽しむ、か……。
第三章 究極のジョークと終わらない夜
老人の言葉にヒントを得た翔は、戦略を変えた。ウケるための公式探しをやめ、「自分が本当に面白いと思うことは何か」を自問自答し始めた。子供の頃に友達と笑い転げたくだらないダジャレ。授業中にこっそり回した、先生の似顔絵の落書き。そういう、誰の評価も気にしなかった頃の、純粋な「面白い」の記憶を掘り起こしていった。
そして、百回目を超えるループの中、ついに彼は一つの答えに辿り着く。それは、テクニックでも、計算でもない。彼の原体験に基づいた、あまりにもパーソナルで、あまりにもバカバカしい、一つの物語だった。
それは、彼が小学生の頃、飼っていたハムスターの「ハム恵」が、回し車を光の速さで回し続け、最終的に時空の歪みに飲み込まれて消えてしまったという、壮大な(もちろん嘘の)冒険譚だった。
彼はフリップ芸のスタイルを捨て、マイク一本の漫談に切り替えた。
その夜の舞台。翔は、いつもとは違う種類の緊張と、確かな高揚感に包まれていた。彼は客席を見ない。ただ、頭の中にいる小学三年生の自分に向かって語りかけるように、ハム恵の物語を話し始めた。
「うちのハム恵、ただのハムスターじゃなかったんすよ。あいつ、たぶん相対性理論を理解してて……」
最初はポカンとしていた客席から、やがてクスクスという笑いが漏れ始めた。翔の話はどんどん熱を帯びていく。ハム恵がブラックホールから送ってきたという、ヒマワリの種に書かれた謎のメッセージ。時空を超えて再会を誓う、飼い主とハムスターの絆。
話がクライマックスに差しかかった時、翔は見た。最前列に座っていた、おかっぱ頭の少女が、腹を抱え、涙を流して笑っているのを。
やった! 心から笑わせることができた!
少女の純粋な笑い声は、鉛のようだった空気を震わせ、会場全体に伝染していく。大きな、温かい笑いの渦。翔は芸人人生で初めて、本当の喝采を浴びた。
これで、呪いは解ける。
万感の思いで舞台の袖に下がった翔は、達成感に震えていた。しかし、その時だった。背後で、照明機材がギシリと音を立てたかと思うと、彼の頭上に、ゆっくりと落下してきた。
嘘だろ。
目の前が暗転する瞬間、翔の耳には、まだ温かい観客の笑い声が、遠ざかるように響いていた。
気がつくと、彼はまた、あの舞台袖にいた。
「……アマショー、出番だぞ」
絶望が、彼の全身を叩きのめした。なぜだ。心から笑わせたはずなのに。何が間違っている?
頭が真っ白になったまま舞台に上がり、彼は無意識にハム恵の話を始めた。だが、もうそこにかつての熱はなかった。客席は再び深海に戻り、彼はその日、交差点で信号無視の車にはねられた。
何十回、何百回とループを繰り返しても、答えは見つからない。翔は、もはや自分が何のために舞台に立っているのかさえ、分からなくなっていた。
第四章 僕だけの喝采
さらに数えきれないほどのループが過ぎたある夜、翔は全てを諦めていた。公園のベンチに座り、空を見上げる。また、あの老人が隣に座り、スマホで何かを見ている。
「兄ちゃん、まだやってたのかい」
老人は、翔がループしている人間だと知っているかのような口ぶりだった。
「もう疲れましたよ。何をしてもダメだ。最高のネタを作って、客を笑わせたのに……それでも、ループは終わらない」
翔は、魂が抜けたように呟いた。
老人はスマホから顔を上げ、じっと翔の顔を見た。
「一つ、聞いてもいいかい」
「……何です」
「兄ちゃんは、自分のネタで、腹の底から笑ったことがあるのかい?」
その一言は、雷のように翔の脳天を貫いた。
自分のネタで、笑う?
考えたこともなかった。ウケるか、スベるか。評価されるか、されないか。それだけが全てだった。客席の少女が笑った時、彼は確かに嬉しかった。だがそれは、呪いが解けるという安堵感と、他人に認められたという達成感から来る喜びだった。彼自身は、あの時、笑っていただろうか? いや、必死だっただけだ。
「本当に面白い芸ってのはな、演者が一番楽しんでるもんだよ」
かつて聞いた言葉が、全く違う意味を持って蘇る。
そういうことだったのか。
呪いの正体は、「誰かを笑わせられないこと」ではなかった。「自分自身が、自分の表現で心から笑えないこと」。他人の評価という呪縛に囚われていたのは、他の誰でもない、俺自身だったんだ。
次のループ。
舞台に上がった翔の表情は、晴れやかだった。彼はマイクの前に立つと、深呼吸を一つした。
「どうもー、アマショーでーす。えー、今日は一つ、僕が世界で一番面白いと思う話をします」
彼は、客席を見なかった。審査員も、ディレクターも、もう彼の世界にはいない。彼はただ、自分というたった一人の観客のために語り始めた。
それは、ハム恵の話でもなければ、練り上げられたネタでもなかった。彼が、この無限ループの中で体験した、数々のマヌケで、滑稽で、哀れな死に様の数々だった。
「百三十回目の死に方なんですけど、これがまた傑作でしてね。鳩のフンが直撃して、あまりの衝撃によろけて、そのままマンホールに……」
彼は、自分の無様さを、失敗を、赤裸々に語った。テクニックも、間も、何もかも無視して、ただ思ったままに。
最初は戸惑っていた客席。だが、翔のあまりに楽しそうな語り口に、少しずつ引き込まれていく。
そして、翔は自分が看板に潰された最初の夜の話に差しかかった時、ついにこらえきれなくなった。
「その看板が『スナック哀愁』って言うんすよ! 俺の人生、どんだけ哀愁漂ってんだって! あはははは!」
彼は、舞台の上で腹を抱えて笑い出した。涙が出るほど、息ができなくなるほど。それは、誰かに見せるための笑いじゃない。心の底から湧き上がってきた、どうしようもなくおかしくて、愛おしい、自分自身への笑いだった。
観客は、数人がつられて笑っているだけだった。ほとんどは、狂ってしまった芸人を眺めるように、ポカンとしている。大爆笑とは、ほど遠い。
だが、翔にとっては、それでよかった。
彼が心から笑ったその瞬間、世界から音が消えた。スポットライトの光が、ふわりと柔らかくなる。落下してくるはずの機材も、鳴り響くはずのクラクションも、もうない。
ループは、終わった。
舞台が終わり、まばらな拍手の中、翔は深く頭を下げた。楽屋に戻っても、誰かが彼を褒めるわけでもない。だが、彼の心は、これまで感じたことのないほどの充足感で満たされていた。
帰り道。かつて看板が落ちてきたビルの下を、彼は少しだけ身構えながら通り過ぎる。何も起きない。代わりに、ポツリと肩に冷たいものが落ちてきた。見上げると、電線にとまった鳩が、すまし顔でこちらを見ている。
「……ついてねーな!」
翔は空に向かって叫んだ。だが、その顔は、なぜか満面の笑みだった。
芸人として成功するかは、まだ分からない。明日もまた、スベるのかもしれない。でも、もう彼は大丈夫だろう。
人生という、時にスベることもある壮大な舞台で、自分こそが、最高の観客なのだから。