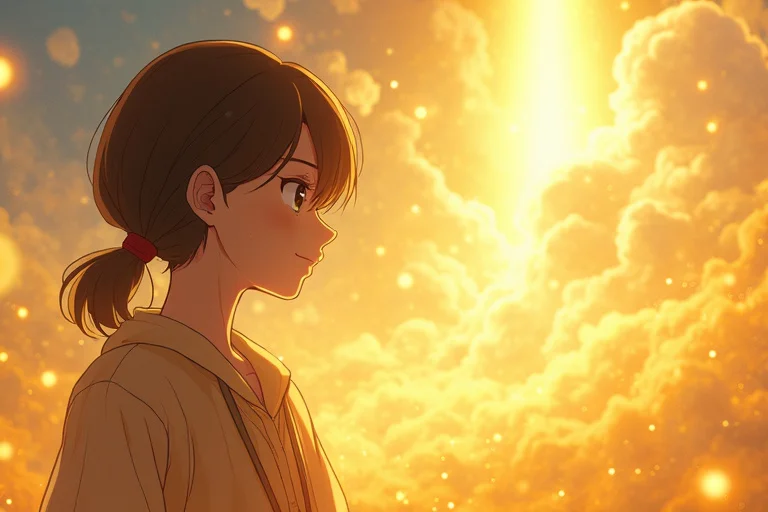第一章 静寂を切り裂くツッコミ
僕、間宮修二は、重度のアレルギー持ちだ。ただし、僕が反応するのは花粉でも甲殻類でもない。「ボケ」に対してである。
人が「ボケ」と認識される言動を発した瞬間、僕の意思とは無関係に、喉がひきつり、口が勝手に動き、脳の奥底から最適化された「ツッコミ」の言葉が光速で放たれるのだ。それは呪いと言ってもよかった。この体質のせいで、僕は真面目な会話を望んでも、相手の些細な言い間違いや天然な行動に「なんでやねん!」と絶叫し、友人関係をことごとく破壊してきた。結果、僕は人と深く関わることを諦め、静寂を愛するようになった。
そんな僕にとって唯一の聖域が、路地裏にひっそりと佇む喫茶店『無風』だった。年季の入った木のカウンター、琥珀色の照明、そして珈琲豆を挽く音だけが響く空間。何より素晴らしいのは、無口で、職人のように黙々と仕事をするマスターの存在だ。彼がボケる姿など想像もつかない。僕は週に三度、この店の隅の席で本を読むのが、人生における最大の喜びだった。
その日も、僕はいつもの席で文庫本を開いていた。芳醇な珈琲の香りが鼻腔をくすぐり、心の平穏が満ちていく。完璧な午後だ。マスターが、僕の注文したブレンド珈琲を運んできた。黒いベストに蝶ネクタイというクラシカルな出で立ちの彼は、いつものように無表情でカップをテーブルに置く。
しかし、僕は目を疑った。カップに添えられているのは、ティースプーンではなく、なぜか一本の長い菜箸だった。
「……え?」
見間違いか? 疲れているのか? 僕は瞬きを繰り返した。だが、そこにあるのは紛れもなく、煮物を取り分ける時などに使う、あの竹製の菜箸だ。マスターは涼しい顔で僕を見ている。なぜ? どうして? 僕の脳内で警報が鳴り響く。まずい。これは、どう考えても「ボケ」だ。来る、アレルギー反応が来る!
「お、お客様……どうか、なさいま……」
僕の喉が、意思に反してヒクリと動いた。空気を吸い込む音がやけに大きく響く。次の瞬間、僕の口から、自分のものではないような、張りのある声が飛び出した。
「出汁でもとるんか! この珈琲、鰹節入っとるんか!?」
静寂の聖域に、僕の絶叫が木霊した。他の客が一斉にこちらを向く。ああ、終わった。僕の安息の地は、今、僕自身の手によって破壊された。顔から火が出るほどの羞恥に襲われ、穴があったら埋まりたい。マスターはきっと、気味悪がって僕を出禁にするだろう。
俯いて唇を噛む僕に、マスターはゆっくりと口を開いた。彼の声を聞くのは、注文の時以外で初めてかもしれない。
「……ふっ」
聞こえたのは、謝罪でも、怒りでもなく、堪えきれないといった風の、微かな息の漏れる音だった。恐る恐る顔を上げると、マスターは、その彫刻のように動かなかった口元を、わずかに綻ばせているように見えた。その瞳の奥に、驚きと、そしてどこか懐かしむような、不思議な光が宿っていた。
第二章 エスカレートする日常とすり減る精神
あの日以来、僕の聖域は変質した。いや、地獄と化したと言っていい。
翌日、恐る恐る『無風』の扉を開けると、マスターは僕を見るなり、お冷のグラスに金魚を浮かべて出してきた。もちろん、おもちゃの金魚だ。僕の身体は即座に反応した。
「夏祭りかっ! ポイ持ってこい、ポイを! 全部すくったるわ!」
その次の日には、僕の席の椅子だけが、なぜかマッサージチェアになっていた。スイッチを入れた途端、背中をグリグリと揉みしだかれ、僕は悲鳴のようなツッコミをあげる羽目になった。
「癒しと笑いの融合目指すな! リラクゼーション喫茶の新境地かっ!」
マスターのボケは日を追うごとに巧妙かつ大掛かりになり、僕のツッコミはそれに呼応するようにキレを増していった。僕の精神はすり減る一方だ。ただ静かに本が読みたいだけなのに、店に入るたびに「今日のボケはなんだ?」と身構えなくてはならない。心臓に悪い。
さらに不可解なのは、常連客たちの反応だった。以前は僕と同じく静寂を愛しているように見えた彼らが、今では僕がツッコむたびに、クスクスと肩を揺らして笑うのだ。それどころか、僕のツッコミを待っているような、期待に満ちた視線さえ感じる。いつしか僕は、この喫茶店の「ツッコミ担当」という、不名誉な役割を背負わされていた。
中でも一番つらいのは、アルバイト店員の佐伯さんの前でツッコミをさせられることだった。艶やかな黒髪と、優しい笑顔が印象的な彼女に、僕は淡い恋心を抱いていた。彼女の前では、知的で物静かな男を演じたい。なのに、彼女が僕のテーブルにナポリタンを運んできたかと思えば、その上にはパセリではなく、小さなブロッコリーが丸ごと一個乗っていたりするのだ。
「森生えとるやないか! 妖精でも住んどるんか、このパスタには!」
僕の絶叫に、佐伯さんは「ふふっ」と可憐に笑う。その笑顔は嬉しい。嬉しいが、違うのだ。僕はこんな風に、面白い人としてではなく、素敵な人として見られたいのに。
ある雨の日、僕の我慢は限界に達した。マスターが出してきた珈琲のミルクが、ピッチャーではなく哺乳瓶に入っていたのを見た瞬間、僕の中で何かが切れた。ツッコミを発動させる前に、僕はカウンターに駆け寄った。
「マスター! もう、やめてください! お願いします!」
絞り出した声は、震えていた。
「僕は……ただ、静かに過ごしたいだけなんです。どうして、こんなことをするんですか……?」
店内の全ての音が消え、雨音だけが窓を叩いていた。マスターは哺乳瓶を置くと、初めて見るような、寂しげな目で僕を見つめた。
第三章 菜箸と涙と引退したボケの神様
マスターはしばらく黙っていたが、やがて重い口を開いた。その声は、いつもの無口な彼からは想像もつかないほど、弱々しく響いた。
「……すまなかった」
彼は深々と頭を下げた。そして、ぽつり、ぽつりと語り始めた。
「私はね、昔……お笑いをやっていたんだ」
衝撃の事実に、僕は言葉を失った。目の前の無口な男が、お笑い芸人?
「コンビ名は『アシンメトリー』。私はボケ担当だった。相方は……日本一のツッコミだと、私は今でも信じている」
マスターの目は、遠い過去を見ていた。カウンターの向こう、何もない空間に、誰かの姿を映しているかのように。
「あいつは天才だった。私のどんな突拍子もないボケも、完璧なタイミングと、愛のある言葉で拾ってくれた。舞台の上で、あいつのツッコミを聞いている時だけが、私が本当に生きていると実感できる瞬間だったんだ」
しかし、その幸せは突然終わった。十年前に、相方は交通事故で帰らぬ人となった。
「あいつの最後の言葉は、『俺のしょうもないボケに、これからも最高のツッコミを入れ続けてくれよな』だった。だが、あいつがいなくなって、私は笑うことも、人を笑わせることも、なにもかもできなくなった。私のボケは、あいつのツッコミがあって初めて完成する。片翼の鳥と同じだ」
芸人を引退し、彼はこの喫茶店を開いた。相方の好きだった静かな空間で、ただ時が過ぎるのを待つように生きてきたのだという。
「そんな時、君が現れたんだ」
マスターは僕をまっすぐに見た。
「初めて君が、あの菜箸にツッコんでくれた時……心臓が止まるかと思った。あいつそっくりだったんだ。タイミング、言葉の選び方、声の張り……。まるで、あいつが君の身体を借りて、私にツッコんでくれたようだった」
涙が、マスターの皺の刻まれた頬を伝った。
「君のツッコミを聞いていると、あいつが隣にいるような気がして……少しだけ、心が救われたんだ。だから、つい……君に甘えてしまった。本当に、すまない」
僕は呆然と立ち尽くしていた。呪いだと思っていた僕の体質が、一人の人間の心を癒していた? 僕が忌み嫌っていたこの声が、誰かにとっての希望だった?
その時、店の奥の席に座っていた初老の紳士が立ち上がった。
「マスター。そして坊や。話は聞かせてもらったよ」
彼は僕に近づくと、優しく微笑んだ。「わしらはね、みんなマスターの、いや、『アシンメトリー』の元相方、片桐さんのファンなんだ。ここにいる常連も、みんなそうだ。マスターが心配で、こうして見守っていたんだよ」
佐伯さんまでもが、申し訳なさそうに頷いている。
「ごめんなさい、間宮さん。私も、マスターの昔のファンで……。あなたのツッコミを聞いている時のマスター、本当に嬉しそうだったから……」
価値観が、ガラガラと音を立てて崩れていく。僕が孤独に戦っていると思っていたこの場所は、実は、一人の傷ついた男を支える、優しさで満ちた空間だったのだ。僕のツッコミは、その優しさの輪を完成させる、最後のピースだった。
第四章 僕がマイクを握る理由
一週間後。喫茶店『無風』は、その日だけ『寄席 アシンメトリー』という看板を掲げていた。店の中央には小さなステージが作られ、一本のマイクがスポットライトを浴びている。常連客と、その噂を聞きつけた昔のファンで、店内は満員だった。
僕は客席の隅で、固唾を飲んでステージを見つめていた。僕の隣には、少し緊張した面持ちの佐伯さんが座っている。
やがて、マスターがステージに上がった。黒いベスト姿はいつもと同じだが、その表情には覚悟のようなものが滲んでいた。
「……どうも。ご無沙汰しております」
深々と頭を下げるマスターに、温かい拍手が送られる。
「十年、舞台から離れていました。もう、人を笑わせる資格なんてないと思っていましたが……ある青年に、背中を押されまして」
マスターの視線が、僕を捉える。僕は小さく頷き返した。
「今日は、天国の相方に捧げます」
そう言うと、マスターはマイクを握り、渾身のボケを放ち始めた。それは、往年のファンを唸らせる、シュールで、どこか哲学的な、彼にしかできないボケの連続だった。観客は笑いながらも、どこか物足りなさを感じていた。そうだ、この最高のボケには、最高のツッコミが必要なのだ。
ボケが佳境に差し掛かった時、マスターはふと、寂しそうに天を仰いだ。
「……なぁ、片桐。聞いてるか。お前がおらんと、やっぱり、間が持たんわ」
その瞬間だった。
僕の身体は、もうアレルギー反応では動かなかった。僕自身の意志が、僕の足を動かしていた。
客席をかき分け、僕はステージに向かって歩き出す。佐伯さんが驚いたように僕を見たが、その瞳には応援の色が浮かんでいた。
ステージの端に置かれていた予備のマイクを、僕は手に取った。
「当たり前でしょ、マスター!」
僕の声が、マイクを通して店内に響き渡る。マスターが、驚いて僕を見た。
「一人でボケ倒して、一人でしんみりしてんじゃないですよ! お客さん、置いてけぼりじゃないですか!」
それは、僕の言葉だった。僕の魂からの叫びだった。
マスターの目に、みるみるうちに涙が溜まっていく。しかし、その口元は、紛れもなく笑っていた。僕が初めて見た、彼の本物の笑顔だった。
「……遅いぞ、相棒」
「すみませんね、ちょっとアレルギーが酷くて」
僕たちは顔を見合わせ、笑った。
その日から、僕の人生は相変わらず騒がしい。でも、もう孤独ではない。僕の言葉は呪いなんかじゃない。誰かの心に寄り添い、笑顔を生み出すための、最高の贈り物なのだ。喫茶店『無風』のカウンターに立つマスターの隣には、時々、マイクを握る僕の姿がある。僕のツッコミは、今も天国の誰かさんと、目の前のボケの神様に、ちゃんと届いているはずだ。