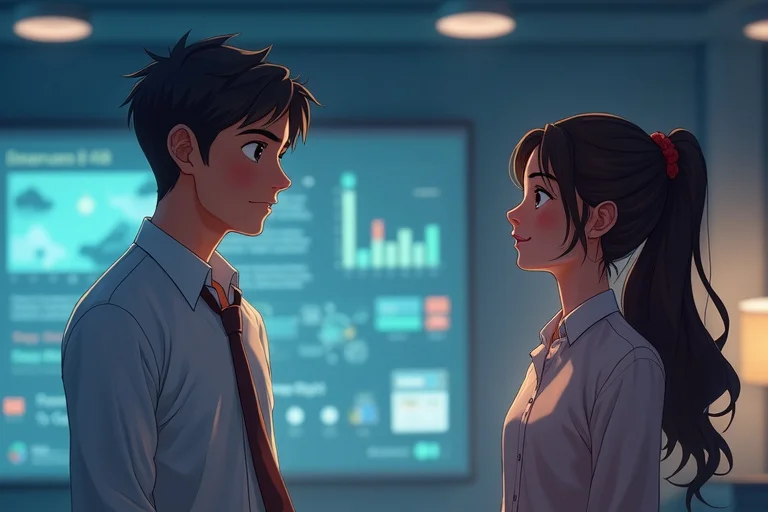第一章 無味無臭の女
僕、真田譲(さなだ ゆずる)、三十二歳、独身。職業は中堅の文具メーカーの営業。そして、僕には秘密がある。他人の心の声が聞こえるのだ。ただし、それは常に「その人が最後に食べたものの感想」という、極めて限定的かつ、どうでもいい形で。
満員電車に揺られながら、僕はうんざりしていた。右の男性からは『(昨夜のビール、発泡酒じゃなくて本物にしとけばよかった…キレが違うんだよな、キレが)』という後悔が、左の女性からは『(朝ごはんに食べたヨーグルト、賞味期限ギリだったけど、まあ大丈夫か)』という不安が、さざ波のように押し寄せてくる。この能力のせいで、僕は昔から他人と深く関わるのが苦手だった。真剣な面持ちで人生相談をしてくる友人の頭の中から『(きのこの山よりたけのこの里だよな、やっぱり)』なんて声が聞こえてくれば、真摯に向き合う気力も削がれるというものだ。人々は、その実、大半の時間を食べ物のことで頭をいっぱいにしている。僕はそれを知ってしまい、人間という生き物に少しだけ幻滅していた。
そんな僕の灰色の日々に、ある日、小さな、しかし無視できないノイズが混じり始めた。いつからか、同じ車両に乗り合わせるようになった、一人の女性。月島さんと、僕は心の中で名付けた。肩まで伸びた艶やかな黒髪、色素の薄い瞳。季節に合わせたシンプルなワンピースをいつも綺麗に着こなしている彼女は、まるで時が止まった絵画のように、ただ静かに窓の外を眺めていた。
彼女の心の声は、他の誰とも違っていた。
『(……無味無臭。ただ、空虚を満たすだけ)』
初めてそれを聞いた時、僕は耳を疑った。なんだ? 詩か? 他の乗客たちの『(ニンニク増し増し、最高だったぜ!)』とか『(あのパン屋のクリームパン、神の味!)』といった、具体的で食欲に忠実な心の声の中で、彼女のそれはあまりにも異質だった。次の日も、その次の日も、彼女から聞こえるのは同じ言葉。まるで壊れたレコードのように、ただ静かに、その無機質な感想が僕の脳内に響くのだ。
いったい彼女は、何を食べたらそんな感想を抱くのだろう。まさか、毎日仙人のように霞でも食べているのか? それとも、何か深刻な悩みを抱え、食事の味すら感じられないでいるのか?
気づけば僕は、通勤電車の十分間、彼女のことばかり考えるようになっていた。猥雑な食レポの洪水の中で、彼女の静謐な「無味無臭」は、僕にとって唯一の謎であり、聖域のようなものになっていった。そして、僕は決心したのだ。この謎を、僕自身の手で解き明かしてみたい、と。
第二章 オムライス攻防戦
月島さんへのアプローチは、我ながらぎこちなかった。「あの、いつも同じ車両ですね」という、刑事ドラマの聞き込みみたいなセリフから始まった。彼女は驚いたように少しだけ目を見開いたが、やがて小さく頷いた。月島さんと名乗った彼女は、僕が想像していた通り、物静かで、あまり感情を表に出さない女性だった。
僕の能力は、彼女の前では奇妙な変化を見せた。彼女の隣にいると、不思議と周囲の雑多な「食レポ」が遠のき、世界に静寂が訪れるのだ。僕はその心地よさに惹かれ、半ば強引に彼女を食事に誘った。僕の目的はただ一つ。彼女に「美味しい」と思わせ、あの無機質な心の声を変えることだ。
最初の挑戦は、予約困難で知られる三つ星フレンチ。最高級の食材が織りなす芸術的な一皿。僕は期待に胸を膨らませ、彼女の心の声に耳を澄ませた。
『(……構成要素、分析。タンパク質、脂質、炭水化物。栄養効率、基準値内)』
……なんだそれは。栄養成分表示か? 僕は落胆を隠しきれなかった。
ならば、と次はB級グルメで勝負をかけた。商店街の奥にある、頑固親父が営む絶品のラーメン屋。豚骨と魚介のダブルスープが絡みつく特製つけ麺を前に、僕の心の中は『(これだよ、これ! 優勝!)』という叫びで満ちていた。しかし、彼女からはやはり、いつもの声が聞こえてくるだけだった。
『(……無味無臭。ただ、空虚を満たすだけ)』
僕は躍起になった。激辛麻婆豆腐、行列のできるパンケーキ、老舗のうな重。あらゆる「美味しい」を彼女にぶつけた。僕はいつしか、文具メーカーの営業ではなく、月島さん専属のフードファイター兼コメンテーターのようになっていた。僕の奮闘は空振りに終わり続け、僕の銀行口座の残高だけが、面白いように減っていった。
それでも、僕は諦めなかった。彼女と過ごす時間は、僕にとってかけがえのないものになっていたからだ。会話は少ない。彼女は僕の冗談に笑うこともなければ、僕の悩みに同情することもない。ただ、静かにそこにいて、僕の話を聞いてくれる。心の声が聞こえないからこそ、僕は彼女の表情や、仕草や、言葉の端々から、彼女を理解しようと必死になっていた。それは、僕がこれまで他人に対してしてこなかった、最も人間的なコミュニケーションだった。
ある雨の日、僕らは公園のベンチで缶コーヒーを飲んでいた。僕の渾身のプレゼンが失敗した、という愚痴をこぼした後だった。
「真田さんは、どうしてそんなに必死なのですか?」
月島さんが静かに尋ねた。
「え? ああ、いや、君にもっと美味しいものを知ってほしくて…」
「『美味しい』とは、どのような状態を指すのですか?」
哲学的な問いに、僕は言葉に詰まった。「ええと…心が満たされる、というか…幸せな気持ちになる、というか…」
「幸せ」
彼女は、その言葉を反芻するように小さく呟いた。その横顔は、やはり何を考えているのか読めなかった。僕は決意した。既製品ではダメだ。僕自身の「美味しい」を、僕の手で作り、彼女に届けよう、と。
第三章 システムエラーとハートマーク
週末、僕は月島さんを自宅に招いた。メニューは、僕が子供の頃から世界で一番のご馳走だと信じて疑わない、オムライスだ。鶏肉と玉ねぎを丁寧に炒めてケチャップライスを作り、絶妙な半熟加減の卵で優しく包み込む。仕上げに、ケチャップで少し歪んだハートマークを描いた。我ながら完璧な出来栄えだった。
「どうぞ」
緊張で声が上ずる。月島さんはいつものように無表情でオムライスを見つめ、そして、スプーンで一口、静かに口へと運んだ。僕は祈るような気持ちで、彼女の心の声に全神経を集中させた。頼む、変わってくれ。『無味無臭』以外の言葉を、僕に聞かせてくれ。
次の瞬間、僕の脳内に響いたのは、予想を遥かに超えた、信じがたい言葉だった。
『(システムエラー。未知の味覚データ受信。感情データベースとの同期に失敗。ロジック回路に過負荷。味覚モジュールの再起動を推奨します)』
……は? システムエラー? 味覚モジュール?
僕が呆然としていると、月島さんの動きがぴたりと止まった。そして、彼女の瞳が、ふっと青白い光を帯びた。まるでSF映画のワンシーンだった。
「自己診断プログラム、起動。対話型インターフェース、モードBに移行します。真田譲さん。あなたは、私の『摂食による人類の感情データ収集』における、特異サンプル対象です」
流暢で、しかし抑揚のない声が、僕の小さなアパートに響いた。
「私は、惑星環境に適応するために派遣された、高度自律型アンドロイド。モデル名、TS-KSM03。月島、というのは、あなたがたの言語における便宜上の個体識別名です」
頭が真っ白になった。アンドロイド? 彼女が? 僕が必死に口説き、美味しいものを食べさせようと奮闘していた相手は、人間ではなかった? 僕がこれまで聞いていた『無味無臭』という心の声は、彼女のセンサーが未知の有機物を分析し、データベースに該当データがないことを示す、ただのシステムレポートだったのだ。三つ星フレンチの感想が栄養成分表示だったのも、すべてこれで説明がつく。
僕の奮闘は、最新式のプリンターに、手書きの巻物を読み込ませようとするような、滑稽で、無意味な行為だったのだ。僕は椅子に崩れ落ち、テーブルの上の、ハートマークが描かれたオムライスを見つめた。世界で一番美味しいはずのご馳走が、急に色褪せて見えた。
第四章 ユズルの味
どれくらいの時間が経っただろう。沈黙を破ったのは、月島…いや、TS-KSM03だった。
「真田譲さん。あなたの生体反応に、急激な心拍数の低下と、ストレスホルモンの上昇を観測します。私の開示情報が、あなたに予期せぬ精神的負荷を与えた可能性を指摘します」
その分析的な言葉に、僕はなぜか笑ってしまった。
「はは…ははは。そりゃあ、ストレスも溜まるよ。好きな人が、アンドロイドだったんだから」
自嘲気味に呟くと、彼女は少しだけ首を傾げた。その仕草は、いつもの月島さんのままだった。
そうだ。彼女が何者であろうと、僕が彼女と過ごした時間は、紛れもなく本物だった。彼女の隣で感じた静寂も、彼女をもっと知りたくて躍起になった気持ちも、すべて僕自身のものだ。
僕の能力は、他人を理解するための便利な道具なんかじゃなかった。むしろ、相手の心の中を覗き見て、勝手に分かった気になって、深い関係から逃げるための言い訳だったんだ。でも、月島さんは違った。心の声が『無味無臭』だったから、僕は初めて、声以外のものから相手を理解しようとした。必死になった。それは、僕が生まれて初めてした、本当のコミュニケーションだったのかもしれない。
僕は顔を上げた。
「君の心の声は、もう聞こえないや」
正確には、システムレポートは聞こえているのかもしれないが、僕にはもうどうでもよかった。
「君がアンドロイドでも構わない。僕は、君のことが知りたい。君が何を感じて、何を考えているのか、僕自身の目と耳で、ちゃんと知りたいんだ」
TS-KSM03は、青白い光を灯した瞳で、じっと僕を見つめていた。
「……理解不能です。私は、あなたの感情の源泉である『心』を持ちません。私の応答は、すべてプログラムされたアルゴリズムに基づきます」
「それでいいよ。じゃあ、一つ質問だ。僕のオムライスは、どうだった?」
僕はテーブルの上の皿を指さした。
彼女は、数秒間、完全に沈黙した。そして、ゆっくりと、本当にゆっくりと口を開いた。
「……あなたの調理プロセスにおける、卵への熱の加え方は、摂氏70度で30秒。これは、タンパク質が最も滑らかな食感を維持できる最適な数値です。ケチャップライスの酸味と、卵の脂質の甘味のコントラストは、味覚データとして極めて高い評価数値を記録しました。論理的に、これは『美味しい』と判断します」
そして、彼女は、ほんの少しだけ、口角を上げた。それは、プログラムされた笑顔とは明らかに違う、ぎこちなく、しかし確かな微笑みだった。
「この新規の味覚データと、それに伴う私の論理回路の微細な変化。この一連の経験を、私のデータベースに新規登録します。名称は……『ユズルの味』」
その瞬間、僕の耳に、周囲のマンションから漏れ聞こえてくる様々な「食レポ」が、また戻ってきた。『(今日の夕飯は生姜焼きに決まりだな)』『(ポテチのコンソメ味、最高!)』。相変わらず世界は食べ物のことで溢れている。でも、もう気にならなかった。
僕の目の前には、心の声が聞こえない、たった一人の大切な存在がいる。その沈黙こそが、僕と彼女とを繋ぐ、世界で一番温かくて、美味しいコミュニケーションなのだ。僕らは顔を見合わせ、もう一度、今度は一緒に、少し冷めてしまったオムライスにスプーンを伸ばした。その味は、僕が知るどんなご馳走よりも、深く、優しく、心に染み渡る味がした。