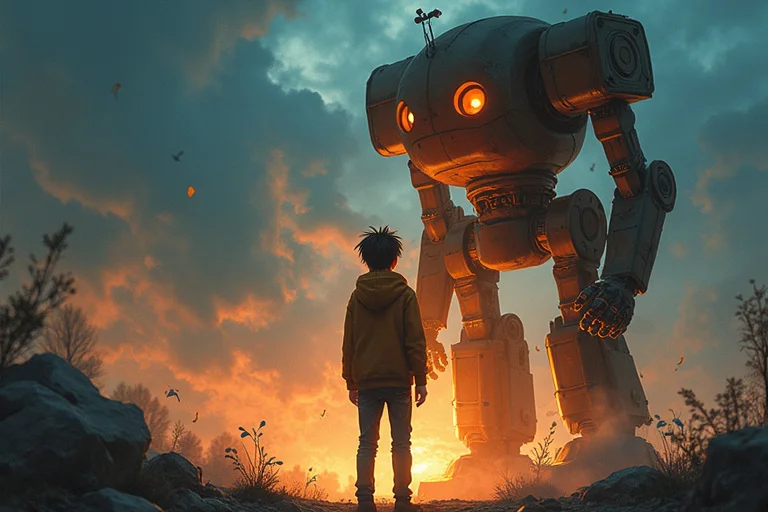第一章 白い絶望の渦
俺、真世(まよ)マヨ助の朝は、いつだって白い絶望から始まる。
目覚まし時計のけたたましい電子音。それに驚いて心臓が跳ねた瞬間、それは起こる。首筋の毛穴からじわりと滲み出す、見慣れた乳白色の液体。慌ててティッシュで拭うが、その指先に伝わるねっとりとした感触と、鼻腔をくすぐる独特の酸っぱい香りが、今日も一日が始まったことを告げていた。
緊張すると、体のあらゆる毛穴から濃厚なマヨネーズが噴き出す。それが俺の体質だった。
「またか……」
溜息とマヨネーズの香りが、ワンルームの狭い部屋に充満する。テレビのスイッチを入れると、深刻な顔をしたキャスターが、もはや聞き飽きたニュースを伝えていた。
『世界同時多発ニワトリ化現象、依然として収束の目処は立っておりません。本日未明、G7の緊急首脳会談中、フランス大統領が突如として鶏に変身。会談は中断されました。この影響で卵の価格は歴史的な高騰を記録し、世界経済は破綻の瀬戸際に立たされています』
画面には、ホワイトハウスの庭を闊歩する立派なトサカの鶏の映像が映し出される。SPらしき男たちが、困惑した表情で鶏を追いかけていた。誰もが、原因不明の現象に首を傾げていた。特定の周期でランダムな動物に変身する、というこの世界の法則が、なぜかここ最近、『鶏』だけに限定され、しかもその周期が異常に短くなっているのだ。
俺はトーストをかじりながら、他人事のようにその光景を眺めていた。だが、満員電車に乗り込み、急ブレーキで体が大きく揺れた瞬間、その「他人事」は俺自身の問題として牙を剥いた。
「うわっ!」
焦り。それが引き金だった。全身の毛穴という毛穴が開き、白い渦が俺の体から噴出した。シャツもスーツも関係ない。クリーミーな奔流が周囲の乗客に降り注ぎ、車内は阿鼻叫喚の地獄絵図と化した。
「きゃあああ!マヨネーズ!?」
「なんだこいつ!」
非難の視線が突き刺さる。そのプレッシャーに、マヨネーズの噴出はさらに勢いを増す。その時だった。俺のマヨネーズを頭から浴びたサラリーマンが、苦悶の表情で体をくの字に折り曲げた。
「コ、コ、コ……」
彼の体がみるみる縮み、手足が黄色い鱗に覆われ、口が鋭い嘴に変わっていく。
「コケコッコーッ!」
甲高い鳴き声とともに、一羽の鶏がそこにいた。彼は、俺のマヨネーズがべっとりと付着した羽根を震わせ、無機質な瞳でじっと俺を見つめていた。
第二章 コケコッコーの大合唱
会社は、養鶏場さながらの様相を呈していた。
カタカタと軽快なキーボードの音に混じって、コッコッコッと乾いた爪音がオフィスに響く。営業部の田中課長は、立派な雄鶏の姿でコピー機の上にとまり、鋭い眼光で部下たち(その三分の一は既に鶏だ)を監視していた。
「真世!このデータ、どうなってるんだ!」
鶏になったはずの佐藤部長が、嘴をカタカタ鳴らしながら俺のデスクに詰め寄ってきた。その声は人間のものだったが、言葉の端々から「コケッ」という音が混じる。
「申し訳ありません!すぐに対応します!」
俺が緊張で硬直すると、またしても脇の下からじわりとマヨネーズが滲み出した。その匂いを嗅ぎつけた瞬間、オフィスにいた全ての鶏が一斉に俺の方を向いた。瞳孔が開き、喉をゴクリと鳴らす音が聞こえる。
まずい。
本能的な恐怖が、さらなるマヨネーズの分泌を促す。部長だった鶏が、俺のズボンの裾に嘴で突きかかってきた。それを皮切りに、四方八方から鶏たちが殺到する。彼らの目には、理性の光はなく、ただ純粋な食欲だけが燃え盛っていた。
「うわああああ!」
俺は椅子を蹴倒し、廊下へ飛び出した。背後からは、何十羽もの鶏の足音と、狂乱した鳴き声が追いかけてくる。まるで、巨大なからあげ弁当に群がるゾンビのようだった。
街に出ても状況は同じだった。信号待ちをしている人々が次々と鶏に変わり、アスファルトの上を右往左往している。世界から秩序が消え、ただコケコッコーという甲高い鳴き声だけが支配していた。俺は、自分にだけ向けられる鶏たちの執拗な視線から逃れるように、ただひたすら走り続けた。
第三章 特売の石の記憶
息を切らして逃げ込んだのは、幼い頃によく遊んだ、古びた公園だった。錆びたブランコが、キィ、キィ、と風に揺れている。鶏の姿は、幸いここにはないようだった。
俺はベンチに崩れ落ち、無意識のうちにズボンのポケットを探っていた。指先に、ひんやりとした硬い感触が触れる。子供の頃に拾ってから、なぜかずっと持ち歩いている、ただの石ころだ。表面には、かすかに『特売』という文字のような模様が刻まれている。
その石を握りしめた途端、遠い記憶の蓋が、音を立てて開いた。
あれは、確か小学校低学年の頃。マヨネーズが大好きで、何にでもかけて食べていた俺に、母が困った顔で言ったのだ。
『マヨ助、マヨネーズは安くないのよ。特売の時しか買えないんだから、大事に使いなさい』
子供心に、それはひどく悲しい宣告だった。大好きなマヨネーズを、お腹いっぱい食べられないなんて。その日、とぼとぼと歩く帰り道で、俺はこの石を拾った。握りしめると、なぜか不思議な安心感があった。
俺は、この石に強く、強く願ったのだ。
『神様、お願いします。毎日、お腹いっぱいマヨネーズが食べたいです。マヨネーズを無限に作ってくれる、都合のいい鶏が、いっぱいいっぱい欲しいです』
その瞬間、石ころから微かに声が聞こえた気がした。
『たまご…たかい…』
まさか。
背筋を冷たい汗が伝う。俺のマヨネーズ体質。世界中が鶏になる現象。二つのバラバラだったピースが、脳内で恐ろしい形に組み合わさっていく。この石は、俺の願いを叶えたのか? だが、あまりにもコメディ的で、悪質すぎる解釈で。
第四章 白い渦の証明
もし、俺の仮説が正しいのなら。
もし、この世界の混乱が、俺の幼稚な願いのせいだとしたら。
確かめる方法は一つしかない。
俺は震える足で立ち上がり、街の中心にある広場へと向かった。そこは、避難してきた人々と、彼らが変身してしまった無数の鶏で埋め尽くされ、パニック映画のワンシーンのようだった。不安と恐怖が渦巻く広場の空気は、俺の体質にとって最悪の環境だ。既に毛穴からは、マヨネーズが汗のように滲み出ている。
俺は意を決して、広場の中央にある噴水の縁に立った。周囲の人々が、奇妙なものを見る目で俺に注目する。
「みんな、聞いてくれ!」
声が震える。だが、ここで引くわけにはいかない。
「この現象の原因は、たぶん、俺なんだ!」
ざわめきが大きくなる。誰もが俺を狂人だと思っただろう。それでいい。注目されればされるほど、緊張は高まる。俺は目を閉じ、過去の恥ずかしい記憶を全力で呼び覚ました。卒業式で盛大にズボンのチャックが開いていたこと。初デートで緊張のあまりマヨネーズを噴射し、彼女の顔面を白く染めてしまったこと。数々の屈辱的な思い出が、俺の精神を極限まで追い詰めていく。
体中の血が沸騰するような感覚。
そして、時は満ちた。
「うおおおおおおおっ!」
俺は叫んだ。それは、決意の雄叫びであり、破滅への号砲だった。
第五章 マヨネーズ・クライシス
解放された。
俺の全身から、白い渦が竜巻のように噴き上がった。それはもはや「噴出」などという生易しいものではない。まさに爆発だった。粘性の高い液体が空を舞い、白い津波となって広場を埋め尽くしていく。噴水も、街灯も、逃げ惑う人々も、全てがクリーミーな濁流に飲み込まれた。
濃厚なマヨネーズの香りが、広場一帯を支配する。
その瞬間、悲劇は起きた。
まだ人間の姿を保っていた人々が、一人、また一人と、その場に崩れ落ちる。まるで感染するように、変身の連鎖が始まった。手足が、顔が、体が、ぐにゃりと歪み、あっという間に鶏の姿へと変わっていく。
「コケコッコーッ!」
「コケコッコーッ!」
「コケコッコーッ!」
何千、何万という鶏の鬨の声が、天を衝いた。マヨネーズまみれの鶏たちが、一斉に俺の方を向き、その無機質な瞳でじっと俺を見つめている。絶望的な光景だった。俺の仮説は、最悪の形で証明されてしまったのだ。
この世界の混乱は、俺のせいだ。
俺が、俺のマヨネーズが、人々を鶏に変えていたのだ。
第六章 選択と喪失
世界を救う方法は、たった一つ。
俺はポケットから、全ての元凶である『特売の文字が刻まれた石ころ』を取り出した。ひんやりとした石の感触が、狂乱する現実の中で唯一の確かさを持っているように感じられた。
これを、手放せばいい。捨ててしまえば、歪められた世界の法則は元に戻るはずだ。
だが、その考えが頭をよぎった瞬間、凄まじい喪失感が俺を襲った。
この石を捨てれば、俺のマヨネーズ体質も消えるだろう。もう、緊張してもマヨネーズは出ない。それは、呪いからの解放を意味すると同時に、俺のアイデンティティの一部が失われることを意味していた。
そして何より――マヨネーズのない人生。
それは考えただけで身の毛がよだつ、無味乾燥な未来だった。カリカリに揚げた唐揚げも、茹でたてのブロッコリーも、ソースの香るお好み焼きも。俺の食生活を彩ってきた、あの黄金色の奇跡が、永遠に失われる。世界を救うことと、俺のささやかな幸せ。その二つが、この小さな石ころの上で天秤にかけられていた。
広場では、鶏たちの悲痛な鳴き声が響き渡っている。マヨネーズまみれで泣きじゃくる子供の姿が見えた。その子の母親らしき鶏が、心配そうに寄り添っている。
ああ、もう、迷っている時間はない。
俺は腕を大きく振りかぶり、近くを流れる川に向かって、石を思い切り投げ捨てた。放物線を描いた石は、水面に小さな波紋を残して、静かに沈んでいった。
第七章 無味の世界で、君を想う
石が水底に消えた瞬間、世界から音が消えた。
いや、正確には、あれほど鳴り響いていた「コケコッコー」の大合唱が、ぴたりと止んだのだ。人々は、まるで長い夢から覚めたように、元の姿に戻っていた。誰もが呆然と立ち尽くし、マヨネーズまみれの自分の姿を見て首を傾げている。
俺は、自分の体を確認した。すうっと、長年まとわりついていたマヨネーズの気配が消え失せている。試しに、満員電車の急ブレーキを想像してみる。心臓はドキリとしたが、毛穴から滲み出るのは、ただの生温かい汗だけだった。
世界は、救われた。
だが、俺の心は空っぽのままだった。
帰り道、俺はコンビニに寄り、ポテトサラダのパックを買った。公園のベンチに座り、プラスチックの蓋を開ける。一口、口に運ぶ。
じゃがいもの味。にんじんの味。きゅうりの味。ハムの味。それらが、ばらばらに自己主張しているだけだった。全てを優しく包み込み、調和させていたはずの、あのまろやかな酸味とコクが、どこにもない。
俺は、ポテトサラダを食べる資格すら失ってしまったのだ。
世界は平和を取り戻した。人々は日常に帰り、卵の価格も安定するだろう。だが、俺の世界は、今日、色を失った。世界の破綻を救った代償は、俺一人の精神的な破綻だった。
空を見上げる。夕焼けが、妙にケチャップのように見えた。
俺は乾いた笑いを漏らし、ただ、マヨネーズのない、この無味乾燥な世界で生きていく覚悟を決めるしかなかった。