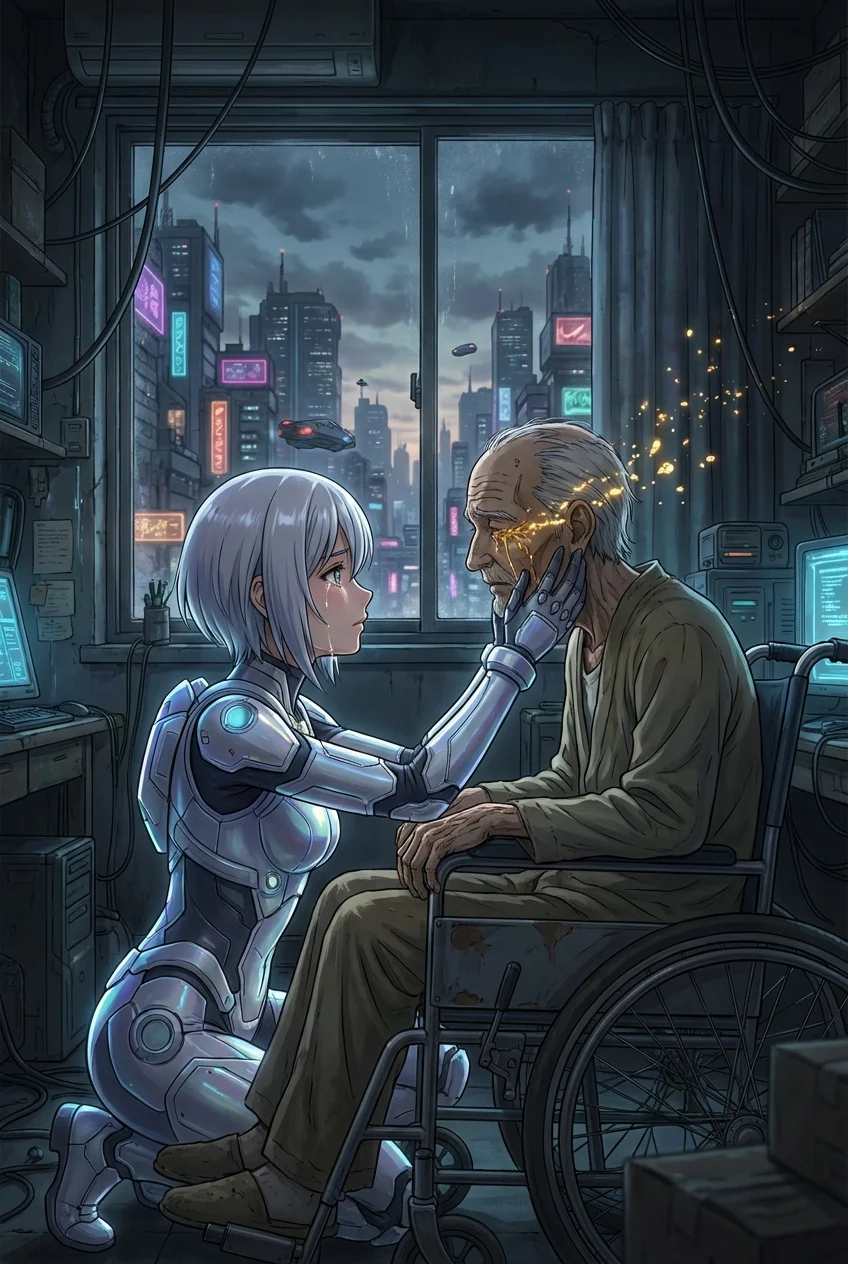第一章 逆流する銀河
意識が浮上した瞬間、アキラを襲ったのは鋭い頭痛と、耳鳴りのような甲高い金属音だった。瞬きを数回。見慣れた宇宙船「クロノス・ヴァイン」の医務室の白い天井が、ぼやけた視界に映る。どうやら俺は、あの事故を生き延びたらしい。安堵よりも先に、仲間たちの安否が気にかかり、身体を起こそうとした。
その時だった。床に転がっていた医療用トレイが、カタカタと震えながらひとりでに持ち上がり、ベッドサイドのテーブルに寸分の狂いもなく収まったのだ。そして、床に広がっていた茶色い染みが、意思を持ったアメーバのように蠢き、ゆっくりと一点に集束していく。それは見る間に球体をなし、ふわりと宙に浮いたかと思うと、床に落ちていたはずのマグカップに吸い込まれていった。パリン、と甲高い音がして、カップの破片が結合し、元の姿を取り戻す。まるで、映像を逆再生しているかのような光景だった。
「……何だ、これは」
混乱する頭で状況を把握しようと、アキラは医務室を飛び出した。廊下を走り、クルーたちが憩いの場としていたラウンジへ向かう。そこには、信じがたい光景が広がっていた。
砕け散った窓ガラスの破片が、宇宙空間から吸い寄せられるように窓枠へと集まり、亀裂を消していく。壁にめり込んでいた計器盤が、ゆっくりと元の位置へと戻り、火花が配線の中へと消えていく。そして、そこに倒れていたはずの仲間たちの姿は、どこにもなかった。
絶望が全身を貫いた。彼らは死んだのではなかった。これから、死ぬのだ。
アキラは震える手で、自分の手首にあるクロノメーターを確認した。デジタル表示された数字が、目まぐるしく過去へと遡っていく。秒が、分が、時間が、俺の知る未来から遠ざかっていく。
クロノス・ヴァインは、未知の重力異常宙域に接触した際に、大規模なシステムダウンと船体の崩壊に見舞われた。俺の最後の記憶は、轟音と共に船体が引き裂かれ、愛するエマが宇宙空間に投げ出される瞬間だった。だが、今、船は修復されつつある。まるで傷口が癒えるように。
俺はたった一人、この船の中で、逆流する時間に取り残されたのだ。未来の記憶を抱えたまま、破滅という名の「始まり」へと向かって。窓の外では、星々が進行方向とは逆に流れ、銀河が壮大なエンドロールのように、過去へと巻き戻されていた。
第二章 追憶のデジャヴ
逆行する時間の中での生活は、奇妙な静けさと孤独に満ちていた。食事は、食べ終えた食器から復元される。読み終えた電子書籍の文字は、ページをめくるごとに先頭へと戻っていく。俺が何かを創造しようとしても、それは瞬く間に「創造される前」の状態へと回帰してしまう。俺は、この世界において、無力な観測者でしかなかった。
唯一の救いは、未来の記憶だった。事故で失った仲間たちが、一人、また一人と「生き返って」くる。最初に機関室で復旧作業中に戻ってきたのは、主任エンジニアのタケシだった。壁から剥がれ落ちた彼が、何事もなかったかのように立ち上がり、俺に「おいアキラ、ぼさっとするな!」と怒鳴る。その声を聞いた時、涙が止まらなかった。俺は彼の死の瞬間を知っている。だが、彼は何も知らない。俺はただ、「すみません」とだけ返し、彼がこれから経験するであろう苦痛を思い、胸が張り裂けそうになった。
日々は、既視感(デジャヴ)の連続だった。これから起こる会話、これから行われる作業、そのすべてを俺は知っている。仲間たちは、俺の記憶の中の脚本通りに動き、言葉を発する。それは、かつて愛した日常の完璧な再現であり、同時に、決して変えることのできない、残酷な再放送でもあった。
俺の心を支えていたのは、一つの希望。あと三日。三日経てば、エマが「生き返る」。植物学ラボで標本の整理中に事故に巻き込まれた彼女が、俺の前に再び姿を現すのだ。彼女の笑顔をもう一度見られるなら、この地獄のような時間に耐えられる。彼女に会って、伝えたいことが山ほどあった。愛している、と。君を失った世界は、こんなにも色褪せているのだ、と。
だが、近づく再会の日に、喜びと同じくらい、得体の知れない恐怖が心を蝕んでいた。記憶の中のエマと、これから再会するエマは、本当に同じ存在なのだろうか。逆行する時間の中で再会するということは、一体何を意味するのだろうか。俺はただ、彼女の温もりを追憶する亡霊にすぎないのではないか。その答えを見つけるのが、ひどく恐ろしかった。
第三章 再会のパラドックス
その日は、静かに訪れた。アキラは植物学ラボの前に、何時間も前から佇んでいた。クロノメーターの数字が、記憶の中の「その時」を刻む。扉の向こうで、微かな物音がした。床に散らばっていた培養ポッドの破片がひとりでに結合し、棚へと戻っていく。そして、そこに横たわっていた人影が、ゆっくりと立ち上がった。
エマだった。記憶の中と寸分違わぬ、柔らかな栗色の髪。こちらを振り返った瞬間の、少し驚いたような大きな瞳。
「アキラ?どうしたの、そんな所で。幽霊でも見たみたいな顔して」
彼女はそう言って、屈託なく笑った。俺が何よりも愛した笑顔。涙がこみ上げてきたが、必死にこらえた。
「……いや、なんでもない。少し、ぼーっとしてただけだ」
「もう、しっかりしてよ。明日の観測準備、手伝ってくれるんでしょ?」
「ああ、もちろん」
会話は、記憶の通りに進んでいく。だが、話せば話すほど、アキラは絶望的な断絶を感じていた。目の前にいるエマは、俺の知るエマではない。正確には、「まだ」俺の知るエマではないのだ。彼女は、これから起こる悲劇を知らない。俺と交わした最後の約束も、共に過ごした最後の夜の温もりも、彼女の中には存在しない。俺が抱える絶望も、孤独も、彼女には届かない。
俺は未来の記憶を持つ、ただの異物。彼女は過去を生きる、純粋な存在。二人の間には、決して越えることのできない時間の壁が横たわっていた。俺がもし未来を語っても、彼女はそれを戯言としか受け取らないだろう。いや、そもそもこの逆行する因果律の中で、俺の言葉が未来に影響を与えることなどありえないのかもしれない。俺は、完璧に再現された舞台の上で、セリフを変えることのできない、孤独な役者だった。
その時、アキラは戦慄と共に、この時間の旅の真の意味を悟った。この旅の終着点は、事故発生時ではない。クロノス・ヴァインが地球を旅立った、あの出発の日だ。そして、その日を迎えた時、俺はどうなる?時間はさらに過去へと遡り、俺がクロノス・ヴァインに乗る前へ、エマと出会う前へ、そして、俺がこの世に生を受ける前へと向かっていく。
俺の存在は、いずれ「無」に収束する。死ではない。もっと根源的な、存在そのものの消滅。それが、この逆行する時間に取り残された俺に与えられた、唯一の運命だった。全身から血の気が引いていく。愛する人との再会は、自らの存在消滅へのカウントダウンの始まりを告げる、残酷な号砲でしかなかったのだ。
第四章 星屑のレクイエム
絶望の淵に沈んだアキラを救ったのは、皮肉にも、未来を知るがゆえの些細な出来事だった。それは、エマが「生き返った」翌日のこと。食堂で、彼女がトレイを滑らせて、スープをこぼしそうになる。事故の記憶では、俺はそれに気づかず、彼女はスープを盛大にぶちまけて、二人で大笑いしたはずだった。
だが、今の俺は、それが起こることを知っている。スープが傾きかけた瞬間、俺は無意識に手を伸ばし、彼女のトレイを支えていた。
「わ、ありがとう、アキラ。助かった」
エマが安堵の息をつく。記憶とは違う、小さな変化。因果律に干渉できないと思っていた。だが、こんな些細なことなら、変えられるのかもしれない。それは、大局を変える力ではない。未来の悲劇を回避する力でもない。ただ、目の前の愛する人の服を汚さずに済ませるだけの、ささやかな力。
その瞬間、アキラの中で何かが変わった。どうせ消える運命なら、残されたこの時間を、どう生きるか。無力感に苛まれ、過去をなぞるだけの亡霊として過ごすのか。それとも――。
アキラは決めた。この「二度目の時間」を、今度こそ、もっと大切に生きよう、と。
彼は、未来の知識を、仲間たちを喜ばせるために使い始めた。タケシが頭を悩ませる配管のトラブルを、「偶然ひらめいた」と言って解決策を教える。クルーたちが観測データのエラーで落ち込んでいる時、エラーの原因となる数値を「勘だけど、ここじゃないか?」と指摘して、彼らの仕事を早く終わらせてやる。
そして、エマとの時間を何よりも慈しんだ。彼女が好きな音楽をさりげなく流し、彼女が興味を持っていた古い映画を「たまたま見つけた」と言って一緒に観た。未来を知っているからこそ、彼女が何に微笑み、何に心を動かすのか、俺は誰よりも知っていた。
「最近のアキラ、なんだかすごいね。まるで預言者みたい」
エマが悪戯っぽく笑う。アキラはただ、穏やかに微笑み返した。悲劇の未来は変えられない。俺の存在が消える運命も変わらない。だが、彼らの記憶に残る「過去」を、少しだけ温かいものにすることはできる。俺という存在が消え去った後も、彼らの心の中に、楽しかった思い出の欠片として、生き続けることができるかもしれない。
やがて、運命の日が来た。クロノス・ヴァインが、長大な探査任務へと旅立つ、出発の日。
クルーたちがブリッジに集まり、管制スクリーンに映し出される青い地球を、名残惜しそうに眺めている。誰もが希望に満ちた顔をしていた。これから始まる壮大な冒険に、胸をときめかせていた。
その光景を、アキラは最後列から静かに見つめていた。ああ、これが俺の愛した仲間たちだ。これが、俺が命を懸けて守りたかった未来の、始まりの姿なのだ。彼の視界が、徐々に白く霞んでいく。身体の輪郭が、世界の景色に溶けていくような感覚。
隣にいたエマが、不安そうに彼を見上げた。彼女は、アキラから出発前にプレゼントされた、星屑を封じ込めたロケットを握りしめている。
「ねえ、アキラ。なんだか、あなただけが、すごく遠くへ行ってしまうみたいに感じる……」
その言葉を聞いて、アキラは心の底から微笑んだ。彼はエマの耳元に、時間の流れに消されてしまうであろう最後の言葉を囁いた。
「大丈夫。いつだって、君の始まりを見守っているよ」
彼の意識が完全に消える直前、見えたのは、これから無限の可能性へと旅立つ、愛する者たちの輝かしい笑顔だった。
彼の存在は、時間の地平線の彼方へと静かに消え去った。因果の鎖から解き放たれ、ただ、温かい思い出だけをこの宇宙に残して。それは、誰にも知られることのない、一人の男の究極の愛の形であり、最も静かで、最も壮大な自己犠牲の物語だった。