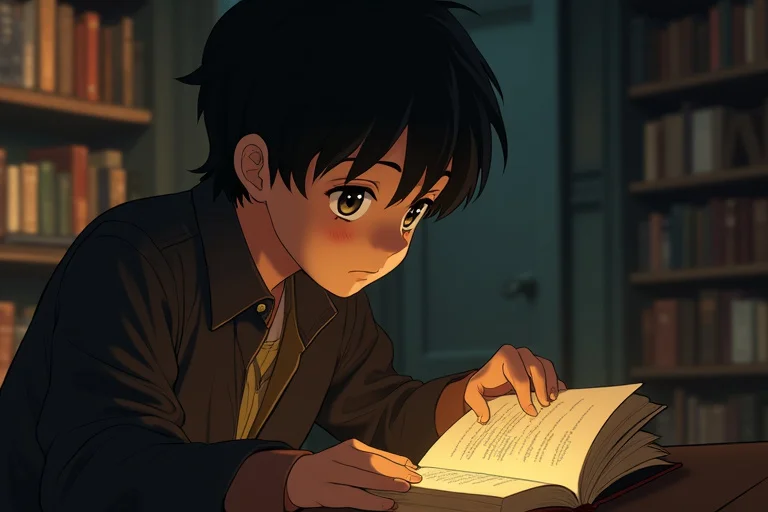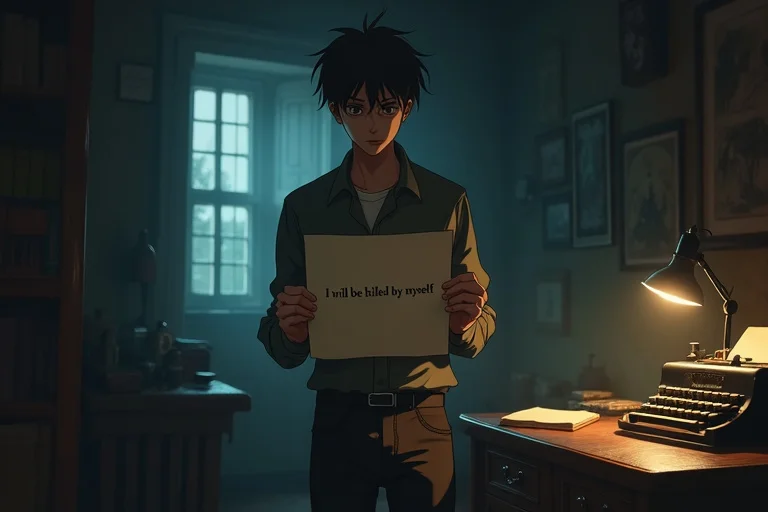第一章 味のない言葉
神保町の古書店『言の葉の森』の店主、音城響(おとぎ ひびき)にとって、世界は味に満ちていた。「ありがとう」という言葉は温かい蜂蜜の味がし、「さようなら」は舌の上に残るミントの苦味があった。彼は、言葉に味を感じる味覚言語共感覚の持ち主だった。この特異な体質は、彼に豊かな内的世界を与える一方で、他人との間に透明な壁を作っていた。人々が軽々しく口にする甘言はときに胸焼けを起こさせ、無神経な言葉は口内を砂で満たすかのようだった。だから響は、言葉が静かに眠る古書の世界に安息を見出したのだ。
そんな彼の唯一無二の理解者が、相良壮介(さがら そうすけ)教授だった。大学で記号論を教えていたという老教授は、週に三度、響の店を訪れ、埃っぽい背表紙を指でなぞりながら、響の感じる「言葉の味」について熱心に耳を傾けてくれた。「君のその力は、言葉が本来持つ魂の響きを捉えているのかもしれないね」と、教授はいつも優しい皺をたたえた目で言った。彼の声は、上質なほうじ茶のような、心を落ち着かせる香ばしい味がした。
その日、一本の電話が、響の静かな世界を粉々に砕いた。相良教授が、書斎で亡くなっているのが見つかったという。警察は、かねてから患っていた心臓疾患による病死と断定した。だが、発見者である家政婦が警察に伝えたある事実が、響の胸をざわつかせた。教授の机の上に、一編の詩が置かれていたというのだ。
響が警察署で対面させられたその遺品は、万年筆で丁寧に綴られた一枚の便箋だった。
『瑠璃色の鳥は歌う、琥珀の夢のほとりで。
銀の雫が玻璃の窓を叩き、沈黙の石が時を刻む。
霧の衣をまとった影が、忘れられた小径で踊る。
我が魂は、ただ虚空を見つめるのみ。』
一読しただけでは、美しい言葉を並べた感傷的な詩にしか見えない。だが、響がその文字を心の中で反芻した瞬間、背筋に冷たいものが走った。
味がしない。
「瑠璃」も「琥珀」も「銀」も、響の舌には何一つ響いてこなかった。まるで、色も香りも失った、ただの記号の羅列。響の世界において、言葉から味が消えることは、星が空から消えることに等しい異常事態だった。それは「無」であり、死よりも深い空虚を意味していた。
刑事は「よくある遺書のようなものでしょう」と事もなげに言った。しかし、響には分かっていた。これは遺書などではない。温かいほうじ茶の味をしたあの人が、こんなにも空っぽな言葉を遺すはずがない。これは、相良教授がその命と引き換えに遺した、無味の謎。彼にしか解けない、最後のメッセージだった。
第二章 孤独な探求
響の孤独な調査が始まった。警察が早々に捜査を打ち切ったため、頼れる者は誰もいない。彼はまず、教授の書斎を訪れる許可を得た。埃とインクの匂いが混じり合った、懐かしい空間。壁一面の本棚は、まるで教授の脳内そのもののようだった。
響は、あの無味の詩を手がかりに、教授の蔵書を片端から調べ始めた。「瑠璃色の鳥」「琥珀の夢」――詩に使われていた言葉をキーワードに、関連しそうな書籍を抜き出していく。神話集、古い詩集、異国の民話。しかし、どの本を開いても、そこに綴られた言葉は豊かな味を伴っていた。甘く、しょっぱく、酸っぱく、苦い。言葉の洪水に溺れそうになりながら、響は焦燥感を募らせていた。
「どうして、あの詩だけが……?」
彼の共感覚は、他人には理解しがたい。調査の過程で話を聞いた教授の同僚や教え子たちも、響が「言葉の味」について語り始めると、困惑したような、あるいは憐れむような表情を浮かべるだけだった。「相良先生は、少し変わった方でしたから」という言葉は、腐った牛乳のような不快な味を残した。
世界から切り離されていく感覚。自分の信じるものが、自分以外の誰にも届かないという絶望。今までもずっとそうだった。だが、相良教授だけは違ったのだ。彼は、響の感じる味を「真実」だと受け止めてくれた。その教授が遺した謎が解けないのなら、自分のこの力は本当にただの呪いなのではないか。
日が暮れ、古書店の明かりだけが路地を照らす頃、響は疲れ果ててカウンターに突っ伏した。目の前には、相良教授が最後に借りていったままになっていた一冊の本がある。『失われた言葉の系譜』。難解な記号論の専門書だ。パラパラとページをめくる。そこに並ぶ専門用語は、どれも金属的で無機質な味がした。
ふと、響の指があるページで止まった。教授の書き込みがあったのだ。ページの隅に、小さな文字でこう記されていた。
『意味は単体で存在しない。文脈という名の鎖によって、初めてその姿を現す』
文脈という鎖。その言葉が、雷のように響の脳を撃ち抜いた。自分は今まで、言葉を一つ一つ、バラバラに味わっていた。もし、教授が伝えたかったのが、個々の言葉の味ではなく、その「組み合わせ」だとしたら? もし、あの「無味」こそが、教授が仕掛けた文脈の鍵だとしたら?
響は勢いよく顔を上げた。店内の古時計が、ぼう、と低い音を立てて深夜を告げた。その音は、まるで始まりの合図のように響の耳に届いた。
第三章 死者の告白
響は、震える手であの詩をもう一度広げた。
『瑠璃色の鳥は歌う、琥珀の夢のほとりで。
銀の雫が玻璃の窓を叩き、沈黙の石が時を刻む。
霧の衣をまとった影が、忘れられた小径で踊る。
我が魂は、ただ虚空を見つめるのみ。』
今度は、言葉を味わうのではない。味が「しない」言葉だけを拾い出すことに集中した。「瑠璃」「琥珀」「銀」「玻璃」「沈黙」「石」「霧」「影」「虚空」。これらの言葉は、響にとって味のない、空虚な記号だった。
しかし、他の言葉は違う。「鳥」「歌う」「夢」「窓」「叩く」「時」「刻む」「衣」「踊る」「魂」「見つめる」。これらの言葉には、微かだが確かに味が残っていた。小鳥のさえずりのような甘酸っぱさ、夢の儚さを思わせる綿菓子のような舌触り……。
なぜだ? なぜ、これほど明確に「有味」と「無味」の言葉が混在している? 響は、無味の言葉だけを便箋の余白に書き出してみた。
「瑠璃、琥珀、銀、玻璃、沈黙、石、霧、影、虚空」
脈絡のない単語の羅列。これでは意味が通らない。諦めかけたその時、響は相良教授の書斎で見た光景を思い出した。壁一面の本棚。それらは、ある規則性をもって並べられていた。著者名の五十音順だ。
まさか。
響は、書き出した無味の言葉を、五十音順に並べ替えてみた。
「影(かげ)」
「虚空(こくう)」
「石(いし)」
「沈黙(ちんもく)」
「瑠璃(るり)」
「琥珀(こはく)」
「玻璃(はり)」
「銀(しろがね)」
「霧(きり)」
まだ、意味をなさない。だが、響はもう一つの可能性に気づいていた。教授は記号論の専門家だ。言葉を、その音や形、あらゆる側面から分析する人だった。もし、このアナグラムが、単語の頭文字だけを拾う形式だとしたら?
「か」「こ」「い」「ち」「る」「こ」「は」「し」「き」
違う。これでもない。焦りと失望が押し寄せる。だが、その瞬間、響の脳裏に、教授の優しい声が蘇った。『君のその力は、言葉が本来持つ魂の響きを捉えている』。魂の響き……音だ。
響は、並べ替えた言葉を、もう一度、声に出して読んでみた。
「かげ、こくう、いし、ちんもく……」
その時、ハッとした。音で繋がる言葉がある。
「いし(石)」と「ちんもく(沈黙)」ではない。「いし(意志)」だ。教授は、響が音で意味を再構築することを見越していたのではないか。
響は、パズルを解くように、言葉を音で繋ぎ、意味を探り始めた。試行錯誤を繰り返すうち、一つの文章が奇跡のように浮かび上がってきた。
「かこ の いし は しずか に とけ、きみ の ちから は しゅくふく に」
過去の意志は静かに解け、君の力は祝福に。
全身の血が逆流するような衝撃だった。これは、相良教授から響個人に向けられた、あまりにも優しく、そして切ないメッセージだった。教授の死は、やはり病死だったのだ。犯人などどこにもいなかった。これは、殺人事件ではなかった。自らの死期を悟った老教授が、孤独な青年に遺した、最後の授業。最後の謎解き。
そして、メッセージはまだ終わっていなかったことに、響は気づく。詩の最後の行、「我が魂は、ただ虚空を見つめるのみ」。この一文だけ、他の部分と明らかに毛色が違っていた。そして、この文にある「虚空」は、先ほどのアナグラムで使った。では、残りの言葉は?
「我が魂は、ただ見つめるのみ」
この言葉を口にした瞬間、響は初めて、その味を感じた。それは、あの懐かしい、上質なほうじ茶の味だった。教授の声そのものの味がした。温かい液体が喉を伝うように、教授の想いが響の心に染み渡っていく。涙が、便箋の上にぽたぽたと落ちた。
第四章 真実の味
相良教授は、すべてを知っていたのだ。響が幼い頃に両親を交通事故で亡くしたこと。そして、その事故に、誰にも言えない秘密が隠されていることを。教授は、響の両親の親友であり、事故の真相を知る唯一の証人だった。彼はその重荷を一人で背負い、響が大人になるのを見守り続けてきた。
直接伝えれば、それはただの残酷な暴露になってしまう。だから教授は、響が自らの力で「真実」に辿り着くための道筋を用意したのだ。共感覚という、彼を長年苦しめてきた呪いのような力を使い、彼自身の手で扉を開けさせるために。
教授が用意した「無味」の言葉たち。それは、何の感情も脚色もされていない、純粋な「事実」の断片だった。響が今まで味わってきた、感情に彩られた言葉とは違う、初めて触れる「真実」の味。それは無味であると同時に、すべての味の根源となる、究極の味だったのかもしれない。
響は、古書店のカウンターで夜が明けるのを見つめていた。東の空が白み始め、窓から差し込む光が、埃をきらきらと舞い上がらせる。彼の世界は相変わらず味に満ちている。だが、何かが決定的に変わっていた。
彼の能力は、呪いではなかった。それは、言葉の魂に触れるための特別な感覚であり、誰かの深い愛情を受け止めるための器でもあったのだ。相良教授が、その命の最後に教えてくれたことだった。
両親の死の真相がどのようなものであれ、もう彼は逃げない。教授が遺してくれた「真実の味」を道標に、自分の過去と向き合う覚悟ができていた。
響は、相良教授が遺した詩集を手に取った。もう一度、あの無味の詩を、今度は感謝を込めてゆっくりと読む。かつて感じた空虚さの代わりに、今はそこに温かいものが満ちていくのを感じた。それは、ほうじ茶の香ばしい風味に似ていた。
彼の孤独が完全に消えたわけではないだろう。これからも、言葉の味に喜び、苦しむ日々は続く。だが、もう彼は一人ではなかった。言葉の味と共に、真実の重みを抱きしめて生きていく。
響は静かに立ち上がり、店の扉を開けた。朝の新鮮な空気が、新しい一日の味を連れて、店内に流れ込んできた。それは、まだ名も知らない、希望の味がした。