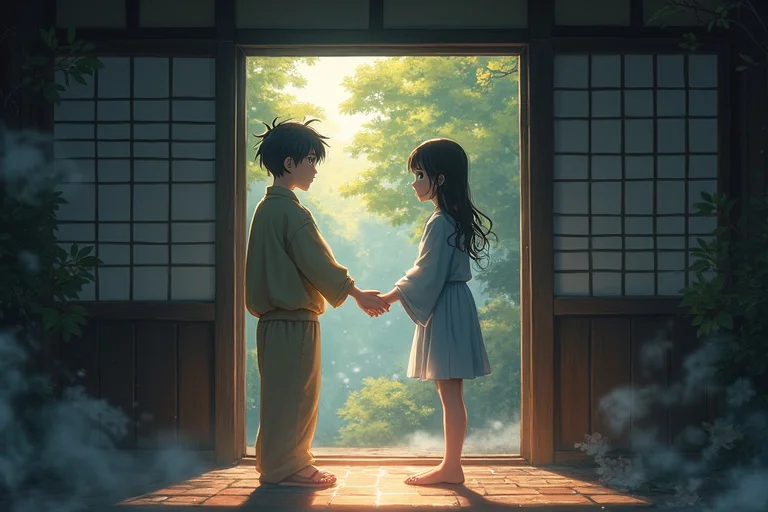第一章 父の不在と父の声
「お父様が、今朝」
電話口で遠い親戚の女性が言葉を濁した時、俺、水野涼介の心に浮かんだのは、悲しみよりもむしろ、ひどく場違いな安堵感だった。これで、もう帰省のたびに気まずい思いをしなくて済む。そんな冷たい思考が頭をよぎり、すぐに自己嫌悪に陥った。
父とは、もう十年近くまともに口を利いていない。母が亡くなってから、あの家には父と、重たい沈黙だけが住んでいた。俺はその沈黙から逃げるように東京へ出て、振り返らなかった。
通夜と葬儀は、まるで他人事のように過ぎていった。涙は一滴も出なかった。ただ、焼香の煙が目に染みただけだ。埃っぽい実家に戻り、遺品整理を始めたのは、すべての儀式が終わった翌日のことだった。父の部屋は、俺が知っている頃とほとんど変わっていなかった。本棚には難解な歴史書が並び、机の上には吸い殻の詰まった灰皿と、飲みかけでぬるくなったお茶。時間が止まったような空間に、父の不在だけが生々しく存在していた。
クローゼットの奥、スーツの内ポケットを探っていた手が、ごつりとした硬い感触に行き当たった。取り出してみると、それは手のひらにしっくりと収まる、川石のように丸く磨かれた黒い石だった。艶やかで、ひんやりとしている。そういえば、父はいつもこんな石をポケットに入れていた。子供の頃、それは父の体温でいつも温かかったのを覚えている。
懐かしさに駆られ、その石を強く握りしめた、その瞬間だった。
『……涼介か』
頭の中に、直接声が響いた。驚いて石を落としそうになる。聞き間違えようのない、低く、少ししゃがれた父の声だった。俺は呆然とあたりを見回す。部屋には俺一人。幻聴か?
恐る恐る、もう一度石を拾い、耳に当てるでもなく、ただ手に持つ。
『久しぶりだな。大きくなったか? いや、もうとっくに大人か。はは……』
声は、確かにこの石から発せられている。いや、違う。石が振動しているわけじゃない。まるで脳に直接、思考が流れ込んでくるような奇妙な感覚。これが、噂に聞く「聲石(こえいし)」というやつか。人が強い想いを遺して死ぬと、その声が愛用の品に宿ることがあるという、都市伝説めいた現象。まさか、無口で感情を表に出さなかったあの父が、こんなものを遺すなんて。
『静かになったな、家が。お母さんがいなくなってから、ずっとだ』
声は感傷的に呟いた。その言葉は、俺が父に抱いていた印象とはあまりにかけ離れていた。父も、寂しかったのだろうか。俺が逃げ出したあの家で、たった一人で。
ひんやりとしていたはずの石が、ポケットの中で父が温めていた時のように、じわりと熱を帯びていくのを感じながら、俺はただ立ち尽くすことしかできなかった。
第二章 薄れる輪郭
東京のアパートに、父の聲石を持ち帰った。最初の数日は、戸惑いと気味の悪さで、机の引き出しの奥にしまい込んでいた。だが、静まり返ったワンルームで一人、夕食のコンビニ弁当を食べていると、ふとした瞬間にポケットの中の父を思い出す。あの重たい沈黙を共有していた父が、今、饒舌に語りかけてくる。皮肉なものだ。
意を決して石を手に取ると、父は待っていたかのように話し始めた。
『涼介、お前が小さい頃、よくキャッチボールをした公園の桜、まだあるだろうか。あの木の下で、お母さんが作ったおにぎりを食べたな。お前、梅干しが嫌いで、こっそり地面に埋めようとしていた』
忘れていた記憶が、色鮮やかに蘇る。そうだ、俺は梅干しが苦手だった。父は怒りもせず、ただ笑って見ていた。俺の中の父は、いつも不機嫌で、新聞の向こう側から俺を睨んでいるような、そんな印象ばかりだったのに。
聲石の父は、俺の知らない父だった。母との馴れ初めを照れくさそうに語り、俺が生まれた日の喜びを、まるで昨日のことのように話した。その声は、生前の無骨さとは裏腹に、不器用な愛情に満ちていた。俺はいつしか、毎晩のように聲石を手に取り、父との対話にのめり込んでいった。失われた十年を取り戻すかのように。生きていた時には決してできなかった、父と子の会話がそこにはあった。
「親父、ごめん。俺、何も知らなかった」
ある晩、俺は思わず声に出して謝っていた。石の中の父は、少し間を置いてから答えた。
『いいんだ。お前は、お前の人生を生きれば』
その声の優しさに、胸が締め付けられた。
しかし、奇妙な共同生活が二ヶ月ほど続いた頃、俺は異変に気づき始めた。
『お母さんの好物は、確か……煮物だったか? いや、天ぷらかな……』
『お前が熱を出して寝込んだ時、何日も看病したことがあったな。あれは、小学校に上がる前だったか、後だったか……』
父の記憶の輪郭が、少しずつぼやけ始めている。以前は淀みなく語っていた思い出が、曖昧な問いかけに変わっていく。声の張りも、心なしか弱々しくなっているように感じた。
焦燥感が俺を襲った。このままでは、父が、父の声が、消えてしまう。
「違うよ、親父!母さんの好物はカレイの煮付けだろ!俺が熱を出したのは小学二年の時だよ!林間学校の前で、すごく悔しがってたじゃないか!」
俺は必死に語りかけた。薄れゆく記憶の断片を、俺の言葉で繋ぎ止めようとした。まるで風に飛ばされそうな古い写真を押さえるように。俺は初めて、父のために何かをしようと必死になっていた。父を失うという事実が、死から数ヶ月経って、ようやく本当の痛みとなって俺の胸に突き刺さった。
第三章 鏡の向こう側
父の記憶の減衰は、止まらなかった。俺がどんなに正確な情報を与えても、その時は思い出せても、数日経てばまた忘却の霧の中に沈んでしまう。それはまるで、穴の空いた器に水を注ぎ続けるような、虚しい作業だった。
俺は憑かれたように聲石について調べ始めた。インターネットの片隅にあるオカルトフォーラム、古書店の埃っぽい棚。情報は少なく、信憑性も怪しいものばかりだった。それでも諦めきれず、藁にもすがる思いで、とあるフォーラムで紹介されていた「聲石の会」という小さな集まりに連絡を取った。
指定されたのは、都心から離れた古民家カフェだった。そこで俺を迎えたのは、穏やかな目をした初老の男性、高村と名乗る人物だった。彼は静かにお茶を淹れると、俺が差し出した父の聲石を、壊れ物を扱うようにそっと両手で包み込んだ。
「……温かい。良い石ですね。あなたのお父様は、あなたを深く愛しておられた」
高村さんの言葉に、俺は少しだけ救われた気がした。そして、記憶が消えていく恐怖を必死に訴えた。どうすれば、父をこの石の中に留めておけるのか、と。
高村さんは、悲しげに首を横に振った。
「水野さん、一つ、残酷なことをお伝えしなければなりません。聲石とは、一体何だと思われますか?」
「死者の……魂や、記憶が宿ったものじゃ……」
「半分は正しく、半分は違います」
高失踪さんは、静かに、しかしはっきりと言った。
「聲石は、死者の魂そのものではありません。あれは……残された者の記憶が、死者の声を借りて再生されているに過ぎないのです」
時が、止まった。耳鳴りがして、高村さんの言葉が理解できなかった。
「どういう……ことですか?」
「聲石が語る記憶は、持ち主であるあなたの記憶そのもの。あなたの記憶の中にある『お父さん』が、お父さんの声で語りかけているだけ。いわば、あなたの心を映す鏡です」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。じゃあ、俺が聞いていた父の愛情のこもった言葉も、俺の知らないはずだった母との思い出も、全部、俺自身が作り出した幻想だったというのか?
「いいえ、幻想ではありません」高村さんは俺の心を読んだように言った。「あなたが無意識の奥底で知っていた、あるいは感じ取っていたお父様の愛情が、聲石を触媒として表に出てきたのです。しかし……」
彼は言葉を続けた。
「聲石の記憶が薄れていくのは、お父様の魂が消えるからではない。持ち主である、あなた自身が……お父様のことを、忘れ始めているからです」
絶望が、足元から這い上がってきた。俺は父を救おうとしていたんじゃない。俺は、自分自身の薄れゆく記憶の残骸を、必死にかき集めていただけだったのだ。父との縁を自ら断ち切り、新しい思い出を作ることを怠ってきた罰。父を二度、失おうとしているのは、他の誰でもない、俺自身だった。
父を忘れてしまう。その恐怖が、死の悲しみを遥かに凌駕して、俺の全身を凍りつかせた。
第四章 沈黙のぬくもり
あの日以来、俺は聲石を手に取るのが怖くなった。自分の記憶の不確かさと向き合うのが、何よりも恐ろしかったからだ。引き出しの奥で眠る石は、まるで俺の怠惰と薄情さを告発する墓標のように思えた。
何日も経って、ようやく俺は再び石を手に取った。覚悟を決めて、耳を澄ます。
『……涼介』
声は、か細く、ほとんど囁きのようだった。だが、まだ、そこにいた。
俺はもう、記憶を補強するように語りかけるのをやめた。ただ、黙って耳を傾ける。消えゆく言葉の断片を、一つ一つ、愛おしむように拾い集めた。それは、俺自身の過去との対話であり、父を忘れないための、静かな儀式だった。
俺は会社に長期休暇を申請し、何年ぶりかに父の書斎を整理し始めた。父が遺したアルバムを開き、几帳面な文字で書かれた日記を読んだ。疎遠だった親戚に頭を下げ、電話をかけ、俺の知らない父の話を聞いて回った。若い頃の失敗談、好きだった音楽、仕事での苦労。一つ一つのエピソードが、俺の中で空っぽだった「父」という名の器を、少しずつ満たしていった。
それは、聲石の記憶を蘇らせるためではなかった。もう、手遅れなのは分かっていた。ただ、俺自身の心の中に、父という人間の輪郭を、永遠に刻みつけておきたかった。
そして、ある秋の夜。いつものように聲石を握りしめると、そこから聞こえてきたのは、もう父の言葉ではなかった。
ただ、ザー……という、川のせせらぎにも似た、穏やかで温かい音だけが響いていた。声は、完全に消えたのだ。
涙が、頬を伝った。父の死の時にも、葬儀の時にも流れなかった涙が、今、静かに溢れ出してきた。喪失感は、確かにあった。しかし、不思議と絶望はなかった。
ポケットの中で、ただの音を発するようになった石は、それでも変わらず温かかった。父の体温のように。いや、これはもう父の体温ではない。父を想う、俺自身の心の温度なのだ。
父はいなくなった。声も、その声が呼び覚ましてくれた記憶も、多くが消えてしまった。
だが、父が俺の中に遺してくれたもの。父を想い、父の不在を悲しみ、それでも父という存在を愛おしむこの心は、確かにここに在る。
家族とは、物理的に側にいることや、記憶を共有することだけではないのかもしれない。たとえ姿かたちがなくなり、記憶が薄れていっても、相手を想い続ける心、その温かい心の繋がりそのものが、家族ということなのかもしれない。
俺は立ち上がり、東京のアパートを引き払う準備を始めた。あの、重たい沈黙が支配していた実家へ帰るために。
がらんとした父の部屋の縁側に座り、夕暮れの空を眺める。ポケットの中の石は、相変わらず静かに、そして確かに温かい。父の声はもう聞こえない。だが俺は、その沈黙のぬくもりの中に、永遠に消えない父の存在を、確かに感じていた。