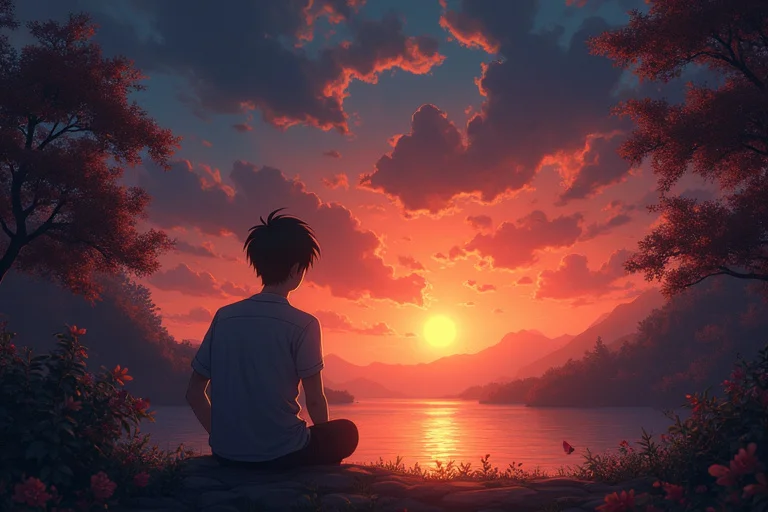第一章 壊れた子守唄の残り香
風もないのに、部屋の空気が微かに震えているように感じた。俺、橘響(たちばな ひびき)は、警察の許可を得て、恩師である老ヴァイオリニスト・有栖川正二郎(ありすがわ しょうじろう)の部屋に足を踏み入れた。享年八十二。発見された時、彼は長年愛用したロッキングチェアに座り、まるで眠るように息を引き取っていたという。警察は心不全による自然死と結論付けた。穏やかな大往生。誰もがそう言って、巨匠の死を悼んだ。
だが、俺だけが知っていた。この部屋には、穏やかさとは程遠い、歪んだ感情の残滓が渦巻いていることを。
俺には、特殊な共感覚がある。人の強い感情が宿ったモノに触れると、その記憶の断片が「香り」となって鼻腔を突き刺すのだ。それは呪いにも似た能力で、俺はいつしか人との深い接触を避け、孤独な調香師として生きることを選んだ。
「形見分けに、先生の愛用品を何か一つでも」と申し出た俺に、遺族は快く応じてくれた。部屋の中央に置かれたヴァイオリンケースに、吸い寄せられるように近づく。黒檀のように艶やかなケースにそっと指を触れた瞬間――来た。
ツン、と鼻を刺すのは、焦げ付いたカラメルのような甘さと、錆びた鉄の匂いが混じり合った、不快な香り。それは「裏切り」の記憶が放つ特有の匂いだ。さらに、その奥から、冷たい氷が肌を撫でるような「恐怖」の香りが立ち上ってくる。そして、何よりも俺を混乱させたのは、それらの不協和音の底で、か細く聞こえるメロディだった。途切れ途切れの、まるで壊れてしまったオルゴールのような子守唄。
これは、ただの病死じゃない。有栖川先生は、死の直前、誰かに裏切られ、何かに酷く怯えていた。
俺は革張りの持ち手を握りしめた。先生は、俺がこの能力を持っていることを知る、唯一の人物だった。幼い俺の苦悩を理解し、「その鼻は、いつか誰かの心を救うためにあるのかもしれないな」と、温かい手で頭を撫でてくれた。その恩師が、こんな不可解な感情の残り香を残して逝ってしまった。真相を突き止めなければ、俺は一生、後悔の匂いに苛まれ続けるだろう。
こうして、俺だけの孤独な捜査が始まった。手掛かりは、この壊れた子守唄の香りだけだった。
第二章 容疑者たちの不協和音
有栖川先生の死の真相を探るため、俺は彼の周辺にいた三人の人物に会うことにした。俺の鼻が捉えた「裏切り」と「恐怖」の香りの持ち主を、この中に見つけ出すために。
最初に訪ねたのは、一番弟子の神崎(かんざき)だった。彼は次世代のホープと目されながら、数年前に突如楽団を辞め、今はしがない音楽教室の講師に収まっている。先生の仕事部屋だった防音室で、彼が使っていたという譜面台に触れた。瞬間、むせ返るような香りが俺を襲う。熟れすぎて腐りかけた果実の甘さと、湿った土の匂い。それは「嫉妬」と「焦燥」が入り混じった香りだった。神崎は、師である有栖川の才能に焦がれ、同時にその才能を超えられない自分に絶望していたのだ。彼の瞳の奥に、消えない熾火のような野心が見えた。彼なら、師を裏切る動機があるかもしれない。
次に会ったのは、先生の一人娘である小夜子(さよこ)さんだ。彼女は憔ेंそりとした表情で、父の思い出を語った。彼女がいつも座っていたというリビングのソファの肘掛けに、さりげなく指を滑らせる。すると、雨に濡れた古い羊皮紙のような、乾いた諦めの香りがした。その奥に、微かに感じられるのは、塩辛い涙の匂い。「悲しみ」と「無力感」。彼女は父親の才能と名声の影で、ずっと孤独だったのかもしれない。だが、そこに殺意に繋がるような、どす黒い感情の香りはなかった。
最後に接触したのは、長年のライバルと噂された指揮者の倉田(くらた)だ。音楽葬で言葉を交わした際、彼が弔辞を読んでいた演台に触れた。そこから香り立ったのは、意外にも、一点の曇りもない「敬意」の香りだった。まるで、澄み切った冬の朝の空気のような、清廉な香り。噂とは裏腹に、彼は心の底から有栖川先生を認め、その死を悼んでいた。
三者三様の感情の香り。しかし、どれも俺がヴァイオリンケースから感じ取った「裏切り」と「恐怖」の核心とは、どこか音色が違っていた。情報は増えるほど、パズルのピースは散らばっていく。俺はまるで、指揮者を失ったオーケストラの中で、不協和音に耳を塞ぐしかない聴衆のようだった。
俺は自分の能力の限界を感じ始めていた。香りは感情の断片を教えてくれるが、その文脈までは教えてくれない。嫉妬が殺意に変わることもあるだろう。だが、それは俺の憶測に過ぎない。俺は本当に、先生の心を理解しようとしているのだろうか。それとも、ただ自分の能力を証明したいだけのエゴに突き動かされているのだろうか。焦燥感が、じっとりと背中に張り付いていた。
第三章 奏者なきアリア
捜査は完全に行き詰まった。手掛かりを求め、俺はもう一度、有栖川先生の部屋を訪れた。がらんとした部屋は、主を失った楽器のように静まり返っている。俺は無意識に、先生の書斎の隅にあった古い楽譜棚に手を伸ばした。埃をかぶった楽譜の束をめくっていると、一冊だけ、手触りの違うノートが指に当たった。それは、先生が個人的に書き留めていたらしい、手書きの楽譜帳だった。
表紙を開き、黄ばんだ五線譜に指を触れた瞬間、俺は息を呑んだ。
今まで嗅いだことのないほど、強く、そして純粋な香りが、脳髄を直接揺さぶった。それは、焼きたてのパンのように温かく、春の陽だまりのように柔らかい、「絶対的な愛情」の香り。そして、長く苦しい旅を終えた旅人のような、深い「安堵」の香り。さらに、その香りの奥深くから、まるで讃美歌のように響いてきたのは、万物を包み込むような「許し」の香りだった。
混乱する頭で、俺はその香りの記憶の主を探った。神崎か? 小夜子さんか? それとも、俺の知らない誰かなのか?
違う。全て違った。
この深く、切なく、そしてあまりにも優しい感情の香りの主は――他ならぬ、有栖川正二郎、本人だったのだ。
俺はその場に膝から崩れ落ちた。どういうことだ。ヴァイオリンケースからは「裏切り」と「恐怖」の香りがした。だが、この楽譜帳は「愛情」と「安堵」を放っている。同じ人物が、死の直前に、これほどまでに矛盾した感情を抱くことがあり得るのか。
その時、楽譜帳の最後のページに、震えるような文字で書かれた一文が目に飛び込んできた。
『愛する孫娘、海へ。このメロディを忘れてしまう前に。パパのパパより』
そして、その下には、あの「壊れた子守唄」の旋律が記されていた。
全てが、繋がった。
有栖川先生は、アルツハイマー病を患っていたのだ。彼が感じていた「恐怖」とは、殺人鬼に向けられたものではない。自らの記憶が、才能が、そして何より愛する孫娘のために作ったこの子守唄が、病によって消え去っていくことへの恐怖だった。彼が感じた「裏切り」とは、誰かに裏切られたのではない。輝かしい人生を共に歩んできた、自らの記憶と身体に裏切られる絶望だったのだ。
彼は、自分が自分でなくなってしまう前に、全ての記憶が混濁してしまう前に、自らの手で人生の幕を引くことを選んだ。最も美しい記憶――孫娘への愛情――が宿るこの楽譜を胸に、安らかに逝くことを。ロッキングチェアに座り、彼は最後の力を振り絞って、自らの死を「許し」、受け入れたのだ。
俺が嗅ぎ取ったのは、殺人事件の痕跡ではなかった。一人の人間が、その尊厳の全てを懸けて、自らの「死」と対峙した、壮絶で、あまりにも孤独な闘いの記録だった。俺は自分の傲慢さを恥じた。能力に頼り、感情の断片を嗅ぎ分けただけで、真実を理解した気になっていた。人の心とは、香りだけで推し量れるほど、単純なものではなかったのだ。
第四章 追憶のパルファン
数日後、俺は小夜子さんに会い、有栖川先生の楽譜帳を渡した。俺の能力のことは伏せたまま、楽譜に残された最後のメッセージと、日記の断片から推測した父君の本当の想いを伝えた。彼は誰かを憎んで死んだのではなく、最後まで家族を愛し、その記憶を守ろうとしていたことを。
小夜子さんは、父が病と闘っていたことに全く気づかなかった自分を責めた。だが、楽譜帳に記された優しい子守唄のメロディと、娘(先生の孫)への愛情に満ちた言葉に触れ、彼女の瞳からは、後悔ではなく、温かい涙がとめどなく溢れた。父の最後の想いは、確かに彼女の心に届いたのだ。
あの日以来、俺の中で何かが変わった。俺は仕事場であるアトリエに戻り、新しい香水の創作に取り掛かった。もう、感情の断片を刺激的に再現するだけの香りは作らない。その感情が生まれるに至った物語、その裏側にある文脈、声にならない想いまでをも掬い上げるような、そんな香りを創りたいと思った。
俺の能力は呪いでもなければ、真実を暴く万能の道具でもない。それは、人の心の深淵を覗き込む、ほんの小さな「きっかけ」に過ぎないのだ。そのことを、有栖川先生が、その命をもって教えてくれた。
数ヶ月後、一本の香水が完成した。
トップノートは、ベルガモットの僅かな苦みと、ラベンダーの静かな安らぎ。それは、忍び寄る病への「恐怖」と「絶望」を表現している。
ミドルノートは、アイリスの知的でパウダリーな香りと、古書のインクのような香り。失われていく記憶と、守りたかった尊厳の香りだ。
そして、ラストノート。肌の上でゆっくりと花開くのは、バニラとムスクが溶け合った、温かく甘い香り。それは、全てを包み込む「愛情」と「安堵」、そして「許し」の香り。有栖川先生が最後にたどり着いた境地。
俺はその香水に、『追憶(L'aria del Ricordo)』と名を付けた。
奏者なきアリア。それは、悲しいけれど、どこまでも優しい愛の香りがした。失われたものへの哀悼と、決して消えることのない、残された愛への賛歌だった。
俺は完成した香水を一吹きし、静かに目を閉じた。鼻腔をくすぐる香りの奥に、有栖川先生の穏やかな笑顔が見えた気がした。