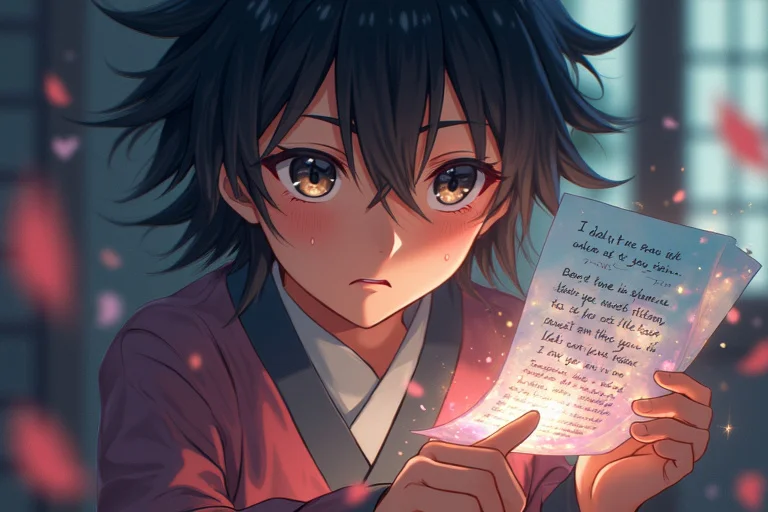第一章 時盗人と星見の憂鬱
江戸の夜は、深い藍色の帳(とばり)に包まれていた。その静寂を裂くように、武家屋敷から悲鳴が上がる。しかし、奇妙なことに、助けを求める声はすぐに途絶え、あとには不気味な沈黙だけが残った。
幕府天文方、暦月弦之介(こよみづきげんのすけ)は、上役から渡された一件書類を前に、眉間に深い皺を寄せていた。この一月で五件目となる、通称「時盗人(ときぬすびと)」の仕業だ。手口はいつも同じ。ある特定の時刻、屋敷の者たちが金縛りにあったかのように一瞬動きを止め、その間に家宝や金子が忽然と消える。被害者たちは、その間の記憶をすっぽりと失っていた。「まるで、時の流れそのものを盗まれたかのようだ」と、人々は畏怖を込めて囁き合った。
「暦月、お主の出番であろう。星や暦を眺めることしか能のないお主には、うってつけの与太話だ」
上役の言葉は、嘲笑を隠そうともしない。剣も振るえず、算盤も人並み。ただ、夜空に輝く星々の運行を読み解くことにかけては、師である天文方の長・星詠景斎(ほしよみけいさい)も舌を巻くほどの才を持つ弦之介。しかし、その才は泰平の世において何の役にも立たず、同僚からは「星見の戯言」と揶揄されるばかり。この奇怪な事件の調査も、事実上の厄介払いであった。
自室に戻った弦之介は、巨大な和紙を床一面に広げた。そこには、江戸の地図が精密に描かれている。彼は、事件が起きた五つの屋敷の位置に、朱で印をつけた。そして、被害時刻をその横に書き記していく。
子(ね)の刻、丑(うし)三つ時、卯(う)の刻半……。
一見、何の関係もないように思える時刻と場所。だが、弦之介の目は、紙の上に描かれた点と線から、常人には見えぬ理(ことわり)を読み取ろうとしていた。彼は筆をとり、事件現場と江戸城を中心に、幾重もの円と直線を引いていく。それはまるで、目に見えぬ天球儀を紙上に再現するかのようだった。
墨の匂いが部屋に満ちる。外ではしとしとと春の雨が降り始め、軒先を叩く音が彼の思考を妨げる。焦りと無力感が、鉛のように肩にのしかかる。自分は本当に、この不可解な事件を解き明かすことができるのか。星を読むだけの、無力な男なのに。
ふと、彼は気づいた。五つの事件現場を結ぶと、歪んだ五芒星が浮かび上がる。そして、それぞれの犯行時刻。それは、その日その場所から見える、特定の星が南中する時刻と寸分違わず一致していたのだ。
「これは……偶然ではない」
弦之介の全身に、ぞくりと鳥肌が立った。犯人は、ただの盗人ではない。自分と同じ、あるいはそれ以上に、天体の運行、すなわち「暦の理」を深く理解している人物だ。これは、暦術を悪用した、前代未聞の犯罪。弦之介の瞳に、初めて憂鬱以外の色――挑戦的な光が宿った。自分の知識が、この謎を解く唯一の鍵なのかもしれない。
第二章 月の調べ、影の周期
弦之介の推察は、上役には一蹴された。「星の時刻だと?馬鹿馬鹿しい」。しかし、彼は諦めなかった。犯人が暦術を使うのであれば、次もまた、何らかの天文現象に則って事を起こすはずだ。彼は過去の膨大な観測記録と照らし合わせ、犯行周期に隠されたもう一つの法則を見つけ出した。それは、月の満ち欠け――朔望(さくぼう)の周期と深く関わっていた。
「次の犯行は、三日後の下弦の月。場所は、深川の材木問屋だ」
弦之介は、自身の計算に確信を持っていた。彼は奉行所に掛け合い、半信半疑の捕り方たちと共に、その夜、問屋の周囲に張り込んだ。闇に紛れ、息を殺す。弦之介は懐から古びた方位磁石を取り出し、天頂を仰いだ。月が、雲間から痩せた姿を現す。予測時刻が、刻一刻と迫っていた。
しかし、その夜、時盗人は現れなかった。夜が明け、徒労感に打ちひしがれる捕り方たちの冷たい視線が、弦之介に突き刺さる。彼の暦は、外れたのだ。
失意のまま帰り道を歩いていた弦之介は、不意に聞こえてきた琵琶の音色に足を止めた。それは、寂寥(せきりょう)と気高さを併せ持った、心を揺さぶる調べだった。音のする方へ向かうと、柳の木の下で、一人の盲目の女琵琶法師が、一心に弦を弾いていた。透き通るような白い肌、黒く長い髪。閉ざされた瞼は、かえって彼女の顔立ちの端正さを際立たせていた。
「その調べ……どこか悲しげですな」
弦之介が思わず声をかけると、彼女はぴたりと手を止め、顔を上げた。
「私の名は、調(しらべ)と申します。この音色が、あなた様の心を曇らせましたか」
「いえ、むしろ、私の心の曇りが、この音色に惹きつけられたのです」
話すうち、弦之介は彼女が先日、時盗人の被害に遭った商家の娘であることを知った。彼女もまた、他の者たちと同じように一瞬、体の自由を奪われたという。だが、彼女には一つだけ、他の被害者と違う点があった。
「目が見えぬ代わりに、私の耳は人一倍敏いのです。あの時……時が止まったように感じた、あの瞬間に、私は音を聞きました」
「音、ですか?」
「はい。キィン、と……まるで、遠くで鳴らされた銀の鈴が、空気に染み渡るような、高く、澄んだ音でございました」
その証言は、弦之介の脳裏に稲妻を走らせた。音。それは、彼の計算にはない要素だった。犯人は、暦術で定めた時刻と場所で、何らかの「音」を使い、術を発動させているのではないか。
弦之介は、調の鋭敏な感覚に希望を見出した。彼は彼女に事件の概要を話し、協力を請うた。調は、静かに頷いた。彼女の閉ざされた瞳の奥に、強い意志の光が灯っているように、弦之介には感じられた。この日から、星を読む男と、音を聴く女の、奇妙な協力関係が始まった。共に過ごす時間が増えるにつれ、弦之介は、孤独だった自分の世界が、彼女の存在によって少しずつ色づいていくのを感じていた。
第三章 皇暦の咎、師の真実
調の証言を得て、弦之介の思考は新たな次元へと飛躍した。暦術と音。この二つを結びつけるものは何か。彼は天文方の書庫に籠もり、古今東西の文献を読み漁った。そして、ついに一つの記述に行き当たる。『天律共鳴』――古代の陰陽師が用いたとされる秘術。特定の天体配置の瞬間に、特殊な周波数の音を発生させることで、地の磁場を乱し、人の精神に影響を与えるという。
「これだ……!」
犯人は、星がもたらす微弱なエネルギーを、音叉のような道具で増幅させているのだ。弦之介は、次の犯行日時と場所を再び算出した。今度は、朔望周期だけでなく、地球と太陽、そして他の惑星の引力が複雑に絡み合う、「特異日」を割り出したのだ。
予測当日。弦之介は奉行所には告げず、ただ一人、予測地点である両国橋の袂(たもと)へと向かった。彼の隣には、調が寄り添っている。彼女の耳だけが、犯人の術を捉えられるからだ。
だが、予測時刻が過ぎても、何も起こらない。またしても、自分の暦は外れたのか。弦之介が天を仰ぎ、唇を噛んだその時、遠くで半鐘が乱打される音が響き渡った。江戸城の方角から、黒い煙が立ち上っている。
「火事……?まさか!」
弦之介の背筋を、冷たい汗が伝った。時盗人の真の狙いは、街場での盗みなどではなかった。それはすべて、幕府の目を欺くための陽動。本命は、江戸城。彼は罠に嵌められたのだ。
急いで城へと駆けつけると、騒然とする人々の中に、師である星詠景斎の姿があった。彼は、鎮火の指揮を執る役人たちに、冷静な声で指示を与えている。その姿は、いつもと変わらぬ、厳格で尊敬すべき師そのものだった。しかし、弦之介は見てしまった。景斎の袖の内から、ちらりと覗く銀色の棒を。それは、音叉だった。そして、彼の顔に浮かんだ、ほんの一瞬の、冷徹な笑みを。
全身の血が凍りつく。まさか。そんなはずはない。だが、すべての点が、線で結ばれていく。犯人だけが持ち得たはずの、高次元の暦術の知識。天文方の長である景斎ならば、それを持っていて当然だ。火災の混乱に乗じて、彼が狙うものとは何か。
弦之介の脳裏に、一つのものが浮かんだ。天文方に代々受け継がれる、門外不出の至宝――『皇暦(こうれき)』。それは、過去数百年、未来数百年もの天体の運行を寸分の狂いなく記した、究極の暦盤。それを手にすれば、天律共鳴を意のままに操り、人の運命、ひいては天下さえも動かすことが可能になる。
「師よ……なぜ……」
弦之介は呆然と立ち尽くした。自分が生涯をかけて探求してきた暦の道。その道を照らしてくれたはずの師が、その知識を、天下を揺るがすための凶器として使っていた。信じていた世界が、音を立てて崩れ落ちていく。空から降る火の粉が、まるで血の涙のように見えた。
第四章 星霜の和音
景斎は皇暦を手に入れ、姿を消した。彼が残した書状には、腐敗した幕政への絶望と、自らが「天意」の代行者となり、この国を大掃除するという、狂気に満ちた決意が記されていた。そして、その計画の成就は、七日後に迫る皆既日食の瞬間に託されていた。江戸全域を覆う影の下、彼は過去最大規模の天律共鳴を引き起こし、府内の全機能を麻痺させるつもりだった。
絶望の淵に沈む弦之介を、奮い立たせたのは調だった。
「弦之介様。あなたの暦は、間違ってはいなかった。ただ、師であるその方の暦が、一枚上手だっただけのこと。……いいえ、本当にそうでしょうか」
彼女の言葉に、弦之介ははっとした。景斎もまた、人間だ。彼の暦は、本当に完璧なのか。弦之介は再び、膨大な計算の海に身を投じた。不眠不休で筆を走らせ、算盤を弾き続ける。師から受け継いだ知識のすべてを総動員し、師の計算を、一から検算していく。
そして、日食前夜。弦之介はついに見つけ出した。景斎の計算における、たった一つの、しかし致命的な「ズレ」を。それは、近年発見されたばかりの、彗星の軌道がもたらす微弱な重力干渉。景斎の皇暦には、その最新の知見が反映されていなかったのだ。その影響で、皆既日食が最大となる時刻は、景斎の予測よりも、一分(いっぷん)ほど遅れる。それは、わずか一分。されど、天律共鳴の術を破るには、十分すぎるほどの時間だった。
皆既日食の当日。空は不気味な黄昏に染まり、太陽が月に喰われていく。人々が不安げに空を見上げる中、景斎が潜む江戸湾の小島では、巨大な音叉が低く唸りを上げ始めていた。
だが、弦之介は動かなかった。ただ、じっと空を見つめ、時を待つ。そして、自らが算出した「真の時刻」が訪れた瞬間、彼は合図の旗を高く振り上げた。
その瞬間、江戸中の寺社仏閣で、一斉に鐘が鳴り響いた。ゴォォン、と地を揺るがす荘厳な音。それは、ただの乱打ではない。調が、景斎の音叉が発する不協和音を「聴き分け」、それを打ち消すために弦之介が導き出した、完璧な「和音」だった。それぞれの寺社が、異なる音階の鐘を、寸分の狂いもなく同時に打ち鳴らす。
無数の鐘の音が江戸の空で一つに溶け合い、壮大なシンフォニーとなって景斎の術と衝突した。景斎の音叉が発していた不快な高周波は、荘厳な和音の中に掻き消され、天律共鳴は発動することなく霧散した。
術は破られ、景斎は捕らえられた。牢の中で、彼は静かに弦之介に問うた。
「なぜ、わかった」
「師がお教えくださったではありませんか」
弦之介は、静かに答えた。
「万象は常に移ろい、決して完成することはない、と。あなたの皇暦すら、例外ではなかったのです。……そして、私には、私の見えない星を教えてくれる、音が聞こえましたから」
数年後。天文方の長となった弦之介は、新しい暦の編纂に励んでいた。それは、天意を笠に着るためのものではなく、農民が種を蒔く時を知り、漁師が潮を読む助けとなる、人々の暮らしに寄り添うための暦だった。
縁側で、弦之介は夜空を見上げていた。隣には、穏やかに微笑む調がいる。彼女は、彼の読む星々の物語を、静かに聴いている。
知識は、時に人を狂わせ、凶器となる。だが、使い方を違えなければ、未来を照らす希望の光にもなる。星々は、何も語らない。ただ、悠久の時の流れの中で、変わらずそこに在るだけだ。その声なき声に耳を澄まし、理を読み解き、より良き明日を紡いでいくこと。それこそが、人に与えられた、ささやかで、しかし尊い営みなのだ。
弦之介は、満天の星々が奏でる、壮大な「星霜の諧調」を聴いているような気がした。