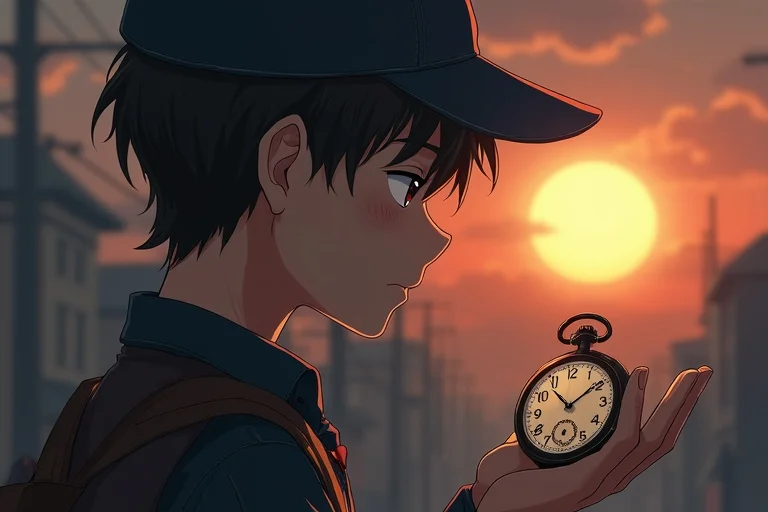第一章 灰色のリスト
空は、停戦協定が結ばれたあの日からずっと、色を失ったままだった。共和国の首都を覆う鉛色の雲は、敗戦という名の巨大な墓標のように、人々の心に重くのしかかっていた。俺、リノの仕事場である中央記憶編纂局もまた、色彩に乏しい場所だった。窓のない地下深くの保管庫には、サーバーの低い唸りと、冷却ファンの乾いた風の音だけが響いている。俺たちは戦争に負けた。そして、賠償として支払うのは、金でも土地でもない。俺たちの「記憶」だった。
「記憶編纂官」と呼ばれる俺の仕事は、戦勝国である大連邦が要求する記憶を選別し、規定のフォーマットに変換して引き渡すことだ。それは、外科手術にも似た、感情を伴わない作業であるはずだった。国家の英雄譚、歴史的な発明の記録、失われた技術の設計図。そういった価値ある「情報」が、次々と俺たちの手で祖国から剥ぎ取られていく。抵抗は無意味だった。抵抗すれば、物理的な破壊が待っているだけだ。俺たちは、文化的な死を受け入れることで、かろうじて肉体的な生を許されていた。
その日、連邦から新たな収奪リストが届いた。ホログラムのディスプレイに映し出された文字列を、俺は無感動に目で追っていく。「建国神話の原典」「旧王家の紋章の意匠」「古代言語の文法体系」……どれも予想の範囲内だ。だが、リストの最後にあった一行に、俺の指は思わずスクロールを止めた。
『項目番号734:名もなき子守唄』
詳細データはほとんどない。記録された時代も、場所も、歌い手も不明。ただ、「ある母親が病弱な息子に歌い聞かせた個人的な旋律」という短い注釈があるだけだった。馬鹿げている。なぜ連邦は、こんな個人的で、歴史的価値も軍事的価値もない、ささやかな記憶を欲しがる? 他の項目が国家の背骨だとするなら、これは爪の先に引っかかった、取るに足らないささくれのようなものではないか。
同僚の誰に聞いても、首を傾げるばかりだった。何かの間違いではないか、と。だが、連邦の命令は絶対だ。俺は、この「名もなき子守唄」の記憶アーカイブを探し出し、引き渡しのために編纂する任を命じられた。
サーバーラックの森の奥深く、忘れ去られたインデックスの中に、そのデータは眠っていた。アクセス権を解除すると、俺の目の前のコンソールに、古い記憶の断片がノイズ混じりに再生され始めた。それは、俺の日常を、そして俺の魂を根底から揺さぶる、静かな嵐の始まりだった。
第二章 子守唄の残響
記憶へのダイブは、冷たい水に飛び込む感覚に似ている。意識がデジタル信号に変換され、過去という名の海へ沈んでいく。俺が最初に感じたのは、乾いた草と、陽光をたっぷり吸い込んだ土の匂いだった。
視界が開けると、そこは小さな木造の家の一室だった。窓から差し込む夕陽が、部屋の隅に積まれた洗濯物の山を橙色に染めている。俺は誰でもない「観測者」として、その光景を眺めていた。部屋の中央には、古びた揺り椅子に腰かけた若い母親と、その腕に抱かれた小さな男の子がいた。男の子の呼吸は浅く、時折、苦しそうな咳が漏れる。母親は、その小さな背中を優しく撫でながら、静かに歌い始めた。
それは、洗練された旋律ではなかった。むしろ、即興で紡がれたような、素朴で、少しだけ音程の外れたメロディ。だが、その声には、言葉では表現しきれないほどの愛情が溶け込んでいた。
『眠れ、眠れ、わたしの小さな光。夜の闇がお前を隠しても、母の歌が道しるべ。星の船に乗り、月の海を渡り、朝の岸辺でまた会おう』
歌詞もまた、ありふれたものだった。しかし、その声色、息遣い、子の額に落ちる涙の温かさ。それら全てが一体となって、圧倒的な感情の奔流として俺の意識に流れ込んできた。それは「情報」ではなかった。それは、紛れもなく「魂」の記録だった。
俺は、自分の頬に何かが伝うのを感じて、はっと我に返った。ダイブ用のヘッドセットを外すと、指先が濡れていた。泣いていたのだ、俺は。戦争で両親を失い、感情に蓋をすることを覚えて以来、一度も流したことのなかった涙が。
この子守唄は、単なるデータではない。この母親にとって、それは病の子の命を繋ぎとめるための祈りそのものだった。この子にとって、それは世界で最も安全な場所だった。こんなにもパーソナルで、神聖なものを、どうして無機質なデータとして引き渡せるだろう。
数日間、俺は仕事に身が入らなかった。食事の味もせず、眠りも浅かった。夜ごと、あの母親の声が耳元で響く。それは、俺が幼い頃に聞きたかった声、俺が誰かに聞かせたかった声でもあった。俺の中で、何かが軋みを上げて崩れ始めていた。これは、ただの仕事ではない。これは、誰かの心を殺す行為だ。俺は、この子守唄を守らなければならない。たとえ、それが国家への反逆を意味するとしても。
第三章 忘れ方の忘却
俺は、禁じられている手段に手を出した。収奪リストを作成した連邦の担当官への、直接通信の要求だ。反逆罪に問われかねない危険な賭けだったが、もはや俺に迷いはなかった。驚くべきことに、要求は数時間であっさりと承認された。
編纂局の最奥にある特別通信室。分厚い防音壁に囲まれた部屋で、俺は巨大なホログラム・スクリーンと向き合っていた。スクリーンにノイズが走り、やがて、軍服に身を包んだ壮年の男の姿が浮かび上がった。胸には、連邦の最高技術顧問を示す徽章が光っている。男は、カイと名乗った。その表情は、俺が想像していた征服者の傲慢さとは程遠く、むしろ深い疲労と憂いを湛えていた。
「項目番号734について、異議があると聞いている。記憶編纂官リノ君」カイの声は、合成音声のように平坦だった。
俺は、込み上げる怒りを抑えながら言った。「異議、というより質問だ。なぜ、あの子守唄を? 何の価値もない、個人の記憶を。あなた方は、我々の歴史や技術だけでなく、魂まで奪うつもりか」
カイはしばらく黙っていた。スクリーンの向こうで、彼はゆっくりと目を閉じる。その沈黙は、俺を苛立たせるのではなく、むしろ奇妙な静けさで満たしていた。やがて、彼は口を開いた。その言葉は、俺の世界を根底から覆す、衝撃的な告白だった。
「奪うのではない。学びたいのだ」
「学ぶ…?何をだ」
「愛し方をだ」カイの声は、わずかに震えていた。「我々、連邦は、勝利を重ねる過程で、あまりにも多くのものを失った。効率を追求し、感情を排し、論理だけを信奉した。その結果、我々は戦争には勝ったが、…内なる戦いには負けた。我々の国では、もはや新しい歌は生まれない。親は子に物語を語らず、人々はただ目的のために生きている。我々は、豊かさの中で精神的に餓死しかけているのだ」
彼は続けた。「我々は、君たちの国の記憶アーカイブを解析するうち、ある事実に気づいた。国家の力とは、英雄譚や技術力だけではない。名もなき人々の、ささやかな日常の記憶の集積…それこそが、文化の真の土壌なのだと。あの子守唄は、我々が百年以上前に失ってしまった、『無償の愛』という概念の、完璧な結晶だった。我々は、それを兵器として使うのではない。それを道しるべとして、我々が何者であったかを、思い出したいのだ」
忘れ方を、忘れてしまったのだ、と彼は言った。どうすれば心を休められるのか。どうすれば誰かを慈しめるのか。その方法を、彼らは完全に失ってしまっていた。
俺は言葉を失った。敵だと思っていた相手の、あまりにも人間的な、痛切な叫び。彼らは征服者ではなかった。彼らは、魂の砂漠を彷徨う、迷える探求者だったのだ。俺が守ろうとしていたものは、彼らが喉から手が出るほど求めている、一滴の水だった。
第四章 記憶の渡し人
通信を終えた俺は、がらんとした通信室に一人、立ち尽くしていた。怒りは消え、代わりに深い哀れみと、そして新たな使命感が胸に込み上げてきた。俺の仕事は、記憶を「奪われる」ことへの抵抗ではなかった。失われた心を「繋ぐ」ための、架け橋になることだったのだ。
俺は編纂室に戻り、再びコンソールに向かった。だが、今度の俺は以前の俺ではなかった。単なる編纂官ではない。俺は、記憶の語り部、「渡し人」だった。
俺は、子守唄の音源データだけを抽出するのをやめた。代わりに、俺自身がダイブで体験した全ての感覚を、データに織り込んでいった。夕陽の暖かさ、乾いた草の匂い、母親の涙の塩味、子の小さな寝息の振動。そして何より、その場を支配していた、言葉にならないほどの愛の密度。俺は、この記憶が持つ文脈と感情の機微を、一つの物語として再構築したのだ。それはもはや、単なる記録データではなかった。それは、追体験可能な「祈り」そのものだった。
完成したデータを送信する際、俺は規定外の行動を取った。暗号化されたテキストメッセージを、データに添えたのだ。
『これは、奪うものでも与えるものでもない。ただ、思い出すための標だ。あなた方の心の奥底にも、かつてこれと同じ温もりが灯っていたことを。この歌が、あなた方の魂の渇きを、少しでも癒すことを願っている』
送信ボタンを押した指は、震えていなかった。
数日後、俺たちの共和国に、小さな変化が起きた。連邦からの次なる収奪リストが、届かなくなったのだ。代わりに送られてきたのは、一つの通信だった。連邦が、自国の失われた民話や童謡のデータを、復元の助言を求めるという名目で、こちらに開示してきたのだ。それは、戦争の勝敗を超えた、文化的な対話の始まりだった。
俺は、自分のしたことが世界をどう変えたのか、その全貌を知ることはないだろう。だが、時折、あの静かな編纂室で目を閉じると、遠い星の向こうで、誰かが不器用に、あの「名もなき子守唄」を口ずさんでいるような気がするのだ。
記憶とは、記録し、保存するだけでは意味がない。誰かの心に届き、受け継がれ、そして新たな物語を紡ぐ種となった時、初めて永遠の命を得る。俺は今日も、失われた記憶の欠片を拾い集める。いつか、どこかの誰かが、その温もりを必要とする日のために。灰色の空の下で、俺は静かに、記憶の渡し人であり続ける。