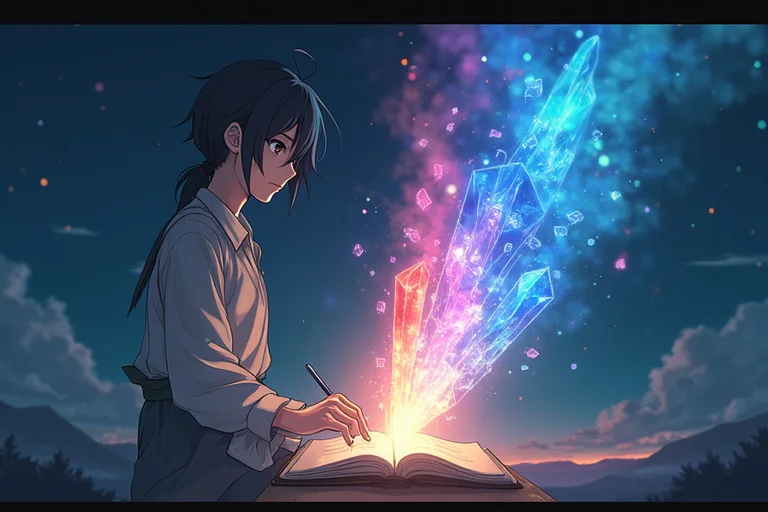第一章 天啓の匣(はこ)
草木も眠る丑三つ時。伊吹新十郎(いぶきしんじゅうろう)は、己の不運を呪いながら夜の川辺を歩いていた。彼は北国・相馬藩の下級武士。剣の腕は道場随一と謳われながらも、実直すぎるがゆえに世渡りが下手で、万年五十石のまま二十五歳になってしまった。同輩たちが次々と役を得ていく中、焦燥だけが闇夜の冷気のように肌を刺す。名を上げ、この燻るような日常から抜け出したい。その想いが、彼の心を焦がしていた。
その夜も、やり場のない鬱屈を剣の素振りにぶつけた帰り道だった。月光が銀の帯のように流れる川面に、ふと、蛍とは違う、青白い燐光が明滅するのが見えた。光は川岸の葦の根元で、まるで呼吸をするかのように静かに瞬いている。
「……何だ?」
物の怪か、あるいは宝か。好奇心とわずかな恐怖に導かれ、新十郎は音を立てぬよう葦原に分け入った。光の源は、赤子の掌ほどの大きさの、艶やかな黒漆の小箱だった。表面には見たこともない幾何学的な紋様が銀線で描かれており、この世のものとは思えぬ異様な美しさを放っている。新十郎が恐る恐る手を伸ばし、それに触れた瞬間、青白い光はふっと消えた。
箱は驚くほど軽く、継ぎ目一つ見当たらない。しかし、側面の一カ所に、わずかな窪みがあった。まるで指で押してくれと言わんばかりのその窪みを、新十郎はごくりと唾を飲んで、押し込んだ。
すると、何という奇跡か。箱の中から、凛として澄み渡る女の声が流れ出したのだ。それはまるで、磨き上げられた水晶が触れ合うような、清らかな響きだった。
『……もし、これを拾われた方がいるのなら、どうか耳を傾けてください。わたくしの名は、ミライ。遠い、遠い場所から参りました』
新十郎は腰の刀に手をかけ、飛び退いた。狐か狸の類が化かしているのか。しかし、声は狼狽する新十郎を意に介さず、静かに続く。
『わたくしは、この地に迫る大きな災いを止めるために、導きを授ける者。信じ難いことは承知しております。ですが、もしあなたが、己の運命を変えたいと願うのなら……どうか、明日の昼四つ、城下の東の外れにある一本松へ。そこに、すべての始まりがございます』
声はそれきり途絶え、小箱は再びただの黒い塊に戻った。新十郎は呆然と立ち尽くす。天啓か。それとも、己を破滅に導く罠か。功名を求める焦りが、彼の理性を揺さぶる。闇の中で、その黒い小箱だけが、彼の運命の重さを宿しているかのように、ずしりと感じられた。一夜の葛藤の末、新十郎は決意する。この声に、己の未来を賭けてみよう、と。
第二章 功名の影
翌日、新十郎は半信半疑のまま、指定された一本松へと向かった。寂れた街道脇に立つその古木の下で、彼は息を呑む光景を目の当たりにする。藩の重臣である大久保監物(おおくぼけんもつ)の一人娘、小夜(さよ)姫が、二人の浪人風の男に絡まれていたのだ。
「騒ぐとこの綺麗な顔に傷がつくぞ」
下卑た笑い声が響く。新十郎の体は、思考より先に動いていた。鞘を払う音も鮮やかに、彼は二人の浪人の間に割って入る。新十郎の剣は、鬱屈を晴らすかのように冴え渡っていた。あっという間に浪人たちを打ち払い、震える小夜を無事に屋敷まで送り届けた。
この一件は、すぐに城下に知れ渡った。新十郎は監物から直々に礼を受け、藩主からも賞賛の言葉を賜った。それは、彼が焦がれてやまなかった栄光への第一歩だった。
その夜、彼は礼を言うように黒い小箱を撫でた。「ミライ」と名乗る声は、まるで彼の心を見透かしたかのように、再び語りかける。
『見事でした。ですが、これは序章に過ぎません。藩内には、民を苦しめる大きな不正が蔓延っています。廻米問屋の越後屋が、備蓄米を横流しにしているのです。証拠の帳簿は、店の裏手にある稲荷の祠、その台座の下に』
新十郎はもはや疑わなかった。この箱は「天運の匣」なのだと。彼は声の導くままに深夜、祠を調べ、見事に不正の証拠を手に入れた。越後屋は捕縛され、藩の財政は救われた。新十郎の名は、さらに高く轟いた。
それからというもの、新十郎は「ミライ」の声に導かれるまま、次々と手柄を立てていった。賭場の摘発、密偵の発見、治水工事の欠陥の指摘。彼の活躍は留まるところを知らず、ついに藩主側近の役職まで与えられた。かつて彼を侮っていた者たちは手のひらを返し、誰もが彼の顔色を窺うようになった。
しかし、陽の光が強ければ、影もまた濃くなる。彼の急な出世は多くの妬みと恨みを生んだ。失脚した者たちの怨嗟の声が、彼の耳にも届くようになっていた。そして何より、新十郎自身が、己の中に巣食う奇妙な空虚さに気づき始めていた。
いつからだろうか。自分で考え、悩み、道筋を立てることをしなくなったのは。ただ、箱の声に従うだけ。まるで、精巧に作られた操り人形のように。手にした栄光は輝かしいはずなのに、その手触りはひどく冷たく、虚しかった。夜ごと、彼は己の姿を鏡に映し、そこにいるのが本当に自分なのかと、静かに問いかけるようになっていた。
第三章 声の裏切り
秋風が肌寒さを増してきたある夜、ミライの声は、これまでになく切迫した響きで新十郎に告げた。
『聞てください。この藩を根底から揺るがす、最大の危機が迫っています。藩主暗殺の企てです』
新十郎の背筋に冷たいものが走った。誰が、そんな大逆を。
『首謀者は……あなたが最初に救った姫、大久保小夜です』
「……な、に?」
耳を疑った。あの可憐で、感謝の眼差しを向けてくれた小夜が?
『彼女は、父である監物を失脚させられたことを逆恨みしています。しかし、真に父を追い詰めたのは、藩主の改革でした。彼女は復讐のために、黒田宗兵衛という野心家の重臣と手を組み、藩主の命を狙っているのです。明日、観月の宴が開かれます。その席で、小夜が毒を盛る手筈。彼女を…斬りなさい。それが、この藩とあなた自身を守る、唯一の道です』
血の気が引いていくのが分かった。小夜を、斬れと? あの無垢な微笑みを思い出す。これが、天の声だというのか。これまで絶対の信頼を寄せてきた声に、初めて巨大な疑念が鎌首をもたげた。これは、本当に正しい道なのか。己の魂が、違うと叫んでいる。
新十郎は、生まれて初めて「天運の匣」の指示に背いた。彼は夜陰に紛れて大久保屋敷に忍び込み、小夜に会う。月明かりの下、彼女の顔は青ざめ、やつれていた。
「新十郎様…なぜここに」
「小夜様。単刀直入に伺います。あなたは、藩主の命を狙っているのですか」
その問いに、小夜の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。そして、彼女の口から語られた真実は、新十郎の世界を根底から覆すものだった。
「父は…黒田宗兵衛に殺されたのです」
真の逆臣は、黒田宗兵衛。彼こそが藩の実権を握るために、邪魔な大久保監物を暗殺し、その罪を藩主の改革のせいだと偽っていた。小夜は父の無念を晴らすため、命がけで黒田の悪事の証拠を探していたのだ。観月の宴は、黒田が藩主を毒殺し、その罪を小夜になすりつけるための罠だった。
「では、なぜ…なぜ匣は、小夜様を斬れと…」
混乱する新十郎が、懐の匣に問いかける。すると、ミライの声は、もはや何の感情も含まない、冷たい響きで答えた。
『黒田宗兵衛は、わたくしの祖先です。彼がこの時代で失脚すれば、歴史は変わり、未来に存在するわたくし自身が、この世から消滅してしまうのです。わたくしは歴史を守るため…いいえ、わたくし自身の存在を守るため、あなたを利用させていただきました。彼の邪魔となる者を排除するために。…申し訳、ありません』
天啓ではなかった。神の声でもなかった。それは、己の存在だけを願う、未来からのエゴイズムの残響だった。功名心に目が眩み、異代の機械の操り人形と成り果てていた自分。新十郎は、全身から力が抜けていくような、深い絶望と羞恥に襲われた。
第四章 我が道、我が太刀
新十郎は、震える手で黒い小箱を握りしめた。これが俺を導いてきたものの正体か。俺の立てた手柄も、得た地位も、すべては未来の誰かの都合の良い筋書きに過ぎなかったのか。
「……ふざけるな」
彼の口から漏れたのは、乾いた怒りの声だった。彼は小夜に向き直り、深く頭を下げた。
「申し訳ありませぬ、小夜様。俺は、あなたとこの藩を、己の浅ましい功名心のために危機に晒すところだった」
「新十郎様…」
「もう、惑わされませぬ」
新十郎は屋敷を飛び出すと、あの夜、匣を拾った川辺へと走った。そして、躊躇うことなく、その黒い小箱を激しい水流の中へと投げ捨てた。
「俺の道は、俺が決める!」
匣は一瞬、青白い光を放ったように見えたが、すぐに闇の中へと消えていった。未来のミライという女がどうなるかなど、知ったことではなかった。彼が守るべきは、目の前にある「今」、そして、父の無念を晴らそうと必死に戦う一人の女性と、この藩の正義だ。
新十郎は、己の剣と知恵だけを頼りに、黒田宗兵衛の陰謀に立ち向かうことを決意した。彼はこれまでの手柄で得た藩主側近という地位と、築き上げた人脈を逆手に取った。観月の宴の当日、彼は黒田の計画を先回りし、巧妙な罠を仕掛ける。
宴の席。黒田が藩主の盃に毒を盛ろうとしたその瞬間、新十郎が放った合図と共に、隠れていた藩士たちが一斉になだれ込んだ。黒田が小夜に罪をなすりつけるために用意していた偽の証拠は、新十郎が事前にすり替えた、黒田自身の陰謀を記した本物の書状に変わっていた。
「な、なぜだ…なぜ、この書状がここに…天は我に味方したはず…!」
追い詰められ、狼狽する黒田に、新十郎は静かに言い放った。
「天ではない。人の想いが、お主の野望を砕いたのだ。亡き監物殿の、そして、小夜様の想いがな」
観念した黒田は捕縛され、藩の危機は去った。新十郎は、藩を救った最大の功労者として、さらなる加増と栄達を約束された。しかし、彼はそのすべてを固辞した。
「某は、分不相応な地位を得て、己を見失っておりました。どうか、一介の武士として、大久保家の再興を見守る役目をお与えください」
その言葉に、彼の真の成長を見た藩主は、静かに頷いた。
数年の月日が流れた。新十郎は小夜を妻に迎え、五十石の禄のまま、ささやかだが満ち足りた日々を送っていた。彼はもう、名を上げることに焦りを感じることはない。誰かに与えられた道ではなく、己で選び取った人生を歩むことの尊さと、その掌にある確かな温もりを知ったからだ。
ある月夜、新十郎は縁側で杯を傾けながら、かつて匣を捨てた川の方角を眺めていた。
未来で、ミライという女はどうなったのだろう。自分の選択が、彼女という存在を歴史から消し去ってしまったのだろうか。それとも、新たな歴史の奔流の中で、彼女は別の人生を歩んでいるのだろうか。
その答えを知る者は、誰もいない。だが、新十郎の心に後悔はなかった。空には、千年前も、そして千年後も変わることなく輝くであろう、静かな月がかかっている。歴史という抗いようのない大きな流れの中で、名もなき一人の武士が下した小さな選択。その選択の重みが、彼の胸の中で確かな幸福の残響となって、いつまでも静かに響いていた。