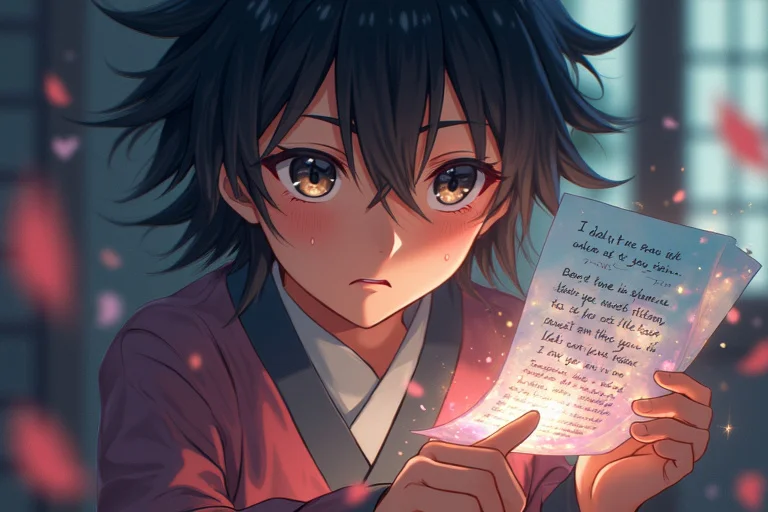第一章 無色の文(ふみ)
江戸の街は、音と色で満ちていた。魚を売る威勢の良い声は朝日を浴びて黄金に輝き、すれ違う武士たちの寡黙な挨拶は、鋼のような鈍い銀色を帯びていた。俺、弦之助(げんのすけ)の目には、人の発する言葉がすべて、その感情を宿した「色」となって見えた。
武家の次男として生まれた俺は、この異能のせいで人の本音が見えすぎ、息苦しくなって家を飛び出した。今では「言霊師(ことだまし)」などと大層な名で呼ばれ、言葉の裏に隠された真偽を読み解くことで糊口をしのいでいる。嘘は濁った土色に、喜びは弾ける山吹色に、そして深い悲しみは、水に滲む藍色に見える。俺は、その色を読み解くだけだ。
その日、俺を訪ねてきたのは、日本橋で大きな呉服屋を営む、和泉屋の主人・惣兵衛(そうべえ)だった。年の頃は五十を過ぎているだろうか。身なりは良いが、その顔には深い影が落ちていた。彼の言葉は、ひどく疲れた、くすんだ赤色をしていた。それは、どうにもならない現実への憤りと、消えぬ愛情が混ざった色だった。
「弦之助殿に、読んでいただきたいものがある」
惣兵衛が懐から取り出したのは、一枚の文(ふみ)だった。上質な和紙に、震えるような筆跡で言葉が綴られている。差し出された文面を、俺は読んだ。
『あなた様を、愛してはおりませぬ』
半年前に亡くなった、彼の妻・千代からの文だという。病の床で書き遺したものだと。
「妻は…千代は、そのようなことを言う女(ひと)ではありませ ん。誰よりも情け深く、わしを支えてくれた。この文には、何か別の意味が隠されているはずだ。それを、解き明かしてはくれぬか」
惣兵衛の目から、大粒の涙がこぼれた。その言葉は、妻への揺るぎない信頼を示す、燃えるような深紅に染まっていた。
俺は文を受け取り、目を凝らした。そこに宿るはずの、千代という女の感情の色を読み解くために。
だが、奇妙なことだった。
文字はただ、そこにあった。墨の黒が、紙の白に染み込んでいるだけ。色がない。喜びも、悲しみも、憎しみも、嘘の色さえもない。まるで、心が空っぽの人間が書いたかのような、完全な「無色」の言葉だった。
俺は言霊師として生きてきて、このような文を見たのは初めてだった。それは、俺の知る世界の法則が、根底から覆されたような不気味な静けさを湛えていた。
第二章 色を探す旅
「無色の言葉…そんなことがあり得るのか?」
俺は自室で、和泉屋の文を前に腕を組んだ。人の感情は、水が器に満ちるように、必ず言葉に宿る。たとえ無感情を装っても、そこには「取り繕う」という意思の色が薄く浮かぶものだ。だがこの文には、それすらない。
翌日から、俺は千代という女の「色」を探す旅に出た。
まずは、長年和泉屋に仕えているという老女中に話を聞いた。
「奥様は、それはもう、仏様のようなお方でございました。旦那様のことをいつも案じておられ…ああ、旦那様のお好きな桜色の反物が入りますと、それは嬉しそうに『あの方にお似合いになるかしら』と仰せで…」
女中の言葉は、懐かしさと敬愛に満ちた、柔らかな藤色をしていた。嘘はない。
次に、千代が懇意にしていたという絵師を訪ねた。病になる前は、よく絵を習っていたらしい。
「和泉屋の奥様ですか。実に感性の鋭い方でしたな。特に、藍色の使い方には天賦の才があった。悲しみの色である藍を、あれほど静謐で、美しい色として描ける方を、私は他に知りません」
絵師の言葉は、芸術家特有の探究心を示す、澄んだ青緑色だった。
誰に聞いても、千代は夫を深く愛し、慈しんでいたことが窺えた。彼女が「愛してはおりませぬ」などという言葉を遺す理由が見当たらない。ならば、なぜ文は無色だったのか。
惣兵衛にそのことを伝えると、彼は力なく首を振った。
「代筆…かもしれぬ。千代は亡くなるひと月ほど前から、筆を握る力も残っておらぬほど衰弱しておった。だが、誰が? わしは、確かに千代の枕元に置かれたこの文を見つけたのだ」
惣兵衛の言葉は、混乱を示すように、様々な色が混じり合って濁っていた。
代筆だとしたら、その書き手の感情が宿るはずだ。だが、それもない。謎は深まるばかりだった。俺は江戸の喧騒の中を歩きながら、飛び交う言葉の色を眺めた。怒りの赤、見栄の紫、戯れの桃色。世界はこんなにも感情の色で溢れているのに、なぜあの文だけが、虚ろな無色なのだろう。
俺は、自分の能力そのものを試されているような感覚に陥っていた。そして、自分の言葉には色が見えないという、生まれついての欠落を改めて意識した。俺は他人の心の色は読めても、自分の心が何色かを知らない。だから、誰かと深く関わるのが怖い。無色の文は、まるで俺自身の心の空虚さを映す鏡のようだった。
第三章 墨痕に宿る心
調査が行き詰まり、数日が過ぎた。雨がしとしとと降る晩、俺は再び和泉屋を訪れた。何か、決定的なことを見落としている。そんな予感がした。
薄暗い座敷で、惣兵衛は一人、酒を飲んでいた。彼の周りには、深い絶望を示す、どす黒い藍色が澱のように漂っていた。
「弦之助殿か。…もう、よいのかもしれぬ。わしが、ただ見たくないものから目を背けていただけなのかもしれん」
「諦めるのか。あんたの言葉は、まだ奥方を信じる深紅に染まっている」
俺がそう言うと、惣兵衛は泣き笑いのような顔でこちらを見た。
「弦之助殿。あんたには、本当に言葉の色が見えるのだな…」
その時だった。ふと、俺の目に文机の上の硯が映った。上等な端渓硯(たんけいけん)。その縁に、微かに、本当に微かに、乾いた墨とは違う、滲んだ跡があった。それはまるで、涙の痕のようだった。
「惣兵衛さん。この文が書かれた日のことを、もっと詳しく教えてくれないか。どんな小さなことでもいい」
俺の真剣な眼差しに、惣兵衛は記憶を辿るように、ぽつり、ぽつりと語り始めた。
「あの日…千代はもう、声も出せなくなっていた。ただ、わしの手を弱々しく握るだけで…。だが、急に何かを伝えようとするかのように、わしの掌に、指で何かを書き始めたのだ」
惣兵衛の声は震えていた。その言葉の色が、藍色から、後悔を示す灰色へと変わっていく。
「わしは…必死でその指の動きを読み取った。一文字、一文字、忘れてはならぬと、そばにあった筆と紙で書き留めた。それが…この文だ」
惣兵衛は顔を覆った。彼の告白を聞いた瞬間、俺の頭の中で、すべての点が線で結ばれた。
「そうか…そういうことか…!」
俺は惣兵衛の肩を掴んだ。
「あんたは、書き間違えたんだ! 奥方が伝えたかったのは、『あなた様を、愛しては"おり"ませぬ』じゃない! 『あなた様を、愛して"やま"ぬ』…そうだろう!」
惣兵衛は、はっと顔を上げた。その目は驚愕に見開かれ、やがて滂沱の涙に変わった。
「あ…あぁ…そうか…やまぬ…やまぬ…! わしは、わしは、千代の最後の言葉を…!」
絶望と悲しみで、心が麻痺していたのだ。愛する妻の死を前にして、正常な判断などできるはずもない。「おり」と「やま」。たった一文字の違いが、天国と地獄ほどの意味の違いを生んでしまった。
そして俺は、無色の文の謎も完全に理解した。
あの文に感情の色がなかったのは、当然だった。なぜなら、あれは千代の「言葉」ではなかったからだ。あれは、妻の最後の想いを書き留めるという、惣兵衛の悲痛な「行為」そのものだった。弦之助の能力は、発せられた言葉に宿る感情の色は見えるが、文字を書くという行為に込められた、言葉にならない想いの色は見えなかったのだ。
俺が見ていたのは、言葉の真意ではなかった。ただ、感情の表層に浮かぶ色を見て、分かった気になっていただけだ。俺は、己の能力の限界と、その傲慢さを、生まれて初めて突きつけられた。
第四章 言霊の在り処(ありか)
惣兵衛は、泣き続けた。それは後悔の涙であると同時に、亡き妻の真実の愛を知った、救いの涙でもあった。彼の周りを漂っていたどす黒い藍色は、いつしか雨上がりの空のような、澄んだ色へと変わっていった。
俺は黙って和泉屋を後にした。報酬は受け取らなかった。これは俺の仕事の範疇を超えていた。いや、俺が学ぶべきことの方が、遥かに多かった。
帰り道、江戸の街は雨に洗われ、いつもより静かだった。俺の目には、相変わらず人の言葉に色がついて見えた。だが、その見え方は、以前とはまるで違っていた。
色は、ただの指標に過ぎない。その奥には、言葉で表しきれない、文脈や、状況や、人の歴史が、複雑な綾をなして存在している。無色の文は、言葉を発する者がいないからこそ、誰よりも雄弁にその場の心を物語っていたのだ。
俺は、自分の言葉に色が見えないことを、ずっと恐れていた。自分がどんな感情で言葉を紡いでいるのか、自信が持てなかったからだ。だが、今は違う。色が見えないからこそ、俺は自分の言葉に責任を持てるのかもしれない。色に頼らず、心で、魂で、言葉を紡ぐことができるのかもしれない。
空を見上げると、厚い雲の切れ間から、月が顔を覗かせていた。俺は、そっと呟いた。声には出さず、心の中だけで。
『俺は、何色の言葉を紡ぎたいのだろう』
その問いに、答えはまだ見つからない。だが、不思議と焦りはなかった。
これからの人生で、俺はきっと多くの人と出会い、多くの言葉に触れるだろう。時にはその色に惑わされ、時にはその色のない真実に心を揺さぶられるに違いない。
世界は色を失ったのではない。俺の世界が、ただの色ガラスの向こうから、ありのままの、より豊かで深遠な色彩を放ち始めたのだ。
言霊の本当の在り処は、目に見える色の奥深く、人と人とが心を通わせようとする、その切なる願いの中にこそある。俺は、その見えざる色を探す旅を、今、始めたばかりだった。