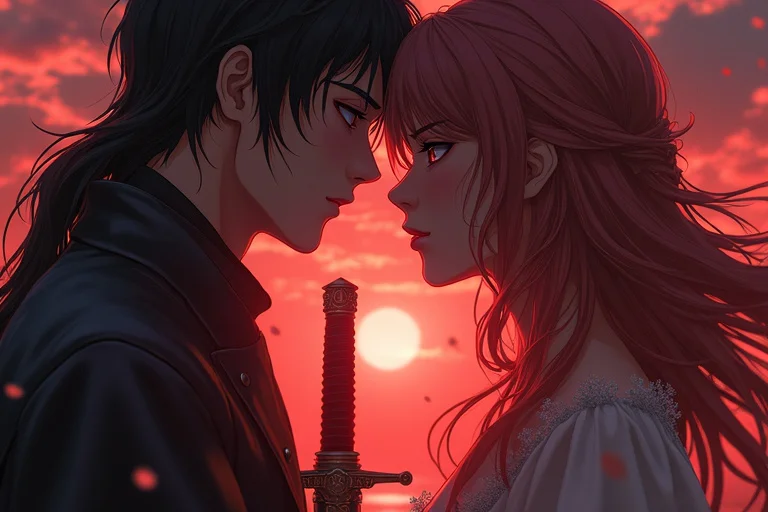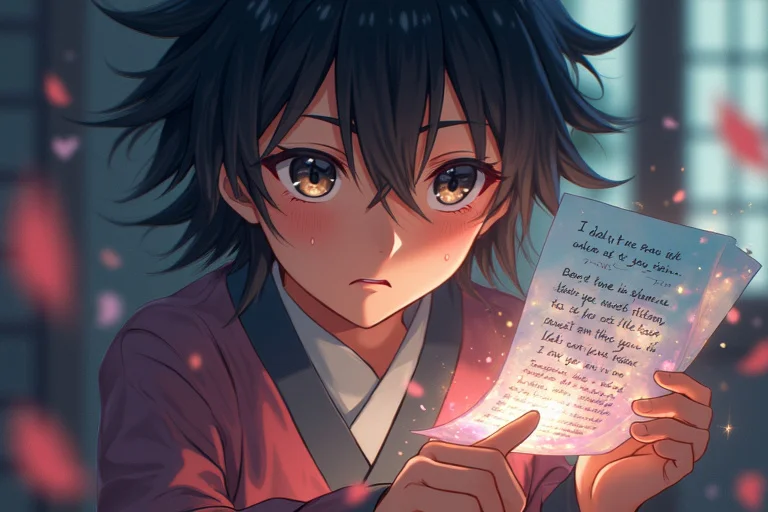第一章 揺らめく灯火
桐生一刀斎(きりゅう いっとうさい)は、己の右目が呪われているのだと信じていた。
かつて「人斬り一刀斎」と恐れられた彼が刀を捨て、辺鄙な村で寺子屋の手伝いなどをして糊口を凌いでいるのは、その呪われた右目のせいだった。彼の右目には、人の命が、胸の内に燃える蝋燭の炎として映るのだ。健やかな者の炎は太く、高く燃え盛り、老いた者のそれは細く静かに揺れる。病に伏せれば頼りなく瞬き、死期が迫れば、まるで風前の灯火のように消えかかる。
人を斬るたび、相手の胸で炎がふっと掻き消える瞬間を、嫌というほど見せつけられた。何十、何百と命の火を消すうち、一刀斎の心はすり減り、刀を握る意味を見失った。以来、彼は右目に映る炎から目を逸らすように、ただ静かに日々を過ごしていた。
その日も、一刀斎は子供たちの笑い声を遠くに聞きながら、寺の縁側で木簡を削っていた。柔らかな陽光が、彼の古びた着物を温めている。だが、ふと顔を上げた瞬間、彼の平穏は音を立てて崩れ去った。
境内で手毬をついている少女、お花の胸の内に灯る炎が、不自然に、そして激しく揺らめいたのだ。
それは病や怪我の予兆とは違う、もっと凶兆めいた揺らぎだった。まるで、見えざる何者かが吹きかける悪意の息に、か細い命が必死に抗っているかのような。一刀斎が過去に数度しか見たことのない、他者の「殺意」に晒された者だけが示す、命の悲鳴であった。
八つになるお花は、この村で生まれ育った天真爛漫な娘だ。誰に恨まれるというのか。一刀斎の背筋を、久しく忘れていた冷たい汗が伝った。
子供たちの無邪気な声が、急に遠のいて聞こえる。木簡を削っていた小刀が、カランと音を立てて足元に落ちた。見れば、己の手が微かに震えている。刀を捨て、人との関わりを絶ち、ただ消えゆくのを待つだけの命だと思っていた。だが、目の前で消えかかっている小さな灯火を前に、彼の心の奥底で、錆びついていたはずの何かが軋みを上げた。
守らねばならぬ。
その衝動は、理屈ではなかった。一刀斎は立ち上がると、寺の奥にある物置へと向かった。そこには、埃をかぶった一本の刀が、布に巻かれて静かに眠っている。再びこれを手にすることは、己の呪いと向き合うことに他ならなかった。
第二章 影を追う刃
刀を再び腰に差した日から、一刀斎の見る世界は色を変えた。村人たちの穏やかな日常の裏で、彼は見えざる敵の影を追い始めた。お花の胸の炎は、日を追うごとに弱々しくなり、その揺らぎは一刀斎の焦燥を煽った。
彼はまず、村に出入りする者たちを改めた。薬売りの行商人、近隣の村から来たという素性の知れぬ浪人。一刀斎はさりげなく彼らに近づき、その胸に灯る炎を右目で凝視した。だが、誰の炎からも、お花に向けられるような明確な殺意の揺らぎは見つけられなかった。彼らの炎は、ただ己の人生のために、淡々と燃えているだけだった。
「近頃、夜になると峠に怪しい人影が出るそうで」
「山の祠が荒らされていたと、猟師の源爺が……」
村人たちの噂話に耳を澄ませど、どれも確たる証には繋がらない。まるで、姿なき悪霊がお花を祟っているかのようだ。
ある雨の夜、一刀斎はお花の家の周りを見回っていた。降りしきる雨が地面を叩く音に混じり、微かな衣擦れの音が彼の耳に届いた。息を殺して闇に目を凝らすと、黒い頭巾をかぶった人影が、お花の家の裏手へと回り込もうとしている。
来たか。
一刀斎は音もなくその背後に迫った。相手が物置の戸に手をかけた瞬間、抜き放った刃の切っ先を、その喉元に突きつける。
「何者だ。その娘に何の用がある」
冷たく低い声に、人影はびくりと体を震わせた。ゆっくりとこちらを向いたその顔を見て、一刀斎は息をのむ。村の薬師、玄庵だった。温和な顔立ちで、村人たちの信頼も厚い男だ。
玄庵の胸に灯る炎は、確かに激しく揺らいでいた。しかし、それは憎悪や殺意からくるものではない。恐怖と、そして何か強すぎるほどの「信念」に身を焦がす者だけが放つ、青白い光だった。
「き、桐生殿……。これは……」
「問いに答えよ、玄庵殿。夜更けに忍び、幼子に何をしようというのか」
玄庵は観念したように、がくりと膝をついた。その手から、奇妙な意匠が施された短刀と、数枚の護符が滑り落ちる。
「……あれは、人ではない」
雨音に紛れそうなほどか細い声で、玄庵は呟いた。
「あれは、この村の精気を喰らう『禍ツ子(まがつこ)』じゃ。このままでは、村そのものが枯れてしまう。わしは、村を守るために……祓わねばならぬと……!」
玄庵の言葉は、一刀斎の思考を激しく揺さぶった。殺意ではない。村を守るという、歪んだ善意。そして、彼の右目が捉えた炎の揺らぎは、玄庵がお花に向ける敵意ではなく、むしろ玄庵自身の「正義」が燃え盛る様だったのだ。
第三章 善意という名の闇
玄庵の告白は、一刀斎が築き上げてきた価値観を根底から覆した。彼はこれまで、人の命を脅かすのは、憎悪や欲望といった分かりやすい「悪意」だけだと信じていた。だが、目の前の男は、村を救うという「善意」のために、幼い少女の命を奪おうとしている。
「禍ツ子だと? 馬鹿げた言い伝えを本気で信じているのか」
「言い伝えではない! 事実じゃ!」
玄庵は必死の形相で訴えた。彼の話によれば、この村では数十年ごとに原因不明の凶作や疫病が流行り、その度に「異質な子」が生まれるのだという。そして、その子を人知れず「還す」儀式を行うことで、村は災厄を免れてきたのだと。
「お花が生まれてから、この八年、村は豊作続きじゃ。だが、それは奴が、これから吸い上げる精気を溜め込んでいるに過ぎん。最近、山の井戸が涸れ、家畜が病み始めた。あれが、本性を現し始めた証拠じゃ!」
玄庵の目は狂信的な光を宿していた。彼の胸の炎が、その言葉を裏付けるかのように、一層激しく燃え上がる。一刀斎は、お花の胸に揺らめいていた炎の本当の意味を、この時ようやく悟った。
あれは、玄庵の殺意に怯えていたのではない。
お花自身の「存在」そのものが、この村の理(ことわり)から拒絶され、世界から消えかかっている悲鳴だったのだ。彼女に向けられているのは、一個人の殺意ではない。村という共同体が無意識に抱く、「異物」を排除しようとする巨大な意思。玄庵は、その代行者に過ぎなかった。
自分の右目は、ただ命の長短が見えるだけ。その炎が何を思い、何に苦しんでいるのかまでは、何も教えてはくれない。見えるものだけを信じ、単純な悪を斬り捨てれば済むと思っていた己の浅はかさを、一刀斎は恥じた。
では、どうすればいい? 村人を守ろうとする玄庵を斬るのか? それはかつての人斬りの所業と何が違う。だが、このままではお花の命が尽きてしまう。
雨はいつの間にか上がっていた。雲の切れ間から覗く月光が、苦悩に沈む一刀斎と、地に伏す玄庵の姿を白く照らし出す。
「……桐生殿。あんたは余所者じゃ。この村の痛みを、絶望を知らんでくれ」
玄庵の言葉が、一刀斎の胸に突き刺さる。そうだ、自分は所詮、流れ着いただけの部外者だ。だが、だからこそ見えるものがあるのではないか。
一刀斎はゆっくりと刀を鞘に納めた。
「玄庵殿。あんたの言うことが真実か、俺には分からん。だが、一つだけ確かなことがある」
彼は静かにお花の家の方を見やった。その壁の向こうで、小さな命の炎が、今も消えまいと必死に揺れている。
「俺のこの目は、あの娘が『生きている』と告げている。理由はどうあれ、それを人の都合で消していい道理はない」
一刀斎の胸の内にも、静かだが、しかし確かな炎が灯り始めていた。それは、人を斬るための虚しい炎ではない。何かを、誰かを、守るために燃える、温かい光だった。
第四章 いのちの在り処
翌朝、一刀斎は村の長老や主だった者たち、そして玄庵を集め、寺の本堂で対峙した。彼の腰には、夜の間に手入れを済ませた刀が差してある。だが、その刀身を抜くつもりはなかった。
「お花殿を、村から出していただきたい」
一刀斎の唐突な申し出に、村人たちはどよめいた。玄庵が険しい顔で反論する。
「禍ツ子を野に放てと申すか! どこで何を為すか分からんものを!」
「ならば、俺が引き取ろう。この娘の命に、俺が責任を持つ」
一刀斎は静かに続けた。「あんたたちの言う通り、村の井戸が涸れ、家畜が病んでいるのかもしれん。だが、それは本当にあの子のせいなのか? 去年は日照りが続いた。家畜の病は隣村でも流行っていると聞く。あんたたちは、得体の知れない不安を、ただ一人の弱い娘に押し付けているだけではないのか」
彼の言葉は、村人たちの心の澱を静かにかき混ぜた。誰もが心のどこかで感じていたはずの、後ろめたさ。言い伝えという大義名分にすがり、見て見ぬふりをしてきた己の弱さ。
「もし、あんたたちの言う禍ツ子が、本当に村の精気を吸うのなら」と、一刀斎は本堂の奥を見やった。「この八年、あれほど無邪気に笑い、歌い、他の子供たちと駆け回っていた娘は、一体何だったのだ。あれは、あんたたちの村が育んだ命そのものではないのか」
その時、本堂の入り口に、お花が立っていた。話を聞いていたのだろう、その小さな顔は不安に強張り、大きな瞳には涙が浮かんでいる。彼女は、自分の胸に灯る炎が見えるはずもないのに、まるでその存在を確かめるかのように、そっと胸に手を当てていた。
一刀斎は、彼女の胸の炎が、以前よりも少しだけ、しかし確かに、力強く輝きを取り戻しているのを見た。それは恐怖の色ではない。生きようとする、強い意志の光だった。
村人たちの間に、長い沈黙が流れた。誰もが、お花の純粋な眼差しから目を逸らすことができなかった。やがて、一番年嵩の長老が、深いため息と共にかぶりを振った。
「……我らの、過ちであったのかもしれんな」
その一言が、村を縛っていた古い呪いを解き放った。
数日後、一刀斎は村の入り口でお花と二人、旅支度を整えていた。村人たちは、詫びの印だと言って、ささやかな食料や路銀を差し出してくれた。玄庵もまた、深々と頭を下げ、薬草の包みを渡してくれた。
「桐生殿。あんたが守ろうとしたのは、あの子の命だけではなかった。我々が忘れかけていた、人の心だったのかもしれん」
一刀斎は何も答えず、ただ小さく頷いた。
お花の手を引き、村を後にする。小さな手は温かい。振り返ると、村人たちがいつまでも見送ってくれていた。
「一刀斎さま、私たちはどこへ行くの?」
見上げるお花の問いに、彼は穏やかに答えた。
「さあな。どこへでも行ける。お前が、お前らしくいられる場所を探しに行こう」
彼の右目には、少女の胸で明るく燃える炎が映っていた。それはもう、いつ消えるかと怯えるような頼りない灯火ではない。未来への希望を宿した、力強く美しい炎だった。
一刀斎は、己の右目の呪いが、少しだけ解けたような気がした。命の終わりを見るだけのこの目は、命の輝きを見つめ、それを守るためのものでもあったのだ。彼の旅は、まだ始まったばかり。見えるものだけが真実ではない世界で、それでも目の前の小さな炎を守るために、彼は歩き続ける。