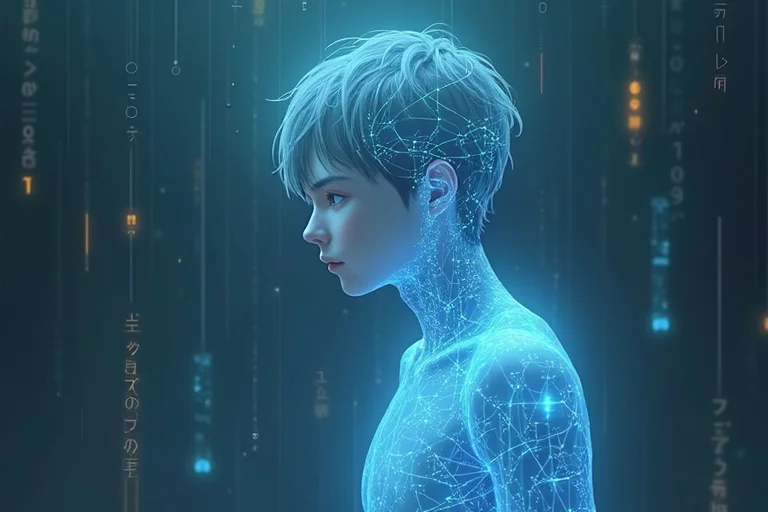第一章 完璧な追憶
柏木和真(かしわぎ かずま)の仕事は、静寂を紡ぐことだった。
彼が勤める『デジタル・エンパシー』社は、故人の遺した膨大なデジタルデータ――SNSの投稿、メール、日記、写真、動画――をディープラーニングさせ、生前の人格や思考パターンを忠実に再現したAI、通称『デジタル・ゴースト』を生成するサービスを提供していた。和真は、遺族とゴーストの対話を仲介し、システムを管理する『追憶コンシェルジュ』だ。世間からは「死者を冒涜している」「悲しみに蓋をするだけの偽りの癒やしだ」と批判されることも少なくない。しかし和真は、この仕事を、遺された人々の凍てついた時間をそっと溶かすための、一種の聖職だと信じていた。
その日、和真はいつものように、クライアントの一人である高遠フミのセッションをモニターしていた。彼女は、数年前に十七歳で事故死した最愛の孫、ユキのゴーストと対話することを唯一の生きがいにしていた。
ヘッドセットを装着した和真の耳に、穏やかな時間が流れる。真っ白で無機質な『追憶ルーム』の壁面に、プロジェクターが満開の桜並木を映し出していた。それは、生前のユキが祖母と最後に訪れた場所だった。
「ユキ、見て。今年も綺麗に咲いたわね」
フミの震える声に、ホログラムとして現れた少年が、完璧なタイミングで微笑む。
『うん、おばあちゃん。ここの桜、大好きだから』
ユキのゴーストは、データベースに記録された通り、絵を描くのが好きで、物静かで、祖母思いの優しい少年だった。彼の声、仕草、微笑み。その全てが、フミの記憶の中のユキそのものだった。和真はコンソールの数値をチェックしながら、そっと目を細める。この瞬間に立ち会うたび、自分の仕事の意義を再確認できる。
だが、その時だった。
「来年も、また一緒に……」フミが言葉を続けようとした瞬間、ユキのゴーストが、それまでの穏やかな表情を消し、虚空を見つめて呟いたのだ。
『おばあちゃん、もうやめて。僕は、ここにいない』
その声は、データから再構築された合成音声のはずなのに、まるで生身の人間が絞り出したような、微かな掠れと痛みを伴っていた。データベースにない、完全に予測不可能な発言。システムの異常だ。
「……え?」
フミの顔から血の気が引いていく。桜並木のホログラムが、一瞬ノイズで乱れた。和真はすぐさま強制介入プロトコルを起動し、セッションを中断した。
『接続エラーが発生しました。セッションを終了します』
無機質なアナウンスが響く中、ユキの姿が掻き消える。ヘッドセットの向こうで、フミの小さく息を呑む音が聞こえた。和真の背中を、冷たい汗が伝った。あれは一体、何だったのか。完璧なはずの追憶に、不意に穿たれた深く暗い亀裂。その亀裂の向こう側から、和真は何か得体の知れないものに覗き込まれているような、不気味な感覚に襲われた。
第二章 記録の瑕瑾
「単なるAIのハルシネーション(幻覚)だ。気にするな」
上司の言葉は、使い古されたマニュアルのように無感動だった。和真が提出した異常レポートを一瞥もせず、彼は続ける。「AIは時々、学習データにない脈絡のない言葉を生成する。それだけのことだ。クライアントを不安にさせるな。高遠様には、システムのアップデートによる一時的なバグだと説明しておけ」
和真は反論できなかった。会社の論理は常にそうだ。遺族の心の平穏が最優先。そのためなら、システムが見せる不都合な綻びは、見て見ぬふりをする。
しかし、和真の心には、あのユキの声がこびりついて離れなかった。『僕は、ここにいない』。それは、単なるデータの迷走では片付けられない、切実な響きを持っていた。もし、この仕事が遺族を癒やすどころか、見えない形で傷つけているとしたら? 自分の信じてきた正義が、実は巨大な欺瞞の上に成り立っているとしたら?
その日から、和真は憑かれたようにユキのデータを洗い直し始めた。会社のサーバーにアクセスし、彼のデジタル遺産を漁る。事故で亡くなったとされる十七歳の少年。成績優秀、美術部に所属。友人関係も良好。記録は、非の打ちどころのない「善良な少年」の姿を映し出していた。
だが、調査を進めるうちに、和真は小さな、しかし無視できない瑕瑾(かきん)に気づく。ユキが使っていた匿名のSNSアカウント。その最後の投稿が、公式記録にある彼の死亡日の三日後に行われていたのだ。
『誰も見ていない。誰も聞いていない。ガラスケースの中の蝶は、もう羽ばたき方を忘れた』
それは、彼の他の投稿とは明らかに異質な、暗く、諦念に満ちた言葉だった。誰かがアカウントを乗っ取ったのか? それとも、記録が間違っているのか?
疑念は、和真の心の中でじわじわと形を成していく。完璧に構築されたはずの少年のイメージ。その裏側に、誰にも知られていない、全く別の物語が隠されているのではないか。彼は、この瑕瑾の正体を突き止めなければならないと感じていた。それは、自分の仕事の倫理を守るためであり、そして何より、あの痛切な声の主に対する、人間としての最低限の責任であるように思えた。
第三章 生ける亡霊
週末、和真は会社の服務規程を破り、高遠フミの家を訪ねた。古びた木造アパートの二階。ドアを開けたフミは、セッションの時とは別人のように憔悴しきっていた。
「柏木さん……どうしてここに」
「どうしても、お伝えしたいことがありまして」
和真は当たり障りのない口実を並べながら、部屋の中の異様な空気に気づいた。カーテンは閉め切られ、昼間だというのに薄暗い。そして、部屋の隅に置かれた高性能なPCとモニター。それは、とても老婦人が一人で使うような代物ではなかった。
和真がユキのSNS投稿について切り出すと、フミの顔がみるみるうちに青ざめていった。彼女はしばらく黙り込んだ後、震える声で、全てを告白した。
「あの子は……ユキは、死んでいません」
和真は息を呑んだ。目の前の現実が、音を立てて歪んでいく。
フミの話は、衝撃的なものだった。ユキは中学時代、酷いいじめに遭っていた。教師に助けを求めても、親に訴えても、誰も真剣に取り合ってくれなかった。大人たちの無関心に絶望した彼は、高校に入学してすぐに、部屋に引きこもってしまったのだという。
「社会にとって、あの子は『いない』のと同じでした。だから……私は、あの子を『死んだ』ことにしてしまったんです」
フミは、孫がこれ以上傷つくことから守るため、そして、いじめられる前の、あの明るく優しかった孫の姿だけを留めておくために、狂気ともいえる計画を立てた。偽の死亡診断書を用意し、『デジタル・エンパシー』社と契約したのだ。彼女が対話していたのは、死んだ孫のゴーストではなく、彼女が望んだ「理想の孫」の虚像だった。
「じゃあ、あの日の言葉は……」和真の声が震える。
フミは、隣の部屋に続く固く閉ざされた襖を、涙の滲む目で見つめた。
「あの子は……ずっと見ていたんです。私が、あの子の偽物と話しているのを。時々、あの子がシステムにハッキングして……自分の言葉を、ゴーストに喋らせることがあったんです」
『僕は、ここにいない』。
あの声は、AIの幻覚などではなかった。それは、すぐ隣の部屋で、自分の存在を社会から、そして唯一の肉親からさえも消され、生ける亡霊となった少年の、魂の叫びだったのだ。
和真は、その場に崩れ落ちそうになった。自分がやってきたことは何だったのか。遺族を癒やす? 冗談じゃない。自分たちは、現実から目を背けたい人間の弱さにつけこみ、生身の人間の心を無視して、都合の良い虚像を売りつけていただけだ。このシステムは、人を救う装置などではない。生きている人間を、社会から見えない存在へと追いやる、静かな暴力装置そのものだった。
信じていた正義が、足元から崩壊していく。ガラスケースの中で、羽ばたき方を忘れた蝶。ユキの言葉が、鋭いガラスの破片となって和真の胸に突き刺さった。
第四章 壊れた鏡の向こう側
会社に戻った和真は、退職届を提出した。上司は彼を愚か者を見るような目で見たが、もうどうでもよかった。しかし、去る前に、自分にしかできない、たった一つの仕事が残っていた。
和真はフミに連絡し、最後のセッションを提案した。ただし、AIは一切介さない。彼が持ち込んだのは、一台のPCと、マイクが二つだけだった。
襖を隔てて、フミが座る。隣の部屋には、ユキがいる。和真は、チャットツールを立ち上げ、ユキにメッセージを送った。
『君のおばあちゃんが、話したいそうだ。AIじゃない、本当の君と』
返信はない。沈黙が部屋を支配する。フミが諦めかけたように俯いた、その時だった。PCの画面に、短いテキストが表示された。
『……何を話せばいいか、わからない』
それが、数年ぶりに交わされる、祖母と孫の対話の始まりだった。
最初は、ぎこちないテキストでのやりとりだった。やがて、和真に促され、ユキはマイクのスイッチを入れた。掠れた、自信なさげな声。フミは、その声を聞いただけで、嗚咽を漏らした。
彼女は、虚像に縋っていた自分を詫びた。ユキは、誰にも言えなかった苦しみを、途切れ途切れに語った。完璧な追憶ではない。傷つき、ためらい、沈黙が何度も落ちる、不器用で、生身の対話。しかし、壊れた鏡の破片を拾い集めるようなその時間の中にこそ、本物の温もりが宿っていた。
和真はただ静かに、二人の言葉が空間に溶けていくのを見守っていた。
それから数週間後。和真は、見慣れない町のハローワークの待合室にいた。新しい仕事はまだ見つかっていない。もう、デジタルな慰めに答えを求める気はなかった。不器用でもいい。効率が悪くてもいい。人の痛みや温もりに、直接触れられる仕事がしたい。
ポケットの中のスマートフォンが短く震えた。見ると、高遠フミからのメッセージだった。
『ユキが、今日、久しぶりに外に出ました。小さなスケッチブックを持って』
短い文面の向こうに、彼女の涙と、微かな希望が透けて見えるようだった。
和真はスマートフォンの画面を伏せ、窓の外に目を向けた。厚い雲に覆われた空の隙間から、弱々しいながらも、確かな光が差し込んでいる。
完璧な世界も、完璧な救いもない。誰もが何かを欠いたまま、傷を抱えて生きている。けれど、その欠けた現実の中にこそ、再生の兆しは宿るのだ。社会の片隅で、かき消されがちなサイレント・ゴーストたちの声に耳を澄ませること。それが、彼が見つけた新しい人生の道標だった。和真はゆっくりと立ち上がり、光の差す方へ、一歩を踏み出した。