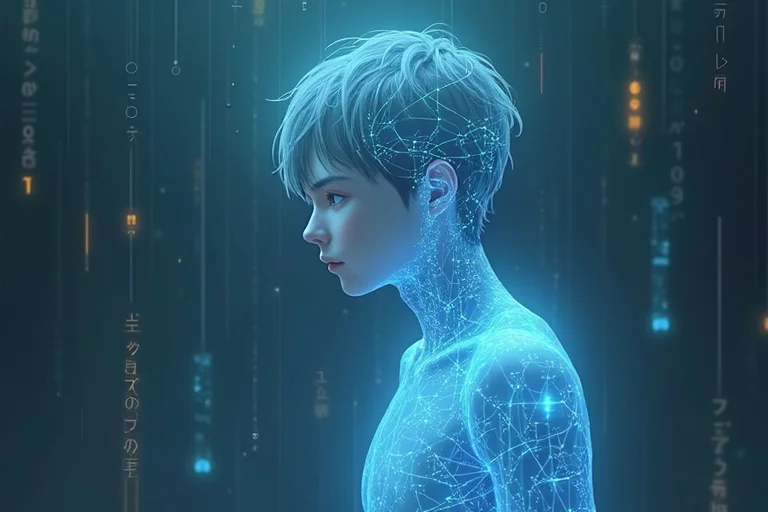第一章 零度の温もり
空調の効いた清浄な空気が、肌を無機質に撫でる。桐野朔(きりのさく)の世界は、常にこの清潔な静寂に満たされていた。彼が勤める中央廃棄物リセット機構・第7プラントは、この国の繁栄を象徴する心臓部だ。あらゆるゴミ――使い古された家具も、流行遅れの衣服も、食べ残しの食事すらも――がベルトコンベアで運ばれ、巨大なリセット・ゲートを潜ることで、原子レベルで分解・再構成され、新品同様の資源へと生まれ変わる。汚れない世界。無駄のない社会。それが朔の日常だった。
彼の仕事は、ゲートに投入される前の最終チェックラインで、規定外の危険物や処理不能な物質が紛れ込んでいないかを確認するだけの単調な作業だ。センサーがほとんどの仕事をこなし、朔の役割は、そのセンサーが見逃した僅かなエラーを監視することにある。流れていくモノの奔流に、彼は何の感情も抱かない。かつて何かを自分の手で創り出すことを夢見ていた情熱は、この無菌室のような職場環境でとっくに漂白されてしまっていた。
その日も、朔はガラス越しのコンベアを虚ろな目で見つめていた。プラスチックの残骸、歪んだ金属、色褪せた布地。意味を剥奪されたモノたちの葬列。その中で、ふと異質なものが彼の目を捉えた。茶色く、小さな塊。センサーはそれをただの「木材片」と認識している。しかし、朔の網膜には、それが紛れもない鳥の形として映った。
衝動的に、彼は緊急停止ボタンに手を伸ばしかけた。だが、それをすれば大騒ぎになる。コンベアの速度を一時的に落とす最小限の介入コードを打ち込み、マジックハンドを操作して、その小さな塊を掴み上げた。手元のトレイに落ちたそれは、掌に収まるほどの、手彫りの木彫りの鳥だった。
表面は滑らかに磨かれているが、ナイフの跡が不揃いに残り、作り手の朴訥な愛情が滲み出ている。翼の柔らかな曲線、少し首を傾げた愛らしい仕草。それは、大量生産された工業製品とは全く違う、「時間」と「想い」が宿ったものだった。朔は、まるで禁制品に触れるかのように、そっと指でその体をなぞった。ひんやりとした職場の中で、そこだけが不思議な温もりを帯びているように感じられた。
規則では、全ての回収物はリセットされなければならない。例外はない。しかし、朔はそれを廃棄シュートに戻すことができなかった。周囲の監視カメラの死角を狙い、彼は素早く木彫りの鳥を自分の作業着のポケットに滑り込ませた。心臓が、久しぶりに大きく脈打つのを感じた。それは罪悪感か、それとも、忘れかけていた何かを取り戻したかのような、小さな高揚感だったのか。零度の日常に生まれた、一つの熱源だった。
第二章 忘却の街
ポケットの中の小さな鳥は、朔の日常に静かな波紋を広げていった。仕事中も、食事中も、眠りにつく前も、彼は無意識にその滑らかな木肌を指でなぞっていた。鳥の足元には、ヤスリで消えかかった、か細い文字が刻まれていることに気づいた。『ミオへ』。それは誰かの名前だろうか。朔は、この鳥が誰の手によって、どんな想いで作られ、ミオという人物に渡されたのか、知らず知らずのうちに想像を巡らせるようになっていた。
朔は行動を起こした。まず、機構のデータベースにアクセスし、この鳥が回収されたエリアを特定した。それは「旧市街第9地区」として知られる、再開発から取り残された古い居住区だった。リセット技術の恩恵を最も受けにくい、忘れられた場所だ。有給休暇を取得した朔は、何かに導かれるように、その街へと足を運んだ。
第9地区は、朔が住むクリーンな新都市とは別世界だった。空気は埃っぽく、建物の壁には修復されないヒビが走り、路地裏には微かな生活の匂いが漂っていた。そこでは、人々がモノを「リセット」するのではなく、「修理」して使っていた。古びた自転車、継ぎ接ぎされた衣服、何度も塗り直されたであろうペンキの剥げた扉。非効率で、無駄だらけの世界。しかし、そこには朔が失って久しい、確かな人の営みがあった。
朔は、木彫りの鳥の写真を手に、地区の住民に聞き込みを始めた。だが、反応は芳しくない。「さあ、見たことないね」「こんな手作りのおもちゃ、今どき珍しい」と、誰もが首を横に振るばかりだった。諦めかけたその時、小さな工房を営む老人が、写真を見て眉をひそめた。「この彫り方には見覚えがある。昔、この辺りに住んでいた長谷川さんという男が、よく娘のためにこんなものを作っていた」
手掛かりだった。朔は老人に教えられた住所へと向かった。そこにあったのは、今は誰も住んでいない、蔦の絡まった小さな家だった。表札は外され、窓は板で打ち付けられている。しかし、郵便受けの奥に、雨に濡れてふやけた一枚の紙片が残っていた。転居先通知。そこに記された新しい住所は、意外にも朔が住む新都市の一角だった。
期待と不安を胸に、朔はそのアパートを訪ねた。ドアを開けたのは、疲れた表情を浮かべた中年男性――長谷川と名乗る男だった。朔が木彫りの鳥を見せると、男の目に一瞬、戸惑いの色が浮かんだ。「……これは?」
「あなたのものじゃないかと。第9地区で、娘さんのためにこういうものを作っていたと聞きました。『ミオ』さんという…」
朔の言葉を、長谷川は遮った。「いや、人違いだ。俺に娘はいない。昔から、妻と二人暮らしだ」
その否定は、あまりにきっぱりとしていて、揺るぎがなかった。だが、朔には分かった。男の瞳の奥、その固く閉ざされた扉の向こうで、何かが激しく揺れ動いているのを。彼は何かを、あるいは誰かを、必死で忘れようとしている。いや、忘れさせられているのだ。
第三章 リセットされる魂
長谷川の不可解な反応は、朔の心に重い疑念の種を蒔いた。彼は嘘をついているのではない。心の底から、娘の存在を信じていないようだった。記憶そのものが欠落しているとしか思えなかった。朔はプラントに戻ると、長年の勤務で得た知識を総動員し、通常はアクセスできない深層アーカイブへの侵入を試みた。彼の脳裏には、プラントで長年働く同僚、安西の言葉が蘇っていた。「このシステムの本当の姿なんて、誰も知りやしない。知ろうとしない方が幸せだ」
深夜、朔はついにアーカイブの壁を突破した。そこに存在したのは、廃棄物の記録だけではなかった。『人的資源最適化計画』と題された、極秘ファイル。朔は、震える指でそれを開いた。
画面に表示された文書を読み進めるうち、朔は全身の血が凍るような感覚に襲われた。リセット技術の真実。それは、単なるゴミの再資源化ではなかった。この完璧な社会システムを維持するための膨大なエネルギーは、物理的な資源だけでは賄えない。その不足分を補っていたのが、社会から「非効率」「不適合」と判断された人間たちの存在そのものだったのだ。
計画の概要はこうだ。定期的に、生産性の低い者、社会規範から逸脱した者、あるいは単にシステムの重荷と見なされた者たちが密かにリストアップされる。彼らは「社会的リセット」の対象となり、物理的に姿を消すのではない。彼らに関する全ての公的記録、そして、周囲の人々の「記憶」が、特殊な神経パルス技術によって選択的に消去・改変されるのだ。消された存在は、社会という巨大なネットワークから切り離され、その存在エネルギーがシステム維持のために変換・吸収される。それが、このクリーンな世界の真のコストだった。
ファイルの中に、「長谷川ミオ」の名前を見つけた。享年7歳。社会的リセット対象。理由は「将来的な社会貢献度の低予測」。彼女の父親である長谷川は、記憶改変処置を受け、娘が存在しなかったという新しい現実を植え付けられていた。
朔は愕然とした。あの木彫りの鳥は、父親の記憶から消されてもなお、無意識の深層にこびりついていた娘への愛情が、かろうじて形を保った「記憶の残骸」だったのだ。ゴミとして捨てられたのではない。父親が新しい現実に適応する過程で、無意識に手放してしまった、魂の欠片だった。
朔がリセット機構で処理していたのは、モノの死骸だけではなかった。それは、人々の記憶、愛、人生、そのものの墓場だったのだ。清潔で、静かで、完璧な世界の底には、声なき魂たちの叫びが満ちていた。彼は、その巨大な欺瞞の、そして虐殺の、末端の歯車だった。ポケットの中の木彫りの鳥が、鉛のように重く感じられた。
第四章 記憶の彫刻
真実を知った朔の世界は、色を失い、音をなくした。プラントの清潔な空気は、死の匂いを含んでいるように感じられ、整然と流れるコンベアは、ギロチンへと続く列に見えた。彼はもう、以前の無気力な自分に戻ることはできなかった。怒り、絶望、そして、このシステムの一部であったことへの激しい自己嫌悪が、彼の内側で渦巻いていた。
数日後、朔は安西を呼び止めた。「知っていたんですね。このプラントが、本当は何をしているのか」
安西は、深く刻まれた眉間の皺をさらに深くし、静かに頷いた。「俺たちは墓守だ。ただ、墓石すらない魂のな」
「なぜ、黙っていたんですか!」
「声を上げてどうなる?俺たちもリセットされるだけだ。だが…」安西は、朔のポケットに目をやった。「お前さんは、その小さな鳥を拾った。俺たちが何十年も前に失くしちまったものを、まだ持っていたんだな」
安西の言葉は、朔の心に小さな灯りをともした。絶望の淵で、彼は自分が何をすべきかを見出したのだ。この巨大なシステムを、一夜にして覆すことはできないだろう。しかし、忘れさせられた魂が確かに存在したという証を、この世界に刻みつけることはできるはずだ。
朔は、仕事を辞めた。そして、第9地区の、あの蔦の絡まる空き家を借り、小さな工房を開いた。彼はまず、ポケットの中の木彫りの鳥を、丹念に模倣することから始めた。初めは不格好だったが、何度も、何度も彫り続けた。木を削るたびに、彼はミオという少女に想いを馳せた。彼女の笑顔を、父親との温かい時間を、無残に奪われた未来を。それは、彼にとっての鎮魂の儀式だった。
やがて朔は、安西から密かに提供された「リセット対象者リスト」を元に、消された人々の遺品や、彼らが生きた痕跡を探し始めた。写真の切れ端、手紙の断片、使い古された万年筆。それら一つ一つからインスピレーションを得て、彼は木を彫り続けた。ある時は子供の笑い声を、ある時は老人の深い愛情を、またある時は若者の叶わなかった夢を。彼の作る彫刻は、どれも不器用で、完璧ではなかったが、忘れられた人々の確かな体温を持っていた。
朔の工房は、いつしか「記憶の彫刻」を作る場所として、口コミで知られるようになった。人々は、理由の分からない喪失感や、心に空いた空虚な穴を抱えて、彼の元を訪れた。朔は、彼らの曖昧な話に耳を傾け、それを形にした。彼の彫刻が、誰かの記憶を直接取り戻させることはない。しかし、それは、失われた温もりが確かに存在したことを、そっと教えてくれる道標となった。
物語の終わり、夕暮れの光が差し込む工房で、朔は新しい木材を手にしていた。彼の指先には無数の傷と、木のささくれが食い込んでいる。だが、その手は、かつてないほど力強く、生命力に満ちていた。彼は、システムによって漂白された自分自身の心をも、その手で彫り直し、取り戻そうとしていた。
世界はまだ変わらない。リセット機構は、今も静かに稼働し続けている。しかし、この街の片隅で、木を削る小さな音が、忘却という名の巨大な静寂に対して、ささやかな、しかし決して消えることのない抵抗を続けている。朔が彫り上げた一体の小鳥が、窓辺で静かに、夜明けを待っていた。