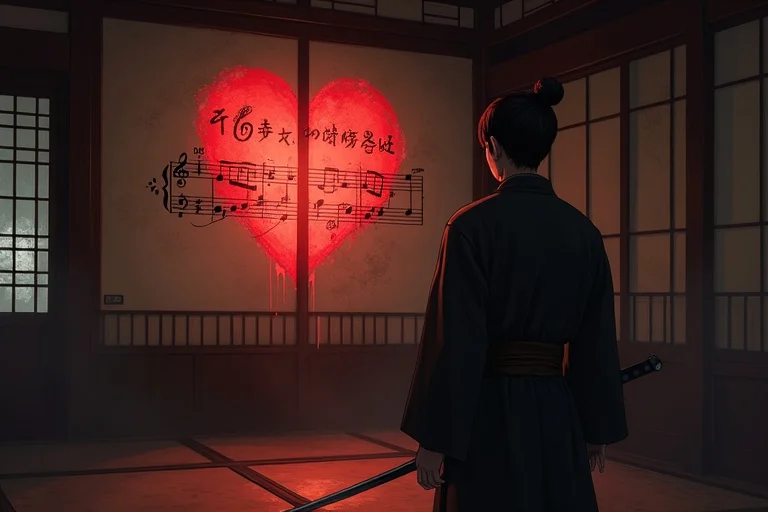第一章 天涙の響き
片桐静馬(かたぎり しずま)は、武士としては出来損ないだった。埃っぽい道場で汗を流すよりも、書庫の黴臭い空気の中で古文書の頁を繰ることを好んだ。父である藩の目付役からは幾度となく叱責された。「武士が筆と墨ばかり弄ってどうする。お前の禄は、その細腕ではなく、刀で稼ぐものぞ」。だが、静馬にとって、刀が奏でる鋼の音よりも、忘れ去られた言葉が持つ静かな響きの方が、よほど心を震わせるのだった。
彼は自らを「言の葉蒐集家」と称し、消えゆく言葉、忘れられた言葉を拾い集め、一冊の書物に書き留めることを生涯の仕事と定めていた。それは、誰に命じられたわけでもない、孤独で、誰からも理解されない営みだった。
ある湿度の高い夏の午後、静馬は城下の古書店で、虫食いだらけの古い地誌を手に取った。その書物の片隅に、まるで墨の染みのように、ひっそりと記された言葉があった。
『天涙(てんるい)』
その二文字を目にした瞬間、静馬の背筋をぞくりとしたものが駆け上がった。意味の解説はない。ただ、その土地でかつて使われていた言葉として記されているだけだ。天の、涙。なんと美しく、そして物悲しい響きだろう。空から降る雨のことか、あるいは流星のことか。想像は膨らむが、確かなことは何も分からない。その日を境に、「天涙」という言葉は静馬の心を捕らえて離さなくなった。まるで、失われた魂が彼を呼んでいるかのように。
他のどんな言葉よりも、「天涙」の正体を知りたい。その言葉が生まれた瞬間の光景を、風の匂いを、人々の息遣いを感じたい。その衝動は、やがて抑えがたい情熱へと変わっていった。
「父上、しばしの間、旅に出るご許可をいただきたく存じます」
父の前に平伏した静馬の言葉に、父は眉一つ動かさなかった。
「また言葉遊びか。好きにせよ。だが、片桐家の人間として恥ずべき行いだけはするな。もはや、お前に期待するものなどないがな」
父の言葉は冷たかったが、静馬の心はすでにここにはなかった。「天涙」という謎めいた言葉の響きが、彼を未知の世界へと誘っていた。荷物をまとめ、使い古した筆と墨、そして白紙の帳面を懐に入れた静馬は、翌朝、誰にも見送られることなく、藩邸の門をくぐった。彼の孤独な旅は、こうして始まった。一つの言葉の幻影を追いかける、果てしない旅が。
第二章 失せものの道
静馬の旅は、想像以上に困難なものだった。街道筋の宿場町で聞き込みをしても、「天涙」という言葉を知る者は誰一人いなかった。老練な商人も、物知りの神官も、首を横に振るばかり。ある者は彼を物好きな若様と笑い、ある者は気味悪がって避けた。
だが、静馬は諦めなかった。彼は「天涙」を探す傍ら、各地で消えゆく言葉を丁寧に拾い集めていった。浜辺の村では、魚を獲りすぎた海への畏怖を込めた『凪謝(なぎしゃ)』という言葉を。山間の集落では、冬の終わりに芽吹く最初の草花を指す『雪割(ゆきわり)』という言葉を。それらの言葉は、土地の暮らしや人々の信仰と分かちがたく結びついていた。言葉とは、単なる音の記号ではない。人々の魂の記憶そのものなのだと、静馬は肌で感じていった。
蒐集した言葉が帳面を埋めていくたび、彼の心は満たされた。しかし、心のどこかで「天涙」への渇望が消えることはなかった。まるで、彼の辞書の最後に埋めるべき、最も大切なピースが欠けているかのように。
季節が二度巡った頃、静馬は奥州のさらに北、凍てつくような風が吹き荒れる宿場にいた。そこで、囲炉裏を囲んでいた猟師から、奇妙な噂を耳にする。
「この先の山奥に、世間から隔絶された隠れ里があるそうだ。そこに住む者たちは、今では誰も使わぬ古い言葉を話すという……」
その言葉に、静馬の心は躍った。もしや、そこに「天涙」の秘密があるのではないか。道は険しく、冬の山を越えるのは命がけだと猟師は言ったが、静馬にためらいはなかった。彼はなけなしの金をはたいて防寒具を整えると、白く染まった山道へと足を踏み入れた。
肌を刺す寒風が、彼の頬を切り裂く。雪に足を取られ、何度も倒れそうになった。意識が遠のきかけた時、彼の目に、雪の中にぽつりと灯る小さな明かりが見えた。幻ではない。そこには、確かに人の営みがあった。
第三章 凍てつく言の葉
その隠れ里は、時が止まったかのような場所だった。住民たちは静馬を警戒し、誰も口を開こうとしなかった。だが、静馬が自らの目的――失われゆく言葉を集めていること――を真摯に語ると、彼らの態度は少しずつ軟化していった。やがて彼は、里の長老に会うことを許された。
深い皺が刻まれた顔の長老は、静馬をじっと見つめ、彼の旅の記録が記された帳面にゆっくりと目を通した。
「……面白いことをする若者がおるものだ」
静馬は意を決して尋ねた。
「長老様。私は『天涙』という言葉を探しております。この言葉をご存知ではありませんか」
その名を聞いた瞬間、長老の穏やかだった表情が、凍てついた湖面のように強張った。里に漂っていた静寂が、一層重く静馬にのしかかる。長い沈黙の後、長老は重い口を開いた。
「その言葉は……この里では、決して口にしてはならん言葉じゃ」
長老が語り始めたのは、百年ほど前にこの地を襲った、凄惨な大飢饉の物語だった。不作が続き、人々は草の根を食らい、ついには土を口にした。餓死者が道端に転がり、赤子の泣き声も聞こえなくなった地獄。そんな絶望の中で、人々は空から静かに降りしきる雪を見上げたという。
「あまりの悲しみに、涙も枯れ果てた。だが、空は我らの代わりに泣いてくださる。あの雪は、天が流しておられる涙なのだ、と……。人々はそう呟き、息絶えていった」
長老の声は、乾いた木が擦れるようにか細く震えていた。
「『天涙』。それは、美しくも何ともない。生きる望みを絶たれた者たちが、最後に絞り出した絶望の言葉。救いのない悲しみの記憶そのものじゃ。だから我らは、この言葉を封印した。二度と、あのような悲劇が繰り返されぬように、と」
静馬は息を呑んだ。彼が追い求めてきた美しい響きの言葉の正体が、これほどまでに痛ましいものだったとは。彼の理想は、無残に砕け散った。だが、衝撃はそれだけでは終わらなかった。
長老は、静馬の懐から覗く刀の拵えにある小さな紋所に目を留めた。そして、静かに言った。
「その紋……片桐家のものじゃな。……あの飢饉の時、この地を治め、我らから情け容赦なく年貢を取り立てていった代官。その名も、片桐……」
静馬の頭を、雷に打たれたような衝撃が貫いた。彼が追い求めた悲劇の言葉は、彼の先祖が犯した罪によって生まれていたのだ。言葉の美しさに酔いしれ、その裏にある人々の血の滲むような痛みから、自分はずっと目を背けていた。己の無知と、一族の罪の重さに、静馬はその場に崩れ落ちそうになった。帳面を持つ手が、震えて止まらなかった。
第四章 魂の辞書
静馬は里に数日留まった。彼は何も手につかず、ただ降りしきる雪を眺めて過ごした。彼が蒐集してきた言葉の一つ一つが、今は重い鉛のように感じられた。言葉の美しさだけを追い求めていた自分は、なんと浅はかで、傲慢だったことか。
旅立つ日の朝、長老が静馬の元を訪れた。
「若者よ。お主の顔は、ここに来た時とは違う。深い悲しみを湛えておる」
「私は……知るべきではなかったのかもしれません。この言葉の真実も、我が家の罪も」
静馬が力なく答えると、長老は静かに首を振った。
「そうではない。言葉は記憶じゃ。美しかろうが、醜かろうが、忘れてはならん記憶を繋ぐためのもの。お主がやっていることは、人の魂の軌跡を拾い集めることと同じじゃ。痛みから目を背けては、真の言葉は見えん」
長老は、静馬の帳面を指差した。
「その言葉を、お主の書物の最初に記すがいい。『天涙』を。そして、その言葉に宿る我らの悲しみを、お主の一族の罪を、決して忘れぬと誓うのじゃ。それが、お主のできる唯一の供養となろう」
長老の言葉は、静馬の打ちのめされた心に、小さな灯火をともした。そうだ、自分の使命は、ただ言葉を集めることではない。その言葉に込められた喜びも、悲しみも、怒りも、その全てを受け止め、後世に正しく伝えることなのだ。美しさだけを求めるのは、偽りだ。
静馬は長老に深く頭を下げ、里を後にした。藩邸に戻った彼の姿に、父は驚きの色を見せた。かつての夢見がちな若者の面影はなく、そこには厳しい風雪に耐え、何かを背負う覚悟を決めた男の顔があった。
静馬は自室に籠もり、新しい帳面を開いた。そして、震える筆で、最初の頁にこう記した。
『天涙(てんるい)――北の地にて、大飢饉に喘ぐ民が、天を仰ぎ、降りしきる雪を自らの代わりに流れる涙と見て、呟きし言葉。その絶望と悲しみを、未来永劫、忘るるべからず』
彼の言の葉を拾い集める旅は、まだ終わらない。だがそれはもはや、美しさを求める旅ではなかった。人間の魂が刻んできた、無数の愛おしくも痛ましい軌跡を辿る、終わりのない巡礼となっていた。その一文字一文字に、彼は自らの魂を込めていく。それこそが、片桐静馬という一人の男が生きた証となるのだから。