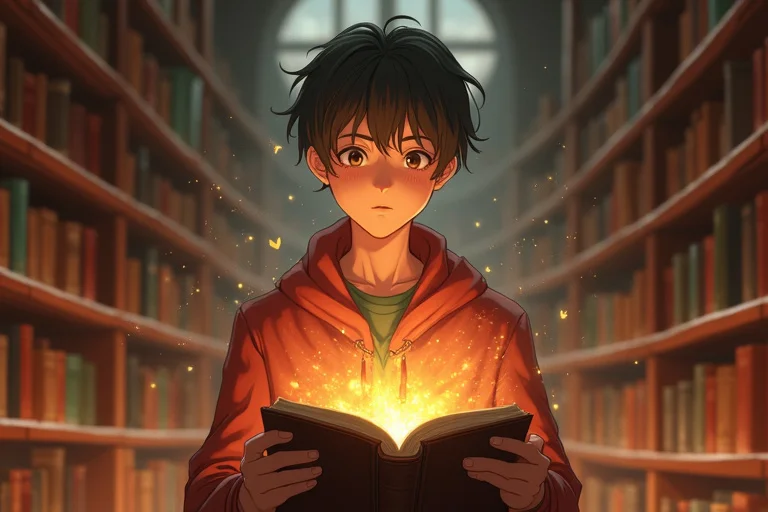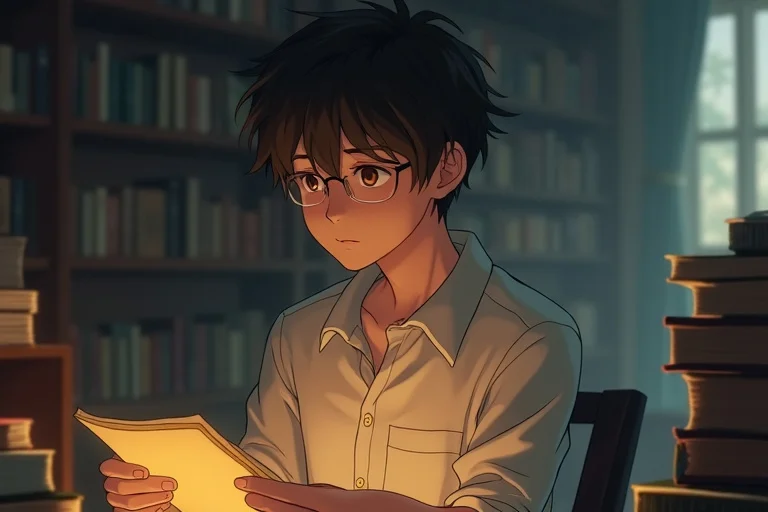第一章 桜のインクと空白の感情
水野葵の日常は、他人の感情の残滓でできていた。古道具屋「時のしずく」の店主である彼女には、生まれつき、物に触れるとその物が経てきた時間の澱、持ち主が込めた強い感情の残響を感じ取る力があった。それは祝福ではなく、むしろ呪いに近い。ひっきりなしに流れ込んでくる他人の後悔、嫉妬、悲嘆、執着。そのノイズの濁流から身を守るため、葵はいつしか他人との間に見えない壁を築き、感情の波が穏やかな古い物たちに囲まれて、息を潜めるように生きていた。
その日も、葵はカウンターの奥で、埃を被った振り子時計のゼンマイを静かに巻いていた。ちり、と店のドアベルが鳴り、小柄な老人が一人、遠慮がちに足を踏み入れた。老人の手には、丁寧に布で包まれた小さな何かがあった。
「これを、買い取っていただけませんか」
しわがれた声で差し出されたのは、一本の木製の万年筆だった。使い込まれて角が丸くなった軸は、持ち主の掌に馴染むように滑らかな艶を帯びている。葵は無言でそれを受け取った。
指先が、桜材と思しき温かみのある木肌に触れた瞬間、世界がぐらりと揺れた。
いつもの、どろりとした感情の奔流とは違う。それは、圧倒的な熱量を持つ「何か」だった。しかし、その正体がわからない。怒りではない。悲しみでもない。憎しみも、焦がれるような執着とも違う。頭の中に流れ込んできたのは、音のない映像。春の柔らかな陽光に透ける満開の桜並木。風に乗り、はらはらと舞い落ちる無数の花びら。そして、真っ白な原稿用紙の上を、インクの代わりにその花びらを散らしながら滑っていくペン先の幻。
強烈な「何か」がそこにある。確かに魂を揺さぶるほどの強い感情が込められているはずなのに、葵の心はそれを捉えきれない。まるで、完璧な形をした美しい器が目の前にあるのに、中身だけが空っぽであるかのような、奇妙な感覚。暖かく、満たされているはずなのに、同時にどうしようもなく空白だった。
「……お客様、これは」
思わず顔を上げると、老人は寂しそうに目を伏せていた。
「妻のものです。あいつは、これでよく何かを書いていました。……もう、私には必要ないものですから」
老人は高松と名乗り、葵が提示した僅かばかりの金額を黙って受け取ると、一度も振り返らずに店を出ていった。
後に残されたのは、沈黙と、カウンターの上に置かれた一本の万年筆。葵はもう一度、恐る恐るそれに触れた。やはり同じだ。桜の花びらが舞う幻視と、正体不明の「暖かな空白」。それは葵が二十八年間生きてきて、一度も触れたことのない種類の感情の残響だった。彼女のモノクロームの日常に、音もなく投じられた、色のない波紋。その波紋の中心を、葵はただ、呆然と見つめていた。
第二章 残響を辿る指先
謎の万年筆は、葵の心を静かにかき乱し続けた。仕事の合間に、食事の途中に、眠りにつく前のベッドの中で、ふとあの「暖かな空白」の感触を思い出してしまう。知りたかった。この感情の正体を。そして、なぜ自分にはそれが読み取れないのかを。
葵はまず、高松老人の言葉を頼りに、彼の妻について調べることにした。しかし、手掛かりはあまりに少ない。万年筆に残された残響も、桜並木と原稿用紙という断片的なイメージばかりで、具体的な場所や人物像には結びつかなかった。
数日が過ぎ、手詰まりを感じ始めた葵は、気分転換も兼ねて駅前の市立図書館を訪れた。地域の郷土史や過去の住宅地図でも見れば、何か分かるかもしれない。そう思ったのだ。古書の棚を漫然と眺めていると、不意に声をかけられた。
「何かお探しですか? もしよろしければ、お手伝いしますよ」
振り返ると、人の良さそうな笑顔を浮かべた若い男性司書が立っていた。名札には「橘」とある。
「……古い文筆家を探していまして。この辺りに住んでいた方かもしれないんですが」
葵は、自分の能力のことは伏せたまま、曖昧に事情を説明した。橘と名乗る司書は、予想に反して興味深そうに話を聞いてくれた。
「面白いですね。手掛かりは何かありますか?」
「桜材の万年筆を、とても大切にしていた、とだけ……」
橘は地域の歴史に詳しく、驚くほど熱心に協力してくれた。二人で古い文芸誌をめくり、過去の新聞の文化欄を漁る日々が続いた。他人と目的を共有し、協力して何かを探す。それは、感情のノイズを避けるために人との関わりを絶ってきた葵にとって、新鮮で、少しだけ居心地の悪い体験だった。
橘と話していると、時折、彼が貸してくれる本に触れることがあった。そこに残された残響は、いつも穏やかで平坦だった。仕事に対する誠実さ、本への愛情。だが、それだけだ。葵が知る世界は、やはり強い感情とは、後悔や悲しみといったネガティブなものと同義だった。
「見つけました!」
ある日の午後、橘が興奮した声で一枚の古い文芸誌のコピーを持ってきた。それは、地域のアマチュア作家が作品を寄稿する小さな同人誌で、そこに「高松千代」という名前と、桜並木を題材にした短い童話が掲載されていた。
「この記事によると、高松千代さんは数年前に亡くなられています。ご主人が今も近くにお住まいのようです」
高松千代。それが万年筆の持ち主の名前だった。葵の胸が、微かに高鳴る。橘はさらに、千代さんが亡くなる前に、自費出版で一冊だけ童話集を遺していたらしいという情報まで突き止めてくれた。ただ、その童話集はほとんど市販されず、今では幻の一冊になっているという。
「心当たりが一つだけあります」と橘は言った。「駅裏の、もう閉めてしまった古い本屋です。そこの店主が、地域の自費出版本を収集するのが趣味だったんです。もしかしたら……」
その言葉に導かれるように、二人は夕暮れの商店街を抜け、蔦の絡まる古書店の前に立った。錆びついたシャッターの隙間から、葵は躊躇いがちに手を差し入れた。指先が、店内に積まれた本の背に、そっと触れる。いくつもの本の、いくつもの平坦な残響が通り過ぎていく。そして――あった。
一冊の、簡素な装丁の本に触れた瞬間、万年筆と同じ、あの圧倒的で、そして理解不能な「暖かな空白」が、津波のように葵の全身を洗い流した。
第三章 モノクロームの世界に落ちた色
橘に礼を言い、借り受けた童話集を抱えて店に戻った葵は、まるで禁断の果実に手を伸ばすように、その本の表紙に再び触れた。タイトルは『さくら色のインクで』。作者、高松千代。
指先から流れ込んでくる奔流は、万年筆の時よりも遥かに強く、鮮明だった。
桜の花びらが舞う幻視。それは一つではなかった。孫の小さな手を引きながら見上げた春の日の桜。病室の窓から夫と眺めた、葉桜になりかけた木々。幼い息子が初めて描いた、拙い桜の絵。その一つ一つの情景に、あの名状しがたい「暖かな空白」が、陽だまりのように寄り添っていた。
ページをめくる。そこに綴られていたのは、変哲もない日常を舞台にした、ささやかな物語たちだった。猫と日向ぼっこをする話。雨上がりの虹を見つける話。孫と一緒に作った、少し焦げたホットケーキの話。どれも、事件らしい事件は起こらない。ただ、ありふれた日々の、きらめく一瞬が、優しい言葉で切り取られているだけ。
葵は、物語を一つ、また一つと読み進めるうちに、全身が震えだすのを止められなかった。そして、最後のページを読み終えた時、彼女はついに、あの感情の正体に思い至った。
これは、「喜び」だ。
純粋な、何の翳りもない、ただそこにあることへの感謝と幸福感。夫への愛情。孫への慈しみ。日常の小さな発見。高松千代という女性は、そのありふれた毎日の中に、数えきれないほどの「喜び」を見出し、それを万年筆で、物語として綴っていたのだ。
葵がそれを感じ取れなかった理由も、同時に悟った。
彼女は、今まで一度も、他人の物から「純粋な喜び」の感情を読み取ったことがなかった。彼女が触れてきた世界は、後悔と悲しみと怒りに満ちていた。だから、葵自身、喜びという感情がどういうものなのか、本当の意味で知らなかったのだ。それは彼女にとって、辞書で意味は知っていても、決して味わったことのない果実のようなものだった。
自分の能力の決定的な欠落。そして、それ以上に、自分自身の心の欠落。
葵は愕然とした。彼女が生きてきた世界は、喜びという、最も鮮やかで暖かい色彩が抜け落ちた、モノクロームの世界だったのだ。これまで感じてきた倦怠感や虚無感の正体は、この決定的な色の欠如だった。
涙が、頬を伝った。それは悲しみの涙ではなかった。自分が何者で、自分の世界がどんなものだったのかを、生まれて初めて正確に理解したことへの、途方もない衝撃の涙だった。
第四章 ありふれた宝物
翌日、葵は童話集と万年筆を携えて、高松老人の家を訪ねた。インターホンを押すと、前回よりもさらに憔悴した様子の老人が姿を見せた。
「……何か、ご用かな」
「これを、お返しに上がりました」
葵は、震える手で童話集と万年筆を差し出した。
「奥様の物語、読ませていただきました。……とても、素敵な物語でした。たくさんの……たくさんの『喜び』が、詰まっていました」
その言葉を聞いた瞬間、高松老人の表情が崩れた。乾いた瞳から、大粒の涙がとめどなく溢れ出す。
「そうか……。君には、見えたのか。あいつが見ていたものが……」
老人は葵を家に招き入れ、ぽつりぽつりと語り始めた。妻が亡くなってから、何もかもが色褪せて見えたこと。妻が大切にしていた日常の輝きが、自分にはもう見つけられなくなってしまったこと。だから、妻の魂が宿る万年筆を手放してしまおうと思ったのだ、と。
「妻は、いつも言っていた。『ありふれた毎日こそが宝物なのよ』って。私には、その宝物が、もうどこにあるのか分からなくなっていたんだ」
老人は、葵から受け取った万年筆を、慈しむようにそっと握りしめた。その指先が、微かに震えている。
「ありがとう。もう一度、探してみるよ。あいつが見ていた宝物を」
その目には、小さな、しかし確かな光が戻っていた。
古道具屋に戻る道すがら、葵は橘に返す本を抱えていた。図書館に寄る前に、ふと、その本の表紙に指で触れてみる。
いつも通りの、穏やかで平坦な残響。仕事への誠実さ。しかし、そのノイズの奥に、ほんの僅か、チカッと点滅する光のようなものを感じた。それは、葵が古書店を探している時に、「誰かの役に立てるかもしれない」と橘が感じた、ささやかな期待と善意。それは、高松千代の残した圧倒的な光に比べれば、蝋燭の灯火にも満たない、あまりにささやかなものだったけれど。
葵は、確かにそれを「喜び」の欠片として感じ取ることができた。
店に戻った葵は、店の窓を大きく開け放った。いつもはただのノイズでしかなかった街の喧騒――車の走る音、人々の話し声、遠くで鳴くカラスの声――が、流れ込んでくる。
彼女の世界は、まだモノクロームのままだ。けれど、その色褪せた風景の中に、初めて、探すべき色の存在を知った。それは、誰かから与えられるものではなく、自らの手で、心で見つけ出していくものなのだ。葵は、流れ込んでくる風の中に、まだ名前のない新しい響きを探すように、静かに目を閉じた。彼女の本当の日常は、今、始まったばかりだった。