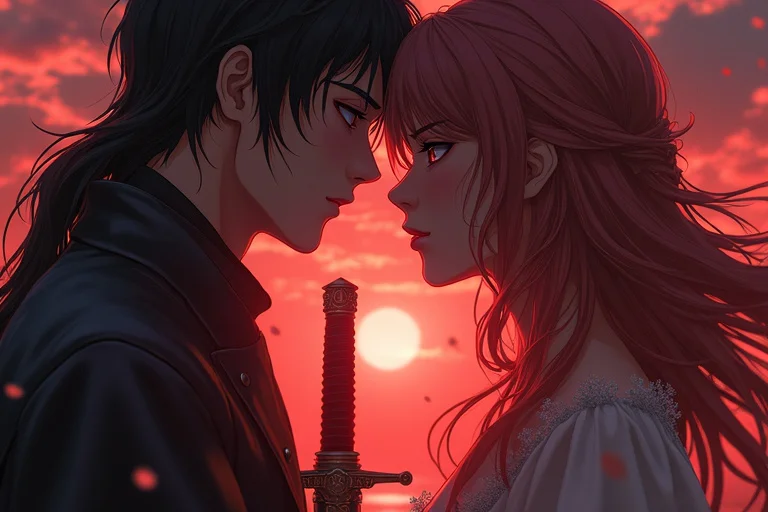第一章 残響の依頼人
江戸、神田の裏長屋。陽の光さえ遠慮するように差し込む薄暗い一室で、橘勘九郎(たちばなかんくろう)は死んだように眠っていた。いや、眠っているふりをしていた。戸板を叩くか細い音は、もう半刻ほども前から続いている。無視を決め込んでいたが、その音は諦めるということを知らないらしい。雨垂れが石を穿つように、勘九郎の意識を苛んでいた。
「……何の用だ」
ついに根負けし、低く掠れた声で応じる。ぴたり、と音が止んだ。そして、戸の向こうから聞こえてきたのは、鈴を転がすような、しかし芯の強さを感じさせる若い娘の声だった。
「『音聞き』の勘九郎様でいらっしゃいますか。お願いがあって参りました」
音聞き。その響きに、勘九郎は自嘲の笑みを浮かべた。触れた物の「最後の音」が聞こえる。そんな呪いのような力を、人はそう呼んだ。それは死者の断末魔であり、壊れた道具の悲鳴であり、捨てられた物の哀哭だった。世界に満ちる終焉の残響を聞き続けるうちに、勘九郎の心はとっくにすり減り、乾ききっていた。
「人違いだ。帰ってくれ」
「いいえ、あなた様だと伺っております。父の……父の無念を晴らしたいのです」
父、という言葉に、勘九郎の眉がわずかに動く。彼はのろのろと起き上がると、乱れた着物を直しもせず、軋む戸を開けた。そこに立っていたのは、年の頃十六、七だろうか。洗い晒しの着物を着た、意志の強そうな瞳を持つ娘だった。お絹、と名乗った娘の話はこうだ。
彼女の父親・儀右衛門(ぎえもん)は、江戸でも評判の絡繰(からくり)師だった。三日前、工房で冷たくなっているのが見つかった。傍らには、彼が心血を注いで作り上げた等身大の絡繰人形が数体、静かに佇んでいたという。奉行所の役人は、過労による心臓の病、つまりは事故死として早々に片付けた。しかし、お絹は納得できなかった。父の体には不審な痣があり、工房の道具の位置も普段と違っていた、と。
「父の最後の声を聞いてはいただけませんか。この絡繰に触れていただければ……」
お絹が差し出したのは、小さな木箱だった。中には、まるで生きているかのように精巧な、小鳥の絡繰人形が収められている。つやつやと磨かれた木肌、本物の羽を使った羽根。勘九郎は眉をひそめた。
「断る。俺は死人の声を聞くために、この力を使わん」
人の死の音ほど、魂を削るものはない。絶望、苦痛、後悔。それらが濁流のように流れ込んでくる感覚は、二度と味わいたくなかった。
「お願いでございます!」お絹は深く頭を下げた。「父は、ただの人形師ではございませんでした。父の作る絡繰には、魂が宿っておりました。その魂の最後の声を、どうか……」
その必死な声に、勘九郎は遠い昔の、守れなかった約束を思い出して胸がちりりと痛んだ。彼は舌打ちを一つすると、娘の手から乱暴に木箱をひったくった。
「……報酬は弾んでもらうぞ」
ぶっきらぼうに告げる勘九郎の目に、諦観と、ほんのわずかな疼きが宿っていることを、お絹は知る由もなかった。
第二章 絡繰の鳥語
儀右衛門の工房は、油と木の香りが混じり合った、独特の匂いに満ちていた。壁一面に並ぶ工具、設計図らしき和紙の束、そして部屋の中央には、異様な存在感を放つ五体の絡繰人形が鎮座していた。武士や町娘、異国の踊り子を模した人形たちは、まるで時が止まったかのように、それぞれのポーズで静止している。
「父は、この子たちを完成させるのを楽しみに……」
お絹の声が震えている。勘九郎は無言で工房を見渡した。確かに、几帳面だったという儀右衛門の仕事場にしては、道具の配置が雑然としているように見える。
勘九郎は、まず儀右衛門が倒れていたという床にそっと手を触れた。目を閉じ、意識を集中させる。――ごとり、と何かが落ちる鈍い音。男の苦悶のうめき声。そして、ざあざあと血の気が引いていくような感覚。それだけだった。これでは何も分からない。
「……人形に触れる」
勘九郎は、一体の武者人形の前に立った。黒漆塗りの鎧兜は、細部まで精巧に作られている。彼は意を決して、その冷たい鉄の籠手(こて)に指を伸ばした。
瞬間、勘九郎の脳裏に、無数の音が洪水のように押し寄せた。
――キィン、と金属を削る甲高い音。木槌が鑿(のみ)を打つ、小気味よい響き。ゼンマイがギリギリと巻き上げられる緊張の音。それらは、人形が生まれるまでの、長い時間の記憶だった。勘九郎は眉間に皺を寄せ、さらに深く意識を沈めていく。最後の音、儀右衛門が死んだ瞬間に、この人形が「聞いた」音を探す。
すると、不意にそれらの喧騒が途切れ、澄んだ音が響いた。
――ピルルル……。
それは、鳥のさえずりのような、美しい笛の音だった。しかし、ただの笛の音ではない。複雑な音階が組み合わさった、聞く者の心を捉える不思議な旋律。その音はごく短く響くと、ぷつりと途絶えた。後には、ただ静寂が残るだけだった。
「……どうでしたか?」
お絹が不安げに問いかける。勘九郎はゆっくりと目を開け、首を横に振った。
「……鳥の鳴き声のような、笛の音が聞こえた。それだけだ」
「笛の音……?」お絹は怪訝な顔をする。「父の工房で笛など……。それに、それが父の死と何の関係が?」
勘九郎にも分からなかった。穏やかでさえあるその音色は、殺人事件の残響とは到底思えなかった。他の人形にも触れてみたが、聞こえてくる最後の音は、すべて同じ笛の音だった。
「何も分からん。あんたの気のせいだったんじゃないのか」
勘九郎はそう吐き捨て、工房を後にしようとした。だが、彼の心には、あの不可解な音色が棘のように突き刺さっていた。あれはただの音ではない。何か、意図を持って作られた音だ。死の現場に不釣り合いなほど美しい、その旋律の裏に隠された意味を、勘九郎の本能が嗅ぎ取っていた。
第三章 歪んだ大義
長屋に戻った勘九郎は、数日間、あの笛の音について考え続けていた。あれは、どこかで聞いたことがあるような、ないような……。記憶の澱をかき混ぜていると、ふと、ある人物の顔が脳裏をよぎった。
高遠主馬(たかとうしゅめ)。勘九郎がかつて仕え、心から尊敬していた元主君だ。勘九郎がまだ武士だった頃、高遠は彼に様々なことを教えた。剣術、兵法、そして、異国の珍しい楽器の奏で方まで。あの笛の音は、高遠が好んで吹いていた、南蛮渡来の鳥笛の音色に酷似していた。
だが、高遠は三年前に藩を追放され、江戸で浪人暮らしをしているはずだ。一介の絡繰師の死に、あの人が関わっているはずがない。そう打ち消そうとすればするほど、疑念は黒い染みのように広がっていく。
勘九郎は、かつての伝手を頼り、高遠の動向と、絡繰師・儀右衛門について密かに調べ始めた。そして、浮かび上がってきた事実に、彼は愕然とすることになる。
儀右衛門は、単なる人形師ではなかった。彼は幕府の御用を務めるほどの腕を持ちながら、裏では特定の藩や思想家のために、特殊な絡繰――人を殺傷するための、恐るべき暗殺絡繰を製作していたのだ。そして、その最大の依頼主こそ、高遠主馬だった。
高遠は、幕府の腐敗を憂い、この国を根底から変えるための革命を計画していた。その手始めとして、幕政の中枢にいる老中を、衆人環視の祭りの席で暗殺しようとしていたのだ。儀右衛門が作った五体の絡繰人形は、そのための暗殺装置だった。人形の内部には、毒を塗った吹き矢が仕込まれており、特定の音色の笛を合図に、一斉に発射される仕掛けになっていた。
儀右衛門は、計画のあまりの非情さに恐れをなし、土壇場で降りようとした。だから、口封じのために高遠の手の者に殺されたのだ。最後の笛の音は、儀右衛門が死の間際に聞いた、暗殺絡繰の最終テストで鳴らされた「起動の合図」の音だったのである。
すべてを悟った勘九郎は、血の気が引くのを感じた。尊敬していた主君は、理想を追い求めるあまり、人の命を駒としか考えない修羅に成り果てていた。自分の呪われた力が、こんな形で過去の敬愛と現在の憎悪を結びつけるとは。
勘九郎の脳裏に、高遠の言葉が蘇る。「勘九郎、力はただ持つだけでは意味がない。何のために使うか、だ」。あの頃は、その言葉が輝いて見えた。だが今は、その言葉が血塗られて聞こえる。無気力な日々を送っていた勘九郎の心に、初めて激しい怒りの炎が燃え上がった。これは、止めなければならない。死者の声を聞くだけだった俺が、初めて、未来に起こる死を、防がなければならない。
第四章 聞こえぬはずの唄
暗殺決行の日は、三日後の上野での祭りの日だった。勘九郎には時間がなかった。彼は高遠の屋敷に単身乗り込んだ。月明かりだけが照らす静かな庭で、二人は数年ぶりに対峙した。
「……やはり、お前か。勘九郎」
高遠は、昔と変わらぬ穏やかな笑みを浮かべていた。だが、その瞳の奥には、氷のような冷たさが宿っている。
「儀右衛門殿を殺したのは、あなたですか」
「大義のためだ。小さな犠牲は厭わん」
「その大義とやらのために、罪なき人々まで巻き込むおつもりか!」
勘九郎の叫びは、高遠には届かなかった。「腐った根を断つには、幹ごと切り倒すしかないのだよ」。高遠は静かに懐から鳥笛を取り出した。「お前も、私と共に来い。お前のその『音を聞く力』は、新しい世を作るためにこそある」
勘九郎は、きつく拳を握りしめた。この人は、何も分かっていない。この力がどれほどの悲鳴と絶望を自分に聞かせてきたか。そして、それが今、何を自分にさせようとしているのか。
祭りの日。喧騒に沸く上野の山。老中の行列が、見物客でごった返す通りを進んでいく。その様子を、近くの茶屋の二階から、高遠と、そして勘九郎が見下ろしていた。高遠の手下たちが、群衆に紛れて五体の絡繰人形を巧みに配置している。
行列が、ちょうど絡繰人形たちの射程に入った。高遠が、ゆっくりと鳥笛を唇に当てる。
その瞬間、勘九郎は懐から一本の粗末な横笛を取り出し、息を吹き込んだ。
それは、かつて高遠が勘九郎に教えた、平和な世を願うという異国の歌だった。ひどく拙く、音も外れていたが、その必死の音色は、鳥笛の複雑な旋律に干渉し、その構造をわずかに乱した。
高遠が目を見開く。彼が鳥笛を鳴らす。だが、勘九郎の笛の音が起動の合図を狂わせた。キィ、ガガガッ、と異音を立て、絡繰人形たちはありえない方向を向き、吹き矢を虚空に、あるいは地面に打ち込んだ。計画は、失敗した。
駆けつけた役人たちに、高遠は抵抗することなく捕らえられた。連行される間際、彼は勘九郎にだけ聞こえる声で呟いた。「お前の聞く音は、死者の声だけではない。……生きる者の声も、聞こえるはずだ」
事件は、幕府によって闇に葬られた。勘九郎はお絹のもとを訪れ、父は立派な男だったとだけ告げた。そして、儀右衛門が娘のために絡繰に隠していた、小さなオルゴールを手渡した。ゼンマイを巻くと、お絹が幼い頃に口ずさんでいた子守唄が、優しく流れ出した。儀右衛門の最後の音は、笛の音ではなく、きっとこの音色だったのだと、勘九郎は思った。
長屋への帰り道、夕暮れの江戸は人々の活気で満ちていた。勘九郎は、道端に転がっていた子供の手鞠に、ふと目を留めた。彼は何気なくそれに手を触れた。
脳裏に響いてきたのは、絶叫でも、悲鳴でもなかった。
――キャッキャ、という子供たちの明るい笑い声。鞠が地面を弾む、生命力に満ちた音。
それは、この手鞠が最後に聞いた、喜びの記憶だった。
勘九郎は、はっと顔を上げた。高遠の最後の言葉が、胸に染み渡る。この力は、死の残響だけを聞くためのものではなかった。生きていた証、喜び、愛、そうした温かい音の記憶もまた、世界には満ち溢れていたのだ。
勘九郎は、夕焼けに染まる江戸の空を見上げ、ほんの少しだけ、口元に笑みを浮かべた。これからは、聞こえてくる声に、耳を澄まそう。死者の無念だけでなく、生者の喜びの声にも。彼の心に巣食っていた長い冬が、ようやく終わりの気配を見せていた。