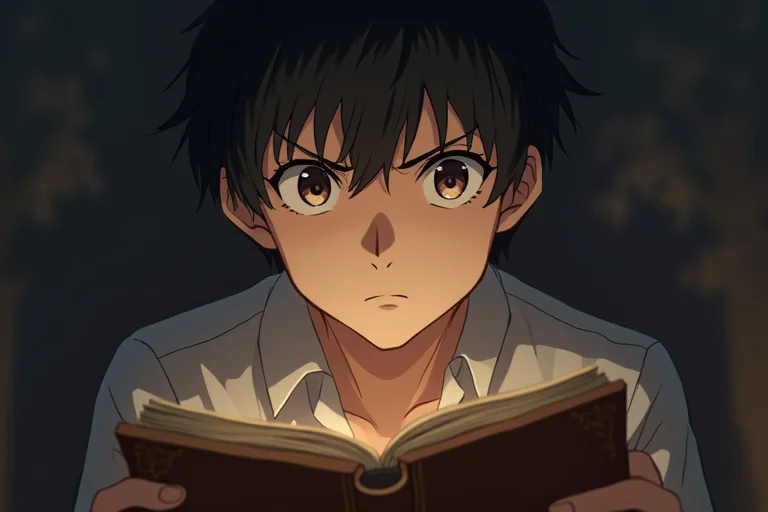第一章 触れられぬ色
俺、カイの手のひらは、死者の最後の言葉を聴くための耳だ。人は死後、その生きた時間の密度が結晶化した「時間砂(タイムサンド)」を残す。俺はその砂に触れることで、持ち主が抱えていた感情の「色」と「温度」を感じ取ることができた。喜びは陽だまりのような温かさと黄金色を、悲しみは肌を刺す冷気と深い藍色を、そして後悔は、皮膚に焼き付くような熱と錆びた赤色を俺に伝えた。
特に強い感情が混じり合った砂に触れると、その残滓は俺の腕に痣となって一時的に浮かび上がる。それは他人の人生の縮図であり、俺にとっては名誉の負傷のようなものだった。誰もが己の「記憶の影」を背負って生きるこの世界で、俺は影のさらに奥深く、その源泉である感情そのものに触れる調律師として生計を立てていた。
その日、俺が呼ばれたのは、裏路地の湿った石畳の上だった。依頼人の警吏が眉を顰め、白い布をめくると、そこに横たわる男の遺体があった。彼の傍らには、一握りの時間砂が静かに零れていた。
「いつものように、頼む」
警吏に促され、俺は屈み込むと、革手袋を外した指先でそっと砂に触れた。
いつもなら、指先に流れ込んでくるはずの情報の奔流に備える。温もり、冷たさ、色、匂い。だが――。
何も、ない。
まるで、乾ききった灰に触れているかのようだ。色も、温度も、感情の揺らぎも一切感じられない。ただ、絶対的な「無」がそこにあるだけだった。俺の能力が、初めて沈黙した瞬間だった。腕には痣ひとつ浮かばず、代わりに背筋を冷たい何かが駆け上がった。
男の足元に伸びるはずの記憶の影もまた、奇妙なほどに薄く、まるで存在しないかのようだった。この空虚さは、死そのものよりも深く、冒涜的な静けさを湛えていた。
第二章 無影の囁き
例の死体は、検死でも不可解な点しか残さなかった。彼の人生は、まるで白紙のページのようだった。家族も、友人も、そして彼自身を証明する過去の痕跡さえも、どこにも見つからなかったのだ。
俺は、あの「無」の感触に取り憑かれていた。自分の能力の根幹を揺るがされたような、言い知れぬ不安。俺は仕事も手につかず、市立古文書館の埃っぽい書架の間を彷徨っていた。この世界の理に関する古い記録の中に、何か手がかりがあるかもしれない。
数日が過ぎた頃、俺は一冊の古びた手記に奇妙な記述を見つけた。
『影を持たざる者、現る。彼らを無影(ムエイ)と呼ぶ。彼らは過去を語らず、感情の痕跡を残さず、虚空の如く生き、塵の如く消ゆ。彼らの時間砂は、ただ空虚なり』
無影。その言葉が、雷のように俺の脳を撃ち抜いた。あの男は、無影だったのだ。手記によれば、彼らは稀な存在として古くから記録されていたが、近年、その目撃情報が密かに増えているという。彼らは一体、何者なのか。
ふと、窓ガラスに映る自分の姿に目が留まった。俺の背後には、他人のそれよりひときわ濃く、輪郭の歪な記憶の影がゆらりと佇んでいた。それは、幼い頃に救えなかった妹の最後の姿。俺が決して手放すことのできない、罪悪感という名の楔だった。この影の重みを知るからこそ、影を持たない存在が信じられなかった。
第三章 虚ろな指輪
無影の噂を追って、俺は都市の再開発から取り残された旧市街に足を踏み入れた。錆びた鉄骨が空を突き、風が寂しい音を立てて吹き抜ける。そこで俺は、彼女に出会った。
廃墟となった教会のステンドグラスの下に、一人の少女が座っていた。年の頃は十代半ば。彼女の足元には、影がなかった。人形のように整った顔には何の感情も浮かんでおらず、その瞳は磨かれたガラス玉のようにただ俺を映すだけだった。
「君が、無影か?」
俺の問いに、少女は答えなかった。ただ静かに立ち上がると、俺の横を通り過ぎようとする。その時、彼女の細い指から、何かが滑り落ちた。カラン、と乾いた音を立てて石畳を転がる、銀色の指輪。
俺は咄嗟にそれを拾い上げた。指輪は中央が完全にくり抜かれた、奇妙なデザインをしていた。まるで小さな「無」を閉じ込めたようなその意匠に、俺は知らず指で触れてしまう。
瞬間、世界が反転した。
視界がノイズに覆われ、感情のない客観的な視点で、断片的な映像が流れ込んできた。燃え盛る家。泣き叫ぶ人々。絶望の淵で天を仰ぐ男。だが、それを見ている「誰か」は、何の悲しみも怒りも感じていない。ただ、事実として記録しているだけだった。
「……っ!」
我に返った時、少女の姿はもうどこにもなかった。手の中に残されたのは、冷たい金属の感触だけ。俺は指輪を見つめた。それは「虚ろな指輪(ホロウリング)」と呼ばれ、かつて最初の無影が遺した唯一の品だと、手記には記されていた。この指輪は、無影の視点を体験させる鍵なのだ。
第四章 忘却の聖堂
指輪は、微かに少女の気配を放っていた。俺はそれを頼りに、迷路のような地下道を下っていく。湿った空気とカビの匂いが鼻をつく。やがて俺は、広大な地下空間にたどり着いた。
そこは「忘却の聖堂」と呼ばれる場所らしかった。天井からは淡い光が降り注ぎ、空間の中央には、都市の記憶そのものを刻み込んだかのような巨大な一枚岩――「記憶の碑」が鎮座していた。碑の表面には、無数の人々の影が蠢くように映し出されている。
そして、その碑を取り囲むように、何十人もの無影たちが静かに佇んでいた。あの少女も、その中にいた。彼らは感情も影も持たず、ただひたすらに、碑を見つめていた。まるで、何かを待つ巡礼者のように。その光景は、荘厳でありながら、異様だった。
彼らは、ここで何をしているのか。
俺が息を潜めていると、少女――リナ、と誰かが呼んだ気がした――が、ゆっくりと碑に向かって歩き出した。
第五章 記憶の洪水
リナが記憶の碑の前に立つと、聖堂の空気が張り詰めた。彼女は、俺が持っているはずの「虚ろな指輪」と全く同じものを指にはめ、そっと碑の表面に触れた。
次の瞬間、世界が絶叫した。
碑が、甲高い悲鳴のような音を立てて激しく明滅を始めた。碑に刻まれていた無数の記憶の影が、黒い奔流となって溢れ出す。それは、蓄積され、圧縮され、耐えきれなくなった膨大な負の感情だった。後悔、憎悪、悲嘆、絶望。それらが物理的な力を持って聖堂を席巻し、俺自身の濃い影さえも蝕み、狂暴に揺らめかせ始めた。
「やめろ!」
俺は叫んだ。だが、声は届かない。その混沌の中で、俺は指輪を通して真実を幻視した。
無影たちは、未来を見ていたのだ。人々が抱える記憶の影が、その「過去の重み」によってやがて世界そのものを押し潰し、停滞させ、死に至らしめる未来を。それを回避するため、彼らは自らの意思で、最も愛し、最も悲しんだ記憶と感情を全てこの碑に「預け」、影のない空虚な存在として生まれ変わったのだ。自己犠牲。それが彼らの正体だった。
しかし、預けられた感情の総量は、碑の許容量をとうに超えていた。今、この瞬間、世界の記憶が暴走し、破滅の引き金を引こうとしていた。
第六章 鎮魂の儀式
彼らは破壊者ではなかった。誰よりも未来を憂う、救済者だったのだ。
俺は決意を固めた。ポケットから取り出した「虚ろな指輪」を、震える指にはめる。そして、暴走する記憶の奔流に向かって、両手を突き出した。
「お前たちの痛みは、俺が聴く!」
俺は、自らの能力を逆転させた。時間砂から感情を「読む」のではなく、碑から溢れ出す膨大な感情を、この身に「受け止め、鎮める」のだ。
凄まじい熱と冷気が、俺の全身を駆け巡る。腕に、胸に、顔に、無数の痣が咲いては消え、消えては咲いた。人々の絶望が、愛する者を失った悲しみが、叶わなかった願いが、俺の魂を直接削り取っていく。
その痛みの奔流の中で、俺は自身の最も深い後悔と向き合っていた。燃える家の中から、助けを求める妹の手。伸ばしかけた俺の手は、炎に阻まれて届かなかった。あの日の熱と、彼女の絶望が、俺の影を何よりも濃くしていたのだ。
だが今、俺は無数の他人の痛みと共に、自分の痛みをも受け入れていた。俺は独りではなかった。過去を背負う全ての人々と、そして過去を捨てて未来を救おうとした無影たちと、繋がっている。
第七章 夜明けの影
どれほどの時間が経っただろうか。気づけば、記憶の洪水は穏やかな川の流れのように静まっていた。記憶の碑は淡い光を放ち、暴走は鎮められていた。世界を覆っていた影の重圧が、少しだけ軽くなった気がした。
俺は膝から崩れ落ちた。全身が引き裂かれるように痛む。だが、不思議と心は凪いでいた。ふと自分の足元を見ると、あれほど濃く、俺を縛り付けていた記憶の影が、まるで夜明けの霧のように薄く、透明に近くなっていた。消えたわけではない。だが、もう俺を苛むだけの重さを持ってはいなかった。
静寂の中、リナが俺のそばに歩み寄ってきた。彼女はそっと俺の手に触れる。その時、俺は確かに感じた。彼女の指先から伝わる、ほんの僅かな「温もり」を。
リナのガラス玉のようだった瞳に、初めて微かな感情の「色」が揺らめいた。それは、感謝の色だろうか。それとも、新しい始まりへの希望の色だろうか。
世界は変わらない。人々はこれからも記憶の影を背負って生きていく。無影たちも、その存在意義を問い続けるだろう。だが、破滅の未来は回避された。過去の重みに潰されるのではなく、それと共に未来へ歩む道が、今、拓かれたのだ。
俺は、薄くなった自分の影を見つめ、そしてリナの顔を見た。空虚だった彼女の顔に、ごく微かな、本当に微かな微笑みが浮かんでいるように見えた。