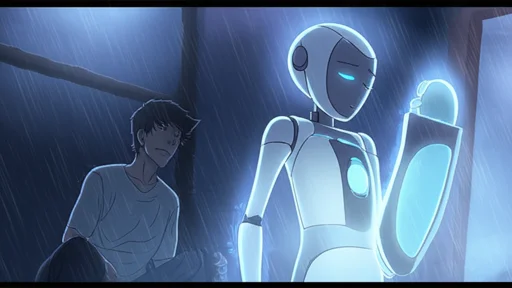第一章 色彩の牢獄
俺の視界は、常に感情の残滓で飽和していた。人が何かを諦める瞬間に立ち上る、鈍い紫煙。予期せぬ喜びが弾ける時に散る、鮮やかな光の粒子。誰かを深く愛し、そしてその想いが薄れる時に漂う、温かい金色の靄。それらは『残響』と呼ばれ、俺の世界を覆い尽くす色彩のカーテンだった。
この能力のせいで、俺はもう何年も、誰かとまともに視線を合わせたことがない。人の顔は、その内面から溢れ出す残響の渦に飲み込まれ、輪郭さえ曖昧になる。街の景色も同じだ。アスファルトの灰色も、建物の煉瓦色も、無数の感情の残響が混ざり合った結果、ただのくすんだ色彩の洪水としてしか認識できない。雨の日のコンクリートの匂い、風が頬を撫でる感触、遠くで鳴る教会の鐘の音。視覚以外の感覚だけが、俺をこの不確かな世界に繋ぎ止める錨だった。
最近、特に世界の色が褪せてきているように感じる。街のあちこちで、感情の澱が急速に黒い霧へと変貌し、景色を侵食しているのだ。喜びの粒子は瞬く間に輝きを失い、悲しみの紫煙は重く澱み、やがてすべてが黒に塗り潰されていく。人々は表情を失い、その歩みからは力が抜けていた。世界から、感情という名の体温が奪われていくようだった。
第二章 忘却の羅針盤
ニュースは連日、『忘却の地』の拡大を報じていた。かつて活気のあった港町が、今では住民の記憶さえ曖昧な無色の廃墟と化した、と。その映像に映る濃密な黒い霧を見つめながら、俺は胸の奥が冷たくなるのを感じていた。あれはただの霧ではない。忘れ去られた無数の感情の、巨大な墓標だ。
その夜、俺は祖母の遺品を収めた古い木箱を開けた。埃っぽい匂いの中に、見覚えのあるケースが静かに横たわっていた。中には、あらゆる光を吸い込むような漆黒のレンズを持つ、古風な眼鏡。幼い頃、祖母は俺の頭を撫でながら、不思議な声で言ったものだ。
「カイ。その目はね、世界が隠している本当の色を見るためのものだよ。もし、いつか世界が悲しみで塗り潰されそうになったら、この眼鏡をかけるんだ。きっと、進むべき道を照らしてくれるから」
祖母の温かい手の感触が蘇る。あの頃は意味の分からなかった言葉が、今、重い意味を持って胸に響いた。俺は眼鏡を手に取り、立ち上がった。確かめなければならない。この黒い霧の先にあるものを。俺にしか見えない、あの異常な残響の正体を。
第三章 無色の調べ
最も近くに発生した『忘却の地』は、電車で数時間ほどの距離にある、かつて美しい湖畔の街として知られた場所だった。駅に降り立った瞬間、空気が違うことに気づく。音がしないのだ。鳥の声も、人々のざわめきも、車の走行音さえも、まるで分厚い壁に吸い込まれたかのように希薄だった。人々は幽霊のように街を彷徨い、その瞳は何も映していなかった。
俺はポケットから祖母の眼鏡を取り出し、震える手でそれをかけた。
瞬間、世界から一切の色が消えた。視界は完全な闇に閉ざされる。だが、その闇の奥で、何かが蠢いていた。街を覆う濃密な黒い霧。その中心から、一条の光が、まるで傷口から流れる血のように滲み出していた。それは、これまで見たどんな残響とも違う、絶望と憧憬が混ざり合った、痛々しいほどに鮮烈な深紅の光だった。
光の線は、湖のほとりに立つ、古びた美術館へと真っ直ぐに伸びていた。俺は、その光に導かれるように、無音の街を歩き始めた。足元に転がる枯れ葉を踏む音だけが、やけに大きく響いた。
第四章 アトリエの沈黙
美術館の重い扉は、軋みながら簡単に開いた。内部は静寂に満ち、壁にかけられた絵画はすべて色を失い、ただの灰色の濃淡となっていた。光の線は、館の最奥、立ち入り禁止の札がかけられたアトリエへと続いていた。
アトリエの中心に、その男はいた。イーゼルの前に立つ老人は、俺の気配に気づくと、ゆっくりと振り返った。かつて世界中の人々をその色彩で魅了した天才画家、エルンスト。彼の瞳には、もはや何の感情も宿っていなかった。
「来たかね、残響を見る者よ」
彼の背後には、巨大なカンヴァスのような装置があった。それは黒い霧を脈動するように吐き出し、空間そのものを歪ませている。
「人々は不完全な感情に苦しみ、醜い澱を世界に撒き散らす。私は彼らを解放しているのだ。すべての感情を浄化し、完璧な静寂という名の、至高の芸術を創造している」
エルンストは静かに語った。彼の言葉には奇妙な説得力があった。だが、俺には分かっていた。彼が作り出しているのは、救済ではなく、虚無だ。
「君のその目に見える『残響』こそが、この世界を汚す最後の不純物だ。それさえ消し去れば、私の芸術は完成する」
エルンストが装置に手をかざすと、黒い霧が渦を巻き、俺に向かって殺到した。視界が急速に黒く染まっていく。喜びの光も、悲しみの煙も、愛の靄も、すべてが虚無に飲み込まれていく。
第五章 奔流の果てに
色彩が消える。世界との繋がりが断ち切られていく恐怖。その暗闇の中で、再び祖母の声が聞こえた気がした。
『色はね、心を映す鏡だよ。醜い色なんて、ひとつもないんだ』
そうだ。醜い色なんてない。不完全だからこそ、美しいのだ。俺は消えゆく視界の中で、恐怖に目を閉じるのではなく、逆に真っ直ぐに装置を見据えた。奪われるものか。これは、俺の世界だ。
その瞬間、流れが逆転した。装置から、堰を切ったように無数の色彩が溢れ出したのだ。それは、エルンストが『不完全』として切り捨て、消し去ったはずの、ありとあらゆる人々の感情の残響だった。歓喜の黄金、絶望の紺青、嫉妬の濁った緑、後悔の鉛色、そして名もなき日々の穏やかな琥珀色。感情の奔流が、巨大な津波となって俺の全身を貫いた。それは痛みであり、歓びであり、途方もない愛だった。
第六章 クリアな世界
膨大な感情の奔流を、俺はただ受け止めた。すると、奇妙なことが起きた。俺の視界を常に覆っていた過剰な色彩が、まるで濁流が澄んでいくように、すうっと晴れていったのだ。
エルンストの装置は、許容量を超えた感情の逆流に耐えきれず、甲高い音を立てて停止した。
俺はゆっくりと目を開ける。
そこには、生まれて初めて見る、クリアで鮮明な世界が広がっていた。
霞んでいたエルンストの顔の深い皺。床に落ちた絵筆の木目。アトリエの窓から差し込む光が、空気中の塵をきらきらと照らし出している。すべてが、驚くほどくっきりと、在るがままに見えた。俺は恐る恐る自分の手を見つめる。指先の爪の、淡い桜色までが見て取れた。
エルンストは、壊れた装置に絶望するでもなく、ただ呆然と俺の目を見ていた。そして、その虚ろだった瞳から、一筋の涙が静かに流れ落ちた。それは、彼自身が忘れ去っていた、悲しみの色をしていた。
第七章 希望の萌芽
忘却の地にも、ゆっくりと色が戻り始めていた。人々はまだ戸惑いながらも、隣人の顔を久しぶりにまじまじと見つめ、かすかな笑みを交わし始めている。
俺の能力は、変容していた。もう、過去の感情が消える瞬間の『残響』を見ることはない。その代わりに、人々の心に宿る、未来への微かな希望の兆しが見えるようになっていた。それは、これから芽吹こうとする決意の、淡い若草色。夜明け前の空のような、静かな期待を孕んだ薄紫色。色彩はもう俺の視界を覆い隠すことはなく、世界の美しさを引き立てるアクセントとして、優しくそこに在った。
俺は懐から祖母の眼鏡を取り出し、その冷たい感触を確かめる。そして、そっと上着のポケットにしまった。もう、これが必要になることはないだろう。
クリアになった視界で、俺は色づき始めた世界を歩き出す。不完全で、ちぐはぐで、だからこそ限りなく愛おしいこの世界を、この目で確かめるために。