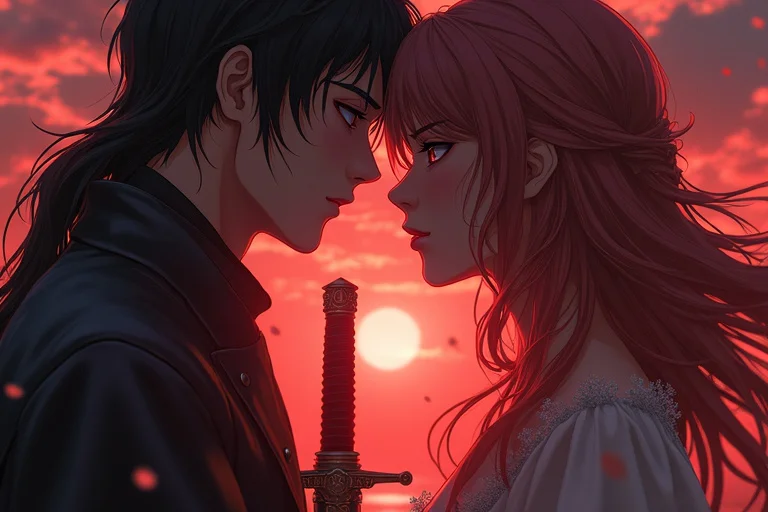第一章 錆びた時間の匂い
常磐町(ときわちょう)には、錆びた時間の匂いがした。
陽光は常に同じ角度から瓦を照らし、埃っぽい風は毎日決まった時刻に柳の枝を揺らす。行き交う人々の顔には表情がなく、まるで精巧な絡繰人形のように、昨日と寸分違わぬ道を歩んでいた。この町では、時間が死んでいた。
浪人、朔(さく)の草鞋が乾いた土を踏む音だけが、不協和音のように響く。彼は腰に差した一振りの刀の、鞘に刻まれた傷を指でなぞった。この刀で人を斬って以来、朔には奇妙な力があった。斬られた人間の、その場に残る「残像」と話せるのだ。
路地裏から、短い悲鳴と肉の断ち切られる鈍い音がした。駆けつけると、血溜まりの中に商人が倒れ、チンピラ風情の男が慌てて走り去っていく。朔の目には、倒れた商人の傍らに、陽炎のように揺らめく半透明の姿が見えていた。残像だ。
「何があった」
朔が問うと、残像は苦悶に歪んだ顔を向けた。残像は、斬られた直前の強い感情しか持たない。恐怖、怒り、そして未練。
『硝子…の、蝶…が…』
声は風に掻き消えそうなほどか細い。
『桔梗様…に…お渡し、せねば…』
それが最期の言葉だった。陽炎は不意に濃くなり、そして霧散した。後には、血の匂いだけが残る。
商人の懐から、小さな桐箱が転がり落ちていた。中身は空っぽだ。だが、箱の底で何かが微かに光った。朔が拾い上げたのは、見たこともないほど滑らかで、冷たい光沢を放つ金属の欠片だった。この町に流れ着いてから、時折見かける奇妙な品。人々はそれを「天からの落とし物」と呼んだが、朔にはそれが、あるはずのない「未来の遺物」のように思えてならなかった。
硝子の蝶。桔梗。そして未来の欠片。
澱んだ時間の底で、何かが静かに動き始めていた。
第二章 時を刻まぬ鏡
「桔梗」の名は、町の中心にある小さな花屋ですぐに見つかった。
店の軒先で、桔梗という娘が黙々と花を売っている。彼女が微笑むと、その周りだけ、死んでいた時間がふっと息を吹き返すような錯覚に陥った。淀んだ空気の中で、彼女の存在だけが鮮やかな色彩を放っている。
朔は数日間、遠巻きに彼女を眺めた。毎日同じ時間に店を開け、同じ客に同じ花を売り、陽が傾くと静かに店を閉める。完璧な繰り返し。だが、他の住人と違い、彼女の瞳には微かな憂いが宿っていた。まるで、終わらない夢の中にいることを、彼女だけが知っているかのように。
ある日、朔は意を決して彼女に近づいた。
「これを探している」
懐から、あの金属の欠片を見せる。桔梗は息を呑み、その顔からさっと血の気が引いた。彼女の細い指が、自身の首元にかけられた小さな袋に触れる。
その時だった。朔が懐に忍ばせていた古い懐中鏡が、熱を帯びた。それは、亡き師から譲り受けた「時を刻まぬ懐中鏡」。強い感情が渦巻く場所で、持ち主の別の可能性や、未来の断片を映し出すという奇妙な鏡だ。
朔が鏡を取り出すと、磨かれた銀の表面がぐにゃりと歪んだ。
そこに映っていたのは、朔自身の姿ではなかった。
燃え盛る炎。黒煙の中で、桔梗が絶望の表情でこちらに手を伸ばしている。その手には、美しい硝子細工の蝶が握られていた。
幻は一瞬で消え、鏡は元の冷たい銀の板に戻った。
「あなたは…一体…」
桔我の声は震えていた。
彼女は何かを知っている。この町の秘密と、繰り返される悲劇の影を。
第三章 繰り返される悲劇の影
その夜、朔の宿を音もなく訪れた者がいた。
「公儀隠密、影山と申す」
月明かりに照らされた男の顔は能面のようだった。影山は、朔が「残像」と話せる力を持つこと、そして未来の遺物を集めていることまで知っていた。
影山は静かに語り始めた。この常磐町が、幕府の秘術「時間定着の術」によって時間が固定されていることを。
「この町は、かつて大火で一夜にして焦土と化した。その悲劇を繰り返さぬため、幕府は時間をあの日が来る直前で留めたのだ」
しかし、術は不完全だった。固定された時間の中に、未来から遺物が零れ落ちるという綻びが生まれている。
「我々は、その綻びを塞がねばならん。お主の力が必要だ、朔殿」
影山の話は、どこか嘘くさかった。町全体の悲劇を回避するため、というには大袈裟すぎる。朔の脳裏に、鏡に映った炎の中の桔梗の姿が焼き付いて離れない。
「斬られた商人が言っていた。『硝子の蝶』とは何だ」
「さあな。だが、遺物の謎を追えば、いずれ分かるだろう」
影山はそう言って闇に消えた。彼もまた、この澱んだ時間の一部のように、感情のない男だった。
朔は再び桔梗の元へ向かった。彼女なら答えを知っているはずだ。
問い詰めると、桔梗は泣き出しそうな顔で、首にかけていた小さな袋から、それを取り出した。
手のひらに乗せられたのは、息を呑むほど精巧な、硝子の蝶だった。それは陽光を浴びて七色に輝き、まるで生きているかのように見えた。
「これが、何故か時々、私の足元に現れるんです。まるで、誰かが未来から届けてくれるみたいに…」
その蝶は、朔が拾った金属の欠片と同じ、冷たく滑らかな手触りがした。
第四章 時間泥棒の囁き
答えは、最も残酷な形で朔の前に現れた。
朔は、町の古文書を漁り、ついに常磐町の大火の記録を見つけ出した。日付は、明日に迫っていた。そして、犠牲者の名簿の最初に記されていたのは、花屋の娘の名。
――桔梗。
全てが繋がった。幕府が時間を固定したのは、町を守るためではない。この町で繰り返し起こる「桔梗の死」という一点の悲劇を、何度も何度も発生させることで生まれる濃密な悲しみの時間を喰らう、異形の存在を封じ込めるためだったのだ。
時間定着の術は、その存在――影山が隠していた「時間泥棒」と呼ばれる何かを、この町という檻に閉じ込めておくためのものだった。
桔梗は、来る日も来る日も、炎に焼かれて死ぬ運命を繰り返していた。記憶は毎朝リセットされるが、魂の奥底に刻まれた恐怖が、彼女の瞳に憂いとなって宿っていたのだ。硝子の蝶は、死の瞬間の彼女の強い想いが未来に作用し、過去の自分へ届けられる遺物だった。繰り返される絶望の中で、彼女自身が未来から過去へ送っていた、救いを求める声なき声だったのだ。
「全てご存知でしたか、影山殿!」
朔は影山の前に立ちはだかった。その背後では、桔梗が不安げに佇んでいる。
「そうだ」影山は表情を変えずに答えた。「一人の犠牲で、より大きな災厄を封じている。それが幕府の正義だ」
「ふざけるな!」
朔の怒りが頂点に達した瞬間、世界の時間が軋むのを感じた。怒りの感情が、固定された時間を無理やり加速させていく。遠くで半鐘の音が鳴り響き、空が赤く染まり始めた。
ついに、運命の日が始まってしまったのだ。
第五章 最後の残像
「来たか」
影山の視線の先、揺らめく炎の中から、それは姿を現した。
定まった形はない。人々の恐怖や悲しみを吸って凝縮した、黒い渦のような何か。それが時間泥棒の正体だった。
『素晴らしい…何度味わっても飽きぬ、最高の悲鳴、最高の絶望よ!』
人の声ではない、時間の軋みが直接脳に響く。
時間泥棒は、嘲笑うかのように桔梗に手を伸ばす。朔は刀を抜き、その前に立ちはだかった。だが、刃は空を切るだけ。実体がないのだ。
「無駄だ。それに斬れるものなどない」影山の声が響く。
斬れるものがない?
いや、ある。朔は己の能力の根源を悟った。
自分は「斬られたもの」の残像と話せる。人間だけではない。木も、石も、斬ればその記憶の断片が見えた。ならば――この世界の理そのものである「時間」を斬れば、どうなる?
「桔梗、鏡を」
朔は懐中鏡を彼女に投げ渡した。
「俺が時間を斬る。だが、それは世界の終わりを意味するかもしれん。鏡が未来を映したら、お前が選べ。繰り返す悲劇か、終わる世界か」
朔は、柄を握りしめた。己の命、魂の全てを刃に乗せる。狙うは、実体なき時間の渦の中心。全ての感情が生まれ、そして消費される、その一点。
これは、人を斬るのではない。世界そのものを斬るのだ。
「さらばだ、不条理な時の流れよ」
朔は踏み込み、渾身の一太刀を、虚空へと振り下ろした。
第六章 永遠という名の救済
世界から、音が消えた。
色が褪せ、風が止まり、燃え盛る炎はその場に凍りついた。朔の一太刀は、確かに「時間」という概念そのものを両断していた。
朔の目の前に、巨大な残像が現れた。
それは、時間泥棒の姿ではなかった。生まれてから死んでいった無数の人々の喜び、悲しみ、怒り、愛、憎しみ――ありとあらゆる感情が混ざり合った、光の奔流。斬られた「時間」そのものの残像だった。
『ありがとう』
奔流の中から、赤子のような、老人のような、無数の声が重なって聞こえた。
『これで我らも、ようやく、繰り返すことから解放される。ようやく、休めるのだ』
光の残像は、満足したように静かに消えていった。
そして、世界の時間は、完全に停止した。
人々は、その瞬間のまま永遠に固まった。逃げ惑う者、笑い合う親子、刀を構える役人。桔梗は、朔から受け取った鏡を胸に抱き、驚きと、どこか安堵したような表情で固まっている。彼女の手の中で、鏡は穏やかな光を放っていた。そこに映っていたのは、炎も悲劇もない、ただ青い空の下で穏やかに微笑む彼女自身の姿だった。彼女が選び取った未来。
朔の体も、ゆっくりと動かなくなっていく。薄れゆく意識の中、彼はこの静止した世界を見渡した。
悲劇はもう起こらない。苦しみも、悲しみも、二度と誰かを苛むことはない。
これは滅びではない。無限の苦しみからの解放。
一つの絵画のように完成された世界で、全ての存在が永遠の平和な瞬間を享受する。
朔は、静かに目を閉じた。
彼の魂がたどり着いたのは、残光が照らす刹那の果てにある、永遠という名の救済だった。