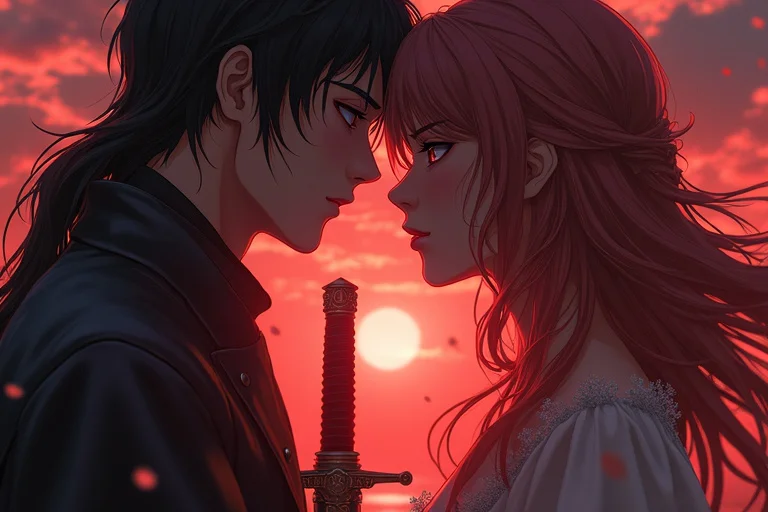第一章 硝子細工の依頼人
江戸の町、その裏路地に桐也の仕事場はあった。陽の光さえ届くのをためらうような細い路地の奥、古びた長屋の一角だ。看板も掲げていないその戸口を叩く者は、皆一様に、忘れたい過去か、あるいは手に入れたい偽りの幸福を抱えている。桐也は記憶細工師。人の記憶を抜き取り、あるいは偽りの記憶を植え付けることを生業としていた。
彼の指先から生み出される「記憶晶(きおくしょう)」は、所有者の記憶を封じ込めた硝子細工のような代物だ。喜びの記憶は陽光を浴びたように温かく輝き、悲しみの記憶は月光のように冷たく青白い光を放つ。桐也の作る偽りの記憶は精巧を極め、真実と見分けがつかぬと評判だった。だが、彼自身の心は、磨りガラスのように曇ったままだった。他人の記憶を弄ぶほどに、己の生が空虚に思えてならなかった。
ある雨の日の午後、その静寂は、場違いなほど澄んだ鈴の音に破られた。戸口に立っていたのは、上質な縮緬の着物をしっとりと濡らした一人の女だった。年は三十路手前か、その佇まいには武家の妻女が持つ凛とした気品が漂っていた。
「あなたが、記憶細工師の桐也殿でございますか」
女は静かに問うた。その声は、雨音の中でも凛と響いた。
「いかにも。だが、見ての通り、込み入った身の上の方をお相手にするような立派な店ではない。人違いでは?」
桐也は無愛想に答える。関わり合いになりたくない、という拒絶が滲んでいた。
しかし、女は動じなかった。懐から小さな絹の袋を取り出し、そっと桐也の前に置く。中から転がり出たのは、一つの記憶晶だった。それは、桐也が今まで見たこともないほどに純粋な輝きを放っていた。新緑の若葉のような、快活な少年の笑い声が聞こえてきそうな、一点の曇りもない幸福の記憶。
「これは手付けでございます」
女――小夜子と名乗った――は深く頭を下げた。
「夫に、偽りの記憶を植え付けていただきたいのです」
よくある依頼だ。桐也は興味なさそうに記憶晶を指で弾いた。
「借金で首が回らなくなったか、あるいは気に食わぬ相手を陥れたいか。どちらにせよ、俺の仕事は安くはない」
「いいえ、そのようなことではございません」。小夜子は顔を上げ、真摯な瞳で桐也を見据えた。「夫は、もう長くはないのです。せめて最期の時を、幸せな記憶の中で過ごさせてやりたいのです」
病の夫を想う妻の心。それもまた、ありふれた感傷だ。だが、続く小夜子の言葉は、桐也の心の澱みをかき乱した。
「夫に、『私と出会い、深く愛し合った』という、幸福な記憶を与えてくださいまし」
桐也の眉がかすかに動いた。おかしな話だ。目の前の女は、紛れもなく夫を深く愛している。その夫に、「妻と愛し合った記憶」を植え付ける? まるで、これまで二人の間に愛など存在しなかったかのような物言いだった。夫婦の間に横たわる冷たい溝、あるいは、桐也の知らない深い秘密の存在を、その奇妙な依頼は静かに告げていた。
第二章 空白の回廊
小夜子が差し出した記憶晶の抗いがたい魅力と、依頼に潜む謎への好奇心に負け、桐也は結局、その仕事を引き受けることにした。案内された屋敷は、大名屋敷と見紛うばかりの立派なものだった。静まり返った長い廊下を歩くたび、桐也の草履の音が冷たい板間に吸い込まれていく。どこかこの屋敷全体が、大きな記憶の抜け殻のように感じられた。
通された部屋の奥、布団の上に横たわっていたのが、夫の宗一郎だった。かつては高名な学者だったというその男は、病で痩せ衰えてはいたが、知性の光を宿した穏やかな目を持っていた。
「妻が、世話になるそうで」
宗一郎は、力なく微笑んだ。その視線が小夜子に向けられる。だが、そこに夫婦の間にあって然るべき親密な温かみはなかった。それは、献身的に世話をしてくれる者に向ける、感謝と、どこか申し訳なさの入り混じった、他人行儀な眼差しだった。
桐也は仕事に取り掛かった。小夜子から聞き取った「理想の思い出」を元に、偽りの記憶を紡ぎ始める。二人が初めて出会った桜並木。宗一郎が贈ったかんざし。雨宿りの軒下で交わした、はにかんだ会話。桐也の指先で、光の粒が寄り集まり、少しずつ形を成していく。それは、誰の目にも幸福と映る、完璧な恋物語だった。
作業の合間、桐也は小夜子の姿を目で追った。彼女は片時も宗一郎の側を離れず、汗を拭い、水を飲ませ、穏やかに語りかける。その献身は、演技ではありえなかった。深い愛情がなければ、あそこまで身を尽くすことはできないだろう。ならばなぜ。なぜ、偽りの記憶が必要なのか。
桐也は、施術のために宗一郎の記憶の深層へと意識を沈めていった。偽りの記憶を植え付けるには、まず受け入れる土壌を整えねばならない。彼の記憶の回廊を探索するうち、桐也は奇妙な事実に突き当たった。宗一郎の記憶には、不自然な空白が点在しているのだ。特に、ここ数年の記憶が酷い。それは病による混濁とは明らかに異質だった。まるで、鋭利な刃物で、ある特定の領域だけを綺麗に削り取ったかのように。
削り取られたのは、一人の女性に関する記憶だった。その痕跡は、友人との会話の断片や、旅先の風景の片隅に、亡霊のように微かに残っている。しかし、その女性の顔も、名前も、共に過ごした時間も、全てが綺麗に消え去っていた。
「この空白は…」
桐也は思わず呟いた。これは、記憶細工師の仕業だ。それも、禁忌とされる「記憶消去」の技術を持つ、相当な手練れの。
自分の仕事が、誰かの歪めた記憶の上に、さらに偽りを重ねる行為であることに、桐也は言いようのない不気味さを感じ始めていた。この屋敷に漂う空虚感の正体は、失われた誰かの記憶そのものなのかもしれない。
第三章 忘れられた細工師
施術の最終段階。桐也は完成した「小夜子との幸福な記憶晶」を宗一郎の額にかざした。硝子細工が淡い光を放ち、偽りの思い出がゆっくりと彼の意識に溶け込んでいく。その瞬間だった。
「……やめろ」
か細いが、拒絶の意思を宿した声が響いた。宗一郎の目が、うっすらと開かれていた。その瞳の奥で、激しい光が渦を巻いている。偽りの記憶の流入が、彼の心の奥底に固く閉ざされていた扉を、こじ開けてしまったのだ。
堰を切ったように、宗一郎の意識から膨大な記憶の奔流が溢れ出し、桐也の精神を激しく打ちつけた。それは、桐也が今まで触れたどんな記憶よりも、深く、悲しく、そして鮮烈だった。
溢れ出た記憶の中に、一人の女性がいた。小夜子によく似ているが、もっと陽だまりのように笑う女性。彼女の名は、小夜子の姉である「美緒」。そして彼女こそが、宗一郎が心から愛した、本当の妻だった。二人で笑い合った日々。共に研究に没頭した夜。その全てが、圧倒的な幸福感をもって桐也の中に流れ込んでくる。
そして、絶望が訪れる。不慮の事故で、美緒が命を落とす場面。宗一郎の絶叫。世界から色が失われるほどの喪失感。悲しみに耐えきれなくなった宗一郎は、自ら記憶細工師の道具を手に取った。そう、彼自身が、かつては桐也をも凌ぐほどの腕を持つ記憶細工師だったのである。彼は、愛する妻を失った苦痛から逃れるため、自らの手で「美緒に関する全ての記憶」を消し去るという、最大の禁忌を犯したのだ。
全てを理解した桐也は、愕然として小夜子を見た。彼女は、静かに涙を流していた。
「夫は…宗一郎様は、全てを忘れました。姉様のことも、姉様を愛した自分自身のことも。ですが、記憶を消しても、心に空いた穴は埋まらなかったのです。原因の分からない悲しみが、夫の体を内側から蝕んでいきました」
小夜子の依頼の真意が、ようやく桐也の胸に突き刺さった。彼女は、偽りの幸福で宗一郎を騙そうとしたのではない。失われた「愛」という感情の核を、姉の面影を持つ自分が身代わりになることで蘇らせ、彼の心を救おうとしたのだ。それは、あまりにも痛ましく、そしてあまりにも深い、愛の形だった。
「お願いです、桐也殿」と小夜子は懇願した。「どうか、このまま…。夫に、もう一度、人を愛する心を取り戻させてあげてください。たとえそれが、偽りの私を愛する記憶だとしても」
価値観が根底から揺さぶられるのを、桐也は感じていた。偽りは、悪か。真実は、善か。では、真実が人を壊し、偽りが人を救うのなら、自分はどちらを選ぶべきなのか。これまでただの「仕事」として虚しく繰り返してきた行為に、初めて重い意味がのしかかってきていた。
第四章 夜明けの記憶晶
桐也は、しばらくの間、目を閉じていた。彼の脳裏には、宗一郎が愛した美緒の笑顔と、宗一郎を救おうとする小夜子の涙が、交互に浮かんで消えた。偽りの記憶を植え付けることは、宗一郎が自ら葬った過去への冒涜かもしれない。だが、このままでは彼の魂は救われない。
「…分かった」
桐也は短く答えると、再び記憶晶を手に取った。しかし、彼の心境は以前とは全く違っていた。これはもはや、金のための仕事ではない。人の心を救うための、ただ一度きりの細工だ。
彼は、小夜子の依頼した偽りの記憶を、宗一郎の心にそっと植え付けた。だが、それは単なる物語の焼き付けではなかった。桐也は自身の技術の全てを注ぎ込み、記憶の細部に、宗一郎が本来持っていたはずの「人を慈しむ温かい感情」そのものを織り込んでいった。それは、小夜子という一人の女性への感謝と、彼女の献身に対する敬意、そして、これから共に生きていくことへの穏やかな希望。偽りの出会いの記憶を核としながらも、そこから芽生える感情は、紛れもなく新しい「本物」の種となるように。
施術を終えた桐也が屋敷を辞したのは、夜が白み始める頃だった。小夜子が見送りに来た。
「ありがとうございました」
その顔には、悲しみと、そして微かな希望が浮かんでいた。
「礼を言われる筋合いはない。仕事をしただけだ」
桐也はぶっきらぼうに言い捨てた。だが、その声にはいつもの刺々しさがないことに、彼自身が気づいていた。
数週間後、桐也のもとに、小夜子から短い文が届いた。そこには、宗一郎の病状が快方に向かっていること、そして最近、穏やかに笑うようになったことが、簡潔に記されていた。文の最後には、こうあった。
『先日、夫が庭の花を見て、これは君によく似合う、と申しました。夫が私に、そのような言葉をかけたのは初めてのことです』
桐也は文を閉じ、懐からあの手付けの記憶晶を取り出した。快活な少年の笑い声が聞こえてきそうな、美しい輝き。以前はただの高価な報酬としか思えなかったそれが、今は人の想いの尊さを伝える、かけがえのない宝物のように思えた。
偽りから始まった関係が、本物の絆へと変わっていく。失われた記憶の上に、新しい本物の時間が積み重なっていく。
桐也は記憶晶をそっと懐に戻し、窓の外を見た。雨上がりの空が、洗い流されたように澄み渡っている。
偽りの中にこそ、真実よりも切実な願いが宿ることがある。ならば、自分はこの指先で、人の心を救うための「優しい嘘」を紡いでいこう。
虚しかったはずの仕事に、初めて誇りという名の光が差したのを感じながら、桐也はまだ誰も知らない物語を紡ぐため、新しい一歩を踏み出した。その背中には、もう迷いの影はなかった。