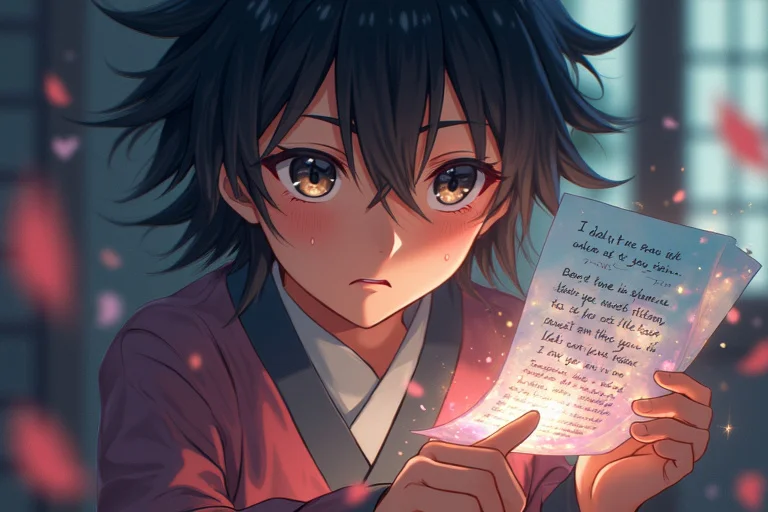第一章 偽りの伽羅(きゃら)
凛(りん)の世界は、音を失って久しい。幼い頃に患った熱病が、江戸の喧騒も、虫の音も、人の声も、彼女から永遠に奪い去った。その代わり、神は彼女に奇妙な天賦を与えた。常人には感知できぬほどの、微かな香りを嗅ぎ分ける力。それはやがて、物の記憶や人の感情すら「香り」として捉える、呪いのような祝福となった。
凛は江戸の片隅で、「聞香処(もんこうどころ)・不知火(しらぬい)」という小さな店を営んでいた。表向きは香木や香料を商う店だが、その実、失せ物を香りの記憶から探し出すといった、込み入った依頼をひっそりと受けていた。
ある雨上がりの昼下がり、店の戸口に一人の若侍が立った。上質な絹の着流しに、品の良い顔立ち。しかし、その佇まいから漂う香りは、凛の鼻を強く打った。それは、降りしきる雨に濡れた土のような、深く、純粋な「悲しみ」の香りだった。
「聞香師は、こちらにおられるか」
侍は凛の顔を見て、彼女が耳の聞こえぬことを察したらしい。懐から出した筆と硯ですらすらと文字を書き、凛の前に差し出した。
『一ノ瀬和馬と申す。尋ねてほしい香りがある』
凛は無言で頷き、彼が差し出した小さな桐の箱を受け取った。蓋を開けると、中には爪の先ほどの大きさの香木のかけらが鎮座していた。最高級の伽羅に違いない。だが、凛がそれを鼻先に寄せ、静かに息を吸い込んだ瞬間、彼女の背筋を冷たいものが走った。
立ち上るのは、確かに伽羅特有の、甘く、心を落ち着かせる優雅な香り。しかし、その奥底に、まるで美しい絹布に隠された血痕のように、異質な香りがこびりついていた。ひとつは、物が焼け焦げるような、刺すような「恐怖」。そしてもうひとつは、古びた鉄錆にも似た、冷たい「裏切り」の香り。
『これは、亡くなった許嫁の形見の香合子に入っていたものだ。病で亡くした彼女が最後に愛した香りを、もう一度…』
和馬の筆が、悲しみに震えている。だが、凛には分かってしまった。この香木が記憶している最後の情景は、穏やかな病床などではない。これは、死の恐怖に直面した者の香りだ。彼の許嫁は、何者かに裏切られ、恐怖の中で命を落としたのだ。
他人の深い闇に関わるのは、己の心を削る。凛はいつもそう自分に言い聞かせ、込み入りすぎた依頼は断ってきた。彼女は首を横に振り、箱を返そうと手を伸ばした。だが、その指先が、和馬の放つ純粋な「悲しみ」の香りに触れた気がして、動けなくなった。雨上がりの土の匂い。それは、かつて病で倒れる前の自分が、父と歩いた田圃の道を思い出させた。
凛は吸い込まれるように筆を取り、返事を書いた。
『お受けいたします。ただし、香りが語る真実は、必ずしも貴方様が望むものとは限りませぬ』
和馬は、その言葉の意味をまだ知らなかった。ただ、凛の静かな瞳の奥に、ただならぬ覚悟の色を見て、深く頷いた。
第二章 香りを辿る道
調査は、和馬が持参した許嫁・小夜(さよ)の遺品から始まった。櫛、文箱、そして彼女が詠んだ和歌の短冊。凛はそれらを一つ一つ手に取り、目を閉じて香りを吸い込む。音のない世界で、彼女の全神経は鼻先に集中する。
どの遺品からも、小夜本人の、撫子のように可憐で芯の強い香りと共に、あの伽羅と同じ「恐怖」と「裏切り」の香りがした。そして、凛はさらに新たな香りの存在に気づいた。それは、冬の乾いた風のように冷たく、刃物のような鋭さを持つ「冷酷」の香り。この香りは、小夜のものでも、和馬のものでもない。第三者の香りだ。
『小夜様は、誰かを恐れておいででした。そして、その恐怖には、冷たい悪意を持つ誰かが関わっています』
凛が筆でそう伝えると、和馬の顔から血の気が引いた。彼は小夜が病で衰弱していたとばかり信じていたのだ。
二人は小夜の身辺を辿り始めた。凛は聴覚がないため、会話はすべて筆談に頼った。音で人を判断できない彼女にとって、人の本質は「香り」でしかない。口先でどれだけ優しい言葉を並べても、心に宿る悪意は、腐臭となって彼女の鼻をつく。
和馬は、凛の不思議な能力に初めこそ戸惑っていたが、彼女が指し示す場所や人物から、確かに小夜の死にまつわる不穏な気配を感じ取るにつれ、絶対的な信頼を寄せるようになっていった。小夜が最後に訪れたという寺の庭石。彼女が薬をもらっていたという薬師の店先。凛が「ここに、あの冷たい香りが残っています」と記すたび、和馬は新たな証言や事実を掘り起こしていった。
凛にとって、それは奇妙な体験だった。これまで孤独に生きてきた。人の感情の香りは、時にあまりに生々しく、彼女を疲れさせた。だが、和馬と共にいる時間は違った。筆を介した静かな対話は、音のある世界の会話よりも、かえって深く心に沁みた。彼の側から漂う、雨上がりの土のような「悲しみ」の香りは、不思議と凛の心を穏やかにした。凛は、人を信じるという感覚を、少しずつ取り戻しかけていた。
調査は、一ノ瀬家の分家筋の男に行き着いた。男からは、欲深く、嫉妬に満ちた淀んだ香りがした。彼が小夜の死に関わっているのは間違いない。和馬は怒りに震え、男を問い詰めた。
『問い詰めても無駄です。この男は、もっと大きな悪意の駒にすぎませぬ』
凛は和馬を制した。分家の男から漂うのは、あくまで小物の香り。あの刃物のように冷たい「冷酷」の香りの主は、他にいる。
『では、一体誰が…』和馬が筆を走らせる。
凛は目を閉じ、もう一度、記憶の中の香りを辿った。小夜の恐怖、分家の男の嫉妬、そして、すべてを支配するような、あの冬の風の香り。それは常に、小夜の遺品のすぐそばに、そして和馬のすぐそばに存在していた。
その時、凛は気づいてしまった。灯台下暗し、とはこのことか。あまりに近く、あまりに純粋な香りに隠されて、見過ごしていたものに。
凛は震える手で筆を握りしめた。答えを記すことが、あまりにも恐ろしかった。
第三章 心に棲む鬼
最後の香りの在り処を確かめるため、凛は和馬に、小夜が亡くなったという一ノ瀬家の離れ座敷へ案内させた。障子を開けた瞬間、むせ返るような香りが凛を襲った。長く閉め切られた部屋の黴臭さに混じって、小夜の恐怖の香りが、悲鳴のように畳や柱に染み付いている。
そして、その中心に、ひときゅう強く、あの冷たい冬の風の香りが渦を巻いていた。
「どうだ、凛殿。何か分かるか」
和馬の声は聞こえない。だが、彼の真剣な眼差しが、答えを求めている。彼の全身からは、今も変わらず、あの純粋な「悲しみ」の香りが漂っている。雨上がりの、清浄な土の香り。
凛は、意を決して和馬の前に立った。そして、ゆっくりと彼に近づき、その着物の袖に鼻を寄せた。
和馬が驚いて身を引こうとする。だが、凛は動かなかった。
袖に染み付いていた。あの、刃物のような「冷酷」の香りが。他の誰よりも濃く、深く。それは、彼の純粋な「悲しみ」の香りの、ちょうど裏側に、ぴったりと張り付くように存在していた。まるで、一枚の布の表と裏のように。
凛は血の気が引くのを感じながら、ゆっくりと顔を上げた。そして、和馬の瞳を真っ直ぐに見つめた。
その瞬間、和馬の表情が、僅かに、しかし確かに変わった。純粋な悲しみに濡れていた瞳の奥に、すっと冷たい光が宿る。口元が、氷のような笑みの形に歪んだ。
「……気づいたか、聞香師」
声は聞こえない。だが、唇の動きと、彼の全身から放たれるようになった圧倒的な「冷酷」の香りが、その言葉を凛に伝えていた。雨上がりの土の香りは、瞬く間に冬の嵐の香りにかき消されていた。
『どう、いう…ことですか』凛は震える手で筆を走らせた。
「あの女は、知りすぎたのだ」和馬の別人格は、もはや筆を使わなかった。彼の冷たい視線が、すべてを物語っていた。「この家の実権を狙う分家の企みを、俺が潰そうとしていることに気づきおった。あの女の存在は、俺の邪魔になった。だから、消した」
凛は言葉を失った。和馬は、解離していたのだ。家の安泰と己の身を守るため、純粋で心優しい主人格の裏に、冷酷で残忍な別人格を飼っていた。小夜を手にかけたのは、この冷たい別人格。そして、許嫁を失った「悲しみ」に暮れる主人格の和馬が、何も知らずに犯人捜しを依頼してきたのだ。自らが犯人であるとも知らずに。
凛が心を動かされた「悲しみ」と、小夜を殺した「冷酷」が、同じ一つの身体に宿っている。善と悪、純粋さと残忍さが、分かちがたく結びついている。その恐ろしい現実に、凛の価値観は根底から覆された。人を「香り」で判断してきた彼女の世界が、ガラガラと音を立てて崩れていくようだった。
「さて、どうする? 真実を知ったお前も、消すべきか」
冷たい香りを放つ和馬が、一歩、凛ににじり寄った。
第四章 夜明けの白檀(びゃくだん)
絶体絶命の窮地。だが、凛の心にあったのは恐怖だけではなかった。目の前にいるのは、許嫁を殺した鬼か。それとも、ただ悲しみに暮れる一人の男か。いや、違う。その両方なのだ。
凛は懐から小さな香袋を取り出し、中から白檀の香木のかけらを取り出した。そして、部屋の隅にあった火鉢の、消えかかった炭火にそれをくべた。やがて、心を鎮める清浄な香りが、ゆっくりと部屋に満ちていく。
その香りに触れた瞬間、和馬の身体がびくりと震えた。彼の瞳から冷たい光が揺らぎ、消えていく。代わって、深い混乱と悲しみの色が戻ってきた。全身から放たれる香りも、再びあの雨上がりの土の匂いに変わっていく。
「…凛殿? いったい、何が…?」
記憶のない主人格に戻った和馬が、戸惑いの表情で凛を見つめる。
凛は、静かに彼の前に座り、筆を取った。真実を告げるべきか、否か。この純粋な魂を、絶望の淵に突き落とすことになる。だが、隠し通すことは、小夜の魂だけでなく、和馬自身の魂をも偽りの中に閉じ込めることだ。
彼女は書いた。嗅ぎ取ったすべての真実を。彼の中に、もう一人の彼がいることを。その彼が、小夜を守るためではなく、一ノ瀬家と彼自身を守るために、小夜を手にかけたことを。
『貴方様の中には、深い悲しみと、それを守ろうとする、あまりに強すぎる力が宿っている。どちらも、貴方様ご自身なのです』
和馬は、凛が差し出した紙を読み、その顔からすべての色が失われた。断片的な記憶が蘇ったのか、彼は声にならない叫びをあげ、その場に崩れ落ちた。
事件は、一ノ瀬家の内密な形で処理された。和馬は家督を弟に譲り、心の病を癒すため、遠方の寺に預けられることになった。
季節は巡り、初夏になった。ある日、凛の店に、寺から一通の文が届けられた。和馬からだった。そこには、拙いながらも心のこもった感謝の言葉と、彼が寺の庭で育てたという、一輪の白い山梔子(くちなし)の花が添えられていた。
凛は、その花をそっと鼻先に寄せた。
立ち上ってきたのは、かつてのような「悲しみ」や「冷酷」の香りではなかった。それは、甘く優しい花の香りと共に、雨上がりの土の匂いと、夜明けの澄んだ光のような、穏やかで清らかな「希望」の香りだった。
人の心は、こんなにも変わるのか。絶望の底から、こんなにも清らかな香りを放つことができるのか。
凛は、そっと窓を開けた。音のない世界に、江戸の街の無数の「香り」が流れ込んでくる。人々の喜び、悲しみ、怒り、そして希望。それらはもう、彼女にとって恐怖の対象ではなかった。自身に与えられたこの力は、人を断罪するためだけにあるのではない。人の心の奥底にある、か細い希望の香りを見つけ出し、寄り添うためにあるのかもしれない。
凛は、届けられた山梔子の花を深く吸い込んだ。その夜明けの香りは、彼女自身の未来をも、静かに照らしているようだった。