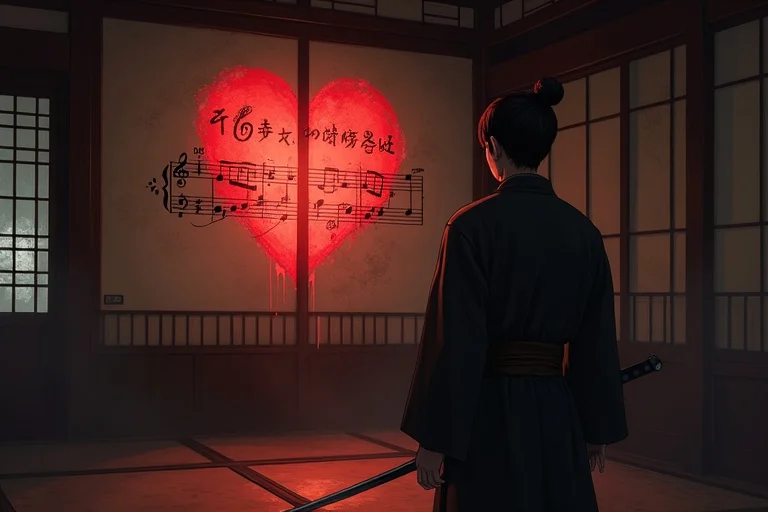第一章 墨の囁き
綴(つづり)の指先が、古びた和紙の上を滑る。インクが掠れた繊細な筆跡。それをなぞる瞬間、彼の意識は紙の記憶へと沈み込んでいく。ふわりと鼻をかすめる白粉の香り、絹ずれの微かな音、そして胸を焦がすような切ない恋慕。綴は、百年前に生きた名もなき女性の、秘められた恋情を追体験していた。
「……見つかるといいな、あなたの想い人」
小さく呟き、指を離す。途端に、現実の古書店の黴とインクの匂いが彼を引き戻した。追体験の反動で、心臓が氷水に浸されたように小さく痛む。これが彼の能力であり、呪いであった。あらゆる『筆跡』は、彼にとって過去への扉なのだ。
店の呼び鈴が、乾いた音を立てた。入ってきたのは、上質な外套を纏った男、晄(こう)だった。彼の肌には、一点の『血の滲み』もない。それは、彼が一度たりとも己の言葉を違えたことのない、稀有な人間であることを示していた。
「また厄介ごとか」
綴が問うと、晄は硬い表情で頷いた。
「街が、病んでいる」
彼の視線は窓の外、雑踏へと向けられる。道行く人々の多くが、手首や首筋に刻まれた『血の滲み』を、スカーフや包帯で隠していた。本来、それは破られた約束の証、社会的な烙印のはずだった。だが、今やその数は異常だった。
「『血の滲み』を持つ者が、この一月で三倍に増えた。社会の信頼構造が、根底から崩れ始めている。原因を突き止めてほしい」
晄の言葉には、視覚化されずともわかる重さがあった。綴は窓の外に広がる灰色の空を見上げ、深く息を吐いた。街全体が、声なき悲鳴を上げているようだった。
第二章 流行る言葉、蝕む肌
調査を始め、綴はすぐに奇妙な事実に突き当たった。新たに『血の滲み』を刻んだ人々のほとんどが、同じ一つの約束を破っていたのだ。
「明日、必ず会おう」
恋人、友人、家族。誰もが口にする、ありふれた言葉。だが、この言葉が異様なまでに流行し、そしていとも簡単に破られていた。急な仕事、体調不良、あるいは単なる寝坊。些細な理由で約束は反故にされ、人々の肌に癒えぬ傷を刻んでいく。
綴は雑踏の中、腕に真新しい『血の滲み』を刻んだ少女を見つけた。滲みはまだ生々しく、まるで泣いているように見えた。彼は声をかけ、その筆跡を辿らせてほしいと頼んだ。少女は怯えたように彼を睨みつけ、人混みへと逃げていった。
その時、風に舞った一枚のメモが綴の足元に落ちた。そこには、少女のものと思しき拙い文字で、こう書かれていた。
『明日、必ず会おうね。駅前のカフェで』
綴はそれを拾い上げ、躊躇いの後、指でそっとその筆跡をなぞった。
瞬間、世界が反転する。
カフェの甘い珈琲の香り。友人を待つ、弾むような期待。しかし、待てど暮らせど友人は現れない。携帯端末に届く、短い謝罪のメッセージ。裏切られたというほどの怒りではない。ただ、ちくりと胸を刺す小さな失望。その感情が、彼女の肌に約束の言葉を墨絵として浮かび上がらせ、そして、破られた瞬間にじわりと血を滲ませる様を、綴は五感で体験した。
「ぐっ……!」
反動が、これまでになく強烈な偏頭痛となって綴を襲う。たったこれだけの、軽い約束の反故で、なぜこれほどの苦痛が? この現象の裏には、個人の感情を遥かに超えた、巨大な何かが渦巻いている。綴は確信した。
第三章 終焉の筆
調査は壁にぶつかった。あまりに多くの人々が、あまりに無自覚に約束を破り、その筆跡は拡散しすぎていた。源流を辿ることなど不可能に思えた。追い詰められた綴に、晄は禁忌の存在を打ち明けた。
「『終焉の筆』と呼ばれる遺物がある」
彼の声は、古い聖堂の静寂の中で低く響いた。
「持つ者の記憶と命を喰らう代償に、この世の全ての『血の滲み』の根源を映し出すという。政府が厳重に封印してきたが……もはや、これに頼るしか道はないかもしれん」
綴は、聖堂の奥に安置された黒檀の箱を見つめた。それを開けることは、自らの過去と未来を天秤にかけることに等しい。だが、街を覆う無数の嘆き、理由もわからず罪人の烙印を押された人々の顔が脳裏をよぎる。彼は、この連鎖を断ち切らねばならないという使命感に駆られていた。
「開けてくれ」
綴の決意に、晄は静かに頷いた。
箱が開けられ、中から現れたのは、星の光を吸い込んだ夜のような、漆黒の筆だった。綴がそれを手に取った瞬間、指先から生命力が吸い上げられるような凍てつく感覚が全身を駆け巡った。脳裏に、過去の所有者たちが味わったであろう、無数の絶望と後悔が濁流のように流れ込んでくる。彼は歯を食いしばり、その激痛に耐えた。
第四章 逆再生される真実
街の中心に位置する、古の広場。綴は、その中央に立ち、『終焉の筆』を天に掲げた。筆は彼の意志とは無関係に震え始め、彼の記憶をインク代わりに、虚空へと巨大な墨絵を描き始めた。
街中の人々の『血の滲み』が、一斉に熱を帯びて共鳴する。広場に集まった人々は、自らの腕や首筋に起きた異変に驚き、空を見上げた。
空に描かれた墨絵は、無数の光景を逆再生し始めた。
「明日、必ず会おう」という約束が破られた、数えきれない瞬間。友人との諍い。恋人の涙。家族の失望。それらの光景が目まぐるしく遡り、やがて、その言葉が人々の間で流行り始めた頃の映像へと辿り着く。
さらに時間は遡る。全ての元凶となった、最初の筆跡へ。
光景は、街を見下ろす丘の上に立つ、寂れた天文台へと移った。月明かりだけが差し込むドームの中で、一人の人物が祈るように、震える手で羊皮紙に言葉を書き記している。その人物の横顔は、悲痛な覚悟に満ちていた。
第五章 星詠みの犠牲
次の瞬間、綴の脳内に流れ込んできたのは、過去ではなく未来の光景だった。
数年後の、まさにこの街。大地が裂け、建物が崩れ落ちる、未曾有の大災害。その地獄絵図の中で、人々が交わした『最後の約束』が、死によって無慈悲に引き裂かれていく。
『必ず助けに行く』と叫んだ消防士。
『無事に帰ってきて』と祈った妻。
『明日、ここで必ず会おう』と誓った恋人たち。
それら全ての重い約束が破られ、世界は絶望の『血の滲み』で完全に覆い尽くされる。破局の未来。
その未来を予見したのが、天文台にいた人物――忘れられた一族の末裔、『星詠み』の詠(よみ)だった。
詠は、その絶望的な未来の因果を断ち切るために、たった一人で途方もない計画を実行したのだ。未来で破られるはずだった数多の『重い約束』の連鎖。その中心にあったのが、災害の日に最も多く交わされる『明日、必ず会おう』という言葉だった。
詠は、その言葉の『重さ』を、未来から現在へと分散させることを選んだ。あえて人々が簡単に破ってしまう『軽い偽りの約束』として、この言葉を意図的に流行させたのだ。
些細な理由で破られた無数の約束。その一つ一つが、未来で死と共に刻まれるはずだった絶望の『血の滲み』を肩代わりしていた。今、街に蔓延する夥しい数の『血の滲み』は、陰謀の証などではない。未来の破滅から人々を救うために捧げられた、『犠牲の印』だったのだ。
綴は、詠の孤独な覚悟と、その深すぎる慈愛を追体験し、声もなく嗚咽した。
第六章 言葉の墓守
全ての真実が、奔流となって綴の精神を駆け抜けた。その代償として、『終焉の筆』は彼の記憶をほとんど喰らい尽くし、その黒い軸には彼の生命そのものが吸収されていくのが分かった。
「綴、何が見えたのだ!」
駆け寄ってきた晄が、彼の肩を掴む。
綴には、二つの道が残されていた。真実を語り、詠を救世主として世界に知らしめるか。それとも、人々が救われたという事実だけを胸に秘め、失われかけた『言葉の信頼』という社会秩序を守るために、全てを曖昧なまま終わらせるか。
綴は、広場にいる人々を見渡した。彼らの肌には、理由も知らぬまま刻まれた罪の印がある。だが、彼らは生きている。愛する人と共に、明日を迎えることができる。
詠が守りたかったのは、人々の命であり、その未来だった。ならば、言葉の信頼が失われたと嘆くこの世界もまた、彼女が救った世界の一部なのだ。
綴は、弱々しく、しかし確かな意志を持って微笑んだ。
「……言葉は、時に嘘をつく」
彼の声は、風に消え入りそうなほどか細い。
「けれど、その嘘が……命を繋ぐこともあるんだ」
彼は真実を語らないことを選んだ。晄に『終焉の筆』を渡すことなく、自らの掌中で固く握りしめる。詠の犠牲と、その嘘を、自分が最後の墓守として背負っていく。
『終焉の筆』が、最後の輝きと共に綴の手の中で塵と化した。彼の記憶と、命の残滓を道連れにして。
綴の肌には、もう一つの約束も、一つの血の滲みも残ってはいなかった。ただ、全てを赦すかのような深い静寂だけが、彼を包んでいた。
夜空を見上げると、ひときわ強く瞬く星が一つ。それはまるで、誰かの涙のように、この世界の真実を静かに見つめているようだった。