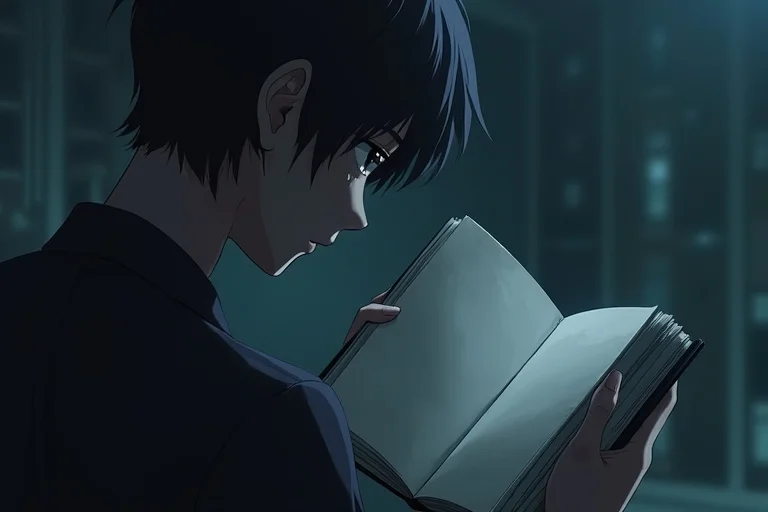第一章 曇りガラスと剥がれた影
橘蓮(たちばな れん)の世界は、常に二重写しだった。古書店のカウンターに座り、インクと古紙の匂いに満たされた静寂の中でページを繰っていても、彼の視界の隅では、常にあり得たはずの未来が明滅していた。
それは、他人の『決断の瞬間』に付随する呪いのような能力。しかし、彼が視るのは常に『選択されなかった未来』の断片。客が手に取った本を買うか買うまいか迷う。男が決断を下し、本を棚に戻す。その瞬間、蓮の脳裏には、男がその本を買い、書斎で夢中になって読み耽り、やがてその一冊が彼の人生を大きく変えることになる、という鮮やかな光景が一瞬だけ映し出されるのだ。だが現実は、男が何も得ずに店を出ていくだけ。蓮に残るのは、実現しなかった幸福の残像と、どうしようもない無力感だけだった。
この世界には、もう一つの奇妙な法則がある。嘘をついた者からは、その影が剥がれ落ちる。それは罪の意識のように地面に染みつくのではなく、まるで意思を持った生き物のように自立して動き出すのだ。街はそんな無数の影たちで溢れていた。持ち主の感情の澱を映したかのように淀んだ黒い人型は、目的もなく彷徨い、時に悪戯をし、時に誰かの孤独に寄り添うように佇む。
蓮はカウンターの隅に置かれた、曇ったガラス球に目をやった。彼の能力の源泉なのか、あるいは観測装置なのか、今となっては分からない。かつては水晶のように透明だったはずのそれは、今や世界中の嘘から生まれた影たちが内部で渦巻き、不気味な灰色に濁っている。
ふと、ガラス球の内部で影の渦が激しくなった。蓮が思わず手を伸ばすと、ひやりとした感触と共に、脳髄を焼くようなビジョンが流れ込んできた。
――炎。燃え盛るビル。崩れ落ちる高架橋。絶望の叫び。
それは、彼が今まで視たことのない、誰の『決断』にも紐づかない、あまりにも鮮烈な破滅の光景だった。そして蓮は気づいていた。最近、街を彷徨う影たちが、まるで何かに引き寄せられるように、皆同じ方角へ、静かに、しかし着実に流れ始めていることを。ガラス球が映した破滅と、影たちの行進は、果たして無関係なのだろうか。古書の乾いた匂いが、不意に焦げ臭い幻嗅へと変わった気がした。
第二章 天文台に集うもの
影たちの流れは、一つの奔流となって街の中心へと向かっていた。蓮は店を閉め、その黒い川の流れを追った。行き着いた先は、開発から取り残された丘の上に立つ、古びた天文台の跡地だった。ドームの白亜は汚れ、観測窓は虚ろに空を睨んでいる。
「あなたも、彼らに呼ばれたの?」
背後からの声に、蓮は息を飲んだ。振り返ると、観測機器の残骸に腰かけた一人の女性がいた。水無月澪(みなづき みお)と名乗った彼女は、影の研究者だという。その瞳は、夜空の星を探すように、純粋な好奇心に満ちていた。
「呼ばれた、というよりは…気になっただけです」
蓮は曖昧に答えた。自分の能力を他人に話したことはない。
「そう? でも、あなたの目、何かを知っている人の目をしてる」
澪は屈託なく笑うと、手にしたタブレットを彼に見せた。画面には、世界地図の上に無数の光点がプロットされ、そのすべてが特定の座標へと収束していく様子が示されている。「世界中の影が、まるで示し合わせたように、各地の『特異点』に集結しているの。ここは、その一つ」
天文台の広場には、既に数え切れないほどの影が集まっていた。彼らは風に揺れる陽炎のように輪郭を震わせながら、静かに、ただそこに在る。それは異様で、どこか神聖さすら感じさせる光景だった。
「彼らは、何かをしようとしている」澪の声が、夜の静寂に響く。「何かを…再現しようとしているのよ。忘れられた、あるいは、起こらなかったはずの何かを」
その言葉が、蓮の胸に突き刺さった。起こらなかったはずの何か。それは、彼が毎日見続けている『選ばれなかった未来』そのものではないか。影たちが再現しようとしているものが、もし自分の視るビジョンと繋がっているとしたら。蓮は、ポケットの中の曇ったガラス球を、無意識に強く握りしめていた。
第三章 偽りの街景
数日が過ぎ、変化はより顕著になった。天文台に集まった影たちは、ただ佇むのをやめ、ゆっくりと動き始めた。彼らは互いに寄り集まり、融合し、一つの巨大な幻影を形作っていく。
それは、蓮がガラス球で垣間見た、あの破滅の光景だった。
歪んだ鉄骨。黒煙を上げるビルの残骸。地面に穿たれた巨大な亀裂。すべてが影で出来た、音のないジオラマだ。しかし、その精巧さと禍々しさは、現実と見紛うほどだった。人々はこの異常事態に気づき始めていたが、実害がないせいか、ただの集団芸術か何かだと遠巻きに眺めているだけだった。だが蓮には分かった。これは警告だ。あるいは、予行演習だ。
「どうして…」蓮は、隣で観測を続ける澪に呟いた。「どうして、こんな光景を…」
「これは『大崩落』の光景よ」澪は静かに答えた。「十年前、世界を滅ぼしかけた大災害。でも、公式記録では、奇跡的に被害は最小限に食い止められたことになっている」
「じゃあ、この光景は…」
「誰かの空想? いいえ、違う」澪は蓮を真っ直ぐに見つめた。「影が再現しているのは、蓮さん、あなたが視るような『選ばれなかった未来』の断片なの。世界中の人々が無意識に捨て去った、無数の可能性の瓦礫。それが集まって、この『あり得たかもしれない破滅』を形作っている」
世界が、選択されなかった未来に侵食されていく。その悍ましい事実に、蓮は眩暈を覚えた。自分の呪われた能力が、世界の崩壊と地続きになっている。その事実は、彼の孤独な心をさらに深く抉った。影が作り出した偽りの廃墟の向こうに、人々が日常を送る本物の街並みが見える。二つの風景の境界線が、今にも溶けて混ざり合ってしまいそうだった。
第四章 世界という名の嘘
「真実を知りたければ、ついてきて」
澪はそう言うと、蓮を街の外れにある彼女の研究所へと導いた。そこは古い倉庫を改造した場所で、壁一面のモニターには、世界各地の『特異点』の様子が映し出されていた。天文台と同じように、影たちが各地で破滅の光景を再現している。
「『大崩落』は、食い止められてなんかいなかった」
澪は、中央のメインスクリーンに一枚の衛星写真を映し出した。それは十年前のもので、大陸の一部が大きく抉り取られ、黒く変色している。蓮が息を飲む。こんな事実は、歴史のどこにも記録されていない。
「世界はあの日、一度終わるはずだった。でも、そうならなかった。なぜだと思う?」
彼女は蓮に向き直り、静かに、しかしはっきりとした声で言った。
「世界が、巨大な『嘘』をついたからよ。『大崩落は起こらなかった』。その嘘を、生き残った全人類が共有することで、この世界は存続したの」
その言葉が放たれた瞬間、澪の足元から、するりと彼女の影が剥がれ落ちた。それは、彼女が嘘をついた証。しかし、彼女の瞳は真実の光を宿していた。世界を救うために、真実を語るという矛盾。その行為が、影を分離させたのだ。
「そんな、馬鹿な…」
「最大の嘘は、最も多くの影を生む。世界そのものがついた嘘は、世界の影を剥がしたのよ。今、集まっているのはその欠片」
蓮の頭が混乱で爆発しそうだった。彼がポケットから取り出したガラス球が、呼応するように熱を帯び、激しく明滅を始めた。蓮はそれに両手で触れる。次の瞬間、奔流のような映像と記憶が、彼の意識を飲み込んでいった。
――十年前。瓦礫の山の中、泣きじゃくる幼い自分がいた。そして、目の前には二つの道が見えていた。暴走した彼の能力が映し出した、二つの世界の未来。
第五章 十年前の選択
記憶の洪水の中で、蓮はすべてを思い出した。
十年前、『大崩落』は確かに起きた。世界は修復不可能なほどに破壊され、人類は滅びの瀬戸際に立たされていた。その絶望の只中で、幼い蓮の能力が覚醒し、暴走した。
彼は視たのだ。二つの、たった二つだけの未来を。
一つは、『真実の未来』。世界の崩壊を受け入れ、瓦礫の中から、生き残った者たちが新たな文明を、全く新しい価値観を、ゼロから築き上げていく未来。それは過酷で、多くの犠牲を伴うが、その先には本物の再生が待っている。
もう一つは、『偽りの未来』。『大崩落は起こらなかった』という巨大な嘘で現実を上書きし、人々が何も知らずに、表面的な平和を享受し続ける未来。傷は癒えず、世界の根幹は腐ったまま、緩やかに停滞し、やがて静かに窒息していく。
幼い蓮は、目の前の惨状と、これから訪れるであろう苦難の未来に耐えられなかった。彼は恐怖に駆られ、泣きながら後者を選んでしまったのだ。
「嫌だ…! みんな、元通りにしてよ…!」
その幼い決断が、世界の運命を決定づけた。世界は彼の選択に応え、『大崩落は起こらなかった』という巨大な嘘で自らを糊塗した。その瞬間に剥がれ落ちた世界の巨大な影が、今、破滅の光景を再現することで、蓮に忘れられた真実を突きつけ、選択のやり直しを迫っているのだ。
天文台に集う影たちは、悪意の集合体ではなかった。彼らは、蓮が捨てた『真実の未来』の残響。忘れられた世界の、声なき叫びだった。ガラス球の中で渦巻いていたのは、無数の嘘の影であると同時に、蓮自身が捨てた、たった一つの真実の欠片でもあったのだ。
第六章 真実の破滅、偽りの救済
蓮と澪が天文台に戻ると、影たちが作り上げた破滅の光景は、ほぼ完成に近づいていた。それはもはや幻影ではなく、確かな実感を伴ってそこに存在していた。影でできたビルの瓦礫に触れると、ざらりとした冷たい感触さえある。現実が、非現実に侵食され、境界が溶け出している。
「このままでは、嘘で塗り固められた世界は重みに耐えきれず、今度こそ本当に崩壊する」澪の声は、切迫していた。「影たちは、そうなる前に『真実』を思い出せと、警告しているのよ」
見上げると、影の廃墟の中心に、微かな光が灯っているのが見えた。それは破滅の炎ではなく、闇夜に咲く一輪の花のように、儚くも力強い希望の光。あれこそが、蓮が十年前に捨てた『真実の未来』の種子なのだろう。破滅の先にある、本物の再生の可能性。
偽りの救済の中で緩やかに死ぬか。真実の破滅を受け入れ、再生に賭けるか。
蓮の手の中のガラス球が、心臓のように脈動し始めた。内部の影が静まり、中央に一点の光が灯る。選択の時が来たことを告げていた。十年前、恐怖から逃げ出した幼い自分。その決断が、この歪んだ世界を生み出した。
「どうすれば…」
蓮の震える声に、澪は静かに答えた。
「選ぶのは、あなたよ。あなたがこの世界を創ったのだから」
脳裏に、偽りの平和の中で何も知らずに笑う人々の顔が浮かぶ。彼らの日常を、この手で終わらせるのか。だが、その平和が、やがて訪れる完全な崩壊までの、つかの間の猶予でしかないとしたら? 蓮は唇を噛みしめ、天を仰いだ。影が作り出した偽りの空は、星もなく、ただどこまでも暗かった。
第七章 夜明けの決断
蓮は、天文台のドームの頂上へと続く、錆びた螺旋階段を駆け上がった。偽りの街並みと、影が作り出す真実の廃墟、その両方を見渡せる場所。風が彼の髪を揺らし、世界の行く末を問うように囁きかける。
彼は脈打つガラス球を、両手で空に掲げた。
「僕は――」
彼がどちらの未来を選んだのか、その言葉を澪が聞くことはなかった。ただ、蓮が決断を下した瞬間、ガラス球から放たれた光が世界を白く染め上げた。影たちが一斉にその動きを止め、音もなく霧散していく。そして、彼らが作り上げていた破滅の光景もまた、夜明けの光に溶けるように消えていった。
気がつくと、蓮はいつもの古書店のカウンターに立っていた。窓から差し込む朝日は、昨日までの光とどこか違って見えた。街の喧騒が耳に届く。それは変わらない日常の音のはずなのに、そこには新しい響きが満ちているように感じられた。
彼の隣には、澪が立っていた。剥がれた影としてではなく、確かな実体を持った人間として、彼女はそこにいた。
「これから、大変ね」
その言葉が、どちらの未来を選んだ結果なのか、蓮だけが知っている。彼は静かに頷いた。
「ああ。でも、今度は一人じゃない」
カウンターの上で、ガラス球が静かに光を放っていた。厚く覆っていた曇りは晴れ、その内側には、かすかな透明感が戻り始めている。もはや二者択一の未来ではない。そこには、これから二人が紡いでいく、無数のきらめく可能性が、まるで星空のように揺らめいていた。世界は、新たな朝を迎えたのだ。