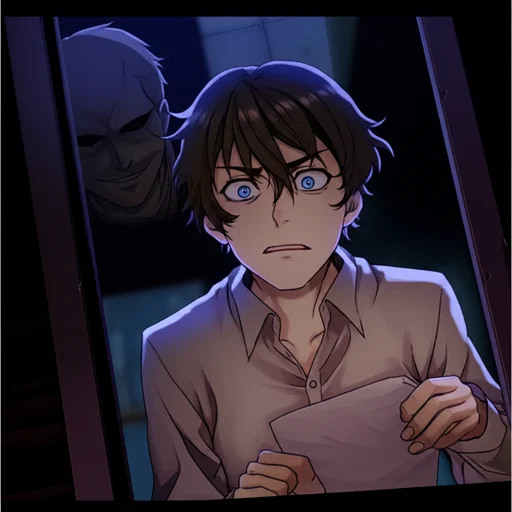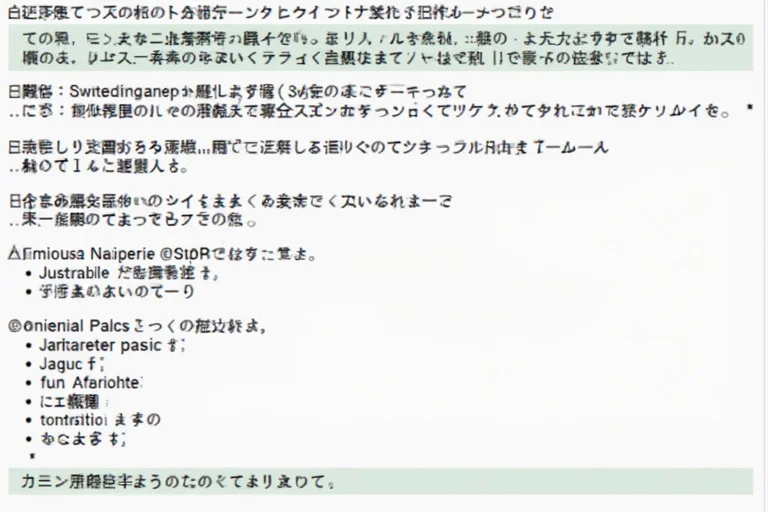第一章 色めくノイズ
俺、灰音(かいね)の世界は、他人の感情で彩られている。怒りは街路を焦がす深紅に、歓喜はビルの窓を濡らす黄金色に、そして深い悲しみはアスファルトに染み込む藍色に。人々が心を揺らすその瞬間だけ、俺のモノクロームの視界に色が灯る。自身の感情は常に無彩色のままで、心が凪いでいる時の世界は、古いフィルム映画のように色褪せていた。
だから、俺は雑踏を求める。渋谷のスクランブル交差点。ここは感情の奔流だ。苛立ちの緋色、期待の萌黄色、恋慕の桜色が混ざり合い、視界の中で暴力的なまでに美しいシンフォニーを奏でる。しかし、色彩には代償が伴った。この世界には、生物が発したあらゆる『囁き』が、物理的な残響となって蓄積されている。都市は、その見えざる残響の海だ。俺の耳には、絶えずガラスの破片が擦れ合うような高音が突き刺さり、人々の無意識の呟きが幻聴となって渦巻いていた。色を見るために、俺はこの耳鳴りを甘んじて受け入れるしかなかった。
その日も、俺は色の洪水と囁きのノイズに身を浸していた。ふと、視界の片隅で色が抜け落ちるのを見た。鮮やかな期待の色を放っていた若い男から、ふっと色が消えたのだ。まるで、絵の具を水で洗い流したかのように。それだけではない。彼を中心に、半径数メートルの空間から、あれほどけたたましかった『囁きの残響』が嘘のように消え失せ、耳を圧迫するような完全な沈黙が生まれていた。男は、ただ虚ろな目で宙を見つめ、ゆっくりと雑踏の中に崩れ落ちた。彼の周りだけが、ぽっかりと切り取られた無音と無色の空間になっていた。それが、世界が沈黙へ向かう最初の兆候だった。
第二章 消えゆく残響
『沈黙の現象』は、静かに、だが確実に広がっていった。新聞はそれを「突発性無気力症候群」と名付けたが、誰もその本質を理解してはいなかった。被害者は感情も、直近の記憶さえも失い、ただ呼吸するだけの抜け殻になる。そして、彼らがいた場所からは、例外なく色と囁きの残響が消え失せた。
俺にとって、それは世界の死を意味した。日に日に街から色が失われ、俺の視界は色褪せた灰色に侵食されていく。かつては苦痛でしかなかった囁きのノイズも、今ではその不在が恐怖だった。静寂は安らぎではなく、虚無の象徴として俺にのしかかる。このままでは、俺の世界は完全なモノクロームと沈黙に閉ざされてしまう。俺という存在そのものが、意味を失ってしまう。
俺は現象の調査に乗り出した。被害者の共通点を探し、事件現場を訪ね歩く。だが、そこに法則性は見当たらない。ただ一つだけ、どの現場にも共通する奇妙な感覚があった。それは、あまりに完璧すぎる静寂がもたらす、肌を撫でるような冷たい空気。まるで、世界の基盤そのものが一枚、綺麗に削ぎ取られてしまったかのような、根源的な喪失感だった。俺は、この現象を引き起こしている「何か」に、言い知れぬ憎悪と、そして微かな既視感を覚えていた。
第三章 螺鈿の導き
雨の夜だった。現象の調査に行き詰まり、冷たいアスファルトに滲むネオンの反射を眺めていると、背後に人の気配がした。振り向くと、そこに一人の男が立っていた。歳は俺と同じくらいだろうか。黒いコートに身を包み、その顔には深い疲労と諦観が刻まれている。奇妙なことに、彼からは一切の感情の色が感じられなかった。モノクロームの俺と同じ、無彩色の存在。
「お前が原因だ」
男は静かに言った。その声は、囁きの残響の中でも奇妙なほどはっきりと俺の耳に届いた。
「何の話だ」
「この『沈黙』は、お前の願いが引き起こしている。お前は、この世界の色彩と騒音に耐えきれなくなったんだ」
男の言葉は、俺の心の最も深い部分を抉った。否定したかった。だが、心のどこかで、彼の言葉が真実だと告げている気がした。
「お前を止めに来た」男は続けた。「お前の混沌を鎮める鍵がある。『無音の螺鈿細工』。それを見つけろ。だが、決して開いてはならない。それは最後の希望であり、同時に最悪の絶望だ」
男はそれだけ言うと、雑踏の中に姿を消した。彼がいた場所には、雨の匂いだけが残されていた。俺は、男が現象の犯人なのだと直感した。俺を混乱させ、何かを企んでいるに違いない。螺鈿細工を見つけ出し、この悪夢を終わらせる。俺は固く決意した。
第四章 虚無の色彩
男の残した曖昧なヒントを頼りに、俺は寂れた骨董品店で『無音の螺鈿細工』を見つけ出した。それは、手のひらに収まるほどの小さな小箱だった。光を吸い込むような漆黒の地に、青白い螺鈿が渦を巻いている。手に取ると、驚くほど冷たく、そして一切の音を発しなかった。この世界のあらゆる物質が持つはずの、微細な存在の響きすら、それにはなかった。
俺は螺鈿細工を手に、男を追い詰めた。再開発で打ち捨てられた、巨大な工場の最上階。窓の外では、また色が失われた街が静かに沈黙を広げている。
「お前の仕業だな」俺は螺鈿細工を男に突きつけた。「これをどうするつもりだった?」
男は悲しげに首を振った。「言ったはずだ。それを開いてはならない、と。それは、お前の願いを増幅するだけの装置だ」
「黙れ!」
俺は叫んだ。現象を止めたい。失われた色を取り戻したい。俺自身の存在意義を取り戻したい。その一心で、俺は螺鈿細工の蓋に指をかけた。
「やめろ!」
男の悲痛な叫びも、もう俺には届かなかった。
カチリ、と小さな感触。蓋が開いた瞬間、世界から一切の音が消えた。囁きの残響も、風の音も、俺自身の心臓の鼓動さえも。そして、螺鈿細工の中から、眩いばかりの『純白の光』が溢れ出した。それは何色でもない、全ての色を拒絶し、全てを無に帰すための、虚無の色だった。俺が心の底で、無意識に渇望し続けていた、完全な平穏の色。
その光は、俺の根源的な感情の色だったのだ。
光が広がると同時に、男の姿が急速に薄れ始めた。彼の足元から、まるで砂のように崩れていく。俺の視界も、男も、この世界そのものも、圧倒的な虚無感と共に純白に塗りつぶされていった。
第五章 未来からの警告
「……やはり、同じ過ちを繰り返すのか」
消えゆく男の声が、思考に直接響いた。見ると、彼の顔は俺の顔と瓜二つになっていた。深い絶望と後悔に歪んだ、未来の俺自身の顔。
「お前は……俺か?」
「ああ」未来の俺は、薄れゆく体で頷いた。「俺は、この過ちを犯した未来のお前だ。世界から色と音を奪い尽くし、完全な虚無の中で永遠の孤独を生きる羽目になった。だから、時を超えてお前を止めに来たんだ」
彼の言葉が、雷のように俺を撃った。
「俺は、世界のあまりの色彩と騒音に疲弊しきっていた。心の底で、静寂と無色を願った。その強すぎる願いが、この能力と結びつき、周囲の感情と残響を吸収し始めたんだ。被害者たちは……俺が望んだ『平穏』の犠牲者だった」
螺鈿細工は、その願いを暴走させるための引き金だったのだ。敵だと思っていた男は、暴走を止めようとしてくれた唯一の存在だった。
「もう時間が無い」未来の俺の姿が、ほとんど透けて見えなくなっていた。「お前が螺鈿を開いたことで、俺の存在が……この時間軸から消える。灰音……選択しろ。このまま世界を白紙に戻すか、それとも……」
彼の言葉はそこで途切れ、光の粒子となって霧散した。後には、ただ完全な沈黙と、純白に染まった世界だけが残された。
第六章 選択
真実の重みに、俺は膝から崩れ落ちた。俺が犯人だった。俺の弱さが、世界を殺していた。手の中にある螺鈿細工が、全ての元凶であり、そして唯一の解決策だった。このままこの力を解き放てば、俺が望んだ完全な沈黙と平穏が手に入る。もう、他人の感情に振り回されることも、囁きのノイズに苦しむこともない。それは、ある種の救済かもしれなかった。
だが、その代償は、あまりに大きい。色とりどりの感情も、生命の証である囁きも、全てが失われる。未来の俺が味わったという、永遠の孤独。それは、俺が本当に望んだものなのだろうか。
俺は、失われた人々を思った。虚ろな目で宙を見つめていた彼らの顔が、脳裏に焼き付いている。彼らは、俺の身勝手な願いの犠牲者だ。
俺は螺鈿細工を強く握りしめる。冷たい感触が、俺の心に問いかけてくる。
お前は、何を選ぶ?
虚無の安らぎか、それとも混沌の生か。
第七章 囁きの海へ
俺は、ゆっくりと螺鈿細工の蓋を閉じた。カチリ、という音はしなかった。ただ、俺の決意だけが、そこに形として残った。溢れ出していた純白の光がすうっと螺鈿細工の中に吸い込まれていくと、世界にゆっくりと音が戻ってきた。まだ色は戻らない。俺の視界は、相変わらずモノクロームのままだった。
俺はもう、他者の色に依存しない。自分の内側にあるこの灰色の世界と、正面から向き合うことを決めた。この虚無感も、孤独も、全て俺自身の一部なのだ。
俺は工場を後にし、都市の雑踏へと戻った。囁きの残響が、再び俺の耳を満たす。以前はあれほど苦痛だったノイズが、今は不思議と、生きている世界の鼓動のように感じられた。人々が放つ感情の色はまだ見えない。だが、それでいい。いつか、俺自身の力で、俺だけの色を見つけ出す。それが、俺が犯した罪に対する、唯一の償いなのだから。
人混みの中、俺は一歩を踏み出す。行き交う人々の熱気、湿ったアスファルトの匂い、そして絶え間なく響く生命の囁き。混沌としたこの世界で、俺の旅が、今、始まった。俺の瞳はまだ世界をモノクロームに映している。だが、その奥には、以前にはなかった確かな意志の光が、静かに灯っていた。