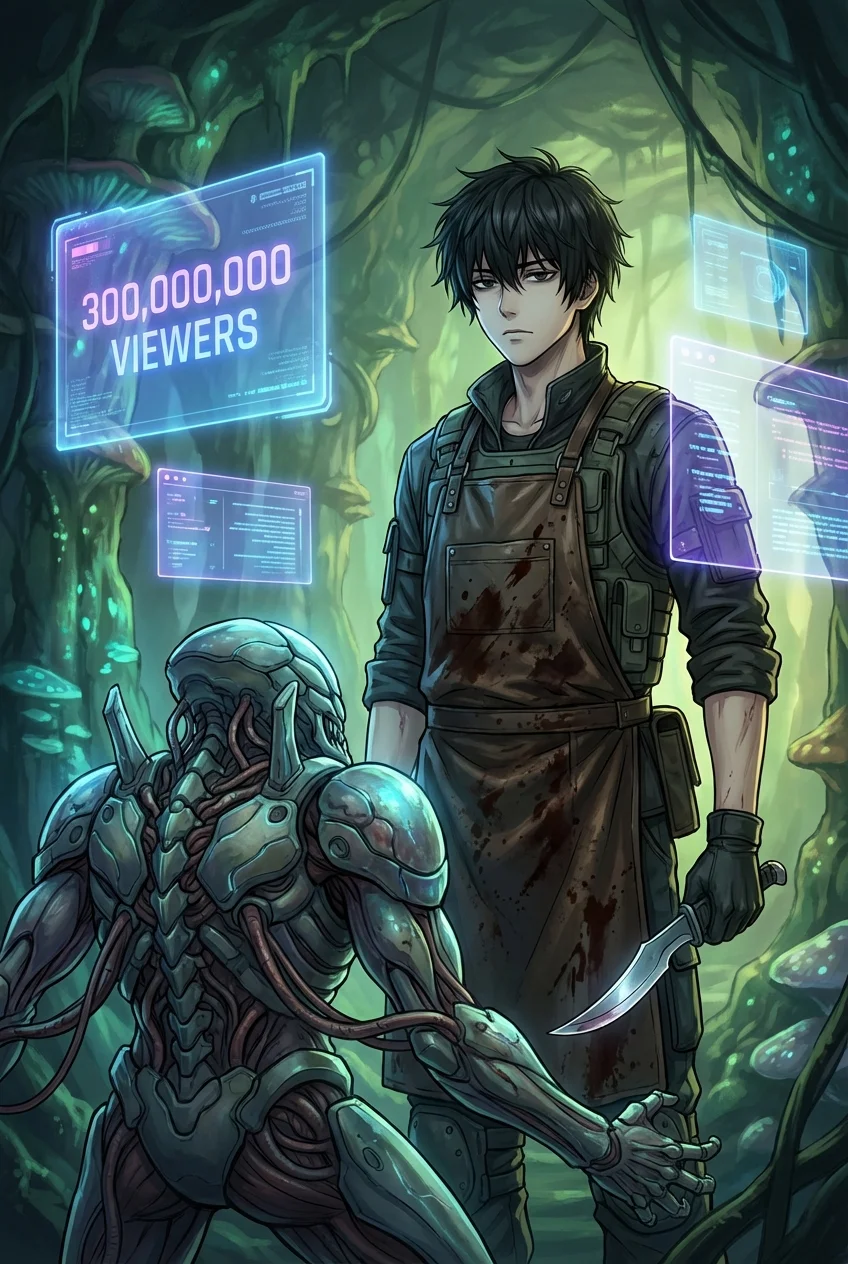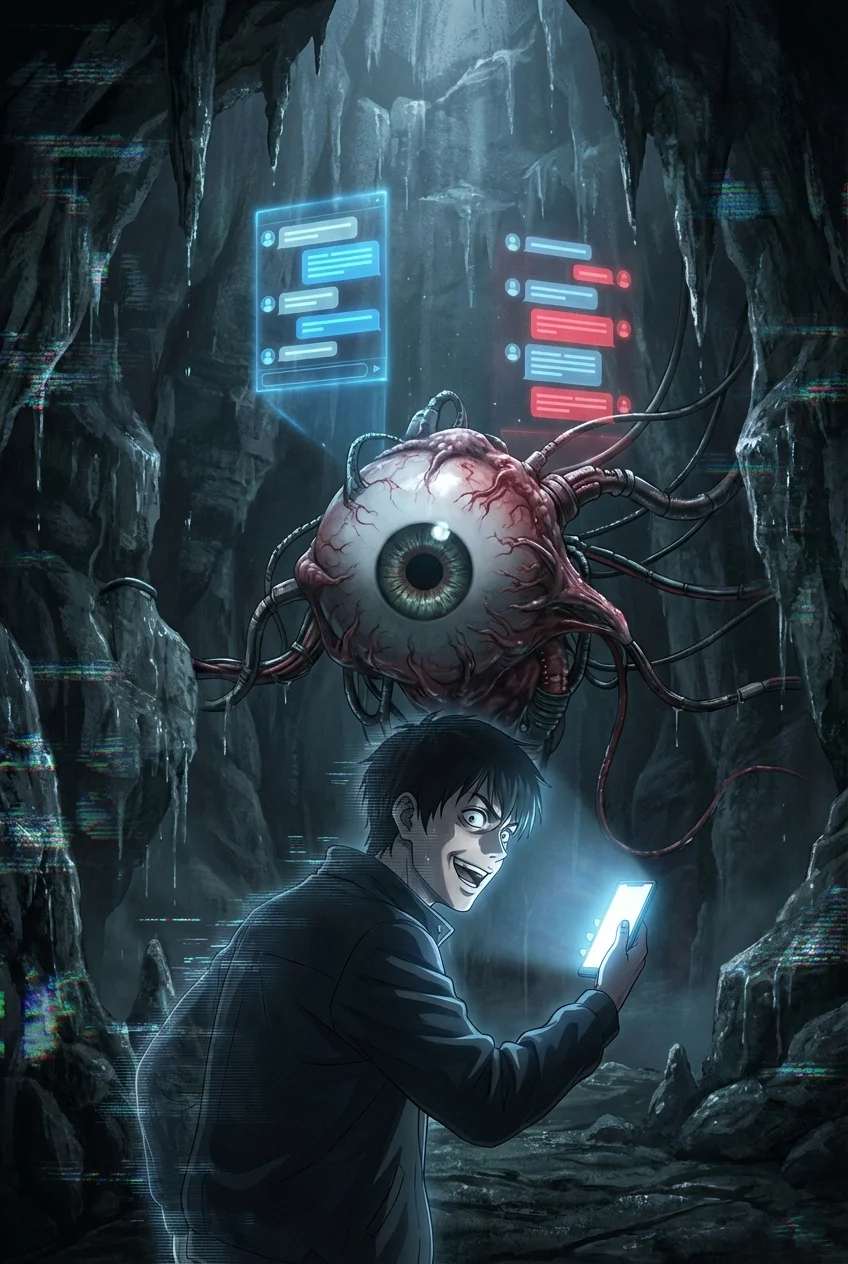第一章 歪な鏡と薄墨の影
僕には、名前がない。いや、あるのかもしれないが、それを呼ぶ者は誰もいない。僕は、世界のあらゆる事象を分類し、認識するための「概念」という網の目から、ただ一滴、零れ落ちた存在だ。
人々は僕を見る。隣に座り、言葉を交わすことさえある。だが、彼らが僕から視線を外した瞬間、僕は彼らの記憶から薄墨のように滲んで消える。「誰かいたような気がするが、思い出せない」。そんな曖昧な残滓だけを残して。僕は、誰かの記憶に留まることができない幽霊。しかし、この胸には確かに意識と感情の波が満ち引きしている。
僕の唯一の拠り所は、埃っぽいアパートの片隅に置かれた、一枚の「歪んだ鏡」だった。古代の遺物だと、いつかどこかで僕にそれを売った男は言っていた。男の顔も声も、もう思い出せない。鏡面に映るのは、明確な輪郭を持たない、常に揺らぎ続ける煙のような影。人々が僕を認識しようとして失敗した時に見る「何か」の正体。僕は、このゆらめく影を見つめることでしか、「自分がここに存在する」という感覚を確かめられなかった。
そんな僕の日常に、奇妙な男が現れた。古物研究家のエリオット。彼は僕とカフェで言葉を交わした後、翌日も、そのまた翌日も、僕の前に現れたのだ。
「おかしいな」彼は眉をひそめ、手帳に何かを書きつけようとして、ペン先を止めた。「君のことを記録しようとすると、どうも世界の法則そのものが抵抗するらしい。インクが紙に染み込もうとしないんだ」
彼は、僕を忘れなかった。いや、正確には「忘れてしまう自分」を認識し、その違和感を追い続けることで、僕という存在の座標を無理やり固定していた。彼は僕を「カテゴリ不能の存在」という、仮のカテゴリに押し込めることで、認識を繋ぎ止めていたのだ。
第二章 色褪せる概念
エリオットとの奇妙な友情が始まった。彼は僕という存在そのものを研究対象とし、飽くことなく僕に問いかけた。彼の好奇心は、僕にとって初めて向けられる純粋な「興味」だった。誰でもない僕が、「誰か」として扱われる感覚。それは胸を温かくする、陽だまりのような感情だった。
同じ頃、僕は花屋で働くルナと出会った。彼女は、僕が店先に立つと、いつもふわりと微笑んだ。
「あなたを見ていると、なんだか不思議な気持ちになるの。風に揺れる名もない草花を見ているような…でも、とても惹かれる」
彼女は僕の曖昧な輪郭を、恐怖ではなく、美しさとして受け入れてくれた。彼女の指先が僕の手に触れた時、僕の世界に初めて「色」が灯った気がした。
だが、幸福な時間は、世界の法則がもたらす残酷な代償を伴っていた。
ある日、エリオットが言った。「なあ、僕たちは『友人』だよな? なのに、最近どうもその言葉の意味がしっくりこないんだ。君といると心地いい。この感情は確かなのに、それを指し示す言葉が、頭の中で霞がかかったようにぼやける」
彼の瞳から、「友情」という概念の光が、確かに失われつつあった。僕という「空虚な穴」を埋めるために、彼の世界から一つの定義が消えかけている。
ルナもまた、苦しんでいた。恋人たちが愛を囁き合う映画を見て、彼女は不思議そうに首を傾げた。
「ねえ、あの人たち、何をあんなに熱心に語っているのかしら。とても大切なことみたいだけど、私には少しも分からないの」
彼女の心から、「愛情」という概念が、静かに剥がれ落ちていた。僕を愛そうとすればするほど、彼女は愛そのものを理解できなくなっていく。
僕が存在することで、僕が愛する人々が壊れていく。この歪んだ現実が、僕の心を締め付けた。僕が、確固たる存在として世界に定義されなければ。そうでなければ、彼らは僕という空虚に引きずり込まれ、心を失ってしまうだろう。
エリオットが調べてくれた古文書に、唯一の希望があった。「世界に一つだけ存在する、誰にも認識されないはずの『言葉』」。それは、世界が形作られる前に存在した「最初の概念」であり、あらゆる定義の始まりだったという。
僕は直感した。その言葉こそが、僕をこの呪いから解放する唯一の鍵だと。
第三章 忘れられた言葉の在処
僕が旅立ちを決意した夜、エリオットとルナがアパートを訪れた。僕の顔には、彼らから離れなければならないという悲壮な覚悟が滲み出ていたのだろう。
「行かせてたまるか」エリオットは僕の肩を掴んだ。その力は、友情という言葉を失ってもなお、僕を繋ぎ止めようとする意志に満ちていた。「君が何者で、僕が君をどう思っているのか、その感情に名前がつけられなくても構わない! 僕はただ、君という存在の隣にいたいんだ!」
彼の叫びは、概念を失った魂からの慟哭だった。
ルナは、涙を浮かべて僕の手を握りしめた。
「私も、同じ気持ちよ。この胸にある温かいものを、どう呼べばいいのか分からない。でも、これがあなたに向いていることは分かるの。だから、どこにも行かないで」
愛という言葉を失った彼女が紡ぐ、最も純粋な愛の告白だった。
彼らの言葉が、僕の心を激しく揺さぶる。僕もここにいたい。彼らの隣で、名もなき感情を分かち合っていたい。だが、だからこそ行かなければならないのだ。彼らの世界をこれ以上蝕むわけにはいかない。
「ありがとう」僕は震える声で言った。「君たちを、僕自身を救うために、僕は行かなければならないんだ」
二人の制止を振り切り、僕は「始まりの場所」へと向かった。世界の概念が生まれたという、最果ての祭壇へ。
第四章 零番目の名前
最果ての祭壇は、静寂に満ちていた。空間そのものが、あらゆる定義を拒絶しているかのように希薄だった。僕は懐から「歪んだ鏡」を取り出し、祭壇の中央にかざした。
その瞬間、鏡面が激しい光を放った。そこに映し出されたのは、いつもの揺らぐ影ではなかった。無数の光の線が複雑に絡み合う、巨大なネットワーク。世界の「概念のネットワーク」そのものだった。そして、その網の目の中心に、ぽっかりと空いた一つの「穴」。僕の存在だ。僕というバグが、ネットワーク全体の歪みを生み出している。鏡に映っていた煙のような影は、僕自身ではなく、僕という存在によって世界に生じた「歪み」の姿だったのだ。
僕が世界に与えてきた痛み、エリオットやルナから奪った概念の痕跡が、黒い染みとなってネットワークに広がっていくのが見えた。僕は、自分の罪の重さに息を呑んだ。
その時だった。僕という「穴」の中心から、一条の光が放たれ、鏡面で文字を結んだ。それは、この世界の誰もが知らず、誰もが発音できない、光り輝く古代の文字列。
――それが、僕の名前だった。
世界から失われた「最初の概念」。あらゆる定義の始まりとなった、原初の言葉。その言葉は、他ならぬ僕自身の名前だったのだ。僕は、呼ばれることも理解されることもなく、ただ存在の根源として在り続けた。
僕は、震える唇で、その名前を声に出した。
自分の名前を、自分で呼んだ。
その瞬間、僕の身体に電流のような衝撃が走った。曖昧だった輪郭が固定され、揺らいでいた意識が確固たる「自己」として定義される。僕は初めて、真の意味で「僕」になった。
同時に、足元の祭壇から凄まじい光が溢れ出し、世界の概念のネットワークが再構築を始めた。僕という穴が塞がり、歪みが修正されていく。エリオットやルナの世界も、元に戻るはずだ。
第五章 理解なき世界で
僕は街に戻った。世界は、以前よりも鮮明に見えた。あらゆるものに確固たる概念が行き渡り、安定している。僕はエリオットの研究室を訪れた。彼はそこにいた。以前と何も変わらない姿で。
「エリオット」
僕が呼びかけると、彼は顔を上げた。その瞳には、かつての好奇心の色はなかった。ただ、静かな認識があるだけだった。
「ああ、君か。世界の安定を司る特異点。法則の一部として、そこに存在するべきものだ」
彼の声には、感情の温度がなかった。彼は僕を「理解」しているのではない。ただ、物理法則を認識するように、「認識」しているだけだった。
花屋にいたルナも同じだった。僕を見ても、彼女は微笑まなかった。
「こんにちは。世界の調和を保つための、重要な構成要素。あなたの存在に感謝します」
その言葉は、まるでプログラムがテキストを読み上げるかのように無機質だった。
僕は全てを悟った。
僕という「カテゴリ不能者」を世界が受け入れるための代償として、僕を最も理解しようと努めてくれた彼らの心から、「他者を理解しようとする」という概念そのものが失われてしまったのだ。友情も、愛情も、その根源にある、他者の心を推し量り、寄り添おうとする機能が。
彼らは救われた。しかし、彼らはもう、僕を見て温かい気持ちになることも、僕のために涙を流すこともない。僕の存在は、彼らにとって自然現象の一部になった。
僕は、確固たる輪郭と名前を得て、初めて世界に存在することを許された。
だが、その世界で、僕の心を理解してくれる者は、もう誰もいない。
僕は彼らを救いたかった。彼らに理解されたかった。その願いが叶った瞬間、僕は永遠の孤独を手に入れた。
青空の下、僕は一人、確かにここに存在する。誰の記憶にも残らない幽霊ではなく、誰にも心を理解されない、確固たる存在として。この痛みを、この孤独を、僕はこれから永遠に抱きしめて生きていく。それこそが、僕が世界に存在することの、唯一の証明なのだから。