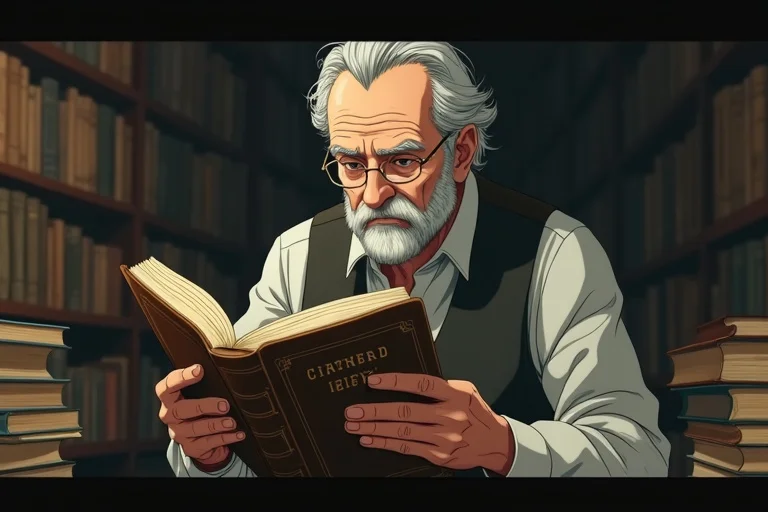第一章 忘れられた約束
神保町の古書店『刻詠堂(こくえいどう)』の主、相沢拓真の日常は、埃とインクの匂いに満ちた静寂そのものだった。かつてジャーナリストとして言葉の奔流に身を投じていた彼は、ある事件を境にその世界を捨て、今は古びた本の背表紙だけが話し相手だった。人と深く関わることを、彼は極端に避けていた。
その静寂が破られたのは、木犀の香りが街角に漂い始めた秋の日の午後だった。店のドアベルがちりん、と遠慮がちな音を立て、一人の小柄な老婦人が入ってきた。上品だが着古されたツイードのコートを羽織り、その顔には深い皺が、まるで地図のように刻まれている。
「あのう、少しだけ、預かっていただけないでしょうか」
老婦人は震える手で、風呂敷に包まれた一冊の本を差し出した。買い取りではない、という奇妙な依頼に、拓真は眉をひそめる。
「預かる、ですか。うちは貸金庫じゃありませんよ」
「分かっております。でも、どうしても。一週間だけ……いいえ、必ず一週間後に、いただきに参りますから」
懇願するような瞳は、ただならぬ切実さを宿していた。拓真はため息混じりに風呂敷を解く。現れたのは、ごくありふれた古い植物図鑑だった。だが、老婦人は特定のページを開いて見せた。『ワスレナグサ』の挿絵が描かれた頁の余白に、万年筆で書かれたと思しき、意味不明な数字の羅列がびっしりと並んでいた。
「これは?」
「私の、大事な覚え書きです。決して、誰にも見せないで。誰にも、この本のことを話さないでくださいまし」
そう言い残し、老婦人は深々と頭を下げて店を出て行った。拓真は「面倒なことに巻き込まれた」と舌打ちしながらも、その瞳の奥にあった悲痛な光が、妙に脳裏に焼き付いて離れなかった。
約束の一週間が過ぎ、二週間が過ぎても、老婦人は現れなかった。あの日の出来事も、埃をかぶった日常に埋もれて忘れかけていた頃、店のドアが乱暴に開けられた。鋭い目つきをした、黒いコートの男だった。
「古い植物図鑑を探している。心当たりはないか」
威圧的な口調。拓真の全身を走る、久しく忘れていた緊張感。それは、危険な取材現場で感じたのと同じ種類の肌寒い感覚だった。彼は無表情を装い、ゆっくりと首を横に振った。
「さあ、図鑑は色々ありますが。お探しのものは、あいにくと」
男は店の隅々までを舐め回すように見渡すと、何も言わずに立ち去った。だが、その視線は拓真の心に棘のように突き刺さった。あの老婦人と、この男。そして、忘れな草の頁に記された数字。それは、拓真が捨てたはずの過去を呼び覚ます、不吉な序曲のように響いていた。
第二章 数字の囁き
男の来訪以来、拓真の静寂は内側から侵食され始めていた。彼は店の奥、私室に持ち帰った植物図鑑を手に取った。ワスレナグサの頁。インクのかすれ具合から、何度も書き直されたことが窺える数字の羅列。暗号だろうか。彼はかつてのジャーナリストの血が微かに騒ぐのを感じながら、その解読に取り掛かった。
『19980423』『42-195』『L-782』『1105』…
一見、無秩序に見える数字。だが、拓真は『19980423』という並びに既視感を覚えた。それは日付だ。彼は書庫の奥から、自分がジャーナリスト時代にスクラップしていた古い新聞の束を引きずり出した。指先が黒く汚れ、インクの匂いが記憶の扉をこじ開ける。
1998年4月23日。その日の紙面を、指が震えながらめくっていく。そして、見つけた。社会面の片隅に追いやられた、小さな三段記事。
『資産家・久我原氏令嬢、誘拐事件から一年。未だ行方不明』
脳裏に雷が落ちたような衝撃が走った。二十年前、世間を騒がせた事件。当時、新米記者だった拓真も取材班に加わっていた。犯人からの要求はなく、身代金の受け渡しも行われず、令嬢・久我原沙織は忽然と姿を消した。迷宮入りした事件として、人々の記憶から消え去っていた。
他の数字も、事件に関連しているのではないか。拓真は憑かれたように調査を続けた。『42-195』は、当時の国会図書館の蔵書番号ではないか? 彼は何年かぶりに図書館へ足を運び、該当する書籍を閲覧した。それは沙織の父親が出版した、マイナーな詩集だった。特定の頁に、鉛筆で薄く印がつけられている。『L-782』は、沙織が失踪当日に乗っていたとされる車のナンバープレートの一部と一致した。
数字は、事件の断片を繋ぎ合わせる糸だった。老婦人は一体何者なのか。なぜ、今になってこの本を自分に託したのか。謎は深まるばかりだった。
調査を進めるうち、拓真は自分の過去の、最も深く、暗い部分に触れざるを得なくなった。この誘拐事件の取材で、彼は大きな過ちを犯していたのだ。警察からのリーク情報に飛びつき、当時、久我原家に出入りしていた庭師の男を、あたかも犯人であるかのように示唆する記事を書いてしまった。結果、男は世間の激しいバッシングに耐えきれず、自ら命を絶った。後に、男は完全なシロであったことが判明した。
拓真のジャーナリスト生命は、その瞬間に終わった。人の人生を言葉で殺してしまったという罪悪感。真実を見極められなかった無力感。それらが彼を苛み、人との関わりを断たせ、古書の壁の中に閉じこもらせたのだ。
この図鑑は、ただのサスペンスではない。これは、自分への断罪であり、同時に、贖罪への招待状なのかもしれない。拓真は固く閉ざしていた心の扉が、軋みを立てて開くのを感じていた。
第三章 贖罪の迷宮
拓真は、ついに老婦人の身元を突き止めた。彼女の名前は、高坂静子。二十年前、誘拐された久我原沙織の乳母だった。事件後、心労がたたって認知症を発症し、今は市内の介護施設で静かに暮らしているという。
施設の面会室で対面した静子は、拓真のことなど覚えていない様子で、ただ窓の外をぼんやりと眺めていた。あの日の切実な光は、その瞳から消え失せている。
「高坂さん、この本を覚えていらっしゃいますか」
拓真が植物図鑑を見せると、彼女は一瞬、それに目を留めた。そして、子供のような無垢な声で呟いた。
「あら、ワスレナグサ……。あの子が好きだったお花……」
その言葉が、拓真の頭の中で全てのピースを繋ぎ合わせた。そうか、暗号なんかじゃなかったんだ。これは、認知症という病と闘いながら、薄れゆく記憶の奔流の中から、決して忘れてはならない真実の欠片を必死に書き留めた、彼女自身の「記憶の地図」だったのだ。
『19980423』は事件の日付、『42-195』は父親の詩集、『L-782』は車のナンバー。そして、まだ解読できていない最後の数字、『1105』。それは何だ? 誕生日にしては不自然だ。拓真は思考を巡らせた。
その時、静子が不意に歌い始めた。それは、沙織が子供の頃に好きだったという童謡だった。その歌を聞きながら、拓真の脳裏に閃光が走った。
「…まさか」
彼は急いで施設を飛び出し、神保町の駅へと向かった。駅のコインロッカー。その一つに『1105』という番号が振られているのを見つけた時、彼は確信した。静子は、沙織の父の詩集が好きだった。その詩集のタイトルは、『十一月の鎮魂歌』。そして、沙織の誕生日は五日。十一月五日……『1105』。
震える手で、彼は古い鍵を差し込んだ。二十年の時を経て開かれたロッカーの中には、小さなカセットテープと、一枚の写真がひっそりと置かれていた。写真には、まだうら若い沙織と、もう一人、見覚えのある男が親しげに写っている。それは、久我原家の顧問弁護士であり、今や政界に進出し、クリーンなイメージで知られる有力政治家、大和田信介だった。
そして、テープを再生した瞬間、拓真は全てを理解した。聞こえてきたのは、沙織を詰る大和田の声と、泣きじゃくる彼女の声。
「君がすべてを公表すれば、私も、君の一族も終わりだぞ!」
これは誘拐事件などではなかった。大和田と不倫関係にあった沙織が、関係を清算しようとしたところ、逆上した大和田に殺害されたのだ。彼はそれを誘拐事件に見せかけて偽装し、全ての証拠を隠蔽した。静子は、その真相を知る唯一の人間だった。彼女は、いつか自分が全てを忘れてしまう前に、誰かに真実を託そうとした。そして、偶然にも、かつてこの事件で人生を狂わせた元ジャーナリストの店を選んだのだ。
拓真は天を仰いだ。なんという皮肉な運命の糸か。自分が誤報で死に追いやった庭師の無念。闇に葬られた沙織の悲しみ。そして、記憶を失いながらも真実を守ろうとした静子の執念。それら全てが、今、この手に託されている。これは、もはや他人の事件ではない。自分の人生を懸けた、最後の贖罪だった。
第四章 真実の在り処
証拠を手に、拓真は大和田の事務所を訪れた。かつて言葉で人を傷つけた男が、今度は言葉で真実を暴くために、敵の懐へ飛び込む。応接室で対峙した大和田は、余裕の笑みを崩さなかった。
「元新聞記者の方が、私に何の御用で?」
「二十年前の、忘れ物をお届けに」
拓真は静かにカセットテープをテーブルに置いた。大和田の顔から、一瞬にして血の気が引く。拓真は畳み掛けた。静子の残した数字のメモ、コインロッカー、沙織との関係。彼はジャーナリストとして培った全ての技術を使い、冷静に、しかし鋭く大和田を追い詰めていく。それは、暴力的な対決ではなく、言葉と真実だけを武器にした、静かなる闘いだった。
観念した大和田は、やがて全てを自白した。二十年の時を経て、偽りの誘拐事件は殺人事件として幕を閉じ、真犯人は裁きを受けることになった。
数日後、拓真は再び静子のいる介護施設を訪れた。窓辺に座る彼女は、あの日と同じように、ただ穏やかに外を眺めている。事件が解決したことも、自分の戦いが終わったことも、もう彼女の記憶にはない。
拓真は、彼女の隣に静かに腰掛けた。
「高坂さん。あなたのおかげで、僕は前に進めそうです」
彼は、老婦人の皺だらけの手をそっと握った。彼女は拓真の方を向き、誰にともなく、ふわりと微笑んだ。その笑顔は、ワスレナグサの花のように、儚く、そして気高かった。彼女が守りたかったのは、特定の誰かの名誉ではない。ただ、そこにあったはずの「真実」そのものだったのかもしれない。
古書店『刻詠堂』に戻った拓真は、店のカウンターに新しい原稿用紙を広げた。埃とインクの匂いが、今は心地よく感じられる。彼はペンを手に取り、ゆっくりと一行目を書き始めた。
それは、二十年前に書くことができなかった、一人の女性の死の真相と、記憶を失いながらも真実を繋いだ乳母の物語。そして、言葉に殺され、言葉に生かされた、一人の男の再生の物語だった。
窓から差し込む西日が、彼の横顔を優しく照らしていた。静寂は戻ってきたが、それはもはや孤独の色ではなかった。彼の心には、確かな温もりと、これから綴るべき言葉たちが満ちていた。