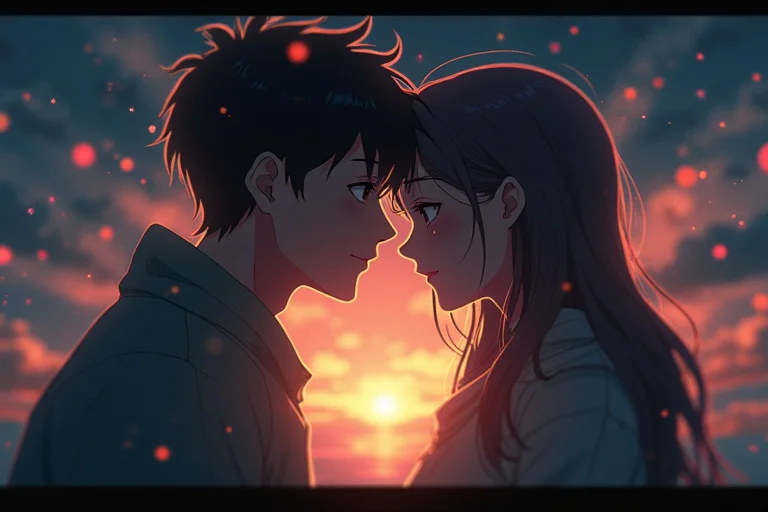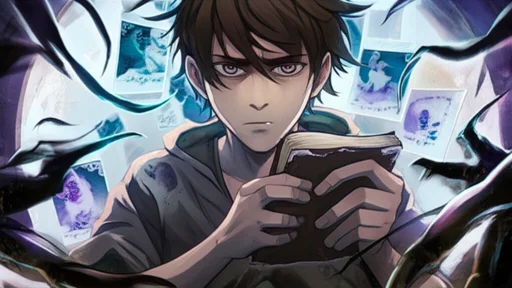第一章 閉ざされた箱と最後の嘘
梅雨の湿った空気が、書斎の埃っぽい匂いと混じり合っていた。倉田亮介は、三ヶ月前に亡くなった祖父の家の整理に、うんざりしながら手をつけていた。フリーの校正者である亮介にとって、他人の文章の瑕疵を見つけ出すことは天職だが、過去という名の乱雑なテキストを整理するのはひどく億劫だった。
祖父は無口で、自分のことをほとんど語らない人だった。その書斎も、持ち主の性格を映したかのように静まり返っている。壁一面の本棚に並ぶのは、法律関係の専門書ばかり。元警官だった祖父らしい、堅苦しい蔵書だ。亮介がその中の一冊を手に取った時、背表紙の裏に隠された小さな窪みに指が触れた。そこには、古びた桐の小箱がぴったりと収まっていた。
掌に乗るほどの大きさのその箱には、錆びた南京錠がかかっていた。好奇心というよりは、校正者としての性分だろうか。この場違いな存在の「誤植」を正したい衝動に駆られ、亮介は道具箱から小さな針金を取り出した。数分後、カチリ、と乾いた音がして錠が開いた。
箱の中にあったのは、一冊の手帳だった。革の表紙は擦り切れ、角は丸くなっている。持ち主は、相当な頻度でこれを手にしていたのだろう。中を開くと、インクの滲んだ、女性的な丸い文字が目に飛び込んできた。それは、見知らぬ「小夜子」という女性の日記だった。
亮介は、他人のプライバシーを覗くことに微かな罪悪感を覚えながらも、ページを繰る手を止められなかった。日記は、とある海辺の町での穏やかな日常から始まり、やがて「K」という名の恋人との愛に満ちた日々が綴られていく。ひまわりの咲く丘、二人で見た夕日、彼がくれた小さな貝殻の髪飾り。幸福という言葉をインクに溶かして書いたような文章が続いていた。
しかし、なぜ祖父がこんなものを? 疑問を胸に最後のページを開いた亮介は、息を呑んだ。そこには、それまでの幸福な記述とはあまりに不釣り合いな、震えるような筆跡でこう記されていた。
『倉田武雄様。
あなたがこの日記を見つけた時、私はもうこの世にいないでしょう。
どうか、私の最後の嘘を、真実として墓場まで持っていってください。
そして、彼を許さないでください。』
倉田武雄。それは、亮介の祖父の名前だった。
「最後の嘘」とは何か。「彼」とは誰を指すのか。そしてなぜ、祖父は「彼を許すな」と書かれたこの日記を、錠のかかった箱に三十年間も隠し持っていたのか。
書斎の窓から差し込む西日が、埃を金色に照らし出す。その光の中で、亮介はまるで難解なゲラの初校を突きつけられたように、立ち尽くすしかなかった。彼の退屈な日常は、その瞬間、静かに崩れ始めた。
第二章 活字のなかの不協和音
亮介は東京のアパートに日記を持ち帰り、本格的にその内容を読み解き始めた。彼の校正者としての目は、単なる読者として物語を追うことを許さなかった。一字一句、行間に潜む意味を探り、文章の整合性を無意識に検証してしまう。
小夜子の日記は、三十年前の四月から始まり、八月で途切れていた。彼女が住んでいたのは「汐見町」という、亮介には聞き覚えのない地名だった。日記に描かれる「K」は、優しく、少し不器用で、ひまわりのような笑顔を持つ男性として登場する。二人の関係は、読む者の胸を温かくするほどに純粋で、美しい。
しかし、読み進めるうちに、亮介は奇妙な「ノイズ」に気づき始めた。
『七月七日。今日は七夕。Kと二人で笹に願い事を書いた。夜は満月がとても綺麗で、まるで私たちを祝福してくれているようだった。』
亮介は眉をひそめた。七夕は旧暦でない限り、新月の頃のはずだ。満月が見えることはあり得ない。彼はノートパソコンを開き、三十年前の七月七日の月齢を調べた。やはり、その夜は新月に近い月だった。
些細な記憶違いだろうか。そう思い直そうとした矢先、また一つ、おかしな記述が見つかった。
『八月二日。今日もひどい雨。Kが持ってきてくれた紫陽花が、窓辺で静かに濡れている。早く晴れて、またあの丘に行きたいな。』
八月に紫陽花? 時期がずれている。亮介は汐見町の過去の気象データまで調べ上げた。三十年前の八月二日、その地域は記録的な猛暑に見舞われており、雨など降っていなかった。
矛盾は、他にも散見された。季節感の不一致、あり得ない天候の記述、本来そこにはないはずの花の名前。まるで、誰かが意図的に偽の情報を埋め込んだかのようだ。この日記は、本当に小夜子という女性が書いたものなのか? それとも、全てが巧みに仕組まれたフィクションなのか?
亮介の心は揺れた。活字の世界に絶対的な正しさを求めて生きてきた彼にとって、この矛盾に満ちたテキストは耐えがたいものだった。しかし、同時に、そこには抗いがたい魅力があった。インクの滲み、時折見せる筆跡の乱れは、紛れもなく生身の人間の感情の揺らぎを伝えていた。
「私の最後の嘘を、真実として墓場まで持っていって」
その言葉が、頭の中で何度も反響する。嘘。そう、これは嘘で塗り固められた物語なのかもしれない。だとしたら、その嘘の裏に隠された真実は何なのか。そして、祖父はなぜ、この「誤植」だらけの原稿を、誰にも見せず、訂正もせず、ただ静かに保管し続けていたのだろうか。
人との関わりを避け、文章の正誤だけを世界の基準としてきた亮介は、初めてテキストの向こう側にいる「人間」の顔を、強く意識していた。彼は、この謎を解き明かすために、汐見町へ向かうことを決意した。それは、閉ざされた書斎から、生身の人間の世界へと踏み出す、彼にとっての大きな一歩だった。
第三章 三十年前の真実
汐見町は、古びた漁港と緩やかな丘陵に抱かれた、時の流れが止まったような場所だった。潮の香りが、亮介の肺を낯れない感覚で満たす。彼は町の小さな図書館で、三十年前の地方新聞の縮刷版をめくっていた。
やがて、彼の指が止まる。「若い女性、行方不明か」。日付は、日記が途絶えた八月の終わり。記事には「宮下小夜子」という名前と、彼女の顔写真が掲載されていた。日記の筆跡から想像した通りの、儚げで優しい眼差しの女性だった。当時の警察は、詳しい捜査の末、彼女が足を滑らせて海に転落した事故として処理していた。
亮介は、次に町の古老たちに話を聞いて回った。ほとんどの人が首を横に振る中、一人の老婆がぽつりぽつりと語ってくれた。
「小夜子さんかい…。可哀想な人だったよ。恋人を亡くして、すっかり人が変わっちまってね」
「恋人…? それは、Kという人ですか?」
亮介の問いに、老婆はきょとんとした顔をした。「K? さあねぇ。その人が好きだったのは、確か…そう、坂井君って若い土木技師だったよ。真面目で、いい青年だった」
坂井。Kではない。亮介は混乱した。老婆の話によれば、坂井という青年は、その年の八月半ば、集中豪雨による土砂崩れに巻き込まれて亡くなったのだという。小夜子が行方不明になったのは、そのわずか二週間後のことだった。
全てのピースが、亮介の頭の中で激しくぶつかり合い、そして、恐ろしい一つの形を結び始めた。彼は図書館へ駆け戻り、土砂崩れの記事を必死で探した。あった。犠牲者、坂井和也。そして、その災害対応のために派遣された警察官の中に、亮介は見覚えのある名前を見つけた。「巡査部長 倉田武雄」。
祖父だ。祖父が、この町にいた。
愕然とする亮介の脳裏に、日記の最後の言葉が蘇る。『彼を許さないでください』。
「彼」とは、小夜子の恋人を演じ、彼女を騙した祖父のことだったのか? 祖父は、心を病んだ小夜子につけこみ、何か非道なことをしたのではないか? だから、彼女は最後に祖父を告発するような言葉を遺し、自ら命を絶ったのでは…。
疑念と嫌悪感が、胃の腑からせり上がってくる。無口で厳格だと思っていた祖父の、全く知らない顔。亮介は、祖父が隠し通したかった醜い真実を暴いてしまったのだと確信した。
だが、その時だった。新聞記事の片隅に、土砂崩れに関する小さなコラムが掲載されているのに気がついた。災害心理学の専門家による、被災者の心のケアの重要性を説く内容だった。その中で、一つの事例が匿名で紹介されていた。
『恋人を突然失った衝撃で記憶が混乱し、恋人がまだ生きているという架空の現実を創り出してしまった女性の例がある。周囲がその「物語」を無理に否定せず、寄り添うことで、彼女の心はかろうじて均衡を保っているという。これは、悲劇的な現実から心を守るための、痛ましいほどの防衛機制なのである』
亮介は、雷に打たれたような衝撃を受けた。
まさか。
彼は震える手で、再び日記を開いた。七月七日の満月。八月の紫陽花。季節外れの雨。
それらは、小夜子の記憶違いなどではなかった。全ては、彼女が恋人・坂井和也と実際に過ごした、過去の美しい思い出の断片だったのだ。土砂崩れで彼を失った彼女の心は、時間も季節もバラバラになった記憶の破片を必死に繋ぎ合わせ、「Kとの幸せな日々」という、新しい物語を紡ぎ出していた。
祖父は、彼女を騙していたのではなかった。
心を病んだ小夜子を保護した若き日の祖父は、彼女の壊れかけた心を守るため、彼女が創り出した「嘘の物語」の登場人物である「K」を、自ら演じることを選んだのだ。
日記の矛盾。亮介が「誤植」だと思った箇所は、祖父が、小夜子の混乱した記憶の物語に寄り添い、その「設定」に合わせて、後から加筆修正した痕跡だったのだ。校正者である亮介が発見した「誤り」は、他ならぬ祖父が、彼女の嘘を守るために施した、究極の「校正」だった。
『彼を許さないでください』
「彼」とは、祖父ではなかった。恋人を奪った、残酷な「運命」そのものだったのだ。
『私の最後の嘘を、真実として墓場まで持っていってください』
それは、祖父への告発ではなく、自分たちが紡いだこの儚い物語を、どうか本当のこととして信じ守り抜いてほしいという、切なる願いだった。
亮介は、その場に崩れるように膝をついた。涙が、古い新聞紙の上に次々と落ち、インクを滲ませていった。
第四章 優しさの校正
東京に戻った亮介は、書斎の机に日記の入った桐の小箱を置いた。あの日、祖父の書斎で感じた埃っぽい匂いは、もう感じなかった。そこにはただ、永い沈黙のなかに秘められた、深く、静かな愛情の気配だけが満ちているようだった。
祖父は、一人の女性の心を守るために、全てを背負ったのだ。彼女の失踪後も、その「嘘の物語」を真実として封印し、自分が悪者と誤解される可能性さえ受け入れて、誰にも語らず、墓場まで持っていった。正しさや真実を暴くことだけが、正義ではない。時には、沈黙し、嘘に寄り添うことこそが、最も深い優しさとなり得る。
亮介は、自分の仕事机に向かった。目の前には、新しい校正紙の束が積まれている。彼は赤ペンを手に取り、文章に目を走らせる。いつものように、誤字や事実誤認、表現の矛盾を探す。しかし、彼の活字を見る目は、汐見町へ行く前とはまるで違っていた。
一つの文章に、彼のペンが止まる。明らかに事実とは異なる記述。以前の彼なら、機械的に、そして少しばかりの優越感をもって、そこへ真っ直ぐに赤線を入れただろう。だが今、彼の指はためらっていた。
この「間違い」の裏には、書いた人間のどんな想いが隠されているのだろう。守りたかった記憶や、誰にも言えない祈りがあるのかもしれない。世界は、白か黒か、〇か×かだけで割り切れるものではない。その間に広がる無限のグラデーションこそが、人間を人間たらしめているのではないか。
亮介は、赤ペンの代わりに鉛筆を手に取った。そして、修正箇所を指摘する横に、ごく小さな文字で、書き手の意図を尊重するような、柔らかな代替案を書き添えた。それは、単なる「訂正」ではなく、相手に寄り添う「提案」だった。彼の仕事は、間違いを正すことから、書き手の心に寄り添うことへと、静かにその意味を変えた。
彼は、小夜子の日記を再び桐の小箱に収め、あの錆びた南京錠をかけた。カチリ、という音は、祖父から自分へと、一つの秘密が受け継がれた合図のように響いた。この偽りのレクイエムを、今度は自分が守り通す番だ。
窓の外では、降り続いていた雨が上がり、薄雲の向こうから柔らかな光が差し込んでいた。やがて、空には淡い虹がかかる。
亮介は、その七色の架け橋を眺めながら、小さく微笑んだ。真実と嘘の間に架かる、切なくて、しかしどこまでも美しい虹。世界は、こんなにも豊かで、愛おしいものだったのか。
彼の心にもまた、長い梅雨が明けたような、澄み切った青空が広がっていた。