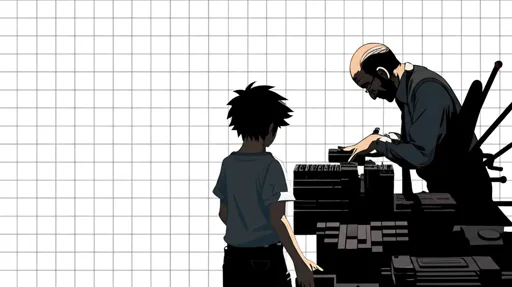第一章 午前零時の来訪者
桐島健斗の時間は、秒単位で管理されていた。三十五歳、大手広告代理店のトップセールスマンである彼の世界は、効率と成果という二つの物差しで正確に計測されている。無駄は罪であり、感情はノイズだ。都心のタワーマンション四十二階にある彼の部屋は、彼の精神を完璧に具現化していた。ミニマルな家具はモノトーンで統一され、生活感という名の不純物は徹底的に排除されている。数ヶ月前に離婚した妻は、そんな彼を「美しい機械のようだ」と評した。それは、彼女なりの最後の皮肉だったのだろう。
その日、健斗は半ば義務感で、一ヶ月前に亡くなった祖父の遺品整理に赴いていた。郊外に残された古い木造家屋は、湿った土と古い木の匂いがした。健斗にとって、それは非効率の塊のような空間だった。埃をかぶったガラクタの山の中から、彼は一台の古びたラジオを見つけた。焦げ茶色の木製フレームに、鈍く光る大きな円形のダイヤル。アポロニア、と洒落た筆記体で記されている。祖父が趣味の電子工作で作ったものだろうか。健斗は無感動にそれを手に取り、処分する品を入れた段ボール箱に放り込もうとして、ふと手を止めた。なぜか、その無骨な存在が、彼の完璧にコントロールされた日常に投げ込まれた異物のように思え、ほんの少しだけ心が動いた。
その夜、健斗は持ち帰ったラジオをリビングの隅に置いた。深夜、仕事を終えてグラスに注いだシングルモルトを一口含んだ時、ふとラジオに目が留まった。時計は午後十一時五十九分を指している。悪戯心が湧いた。彼は電源プラグをコンセントに差し込み、カチリ、とスイッチを入れた。
何も起こらない。ただ、スピーカーから微かなノイズが聞こえるだけだ。やはりガラクタか。健斗がそう思い、電源を切ろうとした瞬間だった。壁掛けのデジタル時計の表示が、0:00に切り替わった。
その刹那、ラジオからノイズが嘘のように消え、クリアな音声が流れ出した。
『……だから言ったじゃないか。その氷、すぐ溶けちまうって』
若い男の声。少し掠れているが、温かい響きがある。祖父の声によく似ていた。
『あら、いいのよ。夏の音だもの。ぽちゃん、て落ちる雫も、風情があって』
可憐な少女のような、しかし芯の通った女性の声が応える。背景には、微かに聞こえる風鈴の音と、遠くで鳴く蝉の声。まるで、真夏の縁側での会話をそのまま切り取ったかのようだ。
『風情ねぇ。千代はいつもそうだな。それより、未来の種の話だが……』
健斗は息を呑んだ。千代。それは、彼の祖母の名前だった。しかし、声が若すぎる。それに、会話の内容がまるで生放送のようだ。周波数を合わせようとダイヤルを回すが、何も変わらない。放送局を示すランプも点灯していない。これは、一体何なんだ? 混線か? それとも、誰かが仕組んだ手の込んだ悪戯か?
会話は数分で途切れ、再び静かなノイズの世界に戻った。健斗は、グラスを持ったまま、リビングの中央で立ち尽くしていた。彼の計算し尽くされた世界に、計測不能な謎が、音もなく忍び込んできた夜だった。
第二章 音の地図
翌日から、健斗の日常に新しい習慣が加わった。深夜零時、アポロニアの前に座ること。それは彼の信条である効率主義とは最もかけ離れた行為だったが、やめられなかった。毎晩、時計が零時を告げると、ラジオは決まって若き日の祖父と祖母の会話を再生した。それはいつも断片的な、他愛もない会話だった。二人が育てていたトマトの話。近所の飼い犬の話。そして、繰り返し登場する「未来の種」の計画。
『あの欅の木の下がいいわ。一番、お日様が当たるところ』
『そうだな。俺たちの未来が、明るく育つようにか』
健斗は、彼がこれまで無駄だと切り捨ててきた、目的のない会話の温かさに戸惑っていた。ビジネスにおける会話は、常に着地点が用意されている。しかし、ラジオから流れる二人の言葉は、ただそこに存在すること自体が目的であるかのようだった。その声に触れるたび、健斗の心の隅で、乾いてひび割れた地面に水が染み込むような、不思議な感覚が広がっていった。
この音声の正体を突き止めなければならない。健斗は持ち前の調査能力を発揮し始めた。会話に出てきた地名「ひばりが丘」、商店街の「すずらん通り」。それらは、祖父が若い頃に住んでいた街の地名と一致した。健斗は週末、その街を訪れた。再開発で様変わりしていたが、古い地図を頼りに歩くと、微かに昔の面影が残っている。会話に出てきた和菓子屋は、モダンなカフェに変わっていた。
健斗は、このラジオが再生しているのは、祖父が遺した昔の恋人との記録ではないかと推測していた。祖母一筋だと聞いていた祖父の、知られざる一面。軽い背徳感と好奇心が、彼を駆り立てた。彼は、実家の物置を再び捜索し、祖父の古いアルバムを見つけ出した。ページをめくると、色褪せた写真の中に、若き日の祖父と祖母がいた。写真の中の祖母は、ラジオから聞こえる声の主とはどこか違う印象だった。もっとおっとりとして、控えめな女性。声の主は、もっと快活で、太陽のような人ではなかったか。
謎は深まるばかりだった。健斗はいつしか、仕事の合間にも、あの声と、二人が語っていた「未来の種」のことばかりを考えていた。それはまるで、音だけで描かれた宝の地図を解読しているかのようだった。そして、ついに彼は一つの結論に達する。未来の種が埋められているのは、祖父の実家の庭にあった、あの大きな欅の木の下に違いない。
第三章 未来の種、過去の答え
秋風が吹き始めた週末、健斗はシャベルを手に、祖父の実家の庭に立っていた。かつて欅の木があった場所は、今は更地になっている。彼は記憶を頼りに、あたりを付けて土を掘り始めた。ザク、ザク、と乾いた土を掘り返す音だけが響く。効率を考えれば馬鹿げた行為だ。だが、彼を突き動かしていたのは、もはや合理的な思考ではなかった。
三十分ほど掘っただろうか。シャベルの先に、カツン、と硬いものが当たった。慎重に土を掻き出すと、そこから現れたのは、錆びついたブリキの菓子缶だった。健斗は鼓動が速くなるのを感じながら、固く閉ざされた蓋をこじ開けた。
中には、ビニール袋に包まれた一枚の写真と、小さなカセットテープが入っていた。
彼はまず、写真を取り出した。そこに写っていたのは、若き日の祖父と、満面の笑みを浮かべる祖母・千代子。そして……二人に抱きかかえられ、無邪気に笑う三歳くらいの男の子。紛れもない、幼い頃の自分自身の姿だった。
健斗は愕然とした。写真の中の祖母は、彼が記憶していたおっとりとした姿とは全く違った。快活で、太陽のように輝いている。ラジオから聞こえてきた、あの声の主そのものだった。なぜ気づかなかったのだろう。人は、年齢と共に声も姿も変わる。そして自分は、祖母の若い頃を、本当の意味で知ろうとしたことすらなかったのだ。
震える手で、彼は持参した古いカセットプレーヤーにテープを入れた。再生ボタンを押すと、聞き慣れた祖父の声が流れ出した。
『……よし、録音できてるな。千代、何か言ってみろ』
『ええ? なあに、急に。……そうねぇ。未来の私たち、元気でやってますか? 健斗は、大きくなったかしら』
ラジオで聞いていた会話の、前後の部分だった。二人は、生まれて間もない孫のために、このタイムカプセルを作っていたのだ。テープは回り続ける。
『健斗。聞こえるか。じいちゃんだ』
祖父の声が、少し真面目なトーンに変わった。
『お前がこれを聴く頃、じいちゃんもばあちゃんも、もうこの世にいないかもしれん。世の中はきっと、今よりずっと速く、ずっと便利になってるだろうな。だがな、健斗。忘れるな。人生で一番大事なもんは、そういう便利さの中にはない。誰かと一緒に過ごす、くだらない時間。笑ったり、ちょっと喧嘩したりする、どうでもいい時間。そういう無駄な時間の中にこそ、一番大事な宝物が隠されてるんだ』
健斗の視界が、急速に滲んでいった。
『このラジオはな、お前がもし、人生の道に迷って、どっちへ進めばいいか分からなくなった時に、帰り道を照らす灯りになればと思って、じいちゃんが作った魔法なんだ。タイマーで、このテープが流れるだけの、簡単な仕掛けだけどな。……健斗。ちゃんと、飯食ってるか。ちゃんと、笑ってるか』
声が途切れ、テープが終わった。健斗は、その場に崩れるように膝をついた。嗚咽が、喉の奥から止めどなく込み上げてくる。効率。成果。無駄の排除。そうやって自分が切り捨ててきたものこそが、祖父が命をかけて守り、自分に伝えたかった宝物だったのだ。妻が「たまには、何もしないで一緒に映画でも観ない?」と言った時、自分は「その時間に何の意味があるんだ」と冷たく返した。あの時の彼女の、寂しそうな顔が脳裏に焼き付いて離れない。
自分は、祖父が遺した魔法の本当の意味を、今、ようやく理解した。これは過去からの音声ではない。未来の自分へ宛てた、愛という名の、最も切実なメッセージだったのだ。健斗は、秋空の下で、子供のように声を上げて泣き続けた。
第四章 ただいま、そして、これから
あの日を境に、桐島健斗の世界は色を取り戻し始めた。彼がタワーマンションの窓から見下ろす街の景色は、もはや単なる無機質な光の集合体ではなかった。一つ一つの灯りの下に、誰かの「どうでもいい時間」があり、愛おしい人生があるのだと感じられるようになった。
彼の仕事のスタイルが、劇的に変わったわけではない。相変わらず仕事は速く、正確だった。しかし、彼は変わった。プロジェクトの会議で、後輩のとりとめのない雑談に、苛立つ代わりに微笑んで耳を傾けるようになった。その無駄話の中から、思わぬ画期的なアイデアが生まれたことが一度や二度ではない。彼は、人間関係という非効率なものの中にこそ、最高の創造性が眠っていることを知った。同僚たちは、彼の変化を「氷が溶けたようだ」と囁き合った。
ある晴れた日の午後、健斗は公園のベンチに座り、スマートフォンを取り出した。画面に表示されたのは、数ヶ月間、開くことのなかった元妻の名前。彼は深く息を吸い、発信ボタンを押した。謝罪をしたいわけではなかった。やり直したいと懇願するためでもない。ただ、心の底から湧き上がる、素直な気持ちを伝えたかった。
「……もしもし。俺だ。突然ごめん。……いや、大したことじゃないんだ。ただ……君と、どうでもいい話をしながら、ゆっくり散歩でもしたいなって、ふと思っただけなんだ」
電話の向こうで、彼女が息を呑む気配がした。彼女がその申し出を受け入れるかどうかは、まだ分からない。未来は、常に不確定だ。しかし、健斗はもうそれを恐れてはいなかった。
部屋に戻ると、リビングの一番良い場所に置かれたアポロニアが、静かに彼を迎えた。健斗はもう、深夜零時にそのスイッチを入れることはない。魔法の時間は、終わったのだ。彼はラジオにそっと触れ、「ありがとう、じいちゃん」と呟いた。
そして、彼は窓を大きく開け放った。ひんやりとした夜の空気が、街の喧騒を運んでくる。車の走る音、遠くで聞こえるサイレン、アパートの窓から漏れる笑い声。それら全てが、彼が生きる「今」の音だった。祖父が遺してくれた温かい音を胸の内にしまい、彼はこれから、自分自身の音を紡いでいくのだ。
健斗は再びスマートフォンを手に取った。誰にかけるというわけではない。ただ、誰かと繋がりたかった。もう一人で時間を効率的に消費するだけの人生は、終わりだ。祖父の愛という名の灯りを頼りに、彼は未来へと、確かに一歩を踏み出した。その足取りは、もう迷ってはいない。