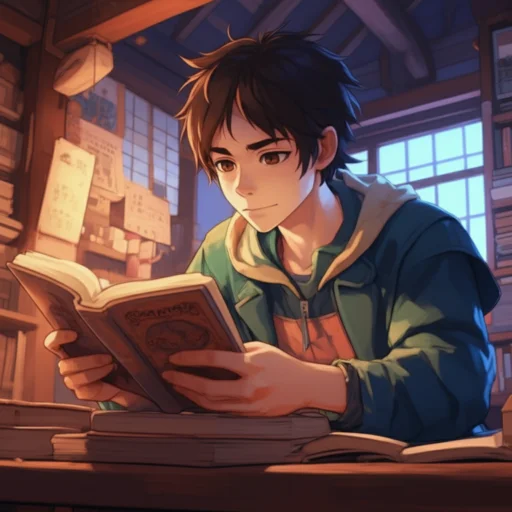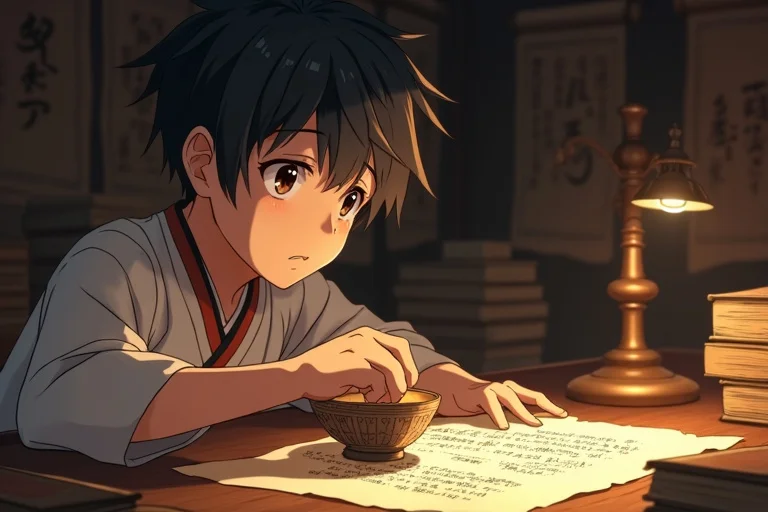第一章 埃の中の邂逅
水野健司は、古紙と黴の匂いが混じり合った空気を吸い込み、静かにため息をついた。神保町の裏路地に佇む古書店「時雨堂」。ひと月前に亡くなった祖父が、人生のすべてを捧げた場所だ。弁護士からの連絡によれば、この店とわずかな預金が健司に遺された唯一の財産だった。
「冗談じゃない」
壁一面を埋め尽くす書架には、背表紙の文字も掠れた和綴じの本や、黄ばんだ洋書がぎっしりと並んでいる。健司にとって、それは価値ある文化遺産ではなく、処分に困る紙の塊でしかなかった。歴史なんて、埃をかぶった過去の記録だ。俺が生きているのは「今」なのに。早くこの店を畳んで、もっとマシな人生を始めたい。その思いだけが、彼をこの陰気な場所に繋ぎとめていた。
その日も、健司は売れ残りの本を段ボールに詰める作業にうんざりしていた。ふと、書架の隅に追いやられた桐の小箱が目に留まる。祖父が「大切なものだ」と言って、誰にも触らせなかった箱だ。蓋を開けると、中には一冊だけ、藍色の布で表装された分厚い手記が収められていた。
何気なくページを繰った、その瞬間。はらりと一枚、羊皮紙のような手触りの紙片が畳の上に落ちた。拾い上げると、そこには万年筆で書かれた流麗な文字が並んでいた。見慣れた祖父の筆跡だ。
『未来の君へ。もし君がこれを見つけたなら、桐野景近という男の魂に触れてほしい』
桐野景近? 聞いたことのない名だ。羊皮紙には、その男のものとされる短い覚書が記されていた。天正十年、本能寺で信長が斃れた直後、主君を裏切り敵方に寝返ったとされる、取るに足らない小豪族の名だった。歴史書では数行で片付けられる、ただの卑劣な裏切り者。
だが、羊皮紙の記述は違った。
『我が裏切りは、汚名を着て一族を永らえさせるための唯一の道。妻の佐紀と、生まれたばかりの息子の寝顔だけが、この胸の痛みを和らげてくれる。願わくば、百年後、千年後の世に、俺の真意を汲む者が現れんことを』
健司は鼻で笑った。なんだ、これは。祖父の創作か? 歴史嫌いの孫をからかうための、手の込んだ悪戯か。しかし、なぜだろう。そのインクの滲み具合や、紙の奇妙な質感から、目が離せなかった。まるで、四百年の時を超えて、名もなき武士の孤独な呟きが聞こえてくるような気がした。健司は、初めてこの埃っぽい店の中で、小さな好奇心の芽生えを感じていた。
第二章 墨痕の道標
祖父の悪戯――そう結論づけるのは簡単だった。だが、健司の心には、桐野景近という男の名が棘のように引っかかっていた。翌日から、彼はまるで何かに憑かれたように、時雨堂の蔵書を漁り始めた。
最初は、ただ祖父の嘘を暴いてやろうという、いささか捻くれた動機からだった。しかし、膨大な古書の世界は、健司の予想を裏切るように、少しずつその深淵を覗かせ始めた。
健司は、羊皮紙に書かれていた『天正十年六月、近江・朽木谷にて』という記述を手がかりに、関連する郷土史や武将の手紙の写しを片っ端から調べ上げた。すると、ある大名家の書状の隅に、走り書きのような形で「桐野勢、我らに内通の由」という一文を見つけた。公的な記録には決して現れない、生々しい情報の断片。健司の心臓が小さく跳ねた。
さらに、別の古文書からは、景近の妻「佐紀」の名と、彼らが治めていた小さな村が、疫病と飢饉に苦しんでいたことを示唆する記述が見つかった。主君は援軍を送らず、見殺しにするつもりだったのではないか。裏切りは、民と家族を救うための苦渋の選択だったのではないか。
点が線になり、線が面になっていく。健司は、眠るのも忘れて古書に没頭した。インクの匂い、和紙の乾いた感触、ページをめくる微かな音。かつては退屈の象徴でしかなかったすべてが、今はスリリングな謎を解くための鍵に思えた。
彼は、桐野景近という人物に、自分を重ね合わせていることに気づき始めていた。歴史の片隅で、誰にも理解されずに汚名を着せられた男。その孤独と葛藤が、何をしたいのかも分からず、社会から取り残されているような自分の焦燥感と奇妙に共鳴した。
「じいさん…あんたは、本当は何を知っていたんだ?」
健司は、祖父の肖像写真に語りかけた。写真の中の祖父は、ただ静かに微笑んでいるだけだった。彼はもはや、店を畳むことなど考えていなかった。この物語の結末を見届けるまでは、ここを離れるわけにはいかない。歴史とは、終わった過去ではない。誰かの強い想いが刻まれた、今に続く道なのだと、健司は感じ始めていた。
第三章 蔵の中の真実
桐野景近の人生を追いかける旅は、一首の和歌に行き着いた。景近が処刑される直前に詠んだとされる辞世の句だ。
『雨上がり 月影宿す 礎(いしずえ)の雫に映る 我が真(まこと)』
健司はこの歌を何度も口ずさむうちに、ある可能性に思い至った。「雨上がり」は「時雨(しぐれ)」の後。「月影宿す礎」は、時雨堂の裏手にある古い石灯籠のことではないか。そして「雫に映る我が真」とは。
いてもたってもいられず、健司は懐中電灯を手に、夜の庭へ飛び出した。雨上がりの湿った土の匂いが立ち込めている。石灯籠の根本を調べると、苔むした台座の一部が、わずかに動くことに気づいた。力を込めてそれをずらすと、ぽっかりと黒い口が開いた。隠し蔵だ。
黴と闇の匂いが噴き出す。錆び付いた梯子を慎重に降りると、そこはひんやりとした石造りの小部屋だった。中央に置かれた小さな木箱。震える手で蓋を開けると、中には黒漆の鞘に収められた短刀と、一通の封書が静かに横たわっていた。
封書を手に取り、健司は息を呑んだ。宛名には、祖父の筆跡で、はっきりと『水野健司へ』と書かれていたのだ。混乱しながら封を切る。そこにあったのは、歴史の真実を告げる手紙ではなかった。
『健司へ。
この手紙を読んでいるということは、君は桐野景近の物語を最後まで旅してくれたのだな。ありがとう。
まず、謝らなければならない。桐野景近という武士は、たしかに実在した。だが、彼が家族を想い、民のために汚名を着たという物語は、すべて、この老いぼれの私が作り上げた創作だ。羊皮紙も、古文書に紛れ込ませた記述も、すべて私が仕組んだものだ。
歴史を嫌う君に、どうすればその面白さと、そこに生きた人々の息吹を伝えられるか。ずっと考えていた。歴史とは、勝者が記した記録の連なりに過ぎない。だが、その行間には、名もなき人々の無数の喜びや悲しみ、そして誰かを想う心が埋もれている。私は、一人の男の「あり得たかもしれない人生」を想像し、君に贈ることにした。
これは偽りの物語だ。だが、もし君が景近の生き様に心を動かされたのなら、その感動は間違いなく本物だろう? 歴史とは、事実を知ることだけではない。そこに生きた人々の心に寄り添い、想いを馳せることなのだと、君に気づいてほしかった。
この店は、君に託す。どうするかは、君が決めなさい。
じいちゃんより』
健司は、その場に崩れ落ちた。追い求めてきたものは、すべて祖父が仕掛けた壮大なフィクションだった。涙が溢れてきた。しかし、それは怒りや失望の涙ではなかった。歴史嫌いの孫のために、これほどまでの愛情と手間をかけてくれた祖父の、不器用で、あまりにも深い想いに対する感謝の涙だった。短刀の冷たい柄を握りしめ、健司は暗闇の中で声を殺して泣いた。
第四章 時雨のあと
夜が明け、蔵から出た健司を、雨上がりの柔らかな朝日が迎えた。空は洗い流されたように澄み渡り、時雨堂の古い瓦を濡らす光は、まるで祝福のようだった。
店に戻った健司は、カウンターに祖父の手紙と短刀をそっと置いた。すべては偽りだった。だが、健司の中で燃え上がった情熱も、桐野景近という男に寄せた共感も、流した涙も、すべてが本物だった。
祖父は、歴史という名の巨大なタペストリーの、一本の「糸」を健司に示してくれたのだ。その糸は、桐野景近という架空の結び目を経て、確かに健司の心に繋がっていた。そして健司は理解した。歴史とは、無数の人々の想いが織りなす、壮大な物語そのものなのだと。勝者も敗者も、名のある者も無き者も、等しくその物語の登場人物なのだ。
健司は、ゆっくりと店内を見渡した。埃をかぶった本の山が、今は愛おしく見えた。一冊一冊に、誰かの人生が、想いが、封じ込められている。この場所は、ただ古い本を売るだけの場所ではない。記録されなかった声や、忘れ去られた物語を拾い上げ、未来へと受け継いでいくための、聖域なのだ。
彼は、祖父がいつも座っていた帳場の椅子に、初めて腰を下ろした。ぎしり、と木が鳴る音は、まるで「よく来たな」という祖父の声のように聞こえた。
数週間後、時雨堂の扉に「営業中」の札が掛けられた。店内は掃き清められ、柔らかな光が差し込んでいる。健司は、訪れた客に、一冊の古い郷土史を手に取って微笑んだ。
「この本には、名前も残らなかった人々の暮らしが記されています。でも、彼ら一人ひとりに、きっと大切な物語があったんですよ」
その声には、かつての無気力さのかけらもなかった。彼の瞳には、過去から未来へと続く、悠久の時の流れを見つめるような、穏やかで確かな光が宿っていた。祖父が遺した最後の物語は、一人の青年の心に、新しい物語の種を蒔いた。時雨堂の歴史は、今、新たな一ページを刻み始めたのだ。