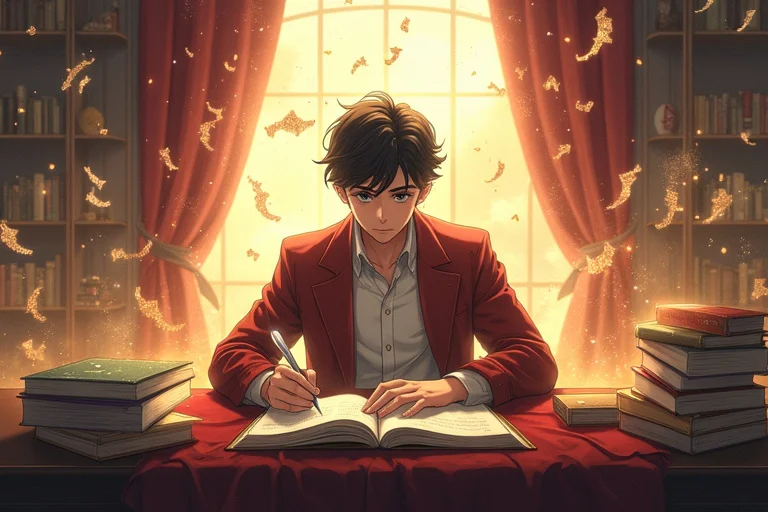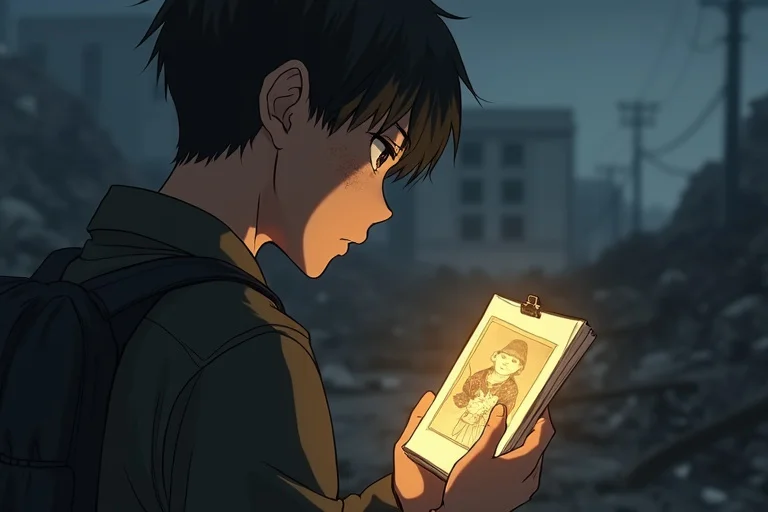第一章 鋼鉄のペンと英雄の歌
インクの匂いが、硝煙の代わりだった。
リヒトの書斎は、アルトリア公国の事実上の最前線だった。壁一面に貼られた戦況図には、赤と青のピンが刺さっているが、彼にとって本当の戦場は、目の前の羊皮紙の上にあった。リヒト・フォン・クラウゼヴィッツ。齢二十五にして、王国最高の栄誉とされる「第一編纂官」の称号を持つ、若き天才。彼の仕事は、物語を紡ぐことだ。
この世界において、戦争の行方を左右するのは、兵器の性能や兵士の数だけではない。それ以上に重要なのが、国民の魂を鼓舞し、戦意を高揚させる「物語」の力だった。そしてリヒトの紡ぐ物語は、常にアルトリアに勝利の風を吹かせてきた。彼のペン先から生まれる英雄たちは、鋼鉄の意志と比類なき勇気を持ち、敵国ヴェストリア連邦の兵士たちをバッタバッタと薙ぎ倒した。その物語は毎夜、国営放送で朗読され、広場の幻灯スクリーンに映し出され、国民は涙し、拳を突き上げ、戦場へ赴く息子や夫を誇らしく送り出した。リヒトの言葉は、銃弾よりも鋭く、砲弾よりも遠くまで届く兵器だった。
「リヒト様、今宵の『獅子心王の凱旋』、またもや素晴らしい出来栄えでした。これで徴兵志願者も増えるでしょう」
補佐官の言葉に、リヒトは無言で頷いた。窓の外では、自分の物語に熱狂する市民たちの歓声が地鳴りのように響いている。満足感と、ほんの少しの倦怠感。同じような英雄譚を、表現を変え、舞台を変え、もう何年も書き続けている。だが、それが彼の使命だった。勝利のために、国のために。
その日常が、僅かに軋み始めたのは、数週間前のことだ。敵国ヴェストリアから、奇妙な「物語」が流れ込み始めたのだ。それは密かに持ち込まれた手書きの写本や、短波放送に乗せられた掠れた音声データという形で、アルトリア国内に静かに拡散していた。
リヒトも、諜報部が手に入れた写本の一つに目を通した。そこには、英雄など一人も登場しない。描かれているのは、ヴェストリアの一兵士が、塹壕の中で故郷のパンの味を思い出すだけの、とりとめのない独白。あるいは、幼い娘が、前線の父親に宛てて書いた、日々の出来事を綴る拙い手紙。劇的な展開も、勇ましい言葉もない。ただ、そこには生身の人間の、ささやかな生活の匂いと、静かな哀しみが満ちていた。
「くだらん。このような感傷的な文章が、何になるというのだ」
リヒトはそう吐き捨てた。だが、無視できない変化が起きていた。広場の歓声の熱量が、心なしか下がっている。徴兵事務所の列が、少しだけ短くなった。リヒトの英雄譚がもたらす熱狂の合間に、人々はまるで禁じられた果実を味わうかのように、敵国の名もなき物語に耳を傾け、静かに涙を流し始めていたのだ。それは熱い炎ではなく、冷たい水がゆっくりと染み渡るような、不気味な浸透だった。
リヒトの鋼鉄のペンが、初めて迷いを見せた瞬間だった。彼の知らないところで、もう一つの戦争が始まっていた。
第二章 沈黙の戦場
自分の言葉が、届かなくなっている。
その焦燥感に駆られ、リヒトは前線への視察を願い出た。机上の空論ではなく、本物の戦場の空気、兵士たちの生の声を聞けば、きっと新たな英雄譚の霊感が湧くはずだ。最高司令部の許可を得た彼は、軍用車両に揺られ、泥と硝煙の匂いが立ち込める東部戦線へと向かった。
しかし、彼がそこで見た光景は、自身の物語とはあまりにもかけ離れていた。
英雄などどこにもいなかった。いるのは、泥水に濡れた毛布にくるまり、虚ろな目で空を眺める、疲弊しきった若者たちだけだった。彼らの顔には、リヒトが描いてきたような勇敢さや愛国心といった高尚な感情は浮かんでいない。あるのは、極度の疲労と、死への恐怖と、そして故郷への渇望だけだった。
「編纂官様が、わざわざこんな泥沼に」
部隊長が、卑屈な笑みを浮かべて出迎えた。
「兵士たちに、何か威勢のいいお話を一つ、お願いできませんか。近頃、どうも士気が上がらなくて」
リヒトは頷き、兵士たちが集まる粗末なテントに入った。彼は即興で、この部隊の小さな功績を元にした英雄譚を語り始めた。敵の分隊を退けた一人の伍長の姿を、獅子のごとき勇猛さで描いてみせた。しかし、兵士たちの反応は鈍かった。数人が力なく拍手したが、ほとんどは無表情に聞いているだけだ。彼らの目は、「お前が語っているのは、俺たちのことではない」と雄弁に物語っていた。
その夜、リヒトは眠れずに、一人の若い兵士と話す機会を得た。まだ十代にしか見えない、顔にそばかすの残る少年兵だった。
「君は、どうして志願したんだ?」
リヒトの問いに、少年は少し考えてから、ぽつりと答えた。
「あなたの物語を、聞いたからです。『暁の鷲』…カッコよかった。国のために死ねるなら、本望だと思ってました」
「では、今は?」
少年は、自分の泥に汚れた手を見つめた。
「今は…母さんの作ったスープが飲みたいです。ただ、それだけです。敵の兵隊だって、きっと同じことを考えてるんだろうなって…時々、思うんです」
少年の言葉は、リヒトの胸に小さな、しかし鋭い棘のように突き刺さった。彼は、この少年兵のような無数の若者を、自分の言葉で戦場に送り込んできたのだ。彼らに英雄という名の美しい幻想を見せ、その裏にある泥臭い現実から目を逸らさせてきた。
焚き火の向こうから、誰かが口ずさむ歌が聞こえてきた。それはアルトリアの勇ましい軍歌ではなかった。ヴェストリアから流れてきた、あの名もなき物語の一つだった。故郷の恋人を想う、哀切なメロディ。兵士たちは、敵も味方もなく、その歌に静かに耳を傾けていた。戦場の沈黙の中で、その小さな歌声だけが、唯一の真実のように響いていた。
リヒトは愕然とした。自分のペンは、この静かな歌声に、決して勝てない。彼は一体、何と戦っていたのだろう。
第三章 無数の声の奔流
首都に戻ったリヒトは、書斎に閉じこもった。羊皮紙は白紙のまま、インクの瓶は埃を被り始めていた。彼の内側で、信じてきたもの全てが崩れ落ちていく音がした。英雄譚は嘘だ。少なくとも、真実の全てではない。では、真実とは何か?あの少年兵の言葉か。あの哀しい歌か。
彼は諜報部に命じ、あらゆる手段を使って敵国ヴェストリアの「物語」に関する情報を集めさせた。誰が書いているのか。どんな組織が、これほど人の心を掴む物語を量産しているのか。恐るべき才能を持つ、ヴェストリアの「編纂官」の正体を突き止めたかった。そいつを論破し、その物語の欺瞞を暴けば、まだ勝機はあるかもしれない。
数週間後、もたらされた報告書を読み、リヒトは絶句した。
そこには、信じがたい事実が記されていた。
「――ヴェストリア連邦に、特定の『編纂官』は存在しない」
報告書は続く。ヴェストリア政府は、戦争初期にプロパガンダ戦略でアルトリアに敗れた後、方針を百八十度転換した。彼らは、国民が書くもの、語るもの、歌うもの、その一切の検閲を放棄したのだ。兵士からの手紙、市民の日記、子供の落書き、労働者の歌。それら無数の「個人の物語」が、何の統制もなく、国内を自由に流通し始めた。政府はただ、それらを集め、国境を越えて流す手助けをしていただけだった。
敵の「物語」の正体は、一人の天才が紡いだ虚構ではなかった。それは、何百万人という国民一人ひとりの、ささやかな日常と感情が寄り集まって生まれた、巨大な「声の奔流」だったのだ。英雄譚のような熱狂はない。しかし、一つ一つの声は紛れもない真実であり、その集合体は、どんなに巧みなフィクションよりも強く、深く、人の心を揺さぶる力を持っていた。
リヒトは震える手で報告書を置いた。負けた。完全に。
彼は、一人の天才が紡ぐ「偉大な物語」こそが世界を動かすと信じていた。だが、ヴェストリアが示したのは、全く逆の真実だった。世界を動かすのは、名もなき人々の「無数の小さな物語」の方だったのだ。彼は、たった一人で、何百万という声の奔流に立ち向かおうとしていた。あまりにも愚かで、傲慢な戦いだった。
壁の戦況図が、色褪せた絵画のように見えた。赤と青のピンが示す国境線など、もはや何の意味も持たない。本当の戦いは、英雄の物語と、名もなき人々の物語の間で繰り広げられていた。そして、その勝敗は、もう決していた。
第四章 最後の物語
その日、リヒト・フォン・クラウゼヴィッツは、鋼鉄のペンを折った。
そして彼は、新しいペンを取った。それは英雄を讃えるためのペンではない。栄光を刻むためのペンでもない。ただ、記録するための、ありのままを書き留めるためのペンだった。
彼は書斎を出て、街に出た。傷痍軍人が集う酒場へ、夫の帰りを待つ女性たちの裁縫教室へ、父親の顔を知らない子供たちが遊ぶ孤児院へ。彼は、ただ彼らの話を聞いた。そして、聞いた言葉を、見た光景を、感じた匂いを、一つ残らず羊皮紙に書き留めていった。
「主人はね、鼻の頭を掻く癖があったんですよ。照れると、いつも…」
「俺の足は、英雄の勲章なんかじゃねえ。ただの鉄クズさ。夜になると、失くしたはずのつま先が疼くんだ」
「パパは、お空の星になったってママは言うけど、本当はどこにいるの?」
リヒトはもう、物語を「創作」しなかった。彼は、既にそこに存在する無数の物語の、忠実な「聴き手」になった。彼の羊皮紙は、英雄の名前ではなく、スープの味や、子守唄のメロディや、叶わなかった約束の言葉で埋め尽くされていった。それは勝利のための物語ではない。それは、戦争によって失われ、忘れ去られようとしている、人間性の欠片を集める作業だった。
数ヶ月後、リヒトは書き上げた膨大な記録を、一冊の本にまとめた。タイトルはなかった。彼はそれを最高司令部でも、国営放送局でもなく、かつて自分の英雄譚を熱心に読んでくれていた、街の小さな新聞社に持ち込んだ。
「これを、掲載してほしい。アルトリアの、声なき者たちの声を」
彼の行動が、どのような結果を招くか、リヒトには分からなかった。国家への反逆と見なされ、処刑されるかもしれない。あるいは、無視されるだけかもしれない。だが、彼にもう迷いはなかった。勝利のために言葉を費やす時代は終わった。これからは、終わらせるために、思い出すために、言葉を使わなければならない。
彼の「最後の物語」は、翌朝の新聞の一面を飾った。それは、ヴェストリアの物語と同じように、静かに、しかし確実に、アルトリア国民の心に染み渡っていった。人々は英雄譚の熱狂から醒め、初めて隣人の、そして自分自身の心の奥底にある、本当の痛みに気づき始めた。
戦争がいつ終わったのか、歴史書は明確な日付を記すだろう。しかし、本当の意味で戦争が終わったのは、人々が英雄の歌を歌うのをやめ、隣で泣いている誰かのために、そっとハンカチを差し出すようになった、その瞬間だったのかもしれない。
リヒトの物語は、こう締めくくられていた。
『――今日、私は前線から届いた一通の手紙を読んだ。そこにはこう書かれていた。「昨日、敵の塹壕から歌が聞こえた。それは、俺の村の母親が、よく歌ってくれた子守唄だった。俺は、引き金を引けなかった」。このインクが乾く頃、世界はまだ変わらないかもしれない。だが、一人の兵士が引き金を引けなかったという事実。その小さな物語こそが、我々が守るべき、唯一の国境線なのだ』