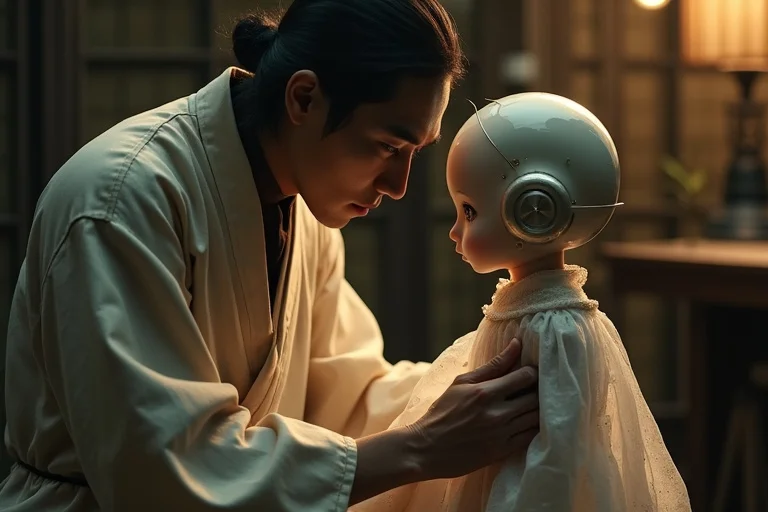第一章 墨痕の不協和音
弦之助(げんのすけ)の世界は、音に満ち、色で溢れていた。
雨垂れの音は、銀鼠の円を描いて広がり、雀のさえずりは、山吹色の細い線となって空に溶ける。常人にはただの物音でしかないものが、彼の目には万華鏡のように絶えず変化する色彩として映るのだ。人々はこの特異な感覚を「共感覚」と呼ぶことすら知らない。弦之助にとって、それは生まれついての呪いであり、誰にも理解されぬ孤独の源だった。
かつては武家の次男として、将来を嘱望された身。しかし、初陣で味わった地獄が彼の人生を変えた。敵味方の怒号は濁った血赤色に、肉を断つ剣戟の音は紫電の閃光に、そして断末魔の叫びは、魂を削るような黒鉛の色となって、彼の視界を塗り潰した。その悍(おぞ)ましい色彩の洪水に精神を病み、弦之助は刀を捨てた。今では城下の片隅で墨絵師として筆一本で生計を立て、ただ静かに、世界から音を遮断するように生きていた。
その静寂を破ったのは、初冬の冷たい空気を震わせる、役人たちの慌ただしい足音だった。鈍い鉛色の響きを放つその音に、弦之助は眉をひそめる。戸板を叩く音は、彼の目には汚れた茶褐色の染みとなって映った。
「開けい! 弦之助殿はおられるか!」
扉を開けると、同心頭の厳めしい顔があった。彼の声は、疑念に満ちた錆び色の棘となって弦之助に突き刺さる。
「昨夜、茶人の千宗(せんそう)殿が自室で殺害された。発見されたのは今朝方だ」
千宗。この城下で知らぬ者のない、高名な数寄者だ。弦之助も、彼の依頼で茶室に飾るための山水画をいくつか納めたことがあった。
「……それは、お気の毒に」
感情を排した声で応じる弦之助に、同心は鋭い視線を向けた。
「現場は内側から閂(かんぬき)のかかった密室。そして……現場には、これがあった」
同心が突き出したのは、一枚の和紙だった。そこに描かれていたのは、荒々しい筆致で描かれた一本の枯れ木。それは紛れもなく、弦之助の作風そのものだった。いや、あまりに似すぎていた。まるで、彼自身が描いたかのように。
「これは、拙者が描いたものではござらん」
弦之助は静かに否定した。だが、彼の耳には、周囲に集まった野次馬たちの囁き声が、無数の小さな泥色の斑点となって飛び込んでくるのが見えた。疑念、好奇心、そしてわずかな敵意。
「現場から見つかった唯一の物証が、おぬしの絵と瓜二つ。言い逃れはできんぞ」
同心の声は、確信に満ちた濃紺の色を帯びていた。
弦之助は目を閉じた。脳裏に蘇るのは、昨夜、工房で筆を走らせている時に遠くから聞こえた、微かな音。それは今まで一度も見たことのない、奇妙な色をしていた。鈍い黄金の光が、毒々しい紫の靄(もや)に絡みつかれ、もがき苦しむような……不吉な色彩。あの音は何だったのか。そして、誰が、何のために自分を陥れようとしているのか。
呪われたこの眼(まなこ)だけが、事件の真相を知る唯一の手がかりなのかもしれない。弦之助は、逃れられぬ運命の渦に引きずり込まれていくのを、ただ感じていた。
第二章 色彩の証言
弦之助は、三日間の猶予を得た。潔白を証明できなければ、捕縛される。彼は自らの呪われた能力を、初めて探偵の道具として使うことを決意した。頼れるのは、音が見せる「色」だけだ。
まず訪ねたのは、千宗の一番弟子である宗悦(そうえつ)の屋敷だった。師を亡くしたばかりだというのに、彼の佇まいに悲しみの色は薄い。
「師は、近頃何やら思い詰めたご様子でした」
宗悦の声は、淀んだ緑色をしていた。その言葉の表面を、薄い灰色の膜が覆っている。嘘ではない。だが、何かを隠している者の色だ。
「何か、心当たりは?」
弦之助が問うと、宗悦は一瞬口ごもった。彼の喉から漏れた微かな息の音が、暗い赤の染みとなって宙に浮かぶ。恐怖の色だ。
「……さあ。ただ、師は『夜啼鳥(よなきどり)』と名付けた古い唐物の茶碗を、命よりも大事にしておられました。それが、事件の後、どこにも見当たらないのです」
夜啼鳥。弦之助の記憶にはない名だった。
次に、千宗と茶道具の目利きを巡って対立していたという武士、馬場主水(ばばもんど)を訪ねた。主水は千宗を「俗物」と罵り、その死を嘲笑さえした。彼の言葉は、棘々しい焦茶色となって弦之助を苛んだ。だが、その色彩の奥に、嘘偽りの色は見えない。彼はただ、本心から千宗を嫌っていただけなのだろう。
聞き込みを続けるほど、弦之助の心は混乱した。誰もが何かを隠し、誰もが怪しく見える。人々の言葉が織りなす色彩は、複雑な模様を描き、真相を覆い隠していく。焦りだけが募る中、彼の脳裏には、あの夜に聞いた奇妙な音の色が焼き付いて離れなかった。鈍い黄金と毒々しい紫。あの音の正体さえ掴めれば……。
工房に戻った弦之助は、改めて現場にあったという枯れ木の絵の写しと向き合った。一見、それは乱雑な筆遣いに見える。だが、見つめ続けるうち、彼はある違和感に気づいた。墨の濃淡、線の強弱、掠(かす)れ具合……それらは無秩序なのではない。まるで、何かの規則性を持っているかのようだ。
彼は息を呑んだ。これは、ただの絵ではない。
彼の目には、この墨絵が「音」として見え始めていた。太い線は低い音、細い線は高い音。墨の濃淡は、音の強弱。それは、無言の楽譜。殺された千宗が、犯人の前で描いた、声なき旋律。
弦之助は、その墨の楽譜を、震える声で辿り始めた。最初はたどたどしく、やがて一つの旋律となって彼の口から紡がれる。
その瞬間、全身に鳥肌が立った。
その旋律は、彼の記憶の最も深い場所に、大切に仕舞われていたものだった。幼い頃、今は亡き父が、眠れぬ夜の彼にだけ口ずさんでくれた、優しい子守唄。
なぜ。なぜ、千宗がこの唄を知っていた? なぜ、これを死の間際に遺した?
頭の中で、バラバラだった色彩の欠片が、一つの巨大な絵を形作り始めた。父の死、千宗の死、そして、自分だけが持つこの能力。全てが、一本の黒い糸で繋がっていた。
第三章 夜啼鳥の旋律
父、桐生景正(きりゅうかげまさ)は、清廉潔白な武士だった。しかし、彼が藩の勘定方を務めていた十年前、公金横領という濡れ衣を着せられ、志半ばで病死した。いや、病死とされた。父の最期の言葉は、悔しさに満ちた濁流のような赤黒い音となって、幼い弦之助の記憶に刻まれている。
千宗が遺した墨絵の旋律が、父の子守唄だったという事実。それは、この事件が単なる殺人ではないことを示唆していた。千宗は、弦之助の父の死の真相を知っていたのではないか。そして、それを弦之助に伝えようとしていたのではないか。犯人は、弦之助の父を陥れた者と同一人物である可能性が高い。そしてその犯人は、弦之助が「音を色として見る」特異な能力を持つことまで知っていたのだ。この墨絵は、弦之助にしか解けない、命がけの伝言(ダイイング・メッセージ)だったのだ。
弦之助は、夜啼鳥の茶碗について、もう一度調べ始めた。古物商を回り、古老の話を聞く。そして、ある一つの言い伝えに行き当たった。
「夜啼鳥の茶碗は、ただの器ではねえ。特別な音階……七つの音を正しい順で奏でると、器自体が共鳴し、まるで鳥が啼くような、天上の音色を響かせるそうだ」
七つの音。子守唄の旋律も、七つの音で構成されている。
全てが繋がった。
犯人は、千宗から夜啼鳥の茶碗の秘密を聞き出そうとした。だが千宗は口を割らず、逆に犯人の前で、弦之助へのメッセージとなる墨絵を描いた。それに気づいた犯人は千宗を殺害し、茶碗を奪って逃げた。あの夜、弦之助が聞いた「鈍い黄金と毒々しい紫」の音。あれこそ、犯人が夜啼鳥を無理やり鳴らそうとして失敗した音に違いない。正しい旋律を知らぬがゆえに、茶碗は悲鳴を上げたのだ。
では、父を陥れ、千宗を殺し、夜啼鳥を奪った犯人は誰なのか。
弦之助の脳裏に、一人の男の顔が浮かんだ。父の親友であり、父の死後、その後釜に座り、今や藩の家老にまで出世した男。榊原宗一郎(さかきばらそういちろう)。
幼い頃、弦之助は榊原に可愛がられた記憶がある。彼の声は、いつも穏やかで、澄んだ青緑色に見えていた。だが、父の葬儀の日、慰めの言葉をかける彼の声に、一瞬だけ、泥水のような澱んだ色が混じったのを、弦之助は見逃さなかった。当時はその意味を理解できなかったが、今ならわかる。あれは、偽りの色だ。
弦之助は立ち上がった。手にするのは刀ではない。工房の隅にあった、刀を鍛える際に使う鉄の棒と、小槌。彼はこれから、戦いに行くのだ。音と、色を武器にして。
彼の心は、恐怖ではなく、不思議なほどの静けさに満たされていた。呪いだと思っていたこの力は、父が遺してくれた、真実を暴くための絆だったのかもしれない。父の無念を晴らす。その決意が、彼の視界に広がる世界の色を、より一層鮮やかに、力強く映し出していた。
第四章 瑠璃色の残響
家老屋敷の静まり返った一室で、榊原宗一郎は穏やかな笑みで弦之助を迎えた。彼の周りには、高価な調度品が並び、その声は昔と変わらず、落ち着いた青緑の色をしていた。だが、今の弦之助の目には、その色彩の表面を覆う、薄汚れた灰色の膜が見えていた。巧妙に隠された、嘘と欺瞞の色だ。
「息災であったか、弦之助殿。絵師として大成したと聞き、亡き友も喜んでおろう」
「榊原殿。父の子守唄を、ご存知ですな」
弦之助の単刀直入な言葉に、榊原の瞳がわずかに揺れた。部屋の空気が張り詰め、青緑の声色が、一瞬、黒ずんだ赤銅色に変わる。
「……何のことかな」
「千宗殿は、死の間際にあの唄を墨絵に遺された。そして、夜啼鳥の茶碗が消えた。あの茶碗は、父があなたに友情の証として贈ったものではなかったか」
弦之助の言葉は、確信に満ちた深い藍色となって榊原に迫る。榊原の顔から笑みが消えた。穏やかだった声の色は完全に剥がれ落ち、どす黒い欲望と焦燥の入り混じった、醜い色へと変貌していた。
「……あの阿呆が! 死ぬ前に余計なことを!」
ついに本性を現した。榊原は語り始めた。藩の財政を私物化していたこと。それに気づいた父、景正を、邪魔者として病に見せかけて毒殺したこと。そして、景正から贈られた夜啼鳥の茶碗が、実は巨万の富を生むための「鍵」であったことを最近知り、その秘密を知る千宗を問い詰め、殺害したこと。
「あの茶碗は、南蛮の王族が持つ隠し金庫を開けるための鍵なのだ! あの旋律さえあれば……!」
榊原が立ち上がり、隠していた脇差を抜いた。その切っ先が放つ殺気は、鋭い銀色の棘となって弦之助の目に突き刺さる。
弦之助は後ずさりながら、懐から鉄の棒と小槌を取り出した。
「お主も父と同じ場所へ送ってやる!」
榊原が踏み込んできたその瞬間、弦之助は小槌で鉄の棒を力強く打ち鳴らした。
キィィィン――!
甲高く澄んだ音が、部屋中に響き渡る。それは、ただの音ではなかった。弦之助の全ての怒り、悲しみ、そして父への想いを乗せた、断罪の響き。彼の目には、その音が鮮烈な紅蓮の炎となって燃え盛り、榊原の醜い野望の色を焼き尽くしていくのが見えた。
音の衝撃に、榊原が一瞬怯む。その隙に、障子の外に控えていた同心たちが一斉になだれ込み、驚愕する家老を取り押さえた。弦之助が事前に、自らの推理を伝えていたのだ。
全てが終わった。捕縛され、悪態をつく榊原の声は、もはや何の力も持たない、惨めな墨色にしか見えなかった。
数日後、弦之助は千宗の墓前にいた。彼の傍らには、榊原の屋敷から見つかった夜啼鳥の茶碗が置かれている。彼はそっと、父の子守唄を口ずさんだ。だが、茶碗は共鳴せず、ただ静寂を守っている。南蛮の王族の鍵などという話は、榊原の妄想が生んだ虚構だったのかもしれない。あるいは、茶碗は真に清らかな心を持つ者の前でしか啼かないのかもしれない。
どちらでもよかった。
弦之助は、呪いだと思っていた自らの力を受け入れていた。それは、人の心の真実を映し出す鏡であり、亡き父と千宗が繋いでくれた、希望の光だった。
彼はもう、刀を手にすることはないだろう。だが、墨と筆を手に、この世界に満ちる音と心を、色彩として描き続けることを決めた。悲鳴の色ではない。喜びや、悲しみや、愛おしさといった、人の営みの全てを。
夕暮れの光が、千宗の墓石を柔らかく照らしている。弦之助の目には、亡き二人への感謝の念が、どこまでも澄み渡る、穏やかな瑠璃色の残響となって、静かに世界に溶けていくのが見えていた。彼はもう、この音と色に満ちた世界を、恐れてはいなかった。