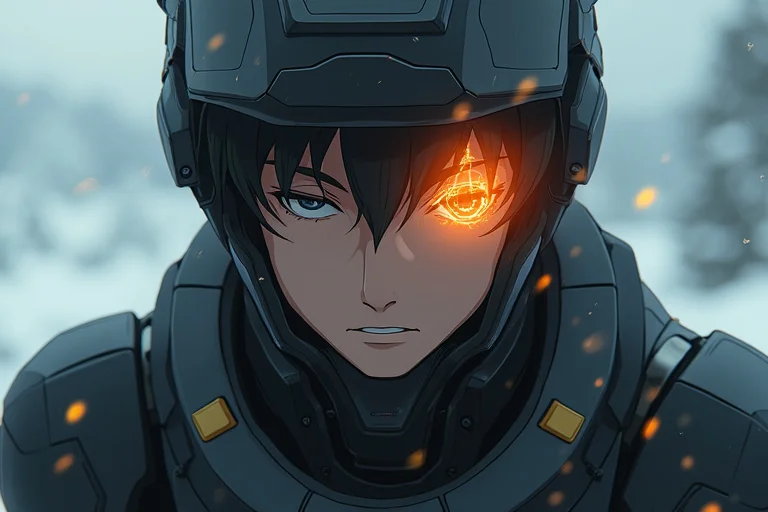第一章 混ざり合う景色
泥と硝煙、そして鉄が錆びる匂いが、ユキオの肺を満たしていた。塹壕の壁に背を預け、握りしめたライフルの冷たさだけが、自分がまだ生きているという唯一確かな感覚だった。これが初陣だった。故郷の村で、家族や友人たちに「英雄になる」と誓ってから、わずか三ヶ月。英雄という言葉の軽薄さが、今は胃の底に鉛のように沈んでいる。
「敵影、前方!」
隣に伏せた古参兵の野太い声が、ユキオの鼓膜を震わせた。反射的に身を低くし、塹壕の縁からそっと目を覗かせる。霧雨が煙る丘の向こうから、灰色の軍服をまとった影が数人、こちらへ向かってくる。その動きは機械的で、人間味を感じさせなかった。そうだ、あれは敵だ。家族を脅かし、故郷を焼く怪物だ。殺さなければ、殺される。上官が何度も繰り返した言葉が、頭蓋の内側で反響する。
ユキオはライフルの照準を、先頭を走る兵士に合わせた。自分とそう年の変わらない、まだ少年と言ってもいい顔立ちだった。雨に濡れた前髪が額に張り付いている。その瞬間だった。
世界が、ぐにゃりと歪んだ。
目の前の敵兵の顔が、突如として鮮やかな色彩を帯びる。照準器の中の景色ではない。ユキオの脳内に、直接流れ込んできた映像だった。
―――陽光が降り注ぐ窓辺。テーブルの上には、焼きたてのパンの香ばしい湯気が立ち上っている。小さな女の子が、覚束ない手つきでユキオの(いや、敵兵の)指を握る。その柔らかな感触、温もり。「お兄ちゃん」と呼ぶ、鈴の鳴るような声。
「う、ぁ……」
ユキオの口から、意味をなさない声が漏れた。何だ、これは。この記憶は、俺のものではない。なのに、どうしてこんなにも懐かしく、胸が締め付けられるのだ。焼きたてのパンの甘い香りが、鼻腔の奥にこびりついて離れない。
混乱で指が動かない。引き金を引けない。その一瞬の躊躇が、命運を分けた。
敵兵のライフルが火を噴き、灼熱の痛みがユキオの左肩を貫いた。身体が後ろに吹き飛ばされ、泥水の中に倒れ込む。遠のいていく意識の中で、ユキオは敵兵の顔を見た。彼は、一瞬だけ目を見開き、何かにおびえるような表情を浮かべていた。まるで彼もまた、ユキオの記憶―――故郷の祭りの夜、線香花火の儚い光を見つめる妹の横顔―――を垣間見たかのように。
第二章 鈍色の錠剤
野戦病院の白い天井を見つめながら、ユキオは左肩の鈍い痛みに耐えていた。軍医は、幸い骨には達していないと言った。だが、ユキオを苛んでいたのは肉体の傷ではなかった。
「記憶混濁だ。敵の新型精神攻撃の一種らしい」
見舞いに来た小隊長は、苦々しい顔でそう説明した。「敵と至近距離で対峙した際に、幻覚や偽の記憶を見せられ、戦闘意欲を削がれる。お前もそれにやられたんだ」
それからユキオたち前線の兵士には、一日二回、鈍い鉛色をした錠剤が支給されるようになった。思考を霧の中に閉じ込めるような、重たい効き目の薬だった。これを飲めば、記憶の流入を防げるのだという。
だが、薬は完全ではなかった。霧の切れ間から差し込む光のように、断片的な記憶は容赦なくユキオの意識に侵入してきた。
射撃訓練の的の向こうに、敵兵の恋人が泣き崩れる姿が見える。夜、毛布にくるまると、敵兵が母親に宛てて書いた手紙の、インクの匂いを感じる。行軍の最中、不意に口ずさんだ歌が、敵国の童謡であることに気づいて愕然とする。
彼らにも、家族がいて、恋人がいて、守りたい日常があった。自分と、何が違うというのだ。
ユキオの指は、引き金を引くたびに震えた。かつてあれほど燃え盛っていた愛国心や敵愾心は、流れ込んでくる無数の記憶の雨に打たれ、今や消えかけの熾火のようにか細く揺らめいているだけだった。
「貴様、最近腑抜けているぞ!」
上官に殴られ、仲間からは「臆病者」と囁かれた。誰も、ユキオの苦しみを理解しない。いや、彼らもまた、同じ恐怖を鈍色の錠剤で無理やり心の奥底に押し込めているだけなのかもしれなかった。
ユキオは自分がゆっくりと壊れていくのを感じていた。敵の記憶と自分の記憶の境界線は日に日に曖昧になり、自分という存在そのものが、寄せ集めのガラクタのように思えてならなかった。
第三章 砕かれた万華鏡
冬が訪れ、戦線は膠着していた。両軍は「鷲ノ巣丘陵」と呼ばれる戦略的要衝を巡り、血で血を洗う消耗戦を繰り広げていた。ユキオの所属する部隊も、その地獄へと投入された。
砲弾が空を裂き、大地が揺れる。泥と雪と血にまみれた丘は、さながら巨大な墓場のようだった。敵も味方もなく、ただ夥しい数の死体が折り重なっている。
総攻撃の号令と共に、ユキオは塹壕を飛び出した。もはや思考は麻痺していた。ただ、機械のように足を前に進めるだけだ。その時、近くで砲弾が炸裂し、爆風で吹き飛ばされたユキオは、偶然にも敵の塹壕へと転がり落ちた。
そこには、一人の敵将校がいた。肩から血を流し、壁にぐったりと寄りかかっている。階級章からして、かなりの高官らしかった。将校はユキオに気づくと、ゆっくりと拳銃に手を伸ばしたが、すぐにその手を下ろした。その瞳には、敵意も憎悪もなかった。ただ、深い諦観と、何かを伝えようとする切実な光が宿っていた。
彼は言葉を発することなく、ただじっとユキオを見つめた。そして、ふっと息を吐くと、そのまま動かなくなった。
将校が息絶えた、その瞬間。
これまで経験したことのない、巨大な記憶の津波が、ユキオの精神を飲み込んだ。
それは単なる断片ではなかった。一人の人間の、濃密な一生分の記憶だった。
―――軍人としての誇り。愛する妻との結婚式。生まれたばかりの息子を抱いた時の、震えるほどの感動。そして……。
ユキオは見た。信じがたい光景を。
目の前で死んだこの将校が、敵国の最高司令官として、なんと自国の指導者と中立地帯で密会している光景を。彼らは、固い握手を交わしていた。
「戦争を終わらせるのだ」指導者は言った。「これ以上の犠牲は、両国にとって破滅でしかない」
「しかし、軍上層部も民衆も、憎しみに囚われている。今さら停戦などと呼びかけても、誰も聞き入れはしないでしょう」と将校は答える。
「だから、これを使う」
指導者が示したのは、試験管に入った黄金色の粒子だった。「『共感粒子(エンパシー・ダスト)』。これを戦場に散布する。兵士たちの意識をナノレベルで繋ぎ、敵の記憶を強制的に共有させる。敵が自分と同じ、心ある人間だと理解させれば、彼らはもう引き金を引けなくなるはずだ」
それは、あまりに理想主義的で、そして悲痛な計画だった。戦争を憎む者たちが、戦争を終わらせるために生み出した、最後の手段。
だが、計画は歪められた。両国の軍部は、この計画の存在を知るや、それを隠蔽。兵士たちに「敵による精神攻撃だ」と偽りの情報を与え、憎しみを煽り、戦争を継続させるための口実として利用したのだ。指導者たちの平和への願いは、戦争を商売にする者たちの野心によって、砕かれた万華鏡のように無惨な破片と化した。
ユキオは、冷たい塹壕の底で、声を殺して泣いた。流れ込んできた将校の無念、指導者たちの苦悩、そして何より、何も知らずに殺し合いをさせられていた自分たち兵士の愚かさが、胸を張り裂きそうにした。
彼の信じていた大義は偽りだった。憎むべき敵は、目の前の兵士ではなかった。真の敵は、この狂ったシステムそのものだった。
第四章 最初の言葉
夜が明けた。凍てついた丘の上に、弱々しい冬の太陽が昇る。ユキオはゆっくりと身を起こした。彼の瞳は、昨日までとはまるで違う、静かで深い光を湛えていた。悲しみも怒りも通り越し、そこには鋼のような覚悟が宿っていた。
彼は、傍らに転がっていたライフルを拾い上げると、それを静かに泥の中へと突き立てた。墓標のように。
「ユキオ!何をしている!」
味方の兵士が叫ぶが、ユキオは振り返らなかった。彼は無防備なまま塹壕から這い上がり、丘の頂上に向かって、一歩、また一歩と歩き始めた。
霧の向こうから、敵の狙撃兵が彼に照準を合わせるのが見えた。死ぬかもしれない。だが、もう恐怖はなかった。
ユキオは息を吸い込み、叫んだ。その声は、砲声の止んだ静かな戦場に、奇妙なほどはっきりと響き渡った。
「君の妹さんは、ピアノが上手なんだろう!いつも窓辺で、『月光』を弾いていた!」
丘の向こうで、ライフルの銃身が微かに揺れた。それは、昨夜ユキオに流れ込んできた、数えきれない記憶の断片の一つだった。
ユキオは歩き続けた。次に遭遇したのは、警戒しながら後退する若い敵兵の一団だった。彼らは一斉にユキオに銃口を向ける。
ユキオは、先頭に立つ兵士の目を見て、静かに言った。
「あなたの母親が作るスープは、少しだけ塩辛い。でも、それがあなたの好物なんだ」
兵士の目が見開かれる。
ユキオは続けた。隣の兵士に。「君が恋人に贈った青い花の名前は、忘れな草だ」
また隣の兵士に。「お前の親父さんは、口癖のように『人生は博打だ』と言っていた」
一人、また一人と、兵士たちの顔から険が消えていく。彼らは銃を下ろし、困惑と驚愕の表情で互いの顔を見合わせた。やがて彼らは、目の前の敵であるユキオの瞳の中に、そして隣に立つ味方の瞳の中に、自分の故郷の夕焼けや、愛する家族の面影を見出し始めていた。
銃声は、完全に止んだ。
まだ戦争が終わったわけではない。この丘の上で起きている小さな奇跡が、すぐに世界を変えるわけでもないだろう。
しかし、戦場の真ん中で、昨日まで殺し合っていたはずの兵士たちが、武器を下ろし、ぎこちない沈黙の中でお互いを見つめ合っている。やがて、誰かが、震える声で最初の言葉を発した。
「俺の故郷では……」
その光景を、ユキオは丘の上から静かに見つめていた。彼の内で鳴り響いていた数多の記憶の残響は、もはや不協和音ではなかった。それは、静かで、しかし確かな希望に満ちた、新しい交響曲の始まりのように聞こえていた。