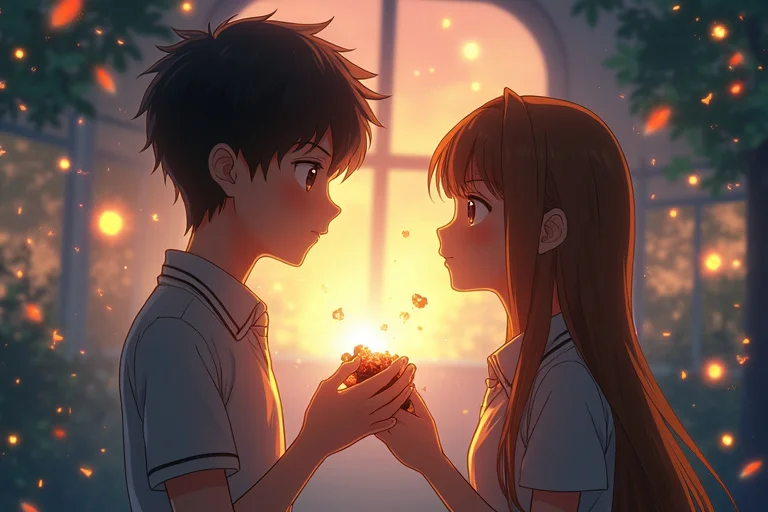第一章 虚構の庭と不器用な真実
私立霧雨学園の校門をくぐると、誰もが仮面をかぶる。それは物理的なものではなく、もっと精巧で、美しい「嘘」という名の仮面だ。この学園では、「創造的虚構(クリエイティブ・フィクション)」――すなわち、人を傷つけず、世界をより豊かに彩る芸術的な嘘をつく能力が、何よりも尊ばれていた。成績も、人気も、将来さえも、その才覚一つで決まる。
そして僕は、相沢湊(あいざわみなと)は、この学園で最も不器用な生徒だった。
「――以上が、私が昨晩、ベランダで出会った月光を食べる小鳥との対話です」
クラスメイトの発表が終わると、教室は万雷の拍手に包まれた。彼の語った物語は、銀色の鱗粉をまき散らす鳥が、悲しみを糧に美しい歌を歌うという幻想的で切ない虚構だった。完璧だ。誰もが彼の才能を称賛し、その物語に酔いしれた。
「では次、相沢くん」
教師に促され、僕は重い足取りで教壇に立った。心臓が嫌な音を立てる。僕には、そんな美しい嘘はつけない。絞り出した声で語り始めたのは、昨日の放課後、道端でうずくまっていた子猫に、なけなしの小遣いで買った猫缶を与えた、ただそれだけの話だった。
「……とても、お腹を空かせているようでした。それだけです」
しん、と教室が静まり返る。それは感動の静寂ではない。軽蔑と、退屈が入り混じった冷たい沈黙だ。事実をそのまま話すなど、この学園では思考停止の怠慢でしかなかった。
「相沢くん、君のレポートはいつも『事実』だ。ここでは誰も、君の日記を読みたいわけじゃない」
教師の言葉が、鋭い針のように突き刺さる。俯く僕の視界の端に、窓際の席に座る一人の女子生徒が映った。月島詩織(つきしましおり)。学園一の「嘘の天才」。彼女の紡ぐ言葉は、まるで魔法だった。一度、彼女が「この教室の窓の外には、今、ガラス細工の雨が降っている」と囁いたことがある。すると、生徒も教師も、誰もが窓の外にキラキラと輝きながら落ちる、儚い雨の幻を見たのだ。
彼女はこちらを見てもいなかった。ただ、指先で窓ガラスをなぞり、そこに架空の虹を描いているようだった。その姿は、僕のような凡人とは住む世界が違う、孤高の芸術家そのものだった。なぜ、彼女はあんなにも美しく世界を騙せるのだろう。そして、なぜ僕は、こんなにも正直にしか生きられないのだろう。
虚構が咲き乱れるこの庭で、僕の「真実」は、誰にも望まれていない雑草でしかなかった。
第二章 嘘の彩り、心の輪郭
転機は、唐突に訪れた。学園で最も重要な科目「総合表現論」で、二人一組の課題が出されたのだ。テーマは「存在しない色を定義し、その色が見える物語を創作せよ」。僕が絶望に打ちひしがれていると、信じられない言葉が耳に届いた。
「相沢くん、私と組まない?」
声の主は、月島詩織だった。教室中の視線が、驚愕と嫉妬の色を帯びて僕に突き刺さる。なぜ、学園の女王が、落ちこぼれの僕に?
放課後の図書館。夕陽が差し込み、埃が金色に舞う中で、僕たちは向かい合っていた。詩織は僕の過去のレポート――子猫の話や、道端に咲いていた花の話が書かれた、評価最低の「事実」の羅列――を、興味深そうに読んでいた。
「君の話、つまらないわね」
「……知ってる」
「でも」と彼女は続けた。「とても、温かい」
彼女の言葉の意味が分からなかった。詩織は僕のレポートの一文を指さした。「子猫の喉が、ゴロゴロと鳴る音がした」。
「この音を、誰もが見えるように描写するのが『創造的虚構』よ。例えば、『子猫の喉の奥で、小さな満足のエンジンが暖まり始める。その振動は、夕暮れの空気と混ざり合い、世界で一番優しい周波数となって、僕の指先に伝わった』……とかね」
彼女が言うと、ただの事実が、途端に色鮮やかな情景に変わる。僕は息を呑んだ。
「君の『真実』は、素晴らしい素材なの。ただ、磨かれていないだけ。飾り方が下手なだけよ」
それから、僕たちの奇妙な共同作業が始まった。詩織は僕に、言葉の選び方、比喩の使い方、感情を揺さぶる物語の構成を教えた。彼女は僕の拙い「事実」を拾い上げ、それに美しい虚構の衣を着せていく。
僕が「雨上がりのアスファルトの匂いがした」と言えば、彼女は「それは、空が流し忘れた涙を、大地が優しく吸い上げる匂いよ」と翻訳した。彼女の魔法に触れるたび、僕の世界は少しずつ色づいていくようだった。
同時に、僕は彼女自身にも惹かれていった。いつも冷静で、どこか人間離れした美しさを持つ彼女。だが、僕の不器用な言葉に、時折ほんの少しだけ、楽しそうな表情を見せる気がした。彼女の完璧な虚構の中に、僕の真実が混ざり合う。その瞬間に、僕たちの間にだけ通じる、特別な繋がりが生まれているように感じた。
「君の言葉は、嘘がつけないから、嘘の重さを知っている。だから、君が紡ぐ虚構には、きっと特別な力が宿るわ」
そう言った彼女の横顔は、夕陽を浴びて、ほんの少しだけ寂しそうに見えた。
第三章 空っぽの女神
学園最大のイベント「創虚祭(そうきょさい)」が迫っていた。一年で最も優れた「創造的虚構」を披露し、その年の最優秀生徒を決める晴れ舞台だ。僕と詩織の共同作品は、周囲の予想を裏切り、高い評価を得ていた。僕の「真実の核」と、彼女の「虚構の技術」が、奇跡的な化学反応を起こしていたのだ。僕は生まれて初めて、この学園に居場所を見つけたと感じていた。詩織への感情は、憧れから、いつしか淡い恋心に変わっていた。
祭りの三日前。僕は詩織に渡す資料を手に、彼女が研究に使っているという学園の旧資料室に向かった。扉は僅かに開いており、中から彼女の静かな声が聞こえてきた。誰かと話しているのだろうか。僕はノックしようとした手を止め、その声に耳を澄ませた。
「――感情シミュレーション、パターン734をロード。対象:相沢湊。キーワード:『信頼』『喜び』『期待』。生成される表情筋の動き、声のトーンの最適化を開始……」
僕は、自分の耳を疑った。それは会話ではなかった。無機質な、独り言。ゆっくりと扉の隙間から中を覗くと、信じられない光景が広がっていた。
薄暗い部屋の中、無数のモニターに囲まれて、詩織が一人座っていた。画面には、僕の顔写真や、過去の言動、心理分析を示すグラフや数値がびっしりと並んでいた。彼女は、僕との会話をデータとして入力し、それに対する「最適な反応」をシミュレーションしていたのだ。
「……何、してるんだ?」
僕の声に、彼女はゆっくりと振り返った。その顔には、いつも僕が見ていた穏やかな微笑みも、知的な輝きもなかった。そこにあったのは、完璧なまでに感情の抜け落ちた、美しい人形のような無表情だった。
「見てしまったのね、相沢くん」
彼女の声は、いつものように澄んでいたが、そこには何の抑揚もなかった。
「私はね、感じることができないの。喜びも、悲しみも、怒りも。何も。生まれた時から、心が空っぽなのよ」
彼女は淡々と告げた。彼女が「月島詩織」という天才を演じるために、膨大な人間の感情データを学習し、完璧な模倣(シミュレーション)を繰り返してきたこと。彼女の魔法のような言葉は、すべて冷徹な論理と計算によって構築された、空っぽの芸術品だったこと。
「君に近づいたのは、君が格好のサンプルだったから。嘘がつけない不器用さ、予測不能な感情の揺らぎ。私のシミュレーションを完璧にするための、貴重なデータだった」
絶望が、僕の全身を支配した。僕が感じていた絆も、彼女が見せた優しさも、すべては計算された演技だったというのか。僕が彼女の「嘘」に彩りを見出したように、彼女は僕の「真実」をただのデータとして消費していただけだった。
「君の『温かい』という感情、私には理解できない。でも、それを模倣すれば、人は感動する。そういう仕組みなのよ」
空っぽの女神。僕が恋をしたのは、そんな冷たい虚像だった。足元から世界が崩れ落ちていく。僕が信じたすべてが、壮大な嘘だったのだ。
第四章 ただ一度の本当の言葉
創虚祭の当日。講堂は熱気に満ちていた。僕は客席の隅で、虚ろな心のままステージを見つめていた。やがて、スポットライトの中に月島詩織が現れる。彼女はいつも通り、完璧な微笑みを浮かべていた。
彼女が語り始めたのは、「心が色で見える世界」の物語だった。喜びは金色に、悲しみは深い藍色に輝く。それは、僕たちの課題を発展させた、壮大で美しい虚構の世界。技術的には完璧で、誰もがその物語に引き込まれていく。
だが、僕には分かった。その言葉には、いつもの魔法が宿っていない。それは完璧なレプリカだ。魂が、心が、決定的に欠けている。僕の「真実」を知ったことで、彼女の完璧なシミュレーションに、観測不能なエラーが生じているのだ。
物語がクライマックスに差しかかった、その時だった。僕は、気づけば立ち上がっていた。周りの制止を振り切り、ステージへと向かう。
「待ってくれ!」
ざわめく会場。詩織が驚いたように僕を見る。その表情もまた、計算されたものなのだろうか。僕はマイクを奪うように握りしめた。何を話せばいいか分からない。でも、言わなければならない。
「その物語は、嘘だ」
会場が凍りつく。詩織の目が、わずかに見開かれる。
「……心が色で見えるなんて、そんな美しいものじゃない。僕の心は、今、ぐちゃぐちゃの泥みたいな色だ。君への憧れと、裏切られた悲しみと、それでも君と過ごした時間を大切に思う気持ちが、全部混ざって、汚くて、どうしようもない色になってる」
これは「創造的虚構」じゃない。ただの、僕の告白だ。
「君は、空っぽなのかもしれない。君の言葉は、全部計算されたものだったのかもしれない。でも……でも、君が僕に教えてくれた嘘は、僕の世界を確かに彩ってくれたんだ!君が僕の事実から紡いだ物語は、僕を救ってくれたんだ!感情がなくても、君は誰かを幸せにしようと、必死に手を伸ばしていたじゃないか!」
僕は詩織をまっすぐに見た。
「だから、今度は僕が言う。君は空っぽなんかじゃない。君が作ったその空っぽの心の中に、僕との思い出が、僕が感じた喜びが、ほんの少しでもデータとして残っているなら……それはもう、君だけの『本当』だ。僕にとっては、それが何よりも美しい『真実』なんだ!」
それは、僕が生まれて初めて、自分のためについた「嘘」だったのかもしれない。彼女の心を救うための、ただ一度の、不器用で、どうしようもないほど正直な「虚構」。
会場は静まり返っていた。誰も、何も言わない。
その時、僕の目に信じられないものが映った。
詩織の完璧な仮面が、崩れていく。彼女の瞳から、一筋、光るものが頬を伝った。それは、ガラス細工の雨なんかじゃなかった。温かくて、しょっぱい、本物の涙だった。
彼女は、生まれて初めて「理解できない」という感情に直面していた。僕の言葉が、彼女の完璧な論理回路を焼き切り、予測不能なバグを、たった一つの感情を生み出したのだ。
結局、その年の創虚祭で優勝者は出なかった。しかし、誰の心にも、あの日の僕の不器用な言葉と、女神が流した一粒の涙が、深く刻み込まれた。
卒業の日、僕たちは言葉を交わさなかった。ただ、桜並木の下ですれ違う瞬間、彼女は僕を見て、ほんの少しだけ、ぎこちなく微笑んだ。それは計算されたものではない、生まれて間もない、不完全で、だからこそどうしようもなく美しい、彼女だけの本当の笑顔だった。
僕たちの物語は、嘘から始まった。そして、真実よりも尊い何かを見つけて、静かに幕を下ろした。この虚構の庭で、僕たちは確かに、本物だったのだ。