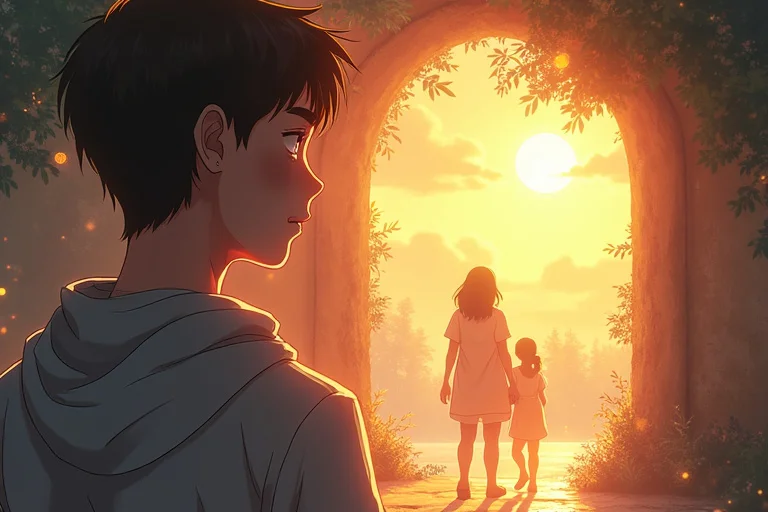第一章 帰郷と黒い残滓
父が死んだ。その知らせは、梅雨の湿気をたっぷりと含んだ重たい空気のように、俺、ケンジの部屋に澱んだ。五年前に家を飛び出して以来、父とは一度も言葉を交わしていない。電話の向こうで嗚咽を漏らす母の声だけが、俺と実家を繋ぐか細い糸だった。
通夜と告別式は、まるで知らない誰かのための儀式のように過ぎていった。親戚たちの囁き声が背中に突き刺さる。「勘当同然だったのに、よく帰ってきたもんだ」「ケンジ君も、少しは大人になったのかしらね」。俺は無表情の仮面を貼り付け、ただ俯いていた。父の顔は、最後まで見ることができなかった。
問題は、初七日を終えた後の遺品整理で起こった。父の書斎は、主を失ってもなお、その厳格な気配を色濃く残していた。インクと古い紙の匂い。壁一面を埋め尽くす法律関係の専門書。弁護士だった父らしい、秩序と理論で固められた城だ。
「お父さん、これをとても大事にしていてね」。母が指さしたのは、書斎の飾り棚に並べられた、色とりどりのガラス細工のような物体だった。パステルカラーの光を放つそれらは、『メモリア』と呼ばれる思い出の結晶だ。
現代のテクノロジーが生み出した、最も感傷的な発明品。専用のヘッドギアを装着して過去の特定の出来事を追想すると、その記憶データが脳波から抽出され、感情の起伏に応じて色や形を変えながら、掌サイズの結晶として生成される。結晶に触れれば、生成者が見た光景、聞いた音、そして抱いた感情までもが、追体験できるという代物だ。
俺はこの『メモリア』が嫌いだった。真実を切り取り、都合の良い感傷に浸るための、空虚な玩具にしか思えなかったからだ。父がこんなものを集めていたとは、知らなかった。
「これは、あなたが生まれた日の記憶」「こっちは、妹のサキが初めて歩いた日よ」。母は一つ一つを愛おしそうに撫でながら、涙ぐむ。サキも隣で静かに頷いている。棚に並ぶのは、家族旅行、運動会、誕生日。どれもが温かな光を放つ、完璧な「幸せな家族」の標本だった。
「茶番だ」。喉まで出かかった言葉を、俺は飲み込んだ。父は完璧な父親を演じ続けた男だ。厳格で、正しく、そして冷たい。俺が家を出たのも、その息苦しい「正しさ」に耐えられなくなったからだ。この結晶たちも、父が作り上げた虚像のコレクションに過ぎない。
その時だった。書棚の奥、分厚い六法全書の影に隠された小さな木箱が、ふと目に留まった。母もサキも気づいていない。そっと手に取ると、ずしりと重い。埃を払い、軋む留め金を外す。
中には、ベルベットの布に包まれて、たった一つだけ結晶が鎮座していた。しかし、それは棚に並ぶどれとも似ていなかった。光を一切通さず、まるで磨かれていない石炭のように、淀んだ黒色をしている。形も歪で、表面には無数の亀裂が走っていた。不気味なほどの負のオーラを放つその結晶は、まるで幸せな記憶のコレクションの中に紛れ込んだ、呪われた遺物のようだった。これが、父の本当の姿なのだろうか。俺は、その黒い残滓から目が離せなくなった。
第二章 虚飾のクリスタル
それから数日、俺は実家の空気に馴染めない幽霊のように過ごした。母とサキは、時折父の『メモリア』に触れては、思い出話に花を咲かせた。リビングには、父が生成した海の結晶から流れ出る、穏やかな波の音と潮の香りが満ちていた。それは、俺が小学生の頃に行った家族旅行の記憶だった。
「ケンジも、触ってみない? お父さん、あなたがサッカーで初ゴールを決めた時、すごく喜んでいたのよ」。母が差し出したのは、太陽のように眩しい黄金色の結晶だった。歓声と高揚感が、結晶から微かに漏れ出している。
「いいよ。興味ない」。俺はぶっきらぼうに答えて、ソファから立ち上がった。母の悲しげな視線が背中に痛い。分かっている。俺は家族の輪を乱す異物だ。だが、あの完璧な結晶たちに触れることは、父の偽善を肯定するようで我慢ならなかった。
父は、いつも俺に「お前のためだ」と言った。進路も、友人関係も、全てに口を出し、彼の価値観という名の定規で俺を測った。俺が音楽に夢中になれば「そんなものでは食っていけない」とギターを叩き壊し、俺が父に反発すれば「感謝を知らない恩知らずだ」と罵った。あの黄金色の結晶の裏側で、父は一体何を思っていたというのか。どうせ「息子が私の期待通りに育っている」という自己満足に浸っていただけだろう。
夜、家族が寝静まった後、俺は吸い寄せられるように父の書斎へ向かった。月明かりが差し込む部屋で、あの黒い結晶が入った木箱を再び開ける。
昼間見た時よりも、その黒さは深く、禍々しい。まるで、宇宙の暗黒そのものを固めたかのようだ。表面の亀裂からは、冷たい空気が染み出している気がした。これは、一体何の記憶なんだ。父が隠したかった、家族に見せたくなかった、本当の顔。俺が知る、冷酷な父の姿そのものなのかもしれない。
好奇心と、父への反発心。そして、ほんの少しの恐怖が入り混じった感情に突き動かされ、俺は震える指を、その黒い結晶へと伸ばした。ひんやりとした、岩のような感触。その瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。
第三章 父が見た悪夢
視界が真っ白に染まり、次の瞬間、俺は知らない場所に立っていた。いや、正確には「立たされて」いた。自分の身体ではない。少し背が低く、手は節くれ立っている。目の前には、古びた安物の食卓。ちゃぶ台の上には、冷めきった煮物と白飯が並んでいる。昭和の香りがする、薄暗い部屋だった。
「いつまで待たせる気だ!」。怒声が鼓膜を突き破った。見ると、酒臭い息を吐きながら、ランニングシャツ姿の男がこちらを睨みつけている。知らない男だ。だが、その鋭い目つきは、どこか父に似ていた。
「すみません、あなた…」。俺は、いや、俺が追体験しているこの身体の主は、か細い声で謝った。それは、まだ声変わりを終えていない、少年の声だった。
次の瞬間、頬に灼けるような衝撃が走った。男に殴られたのだ。少年はなすすべもなく畳に倒れ込む。口の中に、鉄の味が広がった。
「言い訳するな! 親に口答えするとは、生意気な!」。男は怒鳴りながら、少年の腹を蹴りつけた。息が詰まる。苦しい。痛い。恐怖で身体が震える。これは、一体誰の記憶なんだ? 父の記憶のはずだ。だが、この少年は父じゃない。だとすれば、この暴力を振るう男が、若き日の父なのか? いや、違う。もっと歳上だ。
混乱する俺の意識に、少年の絶望が流れ込んでくる。――まただ。父さんは、酔うといつもこうなる。母さんは、俺を守ろうとして、代わりに殴られている。俺がしっかりしないと。俺が、父さんみたいになったら、絶対にダメだ。
その時、はっきりと理解した。この男は、俺の祖父だ。そして、この恐怖に耐えている少年こそ、若き日の父、彰(あきら)だったのだ。俺が生まれるずっと前、父が経験した地獄。この黒い結晶は、父自身の記憶ですらなかった。父が、その父から受け継いでしまった、消せない傷跡の記憶だった。
記憶の光景は、次々と切り替わった。祖母を庇って殴られる父。成績表を破り捨てられる父。「お前は俺の子だ。出来損ないだ」と罵られ、押し入れに閉じ込められる父。どの光景も、暴力と恐怖、そして深い絶望に満ちていた。
父は、この悪夢の中で生きてきたのか。俺が知る、常に正しく、厳格で、揺らぐことのなかった父の姿は、この地獄から逃れるために必死で作り上げた鎧だったのだ。彼が俺に厳しく当たったのは、俺を支配するためじゃなかった。自分が最も恐れていた「父(祖父)」の姿が、自分の中に蘇るのを恐れていたからだ。俺が道を踏み外すことで、自分の中の怪物が目を覚ますのを、必死で抑えつけようとしていたのだ。
「お前のためだ」。あの言葉は、歪んではいたが、嘘ではなかったのかもしれない。それは、息子に同じ地獄を味わわせたくないという、父の悲痛な叫びだったのだ。
俺は、父の孤独の深さに打ちのめされた。彼は誰にもこの苦しみを打ち明けられず、たった一人で、父親という怪物と戦い続けていた。そして、その戦いの記録を、誰にも見つからないよう、この黒い結晶に封印していた。忘れたい、しかし忘れられない、呪いのような記憶として。
意識が現実に戻ってきた時、俺は書斎の床に座り込み、嗚咽していた。手の中の黒い結晶は、相変わらず冷たく、重かった。しかし、それはもう、不気味な残滓ではなかった。父が一人で背負い続けた、あまりにも重い十字架に見えた。
第四章 新しい光
翌朝、俺はまるで生まれ変わったような気分でリビングに下りた。母とサキが、いつものように父の『メモリア』をテーブルに並べていた。そこには、あの黄金色の、俺がサッカーでゴールを決めた日の結晶があった。
「…これ、見てもいいか」。俺が言うと、母は驚いたように目を見開き、そして優しく微笑んで頷いた。
俺は深呼吸をして、その温かな結晶にそっと触れた。
視界に、緑の芝生と青い空が広がる。スタンドからの歓声。ボールを追いかける少年時代の俺。そして、ファインダー越しに俺を見つめる、父の視点。息子の晴れ姿を、少し不器用な手つきでカメラに収めようとしている。
ゴールが決まった瞬間、父の視界が大きく揺れた。歓喜と、安堵。そして、俺の耳に流れ込んできたのは、父の心の声だった。
――よくやった、ケンジ。そうだ、そのまま、真っ直ぐに育て。俺のようには、なるな。お前には、光の中だけを歩いてほしい。この幸せが、ずっと続きますように。
それは、俺が想像していた自己満足などではなかった。ただひたすらに息子の幸せを願う、不器用な父親の、切実な祈りだった。
記憶の追体験を終えた俺の頬を、熱いものが伝っていた。涙だった。父が演じていた「完璧な父親」は、虚飾なんかじゃなかった。それは、暗闇を知る者だけが希求する、光そのものだったのだ。父は、美しい結晶を作ることで、自らの過去の呪いに抗い、「理想の家族」という光を必死に守ろうとしていた。
「お父さん…ごめん」。誰に言うでもなく、俺は呟いた。
その日を境に、俺は変わった。母やサキと共に、父が遺した光の結晶に一つずつ触れていった。そこには、俺が忘れていた、あるいは意図的に無視していた、父の愛情が溢れていた。肩車をしてもらった時の、父の背中の温かさ。自転車の練習に付き合ってくれた時の、焦りと喜びが入り混じった声。全ての記憶が、父の苦悩を知った今、全く新しい意味を持って胸に迫ってきた。
父の遺した『メモリア』は、虚飾のコレクションではなかった。それは、一人の男が、家族を愛し、過去の怪物と戦い抜いた、魂の記録だった。
数週間後、俺は実家を離れる準備をしていた。父の書斎に立ち、あの黒い結晶をもう一度手に取る。そして、その隣に、黄金色の結晶をそっと並べた。光と影。それこそが、父の人生であり、俺が受け継いだものだ。
書斎の隅には、最新型の『メモリア』生成装置が置かれていた。父が使っていたものだ。俺は、しばらくそれを見つめた後、静かにヘッドギアを装着した。
これから、俺は俺自身の記憶の結晶を作る。それは、父を憎んでいた過去の記憶か。それとも、父を理解し、許した、この数週間の記憶か。生成される結晶は、何色になるのだろう。それはまだ、誰にも分からない。俺はゆっくりと目を閉じ、父と過ごした、全ての時間に想いを馳せた。新しい光が、俺の中で生まれようとしていた。